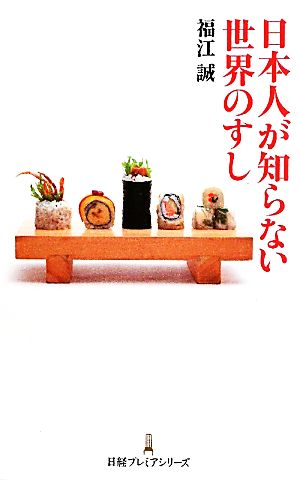日本人が知らない世界のすし の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
メモ 何事も、自国そのものを輸出するのではなく、その国々の文化や嗜好に合うように適応させたものを提供する必要がある。 また、一度受け入れられたものもその時々で変化を遂げる(カリフォルニアでは健康志向からマヨネーズ抜きの寿司が増えている等)。
Posted by
納得できない真実を突きつけられた感じ。 寿司の世界展開とバブル崩壊と中韓シェフの台頭とか、今の世界の日本料理がどのように広まったかが書かれている。 願わくば、外国人で日本料理を学ばれる方へ、現地で好かれるもののみならずオーセンティックな日本料理も紹介していただきたい。そう思わずに...
納得できない真実を突きつけられた感じ。 寿司の世界展開とバブル崩壊と中韓シェフの台頭とか、今の世界の日本料理がどのように広まったかが書かれている。 願わくば、外国人で日本料理を学ばれる方へ、現地で好かれるもののみならずオーセンティックな日本料理も紹介していただきたい。そう思わずにいられなかった一冊。
Posted by
なかなか面白かった。お寿司という切り口はあるけど、ビジネス書としても面白い。海外進出に必要なことは、どの業界も同じ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 海外のあちこちでスシバーや回転寿司が大人気。 フルーツ、唐辛子、チョコ…。 目を疑うネタでも、やっぱりこれは「寿司」。 邪道なんて言えません。 どんな変貌を遂げているか。 どれだけ定着しているのか。 世界の「スシ事情」をつぶさにレポート。 [ 目次 ] 第1章 もはや「邪道」ではない世界の寿司 第2章 なぜ、寿司が「クール」なのか 第3章 女性職人がもて囃される理由 第4章 世界で生きる職人に求められるもの 第5章 こんなに違う「繁盛する条件」 第6章 もう「飯炊き三年握り八年」ではない 第7章 価値に気づいていないのは日本人 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
カリフォルニアロールなんて寿司じゃない!という前に読んでほしい。 「寿司」という日本文化を海外で花開かせるまでに、どういう変化をたどったか(たどるのか)が書かれた本。寿司の話というよりは、寿司ビジネスの話。海外で寿司で成功している人は、寿司職人さんというよりも、むしろビジネスマ...
カリフォルニアロールなんて寿司じゃない!という前に読んでほしい。 「寿司」という日本文化を海外で花開かせるまでに、どういう変化をたどったか(たどるのか)が書かれた本。寿司の話というよりは、寿司ビジネスの話。海外で寿司で成功している人は、寿司職人さんというよりも、むしろビジネスマン(もちろん、女性も)。 カリフォルニアロールも、寿司なのです。
Posted by
最近、一つのテーマに基づいて歴史を辿った書籍を読むことが多い。『世界史をつくった海賊』、『沈没船が教える世界史』『チョコレートの世界史』、『警察の誕生』、『ハプスブルグ帝国の情報メディア革命』などなど。いずれも面白かったのだが、その中で日本の話題がほとんど登場せず、登場しても決し...
最近、一つのテーマに基づいて歴史を辿った書籍を読むことが多い。『世界史をつくった海賊』、『沈没船が教える世界史』『チョコレートの世界史』、『警察の誕生』、『ハプスブルグ帝国の情報メディア革命』などなど。いずれも面白かったのだが、その中で日本の話題がほとんど登場せず、登場しても決してメインストリームではなかったりし、少々寂しくもあった。そんな中で出会ったのが、本書『日本人が知らない世界のすし』。正真正銘の、「日本初、世界へ」というテーマなのである。 ◆本書の目次 第一章:もはや「邪道」ではない世界の寿司 第二章:なぜ、寿司が「クール」なのか 第三章:女性職人がもて囃される理由 第四章:世界で生きる職人求められるもの 第五章:こんなに違う「繁盛する条件」 第六章:もう「飯炊き三年握り八年」ではない 第七章:価値に気づいていないのは日本人 幸か不幸か、世界で意味づけされてしまった「すし」は、もはや原型を留めない。アメリカのカリフォルニアロールはまだしも、ポーランドではラズベリージャムとキャビアがトッピングされており、ポルトガルの首都リスボンではハチミツやナッツもネタとして一緒にまかれている。極めつけは南米ブラジル。バナナ、マンゴーなどを具材に、デザートとして食されているそうだ。まさにコンテキスト(文脈)の世界地図である。 一方で、コンテンツとしての「すし」の原理原則はどこにあるのか。古くは戦後GHQによる統治時代まで遡る。食糧難が深刻だった時代には飲食営業緊急措置令が発令され、喫茶店以外の飲食店がすべて営業を禁止された。そんな中、東京の寿司組合がマッカーサーに嘆願し、特別に営業認可を与えられたのだ。この時に制定されたルールによって、寿司一人前は10貫が標準になり、それまで四〇グラム以上あった握りが半分以下の大きさに規定された。その際、大阪の箱寿司をはじめとする寿司の営業は認められなかったため、郷土料理のひとつであった「江戸前寿司」が全国に広がったのである。 そんな中で悩ましいのは、世界に羽ばたいた寿司職人たちの「すし」への向き合い方である。もはや肉体と精神が分離した状態の「すし」に対して、原理原則を貫くのか、現地の解釈に合わせていくのか。対応は千差万別なのだが、成功している人で原理原則に固執している人はいない。ただし、どこかで譲れない一線というのは持っているようにも思える。肉体は許せど、魂は許さずといったところだろうか。そして寿司の技術以上に大切なのは、コミュニケーションであるそうだ。「腕はいいが、頑固で口下手」では、世界に通用しないのである。 寿司を通じて味わえるのは、魚やシャリだけではなく、食する間や空間そのものも「ネタ」になりうる。そういった意味で、寿司をはじめとする日本食は、食文化というより根源的な視点から「クールジャパン」の文化輸出を広げる促進剤になりうるものである。そして我々が思っている以上に日本のソフトはパワーを持っていると、著者は主張する。「世界は日本を待っている!」、そんな勇気をもらえる一冊である。
Posted by
すし屋の話と思って読むと、読後しっくりこないです。すしを握れることを特徴として海外でビジネスするすし職人の話。そしてすしを握ること以上に、コミュニケーションの能力が必要との結論で、対面でお食事を出す姿勢をあらためて再認識。お客さんのハートまで握ることが肝心とのことです。そしてすし...
すし屋の話と思って読むと、読後しっくりこないです。すしを握れることを特徴として海外でビジネスするすし職人の話。そしてすしを握ること以上に、コミュニケーションの能力が必要との結論で、対面でお食事を出す姿勢をあらためて再認識。お客さんのハートまで握ることが肝心とのことです。そしてすしを握ることはすし学校が教えてくれるし、海外で活躍する道すじまで学習することが可能。なんだか海を渡れば簡単にすし職人と呼ばれることが出来そうだなと安易な気持ちになってしまいました。
Posted by
- 1