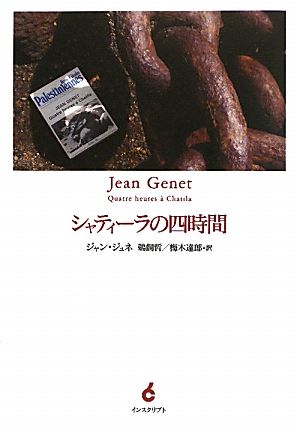シャティーラの四時間 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『ガザに地下鉄が走る日』で紹介されていたので手に取った。エクリチュールであり、ルポルタージュ。 ジュネの「シャティーラの四時間」は全体の四分の一くらいだろうか。その他、「ジャン・ジュネとの対話(ジャン・ジュネ+リュディガー・ヴィッシェンバルト+ライラ・シャヒード・バラーダ/梅木達郎訳)」、「〈ユートピア〉としてのパレスチナ─ジャン・ジュネとアラブ世界の革命(鵜飼哲)」、「生きているテクスト─表現・論争・出来事(鵜飼哲)」、その他パレスチナ国民憲章(早尾貴紀訳)/地図/パレスチナ関連年表などが収録されている。 「シャティーラの四時間」はあまりにも凄惨な虐殺の現場、おびただしい死、死体、腐乱、蠅というものと、フェダイーンたちの周りを囲む、太陽、自由、生と美がエクリチュールとして表現されている。なるほどこういう形でなら、言語化はできるのだな。 後半紹介されている、「エクリチュールはようやくそれを、この死を言うことに役立とう。書くこと―それをつかもうとするたびに思考が崩れてしまう、この極限的な現実と向き合うこと。そして事実、シャティーラの語り手は死の後を追いかけ、死を狩り出し、死を追いつめ、死と子供のように戯れる、馬跳びや双六ゲームによって、ある死体から他の死体へと導かれながら。」という文章がまさに、という感じ。 …道理は彼らの側にある、私が愛しているのだから。だが不正のためにこの人々が浮浪の民にならなかったとしたら、この人々を私は愛していただろうか。 ... 愛(アムール)と死(モール)。この二つの言葉はそのどちらかが書きつけられるとたちまちつながってしまう。シャティーラに行って、私ははじめて、愛の猥褻と死の猥褻を思い知った。愛する体も死んだ体ももはや何も隠そうとしない。さまざまな体位、身のよじれ、仕草、合図、沈黙までがいずれの世界のものでもある …ベイルートからの帰途、ダマスの空港で、イスラエルの地獄を逃れてきた若いフェダイーンに私は出会った。年は十六、七だった。皆笑っていた。アジュルーンにいたフェダイーンにそっくりだった。彼らのように、この少年たちも死ぬのだろう。国を求める闘いは満たすことができる、実に豊かな、だが短い人生を。思い出そう、これは『イーリアス』でアキレウスがする選択なのだ。 ジュネのフェダイーンに対する眼差しは、優しさと愛に満ちている。戦士たちに対する愛が。 「ジャン・ジュネとの対話」も面白かった。 イメージの問題。虐殺のイメージと、それをデモによって対外的に払拭しようと、個人の良心の呵責からも逃れようとするイスラエル。 「<ユートピア>としてのパレスチナ」 …パレスチナ人に対する彼の「愛」とともに、政治は再び美学化されたのだろうか。それとも芸術が、かつてない形で政治化されたのであろうか。この問いが問われる<場>がもはや西洋ではなくアラブ・オリエントであるとき、とりわけ<パレスチナ>と呼ばれるとき、この問い自体が蒙る変形のことを、ジュネを読み続けつつ、私たちはさらに考え続けなければならない… 『愛する虜』も読まなくてはいけません
Posted by
高橋源一郎氏の『非常時のことば』で知って手に入れた本。鵜飼哲氏が解説で紹介しているジェローム・アンキンスの評、「死と子供のように戯れる、馬跳びや双六ゲームによって、ある死体から他の死体へと導かれながら」という言葉が、まさに的確に、この文章の特異な魅力を伝えている。うつくしく、おぞ...
高橋源一郎氏の『非常時のことば』で知って手に入れた本。鵜飼哲氏が解説で紹介しているジェローム・アンキンスの評、「死と子供のように戯れる、馬跳びや双六ゲームによって、ある死体から他の死体へと導かれながら」という言葉が、まさに的確に、この文章の特異な魅力を伝えている。うつくしく、おぞましくも、激しく心をわしづかみにする。シャティーラキャンプの虐殺の現場を歩いて、このような文章を書きのこすような人間が、ほかにいるだろうか。 最近、人文系のムズカシイ文章をさっぱり受け付けなくなっているので、正直、鵜飼哲氏の論考はほとんど理解できていないのだけど、ジュネの中で「政治」と「美学」が不可分なかたちで絡み合っていたことは、なんとなくわかる。このテキストを上演する試みがいくつもなされているというのは興味深い。それぞれの演出家は、死者たちの声にどのような肉体をあたえようとしているのだろう。ぜひ見てみたいものだ。
Posted by
美しさはそこにはない、というのも現象であるからだ。 観る者を魅了し、恍惚とさせる。優美な圧倒とでもいうものだ。 死も、また、そうだ。現象である。 現象である、ということの含意は 体験されて初めて意味をなすものだということだ。 言い方を変えれば、安全に観察することが許されず、 常...
美しさはそこにはない、というのも現象であるからだ。 観る者を魅了し、恍惚とさせる。優美な圧倒とでもいうものだ。 死も、また、そうだ。現象である。 現象である、ということの含意は 体験されて初めて意味をなすものだということだ。 言い方を変えれば、安全に観察することが許されず、 常に巻き込まれてしまうものだ。 ジュネのことはよく知らない。 知らないが、特異な類のシャーマンではないか。 死体ではなく、死を、死体に潜む死を、潜む虐殺を そのままに提出しようとする。 そのおかげで我々はこのことについて 何か話すことができるような気がしてしまう。 連帯感などとは程遠いが、死を体験した当事者であるからだ。 ヨーロッパでも論争になったらしいが、うなずける話だ。 「こんな面倒なものを書きやがって!」 こんなものの当事者になど別になりたくもない、というのに。 けれども、知ってしまえばもう遅い。 そして、嫌になるくらい、美しい。
Posted by
斧でかち割られて膨張した頭部をもつ死体が、こぼれ落ちた脳味噌と飛び散った血が染みついた地面にゴロリと転がっていて、死体にはウジと蝿がたかっている、そういう死臭漂う虐殺現場の惨たらしい様子が現実以上に鮮明になって言葉にされています。 今から28年前の1982年、西アジアは中東のレ...
斧でかち割られて膨張した頭部をもつ死体が、こぼれ落ちた脳味噌と飛び散った血が染みついた地面にゴロリと転がっていて、死体にはウジと蝿がたかっている、そういう死臭漂う虐殺現場の惨たらしい様子が現実以上に鮮明になって言葉にされています。 今から28年前の1982年、西アジアは中東のレバノン共和国の首都ベイルートにあるパレスチナ難民キャンプで大虐殺が行われたことは、すでにジャーナリストの広河隆一の本『ベイルート1982・・イスラエルの侵攻と虐殺』(1983年)や岩波新書の『パレスチナ』(1987年、その後2002年に『パレスチナ新版』を刊行)によって詳細な事実を伝えられていますが、このときヨーロッパ人で最初にこの現場に踏み込んだのが、他でもない『薔薇の奇蹟』や『花のノートルダム』や『泥棒日記』や『葬儀』の、あのジャン・ジュネだったことはあまり知られていないことかも知れません。 私は週刊誌はなぜか読む習慣がありませんが、雑誌といえば「相撲」から「薔薇族」や「通販生活」とかありとあらゆる趣向のものを読みますが、これもまた偶然ですが、1988年の号の「インパクション」という思想・社会運動傾向の雑誌に翻訳が掲載されているのを読んだことがありました。 1982年の9月16日から18日にかけて侵攻したイスラエル軍が、パレスチナ難民キャンプを襲って民間人1,800人以上を銃火器や斧・ナイフで虐殺。男性のみにとどまらず子供・女性・老人・病人・看護師・医師など無差別虐殺でした。 ジャン・ジュネは、24年前の1986年に75歳で亡くなりましたが、ということはこのとき齢71歳。すでに70年代頃から今までのような文学的営為を中止していましたが、その前から参加していた五月革命やベトナム反戦運動などの政治活動の延長線上に、ブラックパンサー党やPLOへとより深く直截的に介入していくのでした。 その行き着いた先の果てには、それこそ言葉など何の役にも立たない、言葉などまったく無力な凄惨な現実が待っているにもかかわらず、おそらく初めからわかっていてあえて、ボロボロになった身体を引きずって、たったひとりこの世界の巨大な暴力と残酷とに対峙していったのだと思います。 その成果がこの本です。事実を伝える5W1Hにもとづいた報道の文章とはほど遠い、あまりにも感情の起伏の激しい、ときには象徴的だったり、ときには詩的で眩惑的だったりするものですが、現実を現実として正確に伝えるために、視覚的な言い換えや、聞こえざる死者の声やその場の死臭を主観的に表現して何が悪いのかと思います。 ついにジャン・ジュネは、今まで誰も到達できえなかった究極の表現を私たちに残して、売春婦の母から生まれて麻薬にまで手を染めた必然の犯罪者としての前半生を超克して、きっちりチャラにするどころか、あまりあるものを創造してこの世を去っていったのです。
Posted by
2010年が生誕100年だったことで、雑誌の「ユリイカ」が、最新号(1月号)でジャン・ジュネ(1910-1986)の特集を組んでいる。この号はすでに買ったものの、まだあまり目を通していない。その前にまず私としては、夏に単行本という形となって出版された『シャティーラの四時間』(イ...
2010年が生誕100年だったことで、雑誌の「ユリイカ」が、最新号(1月号)でジャン・ジュネ(1910-1986)の特集を組んでいる。この号はすでに買ったものの、まだあまり目を通していない。その前にまず私としては、夏に単行本という形となって出版された『シャティーラの四時間』(インスクリプト刊)が自室の脚立に積んだままになっているのを、読み遂せるほうが先決であるように思われた。 1982年9月、西ベイルートのサブラとシャティーラの2つのパレスチナ難民キャンプで3日3晩にわたって続いた大虐殺。ジャン・ジュネは老体に鞭を打ちながら、虐殺終了の翌日にシャティーラ・キャンプに入る。死体、死体、死体。折り重なる死体についての描写。この虐殺の10年前における若きフェダイーンたちとの美しき同行の手記となっている序盤とは、あまりにも対照的な虐殺現場の描写が続く。 明確にパレスチナ支持を晩年の活動ベースにしたジャン・ジュネには、当然のことながら「反ユダヤ主義者」というレッテルが貼られることになった。しかし、ジュネ自身、もし「パレスチナが制度化され領土の要求が受け入れられたときに、私がそれでも支持できるかどうかは分からない。だがそれは大事なことなのだろうか?」と述べている。「大シオニズム」とも評すべき領土拡張主義に対するノンが、そのまま「反ユダヤ主義者」のレッテルに直結してしまうという愚を、私たちの近代は、回避する術を見いだせないままなのである。 いま、「反ユダヤ主義者」のレッテルを貼られて困惑しているもうひとりの人物に、同じ強度のスポットを当てて考察を続行していきたい。『ゴダール・ソシアリスム』の作者に対してである。ジュネからゴダールへ、というのが私の2011年の最初の課題となった。
Posted by
- 1