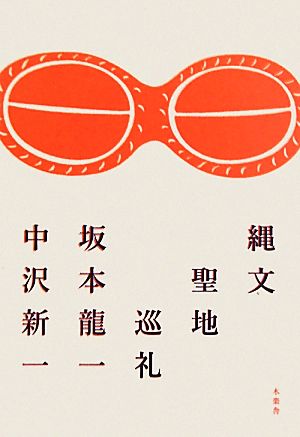縄文聖地巡礼 の商品レビュー
「いちど人間がつくったシステムはなかなか容易に変更できないところがある」「現在の地点に一直線にきたかのような錯覚に陥る」(174頁)それならば縄文時代まで遡って遺跡を旅し、現代に至るほかの可能性が潜在的には生き続け、それを取り出すことで、世界のデッドエンドを超えてゆこうというメッ...
「いちど人間がつくったシステムはなかなか容易に変更できないところがある」「現在の地点に一直線にきたかのような錯覚に陥る」(174頁)それならば縄文時代まで遡って遺跡を旅し、現代に至るほかの可能性が潜在的には生き続け、それを取り出すことで、世界のデッドエンドを超えてゆこうというメッセージが伝わりました。旅した期間は9.11以降、3.11以前のようです。
Posted by
坂本龍一と中沢新一が縄文の遺跡や痕跡のあるところを巡り、対談する本。 1.諏訪 2.若狭・敦賀 3.奈良・紀伊田辺 4.山口・鹿児島 5青森 を2006年から2007年にかけて訪れる。最後の東京での対談は2009年。 「聖地巡礼」と言っても「遺跡めぐりの旅行ガイド」というものでは...
坂本龍一と中沢新一が縄文の遺跡や痕跡のあるところを巡り、対談する本。 1.諏訪 2.若狭・敦賀 3.奈良・紀伊田辺 4.山口・鹿児島 5青森 を2006年から2007年にかけて訪れる。最後の東京での対談は2009年。 「聖地巡礼」と言っても「遺跡めぐりの旅行ガイド」というものではなく、そこで見たものをきっかけに、二人が縄文の文化から、神話、音楽、日本、世界、人間について語りまくる。 最高に面白かった。二人とも何かというと脱原発論に行くところはご愛敬。 中沢新一の「アースダイバー」はとても面白かったのだけど、ちょっと妄想の暴走と分量についていけないところもあったのだけど、 この縄文の本は、お互い暴走が始まりそうになると、やんわりと話が戻って来てくれて、おかげで読みやすい。 坂本龍一がヨーロッパ的な線形の音楽ではなく、非線形の「庭のような音」を作りたいと言っていて、それが2009年の「out of noise」、2017年の「Async」につながるかと思うと興味深い。 随所に出てくるハイデガーとか難しい本を知ってると、一層楽しめるのか、それともこの本のごまかしや浅はかさが見えてくるのかな?と思うのだけど、今のところ何かというと縄文を原発反対に結び付けるところ以外は最高。
Posted by
「観光」「EV Cafe」を読了してから読むと興味深い、「中沢、坂本」が実現したら「細野、村上」は可能なのだろうか。もしくは4人で対談するとか。
Posted by
中沢新一と坂本龍一が、それぞれの問題意識を胸に縄文時代の名残が残る場所を巡りながら意見交換をした対話集。 中沢新一の縄文研究というと『アースダイバー』が思い出されますが、この探訪がきっかけとなってあの作品が生み出されたそうです。 坂本龍一はNYで9.11を体験し、それがきっかけと...
中沢新一と坂本龍一が、それぞれの問題意識を胸に縄文時代の名残が残る場所を巡りながら意見交換をした対話集。 中沢新一の縄文研究というと『アースダイバー』が思い出されますが、この探訪がきっかけとなってあの作品が生み出されたそうです。 坂本龍一はNYで9.11を体験し、それがきっかけとなって縄文へと引き寄せられていったとのこと。 近代社会の崩壊を目にして、原始回帰への興味が生まれたそうです。 国家というものについて考えるために、国家が生まれる前の人間の考え方を知ろうとする旅。 言葉や文字が生まれる前の時代をたどっていく時に、頭で理解しようとしても無理なこと。 二人がそれまで培ってきた知性と感性で、縄文について感じ取っていきます。 まず向かったのは、縄文中期の中心であった諏訪。 この地域は日本に国家というものができてからも、なかなか完全には国家に属さなかったという反骨精神の旺盛な場所だそうです。 若狭が征服した側で、信州は征服された側。 征服された側の怨念は強いとのことですが、その辺りに詳しくないので、どういうことなのか気になりました。 仏教は宗教よりアートに近いという話が採り上げられます。 また、昔の貴族は温泉に入る時、天皇の許可を取らないといけなかったということを知りました。 温泉地にこもることは、死の世界からエネルギーを蓄えることとなるため、反逆の疑いを持たれれないように報告が必要だったのだそうです。 一番印象的だったのが、天皇と南方熊楠との出会いのエピソードでした。 二人は神島で会ったそうですが、お互いに歌を贈り合ったとのこと。 「本の歴史の中でも、こんなに美しい光景はないんじゃないかと思う」と言われているように、尊敬し合う二人の邂逅についてもう少し知りたいと思いました。 熊楠は常にキャラメルの箱を標本箱として利用しており、天皇に御進講した時も、キャラメルの大箱に入れて粘菌標本を進献したとのこと。 自然体です。 縄文の名残を残す土地を訪ね、過去に思いを馳せ、現在の自分たちと人間の未来について思いを巡らせる二人。 それぞれの専門領域に触れながら、漠然とした思いは着実に形をなしていきます。 二人がぴったり息があっている様子が伝わってきますが、全編を通じて、互いの意見にどちらも全く反論をしていないことに気が付きました。 そんなに言うことすべてが流れるように同調していくものなのか、編集上そうなったのか、わかりませんが、反論の上に新たな認識が生まれていく対話も知りたかったと思います。 すっかり縁がなくなったようで、しっかりとつながっている縄文時代と現在。 その道の一流の専門家でも、原点に立ち戻っていきます。 根っこを知ることの大切さを知りました。
Posted by
2013/01/30 小俣図書室--県立図書館。 ISBNが 裏表紙に記載されてなかった。奥付には有った。版元「木楽 舎」は お気楽?
Posted by
縄文の聖地…諏訪、若狭・敦賀、奈良・紀伊田辺、山口・鹿児島、 そして青森…を中沢新一、坂本龍一が旅をする。 では、縄文とはなんだろう… 二人はどこへ旅したのだろう… 冒頭で、中沢新一は、わかりやすくまとめている。 ―いまでは縄文と呼ばれている、おおよそ1万3000~3000年 ...
縄文の聖地…諏訪、若狭・敦賀、奈良・紀伊田辺、山口・鹿児島、 そして青森…を中沢新一、坂本龍一が旅をする。 では、縄文とはなんだろう… 二人はどこへ旅したのだろう… 冒頭で、中沢新一は、わかりやすくまとめている。 ―いまでは縄文と呼ばれている、おおよそ1万3000~3000年 くらい前の時代、その世界を動かしている経済の原理は、 等価交換ではなく贈与でした。 ものを贈るときには必ず、眼には見えないけれども 人間の心にかかわる要素を、お互いが受け渡しをしています。 贈与においては、ひとつとして同じものは存在せず、 等価交換にはなりません。 贈与は生命の働きと結びついていますから、不死でも 不変でもありません。 そう…ふたりは「生命の働き」の基層を旅しようとしている。 その古層の上にのっかているのは、敦賀原子力発電所であり 六ヶ所原子燃料サイクル施設だった…その意味するところを 二人は真摯に考察しようとしている。そして、それは縄文的でないのだ。 さらに、縄文的心層をつかさどるエネルギー、神話の想像力… 人間の祝祭空間の根源は同じところでつながっている…という。 それはエロだというのだ。 生きること、悦ぶこと、 死ぬこと、イクこと…みなつながっているのだろう。 等価交換でない贈与による気持ちのやりとり… ボクには、それが、たいそう美しく、心地よいものに思われた。 それは、見返りを求めぬ愛? 恣意的な誤読と知りつつ云えば… かくして報われぬ「ウェルテル」は、縄文的に幸福であったと感じたのだ。
Posted by
いろんな宗教の形を借りるようなふりしている日本人の心の奥底には自然への思いがある。親しみ、感謝、畏れ。自分は神社仏閣が好きだと思っていたけれどやっぱり基本は自然に対するそういった感情がある。
Posted by
音楽家の坂本龍一と、人類学者の中沢新一が国内の「聖地」を旅行して、対談。 会話は資本主義とか原発に言及したり、「人の生き方について」が主。 それと縄文時代の生き方との比較とか。 お互いに縄文的な何かから着想を得て作品や本を作ったことがあるようで、その話も。 2人のファンか、歴...
音楽家の坂本龍一と、人類学者の中沢新一が国内の「聖地」を旅行して、対談。 会話は資本主義とか原発に言及したり、「人の生き方について」が主。 それと縄文時代の生き方との比較とか。 お互いに縄文的な何かから着想を得て作品や本を作ったことがあるようで、その話も。 2人のファンか、歴史の流れに詳しかったら より楽しめたのかも。 残念ながらほぼ無知識だったので分からない単語が多く、知っている前提で会話が進むので 意味の分からない箇所が結構あった。 それを抜きにしても 会話の面白さは伝わってきたので良いのですが。 所々で挟まれる写真がなかなか良くて、「1000年前の椿の木」を根の苔むした部分のみ写している所なんか好きなセンスでした。
Posted by
装丁は柔らかでふんだんに差し込まれる写真は美しい。 坂本龍一と中沢新一の対談で綴られるが、話そのものはずっと読んでると飽きてきたり、意識が飛んじゃったりしてしまう。 だけど、ところどころ興味深く、特にこの本が311以前に書かれているのに、今後のことを示唆しているような、そんなくだ...
装丁は柔らかでふんだんに差し込まれる写真は美しい。 坂本龍一と中沢新一の対談で綴られるが、話そのものはずっと読んでると飽きてきたり、意識が飛んじゃったりしてしまう。 だけど、ところどころ興味深く、特にこの本が311以前に書かれているのに、今後のことを示唆しているような、そんなくだりがあると少しどきっとする。
Posted by
2010年に出版された「縄文聖地巡礼 坂本龍一・中沢新一」の対談は、2004年から2006年にかけて、二人が9・11以降の「圧倒的な非対称」:貧富の格差拡大と富の偏在してしまった世界。貨幣と言う単一価値基準が世界と人心を席捲する現在の課題、グローバリズム、あるいは資本主義の意味を...
2010年に出版された「縄文聖地巡礼 坂本龍一・中沢新一」の対談は、2004年から2006年にかけて、二人が9・11以降の「圧倒的な非対称」:貧富の格差拡大と富の偏在してしまった世界。貨幣と言う単一価値基準が世界と人心を席捲する現在の課題、グローバリズム、あるいは資本主義の意味を、3000年~13000年前の縄文と呼ばれている時代の先人達の遺跡を巡りながら、自然と共生してきたその文化を感覚として体験し、日本の再発見と未来を探す二人の思索記録だ。 三内丸山遺跡・諏訪・敦賀・若狭・奈良・紀伊田辺・青森・・全国の縄文遺跡とともに青森県六ヶ所村・敦賀、美浜原発・・『原発には本来の意味でのサクリファイスがない、自然からエネルギーを強奪して消費するだけで、人間から贈与しないんだから。非対称なんですね』(坂本)『美浜原発のすぐそばの浜辺では、みんな楽しそうに海水浴してましたけど、あれを見て異様な風景だと思う半面、一神教の神様の前でみんなが幸せそうにお祭りしているのと同じ印象を受けたんです。核技術を生み出した近代科学と一神教のあり方とはよく似ています』(中沢)『一神教は矛盾、あるいは中間項を許さないから、それをつきつめれば核まで行ってしまう』(坂本)フクシマ原発事故の5年前にこの、対談で二人の語った原発・核技術への危惧。この国・世界の未来への想い・・・3・11を迎えてしまった今、この対談は、未だに「おちゃらけて生きている大人達」への痛烈な弔辞なのだろう。中沢氏の「アースダイバー」や「緑の資本論」「森のバロック」と併せ読むことをお勧めする。
Posted by
- 1
- 2