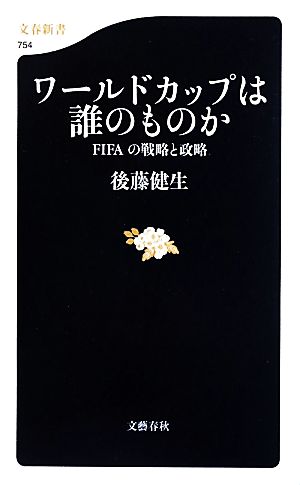ワールドカップは誰のものか の商品レビュー
何故に南アフリカでワールドカップが開催されたのか。政治的介入、どす黒い権力闘争など、知られざる舞台裏にスポットを当てるとともに、南アフリカの歴史を紐解きながら開催の意義について問い直す。このほか日韓同時開催、これまでのワールドカップの開催の経緯も記されており興味深く読んだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 全世界の注目を集めるサッカーの祭典・ワールドカップ。 しかし、華やかなピッチの舞台裏では、さまざまな利権がうごめき、あまたの軋轢が生じてきた。 独裁者の介入、国家の政治的思惑、FIFAの権力闘争…。 その歴史を紐解きながら、ワールドカップのあるべき姿を考える。 [ 目次 ] なぜ南アフリカが選ばれたのか 第1部 ワールドカップと政治(独裁者たちの介入;FIFAの思惑と権力闘争;韓国側の野心が生んだ日韓共催) 第2部 南アフリカ開催の意義(スポーツによる国民意識の形成;南アフリカスポーツの苦難の歴史;黒人サッカーの歴史とワールドカップ) ワールドカップ開催の意義 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
国際サッカー組織内外の勢力争いの歴史の解説は面白い。 一方で日韓共同開催に持ち込まれた経緯など見ると、相変わらず日本には戦略がないのがわかる。 話はまるで変わるが、国際映画祭での「政治」をまとまって解説してくれる本はないかな。断片的には耳に入っているのだけれど。
Posted by
10/31:後藤さんの本だ。とあまり考えず手にした。中身は結構衝撃的な内容で、フットボール文化の普及や世界平和を願ったようなFIFAであるが、アヴェランジェから利益や政治的な手段としてワールドカップがつかわれるようになったとさ、とプレイヤーのがんばりとは別の世界での黒い世界がある...
10/31:後藤さんの本だ。とあまり考えず手にした。中身は結構衝撃的な内容で、フットボール文化の普及や世界平和を願ったようなFIFAであるが、アヴェランジェから利益や政治的な手段としてワールドカップがつかわれるようになったとさ、とプレイヤーのがんばりとは別の世界での黒い世界があるのだなと。鄭夢準(チョンモンジュ)が現れて、2002年が共同開催まだ引きずり込まれるところとか悔しいよ。今の産業(半導体、テレビ、携帯電話、新幹線等)のグロバルへの展開でも如実に現れているけど、国としての機敏さが日本と韓国とは決定的に違うよね、悔しいけど。歴史と市場の大きさが違うといえばそうだけど、食われますよ。 後藤さんはフットボールだけの人だと思っていたけど、文章や経歴をみると国際文化や歴史にも明るいのですね。素晴らしいことだ。しかし、後半の南アフリカのサッカー事情については余計だった。あまり知りたい情報ではないですね。
Posted by
後藤健生「ワールドカップは誰のものか」 W杯の歴史と、南アフリカのスポーツの歴史について書かれた本。FIFAの内情を暴くような本を期待していたので退屈だった。 序章 「なぜ南アフリカが選ばれたのか」 p16 ・ブラッター会長が南アフリカの開催にこだわったのは、会長選挙の時、ア...
後藤健生「ワールドカップは誰のものか」 W杯の歴史と、南アフリカのスポーツの歴史について書かれた本。FIFAの内情を暴くような本を期待していたので退屈だった。 序章 「なぜ南アフリカが選ばれたのか」 p16 ・ブラッター会長が南アフリカの開催にこだわったのは、会長選挙の時、アフリカと南米に票を入れてもらったから。 1章 「ワールドカップと政治」 p33 ・1934年のイタリアW杯の二回戦の対スペイン戦はレフリーにもプレッシャーがかけられていて、史上まれに見る大荒れの試合になった。翌日再試合が行われたが、そちらも大荒れだった。 ・イタリアにあるスタジアムはイタリア在住のイギリス人が建てたものが多いので英語の名称が使われているものが多い。例)「ミラン」というのはミラノの英語読み。 p45 ・アルゼンチンではサッカー選手や監督が政治的な発言をするのは当たり前の事。 ・アルゼンチンの軍事政権は経済的危機にあったペルーに圧力をかけたと言われている。その結果、アルゼンチン対ペルーの試合は6−0でアルゼンチンが勝利し、試合の翌日には、ペルーに向けてアルゼンチンから物資を乗せた船がたくさん出港した。 2章 「FIFAの思惑と権力闘争」 p51 ・アルゼンチンは経済的にイギリスに支配されていた為、多くのイギリス人がアルゼンチンに住んでいた。その関係でサッカーが盛んになった。 ・ブラジルはアルゼンチンの攻撃に耐える為に4バックを考えだしたと言われている。 3章 p69 ・W杯を日本でやるためには、日本サッカーのレベルをあげなくてはならない。その為にはプロ化する必要がある。プロ化するためには各地にスタジアムをつくる必要がある。W杯を行う為にはスタジアムが必要、と。Jリーグの発足とW杯の誘致は車の両輪のようなものだった。 p83 ・日本と韓国の同時開催をする上で運営方法でモメ、ブラッター会長が「二度と共同開催はしない!」と発言した。 4章 「スポーツによる国民意識の形成」 p96 ・アフリカの国境は、植民地支配をしていたヨーロッパ人達が勝手に線を引いた為に国単位でみると民族がバラバラになってしまい、自分達は「◯◯人」だという意識が低くなってしまった。その低い国民意識を強くする為に必要なのがスポーツで、同じユニフォームを着た複数の民族が一緒に闘う事で国民意識を強める事を狙い、成功している。 5章 「南アフリカスポーツの苦難の歴史」 p112 ・オランダで盛んなプロテスタントはカトリックに比べ娯楽に否定的なので、オランダに支配された国はスポーツがあまり流行らなかった。 6章 「黒人サッカーの歴史とワールドカップ」 p153 ・白人に支配されていたアフリカ人にとって「サッカーなら白人に勝てる」という感情は強いインパクトを与えた。 終章 「ワールドカップ開催の意義」 p162 ・フランスのインテリ層ではサッカーを嫌う人が多く、国内リーグの観客動員数は他のサッカー大国に比べて少ない。1998年のフランスW杯開催1年前でも、フランス開催を知らない人すら多かった。
Posted by
後藤健生氏による書き下ろし。 今回2010年は南アフリカでW杯が開催されたのだが、それにまつわる招致の関係やFIFAの戦略。アフリカのスポーツ史など、内容は多岐に渡る。 歴史的記述が多いので、個人的にはちょっと退屈な場所もあった。 でも、FIFAのW杯開催における戦略は大変...
後藤健生氏による書き下ろし。 今回2010年は南アフリカでW杯が開催されたのだが、それにまつわる招致の関係やFIFAの戦略。アフリカのスポーツ史など、内容は多岐に渡る。 歴史的記述が多いので、個人的にはちょっと退屈な場所もあった。 でも、FIFAのW杯開催における戦略は大変示唆に富んでいる。 日韓はFIFAの中でも大成功の大会。 開催場所には理由や正当性が必要である。 本書で残念なのが、本書のタイトルの帰結がはっきりと書いてはいないこと。 まあ、一概に言えないこともあるけれど、日本の2022年の招致のために…という締めはいかがなもんだろ。 ☆3.5だけど、ないので、四捨五入。
Posted by
ワールドカップ招致の裏側に迫るドキュメンタリー、と言いたいところですがこれではトリビア本どまり。人の情念を感じない。
Posted by
なぜ、今回のワールドカップは南アフリカに決定したのか。そのあたりの事情をワールドカップ、南アフリカ双方の歴史から考える。そのついでに過去のアメリカ、日韓共同開催となった裏事情などにも触れる。 正直、南アフリカのスポーツ史を延々と解説するところは退屈だけど、読みどころは過去のワー...
なぜ、今回のワールドカップは南アフリカに決定したのか。そのあたりの事情をワールドカップ、南アフリカ双方の歴史から考える。そのついでに過去のアメリカ、日韓共同開催となった裏事情などにも触れる。 正直、南アフリカのスポーツ史を延々と解説するところは退屈だけど、読みどころは過去のワールドカップにおける各国の圧力と、それを調整するFIFAの柔軟性。 ワールドカップとは、サッカーを競う場でもあり、政治力を競う場でもあるのだ。
Posted by
- 1