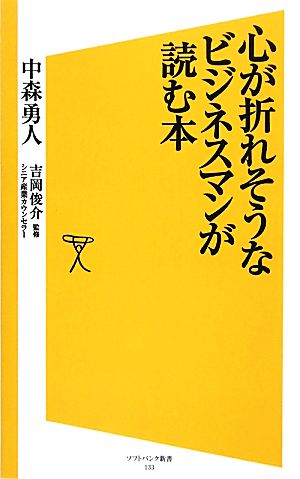心が折れそうなビジネスマンが読む本 の商品レビュー
「チェンジやチャレンジはほどほどに」「閉鎖的な職場ではちっぽけな正義感なんてなんの役に立たない。見て見ぬ振りをすることも必要」
Posted by
◆ 「あなたがいなくても会社は回る」という言葉で少し気持ちが楽になりました。 ◆ 環境が変わりいろいろなプレッシャーがかかる中、落ち着くきっかけの一つになりました。 ◆ ただかなりアクティブな方なので、少しシンクロしづらい部分はありました。
Posted by
あなたの代わりはいくらでもいる コインを入れると働くロボット 家族にとってはあなたの代わりはいない おだやかに、しなやかに、したたかに働くことがこれからのビジネスマンに求められるスキル うつ病 100万人 生涯で15人に1人がかかる国民病 入社時 測定機器の設計エンジニア→3...
あなたの代わりはいくらでもいる コインを入れると働くロボット 家族にとってはあなたの代わりはいない おだやかに、しなやかに、したたかに働くことがこれからのビジネスマンに求められるスキル うつ病 100万人 生涯で15人に1人がかかる国民病 入社時 測定機器の設計エンジニア→39歳で課長代理 プログラミングスキルは新入社員以下→マニュアルを買い読み漁り→頑張っても差は開く一方→焦り、プレッシャー、傷つくプライド、将来の不安、寝不足、疲労の蓄積 布団で一日、気が付くと夕方→抑うつ状態→会社退職→再就職失敗、離婚 →心が折れそうなときは我慢せず、専門家へ 気分が落ち込む抑うつ→うつ病が発症するスイッチはさまざま(左遷、離婚、栄転、出産…) 年度末、中間期の忙しさから解放→4月10月はホッとして緊張の糸が切れる 昇進うつ→今までは悪役上司がいたが自分が上司になった きつい言葉→夫婦からの言葉は蓄積→☆対処法を考えておく 最低でも2週間に1度はガス抜きする習慣→仕事中毒になっていないか? うつ病は精神科医やカウンセラーでもかかる病気 自分はかからないとの根拠のない自信をもたないこと☆蛇に噛まれない体質なし・かぜのウイルスに接すれば罹患、接しなければ罹患せず うつ病のことを知っていたことで救われた→☆体験談を読んでおくこと 職場の嫌なヤツ、苦手な人→使ってやるくらいの大胆な気持ち 左遷 少し前までは寝る間も惜しんで仕事→急に暇、働く人を尻目にそっと定時退社→将来の不安を掻き立てたりした→仕事と関係ないところで自分磨き 階段も人生も踊り場がなければ次のステージに上がることができない。 チェンジ、チャレンジ→サラリーマンは22歳から65歳までの43年間働く=チェンジ、チャレンジしていたら体がもたない→見るだけにすること 上司の評価=さじ加減 自分の評価が気になりびくびく 部下に対しても気持ち良い拍手や応援をできない リストラ問題で会社と戦う姿勢→メルマガ、出版社へ企画 ライターズネットワーク 大人の寄り道 気分転換になるようなお店 一人で舌鼓 プチ贅沢 讃岐うどん研究家 木田武史 アフター5食べ歩き 讃岐手打ち釜たけうどん 朝方 朝は気持ちを安定させるセロトニンが太陽を浴びて活性化 1冊200頁1カ月 朝6時起床、パジャマのまま1時間パソコン→プリントアウトし通勤電車でチェック→昼休み、昼食中にリライト→帰りの電車で次の日の原稿アイディアメモ→帰宅後、晩飯、風呂、就寝→翌朝、メモをもとに原稿 朝から通勤電車で眠むり疲れている人→会社でもシャキッとするのに時間がかかるだろう→早起きは健康とお金に雲泥の差 コカコーラの赤いベンチ→そこに行くとアイディアが浮かんできた→心のよりどころを持つこと 三方よし 近江商人 高島屋、西武、東レ、ワコール、日本生命 近江商人の流れ 週末の達人 小石雄一 全国人脈作りフォーラム あなたがいなくても仕事は回る 松井「不動心」自分がいなくてもヤンキースが勝ち続けた。自分の代わりはいくらでもいるという現実も真摯に受け止める必要があった。 スポーツ選手 体のやわらかさ ビジネスマン→しなやかな体、おだやかに、したたかに 組織や上司とどうしたらしなやかに付き合うことができるか?どの程度の距離をもって接するのがいいのか?→気持ちが楽になった したたかに→上司の意向を盛り込む。 内部告発、社長へ直訴→閉鎖的な職場ではちっぽけな正義感なんて何の役にも立たない。→むしろ見て見ぬふりをするほうが身を守る手立てになる。 仕事がはかどるから休日も会社へ→自信がなく常に将来への不安→将来の安定や豊かさは永久にやってこない 転職は在職中にせよ→会社の人事担当者のチェックするポイント 米国の富裕層 医者と弁護士と会計士の友人→頼れるブレーンをもつこと ☆法テラス利用方法確認 カウンセラー→うつ病になってからではネットで検索すらできない→早めに探しておくこと うつ病→会社に迷惑、ストレスがない法がいいと判断→会社退職→休業補償なし→経済的苦境→うつの長期化 ニューロンの連結部分 シナプス間で神経伝達物質が不足→ストレス、ショックが原因 雑誌の取材で嬉々として将来を語っている人を前に→苛立ち、怒り→空気氷つく→自分では気づかず うつ病はある日、突然に→自分の精神力を過信しない
Posted by
心が折れる、というか、仕事柄数字を気にしなくてはならない人間だもんで、まあタイトル買い。 激務と家庭不和のために鬱病になったという作者らしいのだけれど、 「へ~、ふーん、そー。で?」 という感想。 ・一つ所にいるとなにかあったときに大変だから、外の人たちとのパイプをつくる ・...
心が折れる、というか、仕事柄数字を気にしなくてはならない人間だもんで、まあタイトル買い。 激務と家庭不和のために鬱病になったという作者らしいのだけれど、 「へ~、ふーん、そー。で?」 という感想。 ・一つ所にいるとなにかあったときに大変だから、外の人たちとのパイプをつくる ・自分の存在を気にかけてもらうためにインパクトのあることをする(名刺を複数持つ、など) ・とりあえずヤバくなったら休め まあ現状終身雇用なんて夢のまた夢だし(莫大な利益を上げている人を除く)、外へのパイプに関してはそらそうだよなあとは思いつつも、本当にヤバくなったら休めというけど簡単に休めないから病むんじゃないのか、と。 インパクトをもってして自分のことを記憶の片隅にでも、というのも理解はできるのだけれど、まるで浮気性の人間みたいに見えなくもない。 この会社よりいいところがあったらそりゃ行きますよというのはだれしもが思うことだろう。 ただ、そういった人間が現状より高みに登れるのか?というと、若干の謎が残る。 だって、不満があるのに今の会社に身をやつせなんて言われたって、面倒って思うだけでしょう? 自分がいなくても会社が回るのは、そうでなければ利益だって出せないし、ひと一人いないだけで立ち行かなくなるのならば遅かれ早かれその会社は……、ともいえる。 だから、自分がいなくても、というのはちょっと違うのではないかと思う。 頑張る、と、頑張らない、の境目はとても曖昧なもので、断定してはいけないのではないだろうか。
Posted by
読み物としてはおもしろく、あっという間に読めました。ただ、実感は何も惹き起こされませんでした。ワークとライフをきっちりと2分して、仕事がきつすぎるときは、しなやかに調整を入れていこうといっても。。。かえってこういった責任感の認識が「うつ病」リスクなのかもしれないのですが。
Posted by
心が折れるような経験は、誰しも多かれ少なかれあるだろうとは思います。私自身、仕事で思うような成果が出なかったり、大きなミスをしてしまったりして心が折れそうになったことはあるし、(10年近く前ですが)その結果で体調を崩して2か月ほど休職したということもあります。 とはいえ、自分の経...
心が折れるような経験は、誰しも多かれ少なかれあるだろうとは思います。私自身、仕事で思うような成果が出なかったり、大きなミスをしてしまったりして心が折れそうになったことはあるし、(10年近く前ですが)その結果で体調を崩して2か月ほど休職したということもあります。 とはいえ、自分の経験に比べれば著者のほうがずっと波瀾万丈の生き方をしてきていますし、本にできるだけのことはあります。ただ、その分読者は自分のこととしてとらえられなくなって参考になりづらかったかもしれないし、自分事としてとらえてしまうと余計に心が折れる気分になったかもしれません。自分も、読んでいてつらい思いにさせられたところが何か所かありました。 フルタイムで雇用されていれば、1週間168時間の半分くらいは(通勤や休憩も含めて)勤務先に拘束されている、言い方を変えれば仕事に関わっているといえます。だから仕事で心が折れるような事態を避けるには、仕事そのものをポジティブにとらえていかないとならないでしょう。ワークライフバランスが叫ばれていますが、これは仕事以外の部分を軽視しすぎた反動で生まれたものであり、仕事が苦痛であるという前提があるのは違和感を持ちます。 話がそれましたが、自分に与えられた仕事をポジティブなものにする方法はいくつかあります。まずは与えられた仕事の意味を理解すること。私たちはロボットではなく、感情を持つ人間ですから、なぜその作業が必要なのか、いつまでに成果を出さなければならないのか、理解すればモチベーションにもなるし目標にもなります。「理由など説明する必要はない、いいからやれ」などという上司や経営者は今でもいるのでしょうか。いるとするなら、成果への障害となっているので改善を求めるべきでしょう。 もうひとつは、相手の立場からものを見てみること。ひとつの仕事には様々な利害関係者がいます。指示を出す上司もそうですし、顧客や取引先も成果物を享受する立場です。1つ目の話ともつながりますが、相手の立場から与えられた作業を見れば、なぜ自分がそれをする必要があるのかが見えてきますし、自分がそれをうまくやれば、あるいは逆に失敗すれば、誰にどんな影響があるのかも見えてきます。 上司が口うるさいのも理由があります。それは仕事を順調に進めるために必要なことを知らせてくれているのかもしれないし、自分に対する期待の大きさなのかもしれません。また、顧客を喜ばせるために何をすればいいのかという考え方から、気配りや改善も生まれてきます。これらは自分の立場からものを見ているだけでは決して気づかないし、気づいたとしても小手先のテクニックであって応用が利かないものになってしまいがちです。 本書で残念だと思ったのは、そういった他者の視点がなく、自分がうまく立ち回っていくためにどうすればよいか、という話に終始しているところです。著者は会社に疎まれ、追われた経験や、事業を立ち上げたときには資金を持ち逃げされた経験があるわけで、社会を信用できないと感じているのかもしれませんが、やっぱり何か違うよなあ、というところです。 仕事や自分を客観的、相対的にとらえること。そして逆に心が折れる行動、たとえば会社を休んだり辞めたりするのではなく、いつも通りの行動を積み重ねていくうちに時間をかけて気持ちを立て直していくことが、心を折らないためにとるべきなのではないでしょうか。
Posted by
タイトルでは「折れそうな」ですが、 実際に「折れた」方が著者です。 昨日の今井氏の著書 同様に経験者が語る内容ですので 真実味たっぷりです。 その中でも 「社外のパイプをつくり、いざというときには頼れる仲間をつくろう」 というところが、昨日の今井氏の著書と重なりま...
タイトルでは「折れそうな」ですが、 実際に「折れた」方が著者です。 昨日の今井氏の著書 同様に経験者が語る内容ですので 真実味たっぷりです。 その中でも 「社外のパイプをつくり、いざというときには頼れる仲間をつくろう」 というところが、昨日の今井氏の著書と重なりましたね。 社内ではなく、 利害関係が少なくなる社外での人間関係構築に力をいれましょう。 ってことなんですよね。 もちろん家族も大切ですが、肉親以外でも利害関係抜きで頼れる仲間がいると さらに強くなれるってことだと思います。 自分で言うと大学時代の親友なんかが、ばっちり当てはまりました。 大学時代の親友と遠く離れていても、いろいろバカ話をしたりする関係が 今もなお続いているからこそ、自分は強く生きているのだと感じます。 みなさんはどうでしょうか。
Posted by
(2010年10月5日より読書開始) 自らの闘病経験を交えて書かれた「頑張り過ぎない生き方」への指南本。 自己啓発本にありがちな「社外に人脈を」とか「複数の名刺を持て」という記載もポジティブな観点からではなく、有事の際のセーフティーネットの観点から書かれているのが面白かった。...
(2010年10月5日より読書開始) 自らの闘病経験を交えて書かれた「頑張り過ぎない生き方」への指南本。 自己啓発本にありがちな「社外に人脈を」とか「複数の名刺を持て」という記載もポジティブな観点からではなく、有事の際のセーフティーネットの観点から書かれているのが面白かった。 ただ、記載の多くが自らのデビューのきっかけとなった前の会社での事となっており、実際の「折れて」しまった独立後の記載が薄かったり、「ゴミ箱を漁った」という表現も、そのインパクトと比較して記述量が少なく、やや不満が残った。 予め手許に用意しておいて、実際に「折れそう」になる前に読むのがよいのではないだろうか。
Posted by
昨年から、結構心が折れそうな場面が多く訪れております。最近はようやくそんな状況に慣れてきたかな、って感じですが。なれるというのは本当にいいことなのか、よくわかりません。気持ちの整理がしたくて、本書に目をつけてました。立ち寄った書店になかなか無くって、ようやく購入できました。
Posted by
うつ病になった筆者が題の通りに「心が折れそうなビジネスマン」へ経験談とメッセージをつづった本。 本屋でこの本に目がとまった人 = まさに心が折れそうな人は、ぜひ読むべき本だと思う。 内容は、いってしまえばありきたりで ・がんばりすぎない ・あなたがいなくても会社は回る ...
うつ病になった筆者が題の通りに「心が折れそうなビジネスマン」へ経験談とメッセージをつづった本。 本屋でこの本に目がとまった人 = まさに心が折れそうな人は、ぜひ読むべき本だと思う。 内容は、いってしまえばありきたりで ・がんばりすぎない ・あなたがいなくても会社は回る ・「うつ」のサインに早期に気付いて手を打とう なのだが、 左遷、リストラ、起業、果ては借金地獄でのゴミあさりまで経験した筆者の体験に基づく暖かいメッセージは、すでに病気のせいで思考が凍りつきかけた「うつ」あるいは「抑うつ傾向」の人の心にも届くかもしれない。 いや、実際、すでに「うつ」になってしまった人に、「治療しなくては」という考えを持たせるのは大変なことも多いので。
Posted by
- 1
- 2