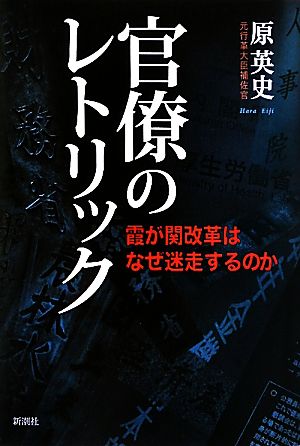官僚のレトリック の商品レビュー
いやもう、官僚の「酷さ」は色々と見聞しているけども、酷いもんだ。法案でも答弁でも、ちょっとした言葉の端々に罠を仕掛ける。省益優先と言われてもしょうがないね。 筆者が、特に本の最初の方で何度も、高い志を持って仕事をしている人が大半で身の回りにもたくさんいると書いているのが余計そら寒...
いやもう、官僚の「酷さ」は色々と見聞しているけども、酷いもんだ。法案でも答弁でも、ちょっとした言葉の端々に罠を仕掛ける。省益優先と言われてもしょうがないね。 筆者が、特に本の最初の方で何度も、高い志を持って仕事をしている人が大半で身の回りにもたくさんいると書いているのが余計そら寒い。 この本は民主党政権の時に書かれてるので、出だしは悪くなかったけど、天下りにきちんと手を打てなかったことから、政治主導がつまづいたことを分析している。 官より政の主導がなんでいい?かと言えば、それは選挙で結果が出るからだと書いてるが、まさにその通りになったのね。 この頃は民主党もちゃんと、政策の勉強とかやってたらしいわ。 最近ネットではもてはやされている麻生さんだが、あんまりいい印象がなかった理由も思い出した。
Posted by
古賀茂明氏の著書に登場した人物であったので期待して読んだが、古賀氏に比べるとやや驕りが感じられる気がしたのは私だけだろうか。 官僚にまともに働いてもらうためには、それなりのインセンティブを働かせる仕組みが必要だというのが本書の主張だと解した。 もちろん、民間的な発想としては、常識...
古賀茂明氏の著書に登場した人物であったので期待して読んだが、古賀氏に比べるとやや驕りが感じられる気がしたのは私だけだろうか。 官僚にまともに働いてもらうためには、それなりのインセンティブを働かせる仕組みが必要だというのが本書の主張だと解した。 もちろん、民間的な発想としては、常識的でまともななことを述べているのだが、官僚の働き方・考え方が染み付いていて、節々にそれが垣間見れ、どうも馴染めなかった。 それにしても、渡辺喜美氏が古賀氏の著書に引き続き登場したが、なかなかの人物だ。2世議員で親も親だし全く共感できなかったのだが。
Posted by
[細密な楼閣との暗闘]第一次安倍政権から議論が活発化し、民主党政権が政権交代の目玉とした「霞が関改革」。国民の大きな支持を得たたものの、霞が関を頂点とする官僚たちの前に大きな改革には至らなかったとされるこのテーマを基に、政治家と官僚の扉隔てた先での暗闘、そしてそこから学ぶ公務員改...
[細密な楼閣との暗闘]第一次安倍政権から議論が活発化し、民主党政権が政権交代の目玉とした「霞が関改革」。国民の大きな支持を得たたものの、霞が関を頂点とする官僚たちの前に大きな改革には至らなかったとされるこのテーマを基に、政治家と官僚の扉隔てた先での暗闘、そしてそこから学ぶ公務員改革の今後の展望を綴った作品です。著者は、自身も行革大臣補佐官として公務員改革に取り組んでいた原英史。 政治というものがすなわち言葉をめぐる駆け引きであることを痛感させてくれる一冊。それ自体の善し悪しはひとまず置いておいて、まずは官僚という存在がどのようにして物事を動かしているのかというのを知る上で非常に有益だと思います。霞が関改革というただでさえ内々な話を、そのさらに深奥から関わっていた人物が書いているんだから新鮮な知見が得られないはずがない。 また表題にもあるように、官僚が持ち出してくるレトリック(修辞)の数々には、その世界に触れたことがない人ほど唖然とさせられること間違いなし。民主党が唱えた「政治主導」がこのレトリックの前に敗れ去っていく姿が本書では描写されているのですが、このレトリックに勝る言葉を持てなかった、そしてレトリックのつけ入る隙を与えたところにその迷走の源流はあったように感じられます。 〜「脱官僚」の迷走の裏側には、鳩山内閣のできていなかったことが横たわっていた。「司令塔を作る」、「官僚機構の手綱を握る」。この二点を怠った(あるいは先送りにした)ことは、致命的な失敗だったのだ。〜 立場上、レビューが書きづらい本なんですが☆5つ
Posted by
民主党政権下で、かつ、東日本大震災前の本で、今更感もありますが、読んでみてまだまだ参考になる、と思いました。色々な意味で。
Posted by
第1次安倍内閣から麻生内閣までの公務員制度改革の失敗の経緯をインサイダーの立場から検証し、民主党政権の「脱官僚」がなぜうまくいかないかを分析している。公務員制度改革などの動きに反対し、それらを骨抜きにする官僚側の論理=レトリックがどういうものかがよくわかる。しかし、官僚側の論理に...
第1次安倍内閣から麻生内閣までの公務員制度改革の失敗の経緯をインサイダーの立場から検証し、民主党政権の「脱官僚」がなぜうまくいかないかを分析している。公務員制度改革などの動きに反対し、それらを骨抜きにする官僚側の論理=レトリックがどういうものかがよくわかる。しかし、官僚側の論理にも一理あるのは確かで、それをレトリックだと一蹴する本書の論調には少し疑問も感じた。
Posted by
官僚でも優秀な人はいるということはあるのでしょうけど。難しいことや分かりにくいことを、わかりやすく説明したり解決するのが「頭のいい人」だと思ってます。分かりにくいことをことさらの分かりにくくしているのは決して頭のいい人たちのやることではないと思います。そういう意味で、個人的な見解...
官僚でも優秀な人はいるということはあるのでしょうけど。難しいことや分かりにくいことを、わかりやすく説明したり解決するのが「頭のいい人」だと思ってます。分かりにくいことをことさらの分かりにくくしているのは決して頭のいい人たちのやることではないと思います。そういう意味で、個人的な見解ですが、官僚は頭のいい人たちとはいえないな。と、思いました。わざとやっているでしょうけど、それは「悪知恵」というものだと思います。
Posted by
著者は元官僚。見事なまでの欺瞞に満ちた霞が関修辞学を白日の下に晒す。官僚に操られている政治家の実態も赤裸にされている。政治主導の暴走と迷走に明け暮れる民主党。自民党が霞ヶ関改革に敗北した経緯も非常に興味深い。最後に脱官僚のための五カ条がささやかながら示されているが、これも徒花なの...
著者は元官僚。見事なまでの欺瞞に満ちた霞が関修辞学を白日の下に晒す。官僚に操られている政治家の実態も赤裸にされている。政治主導の暴走と迷走に明け暮れる民主党。自民党が霞ヶ関改革に敗北した経緯も非常に興味深い。最後に脱官僚のための五カ条がささやかながら示されているが、これも徒花なのか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2012/02/03:読了 ざっと読み。 官僚の意図的なサボタージュや政治家の方針を テクニカルにつぶす方法が記載されている。 あまり、興味がわかなかった。 政治家の意図を曲解するような語句を、本来の文書に 潜り込ませて、あとから政治家が気がついても、 あとの祭り。もし、軌道修正しようとしても、あのとき ああ言ったのに、撤回するのかと、マスコミや野党に 言わせるなど... 読んでいて、そういう人も、そういう人が上にいる国も、 なんだか、悲しくなるような内容。
Posted by
安倍~鳩山政権までの「脱官僚」施策を網羅。独自の修辞学を駆使する官僚が、抵抗勢力として描かれている。最後に脱官僚実現の五箇条が記されているが、これは筆者が特別顧問を務める大阪市でモデル的に実践されているもよう。
Posted by
なぜか最近よく読んでいる「公務員制度改革」関連の一冊で、渡辺喜美氏の補佐官をしていた方の回顧録。公務員制度改革が叫ばれた歴史は長く、古くは池田勇人内閣時代にも似たような提言がなされていたようで、読んだ限りでは今の民主党のやろうとしていることはむしろ後退しているように見える。 散々...
なぜか最近よく読んでいる「公務員制度改革」関連の一冊で、渡辺喜美氏の補佐官をしていた方の回顧録。公務員制度改革が叫ばれた歴史は長く、古くは池田勇人内閣時代にも似たような提言がなされていたようで、読んだ限りでは今の民主党のやろうとしていることはむしろ後退しているように見える。 散々な言われようだった安倍内閣があのまま続いていたらより攻めた法案が通っていたかもしれないと思うと、民主主義とかジャーナリズムとかって何なのだろうと思わなくもない。 もっとも、一説にはだからこそ霞が関の徹底的な反抗にあってネガティブキャンペーンが打たれて倒閣されたという話もあるし、「どっちにしろ渡辺も中川秀直も所詮ポーズ」という話もあるし、実際のところはよく分からない。
Posted by
- 1
- 2