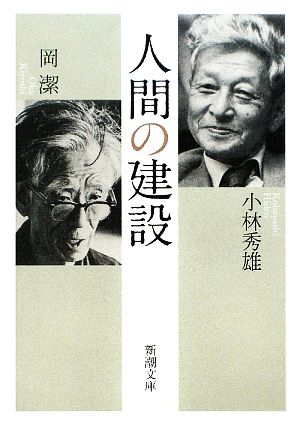人間の建設 の商品レビュー
おすすめ。 #興味深い #考えるヒント 書評 https://naniwoyomu.com/30721/
Posted by
話の内容について、さすがに古いと思う所もあるけれど、難しい蘊蓄や専門用語も余りなく、真摯に深いところを探るような対談で面白かった。 真面目に様々な事を考えて、哲学の域まで行く人というのはさほどいないと思うし、そこまで行っている両者の対談というのは貴重なものではないだろうか。 数学...
話の内容について、さすがに古いと思う所もあるけれど、難しい蘊蓄や専門用語も余りなく、真摯に深いところを探るような対談で面白かった。 真面目に様々な事を考えて、哲学の域まで行く人というのはさほどいないと思うし、そこまで行っている両者の対談というのは貴重なものではないだろうか。 数学者の岡氏が、情や、情緒というものを大切に思っているというのが意外だった。
Posted by
批評家小林秀雄と数学者岡潔の対談。 今の感覚からするとうーん、と思う部分も多々あるが対談の端々から感じる知性の瑞々しさや柔らかさからはキラキラと光るものも多く感じる。 特に「情緒」≒「直感」の考え方はとても面白く感じた。 あと小林秀雄がどうしても岡潔とベルクソンを引き合わせたい...
批評家小林秀雄と数学者岡潔の対談。 今の感覚からするとうーん、と思う部分も多々あるが対談の端々から感じる知性の瑞々しさや柔らかさからはキラキラと光るものも多く感じる。 特に「情緒」≒「直感」の考え方はとても面白く感じた。 あと小林秀雄がどうしても岡潔とベルクソンを引き合わせたい感が面白かった。
Posted by
「〔岡〕昔の(日本の)国家主義や軍国主義は、それ自体は、間違っていても教育としては自我を抑止していました。だから今の個人主義が間違っている。自己中心に考えるということを個人の尊厳だなどと教えないで、そこを直してほしい。 《中略》 神風の恐しさは見たものでなければわからない《中略》...
「〔岡〕昔の(日本の)国家主義や軍国主義は、それ自体は、間違っていても教育としては自我を抑止していました。だから今の個人主義が間違っている。自己中心に考えるということを個人の尊厳だなどと教えないで、そこを直してほしい。 《中略》 神風の恐しさは見たものでなければわからない《中略》ものすごい死に方をしている。」(p.119) 「〔岡〕私は日本人の長所の一つは、《中略》神風のごとく死ねることだと思います。《中略》 あれができる民族でなければ、世界の滅亡を防ぎ止めることはできないとまで思うのです。」(p.139) 「〔小林〕特攻隊というと、批評家はたいへん観念的に批判しますね。悪い政治の犠牲者という公式を使って。特攻隊で飛び立つときの青年の心持になってみるという想像力は省略するのです。」(p.140) 批評家・小林秀雄と数学者・岡潔の対談。 話題が広範に渡り、無限の知の泉が2つ湧いているかの如く。 岡氏の専門である数学と物理学との関係、ベルクソンと時間概念に焦点を当てた哲学議論、ピカソやゴッホなどの絵画芸術 、ドストエフスキーとトルストイに関するキリスト教とロシア文学論、など。 哲学史や美術史から物理学の簡単な解説まであり、登場人物も多いので、手元に置いておくと、ちょっとした「大人の百科事典」のように使えそうだ。 その中で特に印象的だったものを、ここの冒頭に引用した。 戦後の個人主義とそれを基礎とした教育制度についての問題提議である。 個人主義の反対概念として、特攻のような「自己を捧げる」行動については、バーリンやラインホールド・ニーバーが主張した「(宗教道徳に基づく)自己犠牲の精神」と通ずるものがある。 また、「特攻ができる日本人でなければ、世界の滅亡を防ぐことはできない」という岡氏の言葉は、タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』を想起させた。 世界を救うために自らの命を擲つ2人の男性の物語だ。 近代思想のメインストリームである単純な個人主義礼賛・全体主義批判では、特攻とは若者の未来を奪う許されざる戦法と批判される。 現代の日本では、自分も含めて、そういうパターンがどこかに染みついているが、それは思考停止でもある。 それをずばり指摘した小林氏の、「悪い政治の犠牲者という公式を使って」と言う言葉は、あまりに核心をついている。 この対談の当時、両氏のように問題提議する賢人がいたことは、社会の財産であったと感じた。 「自己犠牲」というテーマは今後さらに掘り下げたい。 この本はたまたま飲みつつ読んだが、知的な肴のおかげで大変良い時間を過ごせた。 茂木健一郎は解説で、本書について、「声に出して読みたい対話」「音楽に似ている」と語っていたが、飲酒で程よく脱力した脳にすっと吸収するような読み方も悪くなかった。 そのような体験を提供してくれる読書は素晴らしい。 酒の肴になるような、知性溢れる本が他にも無いものか、と探してみたくなった。 蛇足であるが読書メモとして、 去年読んだ小林秀雄の『本居宣長』は「失敗作」という評判であることを読後に知ったのだが、本著で小林氏が『本居宣長』執筆のくだりから、 「この頃、仕事をしていて、とんでもない失敗をするかもしれないなと、いつでも思う」 と自ら予告しているのには思わず吹いた。 作家の永井龍男と小林秀雄が友人同士、ということも知り、洒落た2人にもほのぼのした。
Posted by
「知の巨人」同士の対談は、緊張感に溢れている。これを本当に読んでいくには、自分自身にいろいろな蓄積がなければならない。古今東西の古典、そして、それをめぐる思索をいかに巡らしてきたかによって、この対談がどれだけ楽しめるかが決まってくるのであろう。そういう意味で、自分自身ももう少し行...
「知の巨人」同士の対談は、緊張感に溢れている。これを本当に読んでいくには、自分自身にいろいろな蓄積がなければならない。古今東西の古典、そして、それをめぐる思索をいかに巡らしてきたかによって、この対談がどれだけ楽しめるかが決まってくるのであろう。そういう意味で、自分自身ももう少し行くとして、将来もう一回読んでみたい対談であった。
Posted by
批評家の小林秀雄と、数学者の岡潔による、 まさに知の巨人といった2人の対談。 正直難しくてわからない数学の話しもありましたが、理系とか文系とかのベクトルを超越した地点での、高度な知性での対話は、圧倒的で伝わってくるものがありました。 小林秀雄がベルクソンを評価している理由など...
批評家の小林秀雄と、数学者の岡潔による、 まさに知の巨人といった2人の対談。 正直難しくてわからない数学の話しもありましたが、理系とか文系とかのベクトルを超越した地点での、高度な知性での対話は、圧倒的で伝わってくるものがありました。 小林秀雄がベルクソンを評価している理由など、情緒的かつ逸脱を許さない人生観の情が伝わってきて、そういう感覚が岡潔との共通点だと思いました。 キリスト教の不信や資本主義の蔓延、または敗戦からの個人主義の導入によって、民衆の知力の低下を憂う、有意義な対話であると思います。
Posted by
数学者と文章家の歴史的対談。 何かを究めた人たちは畑は違えど、物事に対する考え方、表現の方法が似通うものなのか。 喧嘩のようなやり取りになるかと思いきや、お互いをリスペクトする両者の考えの調和は小気味良い。 理解ができない事柄も多々あるが、再読を繰り返し、歳を重ねながら、理解を深...
数学者と文章家の歴史的対談。 何かを究めた人たちは畑は違えど、物事に対する考え方、表現の方法が似通うものなのか。 喧嘩のようなやり取りになるかと思いきや、お互いをリスペクトする両者の考えの調和は小気味良い。 理解ができない事柄も多々あるが、再読を繰り返し、歳を重ねながら、理解を深めたいと感じる。 茂木健一郎氏の「情緒」を美しく耕すために の締めが秀逸でこの本に相応しい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
友人に勧められて。 小林 …誰でもめいめいがみんな自分の歴史をもっている。オギャアと生れてからの歴史は、どうしたって背負っているのです。伝統を否定しようと、民族を否定しようとかまわない。やっぱり記憶がよみがえるということがあるのです。記憶が勝手によみがえるのですからね、これはどうしようもないのです。これが私になんらかの感動を与えたりするということもまた、私の意志ではないのです、記憶がやるんです。記憶が幼時のなつかしさに連れていくのです。言葉が発生する原始状態は、誰の心のなかにも、どんな文明人の精神のなかにも持続している。そこに立ちかえることを、芭蕉は不易と読んだのではないかと思います。(p.133) ベルクソンの「物質と記憶」にその後言及。
Posted by
薄い本ではありますが、一度読んだだけでは理解できません。とても深い本だと思います。何度も繰り返し読む価値のある本のような気がします。 年齢によっても感じ方は異なるでしょう。 ドストエフスキーやトルストイと言ったロシアの小説家の名前が出てきましたが、まだ私は読んだことはありません。...
薄い本ではありますが、一度読んだだけでは理解できません。とても深い本だと思います。何度も繰り返し読む価値のある本のような気がします。 年齢によっても感じ方は異なるでしょう。 ドストエフスキーやトルストイと言ったロシアの小説家の名前が出てきましたが、まだ私は読んだことはありません。罪と罰や白痴にチャレンジしてみようと思います。 私の故郷、三重出身の本居宣長や芭蕉の話も出てきました。この2人に関する私自身の無知さにも忸怩たる思いです。少しは勉強したいと思う読後感です。
Posted by
面白いが、文理の碩学泰斗が対談していることに価値があるのであってその内容に価値があるかは疑問である。 世の中の中年男性が2人と同じくらい理性的でかつ低俗でないならば、きっと同じような会話をするのだと思う。 もちろんここから何らかのインスピレーションを引き出すこともありうるのだろう...
面白いが、文理の碩学泰斗が対談していることに価値があるのであってその内容に価値があるかは疑問である。 世の中の中年男性が2人と同じくらい理性的でかつ低俗でないならば、きっと同じような会話をするのだと思う。 もちろんここから何らかのインスピレーションを引き出すこともありうるのだろうけど、一読した限りではそれは難しかった。
Posted by