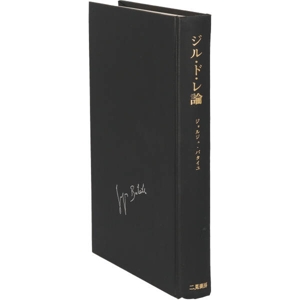ジル・ド・レ論 ―悪の論理― の商品レビュー
バタイユは、ジル・ド・レは狡猾な人間には程遠い愚者であったと結論付ける。 親に放任され、若くして莫大な財産と地位を得た元帥は、聖なる処女のジャンヌ・ダルクの戦友にして、血にまみれた幻夢を現実として彷徨し後世、青髯と異名をとる永続的な怪物であり続ける存在なのだ。
Posted by
ジル・ド・レの悪名の高さは耳にしていたけどこれほどとは思わなかった。もう少し品のあり、独特の美学を持って罪を重ねていたのだと思っていたがそうでもなかった。 理性とは正反対の怪物性を持っていたジル・ド・レはまさにキリスト教に在り方を示しているという点は納得した。どんな罪を犯そうとも...
ジル・ド・レの悪名の高さは耳にしていたけどこれほどとは思わなかった。もう少し品のあり、独特の美学を持って罪を重ねていたのだと思っていたがそうでもなかった。 理性とは正反対の怪物性を持っていたジル・ド・レはまさにキリスト教に在り方を示しているという点は納得した。どんな罪を犯そうとも祈れば救われる、これはキリスト教において人間の暴力性が計算に入っていることを示唆しているともいえる。 特に意外だったのがジャンヌ・ダルクとの関係性。ジャンヌに対して異常なほどの愛を注いでいるイメージだったが、どうやらジャンヌの人気を利用していただけで愛情はなかった。というか人を愛せるはずがないとまで書かれていた。 彼は最恐のサディスティックかもしれない
Posted by
バタイユ著作集の第8巻。訳者あとがきにあるが、フランスにおける歴史的裁判の1つである、ジル・ド・レの裁判。美少年を誘拐し、強姦し殺害を繰り返す。また、莫大な財産を相続したジル・ド・レはそれを惜しげもなく使い、多くの散財をし、借金をした(それがきっかけで最初に書いた強姦事件が発覚...
バタイユ著作集の第8巻。訳者あとがきにあるが、フランスにおける歴史的裁判の1つである、ジル・ド・レの裁判。美少年を誘拐し、強姦し殺害を繰り返す。また、莫大な財産を相続したジル・ド・レはそれを惜しげもなく使い、多くの散財をし、借金をした(それがきっかけで最初に書いた強姦事件が発覚するわけだが)。そして、自らを救うために降魔術におぼれ、その生贄としても子供を殺す。 バタイユはそのような猟奇的な性、また非常識的な悪を体現したジル・ド・レに注目し、その特殊な例から、その悪、エロティシズムを通して、キリスト教を読み説いている。 まず、バタイユはジル・ド・レを悲劇的犯罪者と置く。それは、悲劇が犯罪を根源として生ずるからである、とする。また、ジル・ド・レの行為に対して、行為によって直接得られる快楽よりも、死の働きを眺めることを重視していると、バタイユは分析する。すなわち、普通に言われる、直接的行為としてのネクロフィリアやペドフィリアではなく、第三者としてそれを見ることにより興味を持っていたと考えたのだ(※もちろん、ジル・ド・レ本人が強姦の後殺したケースもたくさんあるが、仮に前者の直接的な行為を好むのであれば、ジル・ド・レが部下たちに子供達を殺させるという事がかなりの数存在するという事実を無視することになるからだろうか。また、バタイユが指摘するように、手足を切断し、内臓を取り出させるという行為を、ジル・ド・レが行った事がそれを論拠づけるのか)。そして、バタイユが指摘する重要な点は、P.17にあるが、「ド・レは最後まで自分は救われるものと思っており」、「悪魔の助けを乞い、悪魔によって自分の財政を立て直しうるものと期待しながらも、彼は最後に至るまで、善きクリスチャンであり信心深い人物であった」ということだ。つまり、彼にとって、救われる事を期待して行った行為であり、彼にとって、これらの事件は罪という意識がなかったのかもしれない、という事だ(事実、彼は裁判の途中から、急に敬虔な活動を行っている)。 で、バタイユがここから推測するキリスト教の重要な点は、そもそもキリスト教は、いかなる犯罪に対しても、赦しを与えるもので、またそもそもキリスト教は赦しを与えるために、犯罪を要請するものだ、ということだ。そもそも、「キリスト教は暴力を計算に入れているのだ」。 これ以後は、ド・レの当時のヨーロッパ世界の状況と、彼の活動、家族との関係などからド・レの活動を読み解いていく。あんまり面白くない笑(上で述べた事の論証だから)。 バタイユを読んでいて、疑問に思うのは(というかまだ理解できないのは)、彼が何を「聖なるもの」と見なしているか、である。P.14にこの記述があるが、イマイチ良く分からないんだよなぁ。あと、訳者が指摘していて、確かに!と思うのは、あんな小説(眼球譚など)を書く小説家でもある、バタイユがジル・ド・レを「嫌悪すべき」、「奇怪な」、「怪物」などと主観的な呼び方をする一方、マルク・ブロッホやホイジンガの論文を引用した客観的な見方をするなど、主観と客観が混ざり合った、不思議な文章になっていることだ。これのおかげで、小説ではないけれども、論文というにはちょっと軽いといった印象を受ける。また、バタイユの新たな一面が見えた本だった。
Posted by
- 1