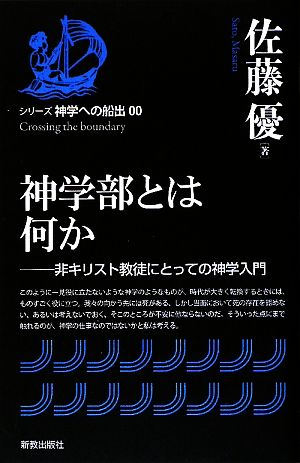神学部とは何か の商品レビュー
神学とは虚学で、現実と具体的関わりを持たない、だから議論はハッキリした結論は出ず。恐ろしいことに、おおむね「敗者が論理的には正しい」という歴史を持つ。教会の東西分裂となった「(三位一体を前提として)精霊は父からか、父とキリストからか?という命題で対立し互いに相手を破門(神の救済の...
神学とは虚学で、現実と具体的関わりを持たない、だから議論はハッキリした結論は出ず。恐ろしいことに、おおむね「敗者が論理的には正しい」という歴史を持つ。教会の東西分裂となった「(三位一体を前提として)精霊は父からか、父とキリストからか?という命題で対立し互いに相手を破門(神の救済の拒否=テロリズム許可)した。ニカイア信条の「子からも」の部分を正教会(東方協会)が削除したとカトリック教会が言いがかりをつけたのだが、のちに文献学が発達すると5,6世紀に挿入された文言であったことが明らかになったが、カトリックは錯誤を認めて謝ったりしない。地動説を放棄したガリレオのように。免罪符を告発したルターのように。 「全能の神を信じる」前提の議論で、「結論が先にある」から迫害されときには命を落とした=普通の社会的意味では負けたほうが「正しい」 佐藤も外務省公金私的流用嫌疑で逮捕拘束されたとき、鈴木宗男の証拠隠滅の恐れで釈放されない(鈴木を告発に回れば自由になれる)取り調べで「それなら釈放されなくていい」513日の拘禁に耐えたのは「神学による訓練があったからこそ」と言っている。 目の前に猛獣が居て吠えたら「恐怖」を感じる。しかしどこかにいる何かの咆哮を聞いたような気がしただけなら「不安」を感じるだろう。(p52)人間はたいてい、日常的には死ぬということを意識していない…しかしわれわれのは確実に死ぬ存在である。そのことを意識した瞬間に、われわれの中に不安が生じる。 (p60)「聖書には、選ばれた者については書かれているが、選ばれない者については何も書かれていない」…決して裁いてはならないのだ。
Posted by
・人間はいつか死ぬ。だから、生きることの意味を知る必要性が出てくる。人間は死ぬときに「自分の人生は何だったのか」と誰もが考えるのである。神学はそのときへの備えになる。
Posted by
神学は虚学!意表を突くスタートなのだが、逆にすべての学問の影に寄り添い、理解を深めさせるもの。非クリスチャンのための本と言いながら難易度は高い。非キリスト教徒にとっての神学はあり得ないが無神論者の神学はあり得るというのは納得。 中世の神学論争「針の上で天使は何人踊れるか」が極めて...
神学は虚学!意表を突くスタートなのだが、逆にすべての学問の影に寄り添い、理解を深めさせるもの。非クリスチャンのための本と言いながら難易度は高い。非キリスト教徒にとっての神学はあり得ないが無神論者の神学はあり得るというのは納得。 中世の神学論争「針の上で天使は何人踊れるか」が極めて重要な論争だった!そして、答えがなく、数百年後にまた繰り返されるとはいかにも神学論争。それを「旅人の神学」(P43)というのだそうだ。P97に紹介される聖書の「カエサルの銘が刻まれた銀貨」の話は今まで気づかなかった視点で目から鱗。著者がモスクワ大学で哲学部科学的無神論学科に飛び込み、教授の半分がキリスト教徒だったとは笑える話。そして経済学部のマル経と近経の逆転も。
Posted by
西ヨーロッパでは、神学部がないと総合大学とは呼べない。神学は全学部の下地になり得る。経済神学、数理神学、歴史神学、医学神学など。 フィリオクエ論争。聖霊は父と子からも発出するか。ニカイアコンスタティのポリス信条では元々、子から、はなかった。 ナチス時代、ドイツ的キリスト者という運...
西ヨーロッパでは、神学部がないと総合大学とは呼べない。神学は全学部の下地になり得る。経済神学、数理神学、歴史神学、医学神学など。 フィリオクエ論争。聖霊は父と子からも発出するか。ニカイアコンスタティのポリス信条では元々、子から、はなかった。 ナチス時代、ドイツ的キリスト者という運動があり、新ナチだった彼らはヘブライ語聖書やパウロ書簡を省こうとした。 1980年代、ソ連にはロシア語があえて下手になるような学部があった。外国人がスパイ活動をしにくくするtsめ。
Posted by
虚学である神学について佐藤先生が解説。 各大学の学部についての説明が丁寧で進路を目指す方は一読されたほうが良いのでは。
Posted by
「私のマルクス」、「はじめての宗教論」でほぼカバーされている内容だけれども、進路に悩む高校生向けとして大変親切な書かれ方だと思う。ロシア人の悪に対する考え方が興味深い。
Posted by
佐藤優氏の他の著書を読み、広い知識をもっておられることがわかったので、どのような経歴をお持ちなのか調べてみた上で、この書を読めばどのような背景を持っているのかわかると思い、読んでみることにしました。 キリスト教神学が、聖書神学、歴史神学、組織神学、実践神学の4つに分類される、とい...
佐藤優氏の他の著書を読み、広い知識をもっておられることがわかったので、どのような経歴をお持ちなのか調べてみた上で、この書を読めばどのような背景を持っているのかわかると思い、読んでみることにしました。 キリスト教神学が、聖書神学、歴史神学、組織神学、実践神学の4つに分類される、といった解説はどこでも見られるものではないので、”非キリスト教徒”にとっては理解の一助となりました。 同じく佐藤優氏の『同志社大学神学部』と読むと佐藤氏自身について、または神学という学問についてより深く知ることができると思います。
Posted by
松丸本舗で手にした佐藤優の本。やはり、この人の本は気になる。 冒頭、「神学と虚学である」と始まる。「えっ?!」と思うが、虚学とは佐藤優が名づけた言葉で、他の工学や経済学を実学とし、それに対して神学を虚学と定義した。ここで、「虚」は普通の人間には見えない事柄を指す。したがい、目に...
松丸本舗で手にした佐藤優の本。やはり、この人の本は気になる。 冒頭、「神学と虚学である」と始まる。「えっ?!」と思うが、虚学とは佐藤優が名づけた言葉で、他の工学や経済学を実学とし、それに対して神学を虚学と定義した。ここで、「虚」は普通の人間には見えない事柄を指す。したがい、目に見えない事柄を対象とする知的営為が「虚学」となる。人間の「虚」の部分を神学特有の「虚」の方法で扱う。 神学を語るのも、相変わらず切れ味がいい。個人的な経験も持ち出しつつ、神学という切り口で世界を読み解く方法は、読むものを引き込む力をもっている。これも、神学的手法というものか。 以下、いくつか印象に残った箇所を引用する。 秩序が成り立つためには、どこか秩序が完全に崩れている場所がないといけないのです。そういうふうになっていないと、秩序というものは成り立たないのです。(中略)野本先生は、ユダヤ教のカバラのことを暗示していたのだ。(p.18) 神学的な議論はだいたい、このように論理的に正しい者が負けて、間違っている者が政治的に勝利するという傾向があるわけだ。ここを覚えておいてほしい。(p.25) 人間はその本質において何かを信じる存在である。全く何も信じていない人というのは、人間として存在しえない。例えば現代日本において大多数の人間が信じているものは貨幣である。これがもっとも力を持つ宗教である。そしてこの「貨幣の宗教」に準ずるのが、「国家権力という名の宗教」である。(p.62) 私は、具体的な状況を抜きにした一般的提言はできないが、先ほど述べた、関係の類比という考え方で聖書をひもとき、イエスのリアリティというものを考えることが重要だと思う。イエスが考えていた愛というものはどういうことなのかと。それを自分の言葉で、キリスト教徒でない人にもわかるように専門用語を使わずに翻訳しなおす作業が、今の社会と国家を強化するために重要だと考えている。(p.94) 私自身がカール・バルトから強い影響を受けたことは先述したが、バルトには学生時代からずっと違和感があったし、今もある。特に、「神学とは最も美しい学問だ」というバルトの言葉に落とし穴があると感じる。私は神学が美しい学問であると思わない。その美しさにとらわれてしまったことが、バルトの限界だったように思う。(p.108) 世界には、「絶対に正しい」ということは存在するはずだ。しかし「絶対に正しい」ことは、人間の側から見る限り複数存在する。「絶対に正しい」ことが複数あるということに、絶えていく力が求められる。人間には絶対に「正しい」ことは一つであると信じたい傾向があるからである。しかし、その限界を克服しなくてはならない。そうしないと平和な形で人間が共存し、生き残っていくことが出来なくなるからだ。その点を乗り越えていかなければならないのが信仰だと思う。「私の良心」と「他者の良心」は違うかもしれない。しかし、「それぞれの良心」に従って動いている人の言動や行動というのは、どこかで共通しているものがあると思う。それは言葉では簡単にあらわせない。(p.138) 人間には元来表象能力がある。神学の基礎的訓練をきちんと受ければ、極限的な状態を追体験し、極限状態にある人に共感を持つことが出来るのである。神学のポイントというのは、人間の限界を知ることである。自分自身が限界のある人間であることを知れば、限界状況にある他者に共感することができる。
Posted by
2012年のやりたいこと100のうちの一つ、宗教関連の本を数冊読もうのテーマに基づいて読んでみました。キリスト教ではなく、敢えて神学にしたのは、神とはというのは宗教を学ぶ上で普遍的な画がわかるものかという結構単純な理由により。 シスマとか大学の学部でやった法史学の授業の内容を...
2012年のやりたいこと100のうちの一つ、宗教関連の本を数冊読もうのテーマに基づいて読んでみました。キリスト教ではなく、敢えて神学にしたのは、神とはというのは宗教を学ぶ上で普遍的な画がわかるものかという結構単純な理由により。 シスマとか大学の学部でやった法史学の授業の内容を思い出した。冒頭で著者が述べてた、他の学問はたかだか200年で発展したもの、神学は2000年の歴史を紐解くものだという件に納得。法史学は1600年位まで殆ど宗教史の色合いがあった。それは自然法の概念に宗教とか神の概念ががっしり入り込んでいるのだからではないのかな、と思ってもみました。 世界史勉強し直そう、そう思わせてくれる本。でも、入門の割にワタシの学力だと相当きつかった…。
Posted by
知らない名前がずらずら。現在はともかくとして、少なくとも中世、場合によっては近代まで西洋のトップレベルの頭脳は神学というものにコミットしてきたんだろう。それこそテーマがテーマであるから、人生をかけて打ち込んで。 そのような事実を知ってはじめてフョードルの言葉の重みがわかる。神は存...
知らない名前がずらずら。現在はともかくとして、少なくとも中世、場合によっては近代まで西洋のトップレベルの頭脳は神学というものにコミットしてきたんだろう。それこそテーマがテーマであるから、人生をかけて打ち込んで。 そのような事実を知ってはじめてフョードルの言葉の重みがわかる。神は存在するのか?と聞くと、神は存在しないと答えた息子のイワンに対して、フョードルはこのように言う。 「まったく考えただけでも、やりきれなくなるよ、どれだけ多くの信仰を人間が捧げ、どれだけ多くの力をむなしくこんな空想に費やしてきたことだろう、しかもそれが何千年もの間だからな!」
Posted by
- 1
- 2