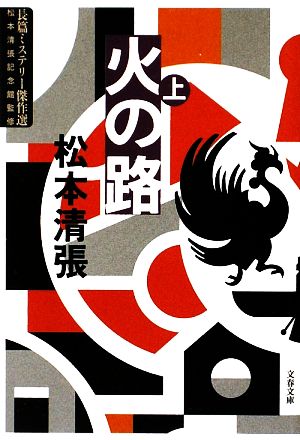火の路 新装版(上) の商品レビュー
2009年、生誕100年を記念して文春文庫から“長篇ミステリー傑作選”として刊行されたもの。一緒に購入したのは『十万分の一の偶然』であった。飛鳥時代の日本にゾロアスター教が伝来していたのではないか、という魅力的な古代史仮説が作中に論文の形で提示される一方、そこは松本清張で、骨董品...
2009年、生誕100年を記念して文春文庫から“長篇ミステリー傑作選”として刊行されたもの。一緒に購入したのは『十万分の一の偶然』であった。飛鳥時代の日本にゾロアスター教が伝来していたのではないか、という魅力的な古代史仮説が作中に論文の形で提示される一方、そこは松本清張で、骨董品の贋造や学閥主義の弊害といった、どす黒~い人間模様も描かれている。で、ゾ教伝来仮説の信憑性は、実際どうなのだろう?
Posted by
テーマについての知識がものすごいです。半分小説、半分論文のような作品で、とても読み応えがあります。1回読んだだけでは、全く消化できず、定期的に読んでいます。
Posted by
古代史を専攻する大学の非常勤講師・高須通子が、主人公。古都奈良で古石を探索する旅で、歴史を扱う雑誌編集者とカメラマンに出会うところからストーリーは展開する。暴漢に襲われた古老の男性を助けたことが、主人公の研究テーマに大きな影響も与える。古代史、巨石、そして時代の変遷とともに再利用...
古代史を専攻する大学の非常勤講師・高須通子が、主人公。古都奈良で古石を探索する旅で、歴史を扱う雑誌編集者とカメラマンに出会うところからストーリーは展開する。暴漢に襲われた古老の男性を助けたことが、主人公の研究テーマに大きな影響も与える。古代史、巨石、そして時代の変遷とともに再利用されたり捨て去られした石や石垣。また、宗教や徐呪術などの儀式を思わせる古い巨石ゆえに、仏教のみならず渡来人によってもたらされたであろう仏教以外の宗教や異教など伝来は、古文書には明確に記されていない等、著者の清張の見解も強く反映されている。また、大学といった派閥・門閥といった独特な組織文化を嫌悪する清張の日本のアカデミズム対する反発も強く現れている背景も見受けられる。しかし、それにしても清張独自の古代史解釈・解説に紙面が多く費やされており、その点が、読者によって評価が大きく分かれると思われる。個人的にも、この点は大いに閉口……。
Posted by
専門的なところは斜め読みしてしまいました。汗。 本書は昭和48年~49年に書かれていますが、学界のドロドロ感が凄い。。。 今も変わっていないのかな、、、?
Posted by
年末年始、奈良に行ったので。奈良からイランへと繋がっていく物語のスケールにワクワク。専門用語も調べながらコツコツ読んでます。
Posted by
初の松本清張作品。 古代遺跡が題材という事で手に取ったのですが、何とも読みにくい。 専門的な事がずらーっと書いてあるので所々、斜め読みに。 理解なんてほぼしてないのに、何だか賢くなった気分です。
Posted by
新進の考古学者・高須通子は、石造物の調査のために訪れた奈良で、殺傷事件に巻きこまれた海津信六を助ける。海津は、かつてT大史学科に籍をおく気鋭の研究者だったが、ある事情で学界を追放された過去があった。通子は、酒船石の用途を研究するうちに海津の示唆を受け、ペルシア文明との関連を調査す...
新進の考古学者・高須通子は、石造物の調査のために訪れた奈良で、殺傷事件に巻きこまれた海津信六を助ける。海津は、かつてT大史学科に籍をおく気鋭の研究者だったが、ある事情で学界を追放された過去があった。通子は、酒船石の用途を研究するうちに海津の示唆を受け、ペルシア文明との関連を調査するためイランへと旅立つ。
Posted by
朝日新聞朝刊に連載されていた「火の回廊」を毎朝楽しみにしていたのを思い出して、四天王寺秋の青空古書市にて古本上下2冊ゲット。 明日香板蓋宮、高井田横穴群、百舌古墳群などなど、やたらに詳しく日本史を習っていたあの年。その前年には、アケメネス朝やササン朝やらと初めて教えられたダイナ...
朝日新聞朝刊に連載されていた「火の回廊」を毎朝楽しみにしていたのを思い出して、四天王寺秋の青空古書市にて古本上下2冊ゲット。 明日香板蓋宮、高井田横穴群、百舌古墳群などなど、やたらに詳しく日本史を習っていたあの年。その前年には、アケメネス朝やササン朝やらと初めて教えられたダイナミックな世界史に心躍らせていたあのころ。新発見の高松塚古墳の見学に行列ができていたあの当時を思い出しながら、一気に読み直してしまった。 しかし... 今、あらためて読む価値は、それほど無いかなって評価を付けざるを得ない。 ワープロ&パソコンの出現が引き起こしたのだろうか、推理小説を含めた娯楽小説は、ここ40年ほどの間にいかに大きな進化をなし遂げたことだろうか。最近の良質娯楽小説の方が、論理やストーリーの複雑さ&矛盾の無さの点でも、人物描写の点でも名手松本清張の作品より上であると評価せざるを得ない。
Posted by
- 1