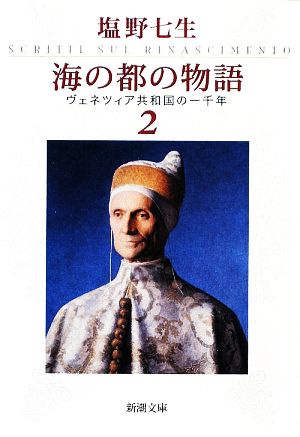海の都の物語(2) の商品レビュー
この本はヴェニス商人と政治の技術について。ビジネス書、経営学の本としても読める。合理主義を徹底しているヴェネツィア人のしたたかさと苦労がわかる。 資金の集め方、交易市場、定期航路ムーダの確立は特におもしろい。モンゴル帝国や織田信長の考え方も似たものがあったのだろうか。自分一人の...
この本はヴェニス商人と政治の技術について。ビジネス書、経営学の本としても読める。合理主義を徹底しているヴェネツィア人のしたたかさと苦労がわかる。 資金の集め方、交易市場、定期航路ムーダの確立は特におもしろい。モンゴル帝国や織田信長の考え方も似たものがあったのだろうか。自分一人の利益にしない共同体の意識も発見だった。 共和政の維持・確立と政教分離を徹底してもなお波乱の要素は残る。有事には権限は与えても専制的な君主は必ず生み出さない。クィリーニ・ティエポロの乱は準備万端にみえてあっさりひっくり返る。元首ファリエルの乱もはね返した。 それぞれできあがった制度の強さはあるのだろうが、根底にはヴェネツィアの強さと弱さを認識した人々の強固な意思がある。現代にも学びはあるのではないか。
Posted by
今回は元首たちがいかに安定した政治体制を築いてきたかを教えてくれる。プロローグでシェークスピアの「オセロ」「ヴェニスの商人」がありえない話とあるが、本筋と関係ないのでご愛嬌。 宗教の排除、政治のプロ育成など強力な統治能力を発揮した内政を実現、維持できたのは、資源を持たない貧しい国...
今回は元首たちがいかに安定した政治体制を築いてきたかを教えてくれる。プロローグでシェークスピアの「オセロ」「ヴェニスの商人」がありえない話とあるが、本筋と関係ないのでご愛嬌。 宗教の排除、政治のプロ育成など強力な統治能力を発揮した内政を実現、維持できたのは、資源を持たない貧しい国だからこその危機感から生まれた。
Posted by
Posted by
中世においてさえ、キリスト教の教義よりも自国の利益を優先させていたヴェネツィアだが、トランプ大統領の“アメリカ・ファースト”みたいな傲慢さが感じられないのは、資源に乏しく人口も十分でない中、生き残る為には大国相手の外交努力を怠らず、いざ戦争となったら、国を挙げて戦わざるを得なかっ...
中世においてさえ、キリスト教の教義よりも自国の利益を優先させていたヴェネツィアだが、トランプ大統領の“アメリカ・ファースト”みたいな傲慢さが感じられないのは、資源に乏しく人口も十分でない中、生き残る為には大国相手の外交努力を怠らず、いざ戦争となったら、国を挙げて戦わざるを得なかったから、か。
Posted by
本書ではヴェネツィアの経済と政治について焦点が当てられています。前半はヴェニスの商人の姿について、シェークスピア作品に出てくるものとはずいぶん違う合理的な仕組みを構築していた姿がわかります。大きなカギは今風にいえばリスクヘッジということでしょうか。ヴェネツィアは経済面でこの技術に...
本書ではヴェネツィアの経済と政治について焦点が当てられています。前半はヴェニスの商人の姿について、シェークスピア作品に出てくるものとはずいぶん違う合理的な仕組みを構築していた姿がわかります。大きなカギは今風にいえばリスクヘッジということでしょうか。ヴェネツィアは経済面でこの技術にとても優れていたのだという印象を受けました。 また後半では、政治について記載がされていて、特に1297年に行われた当時の元首ピエトロ・グラデニーゴによる政体改革が今後のヴェネツィアを長命に導くきっかけになったとして紹介されています。この政体改革では権力の相互監視と権力の集中と分散の微妙なバランスが実現していますが、これは今の世界を見渡しても確かに塩野氏の言うように「いかに実害を少なくするか」という面に焦点を当てた仕組みといえそうです。本書の読了後に思ったのは、資源のない国の政治経済のあり方についてずいぶん日本にも示唆があるじゃないか、ということを塩野氏は暗に述べている気がしました。本書もお勧めです。
Posted by
2巻は12〜14世紀について。 マルコ•クィリーニ、バイアモンテ•ティエポロの乱の際に、反乱軍の旗手の頭の上に窓から小さな石臼を落として内乱を回天させた女性が、乱後に功績を認められ、何でも望むものを褒美として得られることとなった際に、女性が望んだものが、祭日に自分の窓からヴェネ...
2巻は12〜14世紀について。 マルコ•クィリーニ、バイアモンテ•ティエポロの乱の際に、反乱軍の旗手の頭の上に窓から小さな石臼を落として内乱を回天させた女性が、乱後に功績を認められ、何でも望むものを褒美として得られることとなった際に、女性が望んだものが、祭日に自分の窓からヴェネツィア共和国の国旗を掲げる権利と、家賃を据え置く権利だった、という愛国心あふれる慎ましやかさと、国がそれに応えて、その158年後でも家賃が実際に据え置かれていたことが記録として確認出来る点が素晴らしい。
Posted by
第二巻には海の都の物語第四話「ヴェニスの商人」と第五話「政治の技術」が収められている。著者がまるで株式会社だというヴェネツィアの国がかりの商売の仕方が詳しく語られる。一匹狼の集まりで国の安定などあまり考えなかったジェノヴァに比べヴェネツィアは航海途中に次々と立ち寄って商売できる基...
第二巻には海の都の物語第四話「ヴェニスの商人」と第五話「政治の技術」が収められている。著者がまるで株式会社だというヴェネツィアの国がかりの商売の仕方が詳しく語られる。一匹狼の集まりで国の安定などあまり考えなかったジェノヴァに比べヴェネツィアは航海途中に次々と立ち寄って商売できる基地をアドリア海沿岸の各地につくりいわば海の高速道路を作ったそうだ。その間十字軍その他の戦争もあるが、巧みな外交でなるべく実害が及ばないように、ともかく商売さえ効率的にできるように、というポリシーがぶれないところがヴェネツィアだ。政治的には、君主制になるのを極端に嫌い、何事も合議によって決定するための組織がしっかりできていた。国を揺るがすような謀反はに2回しかなかく、それも失敗に終わっている。政治改革を行った賢い元首も出たが、組織上、元首といえども専横にならないよう監視の仕組みがあった。
Posted by
ヴェネツィアが小さいながらも近代まで続く国家をなぜつくれたのか、中世に始まった様々なシステム。 図書館で借りましたが、自分で購入して何度も読みたくなりました。
Posted by
ヴェネツィア共和国は十字軍の熱狂に乗じて東地中海に定期航路を確立し、貿易国としての地歩固めに成功。異教徒との通商を禁じるローマ法王を出し抜き、独自の経済技術や情報網を駆使して、東方との交易市場に強烈な存在感を示した。宗教の排除と政治のプロの育成に重点をおき、強力な統治能力を発揮し...
ヴェネツィア共和国は十字軍の熱狂に乗じて東地中海に定期航路を確立し、貿易国としての地歩固めに成功。異教徒との通商を禁じるローマ法王を出し抜き、独自の経済技術や情報網を駆使して、東方との交易市場に強烈な存在感を示した。宗教の排除と政治のプロの育成に重点をおき、強力な統治能力を発揮した内政にも裏打ちされた「ヴェネツィア株式会社」の真髄を描き出す。
Posted by
ヴェネチア商人のありかたと政体について 編年体ではないので予備知識がないとわかりづらいが 6冊読み終えてさらに読み返して理解するかたちというべきか そうでないとわかりづらいところが まだこのころの作者の実力というべきか
Posted by