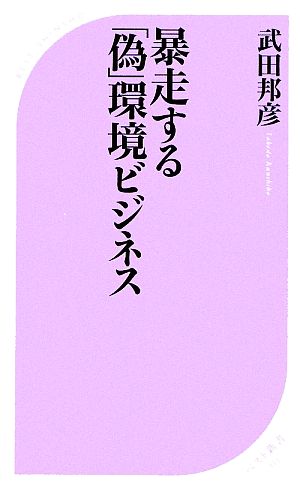暴走する「偽」環境ビジネス の商品レビュー
これまで抱いていた環境問題に対する認識が一変させられる。誤報を流し続けるNHKの指弾に始まり、偽環境ビジネス、偽リサイクルの欺瞞を暴く。真の環境問題とは何かを冷静に見つめ直すことができる。
Posted by
環境にやさしい生活、企業経営という言葉を聞くと否定はできないのですが、その内容を見ると首をかしげることがあります。京都議定書の内容は、国によってはプラスしても良いとか、絶対値の議論ではなく、相対値(ある基準年を基に低減率)で決めるのは、地球上の二酸化炭素を減らすのが目的であれば理...
環境にやさしい生活、企業経営という言葉を聞くと否定はできないのですが、その内容を見ると首をかしげることがあります。京都議定書の内容は、国によってはプラスしても良いとか、絶対値の議論ではなく、相対値(ある基準年を基に低減率)で決めるのは、地球上の二酸化炭素を減らすのが目的であれば理解ができません。 もっとも日本の経済成長を抑えるのが目的というのであれば、理解できます。二酸化炭素の低減がなんのために必要なのかも不明瞭な点がありますが、それを積極的に行うのであれば、日本の省エネ技術を格安で(場合によっては経済援助という形で)広めたほうがよほど効果的だと思います。 本書は、環境に関する報道に疑問を投げかけている武田氏の著作ですが、全面的に受け入れられないにしても、なるほどと思った部分もありました。 以下は気になったポイントです。 ・ 1990年比較で二酸化炭素の増加量は、日本平均で15%増加に対してNHKは80%も増加した(p12) ・NHKで放送していた、1)南極は温暖化している、2)南極の氷は溶けて減っている、というのは、IPCCやNASAの報告とは異なっている(p17) ・南極はマイナス40℃なので、降るなら必ず雪で雨が降ることはない、温暖化すれば結果的には南極の氷は増加する(p21) ・北極海の氷の面積は2007年に401万km2と低くなったため、NHKは氷がなくなると報道したが、2008年11月にはその倍には回復している(p31) ・2008年1月に紙のリサイクル偽装が見つかる前に、100%リサイクルは無理で70%リサイクル紙を認めるように要請したが、環境省は認めなかった(p56) ・日本では政府の出先機関としての検察が告発した刑事事件の有罪率が99%という世界でもまれに見る判決がでるのが特徴(p81) ・環境サミットで宣言された大きな進歩として「予防原則」の採択がある、「環境が破壊されてから対策をとるのではなく、その前に対策を採る」というもの、これにより、科学的にそれが証明されていなくても、規制してよいことになった(p90) ・バード・ヘーゲル決議(アメリカは中国やインド等の発展途上国が削減しない場合には、条約を批准しない)や、ベルリン・マンデート(発展途上国は二酸化炭素規制不要、基準年を1990年)の2つが、京都会議の失敗は決定していた(p93) ・1990年の統一ドイツの二酸化炭素排出量は、1~9月までは東西ドイツの合計、10月以降は統一ドイツだが、当時は東ドイツ発電所が動いていたので12.5億トンであり、人口換算で1.6倍(p96) ・環境に優しいとされるスウェーデンの電力の半分は原子力、残りは水力である、水力発電は砂利がたまってしまいそれを抜くと、腐った水が大量にながれて下流や海を汚すという弊害がある(p109) ・日本、アメリカ、カナダは1997年までにかなりの省エネルギー努力をしていたので、表面上の削減目標は-6、-7、-6%であるが、実質は-19、-22、-25%となる(p125) ・材料には金属、無機、高分子の3種類あるが、一度使ってもあまり劣化しないもの=リサイクルに意味があるものとして、金属材料があるが、そのほかは悪化するので再利用は難しい(p143) ・貴金属がリサイクルできるのは、天然にある状態よりも携帯電話等に含まれるほうが品位が高いから(p144) ・日本のプラスチックの生産量は1400万トンである、輸出が300万トンなので国内消費は1100万トンである、リサイクル対象の包装使用分は430万トンでリサイクルの割合は1%(公称8万トン、実質1%)消費量は減らない(p157) ・レジ袋はもともとスーパーが出現して万引きが増えたときに誕生した、万引きを減らすために買い物袋を持ってこないようにするために、買い物カゴを用意して、レジで半透明な袋に入れてもらう方式を考えた(p207) ・200海里の領海及び陸地をあわせた面積では日本はかなり大きくなり、人間一人当たりの生産高を考えると日本はアメリカよりも強い力を持つことになる(p218) ・19世紀の初めに産業が発達し、それまで鉄の精錬を木材に頼っていたので森林が破壊された、その環境破壊を食い止めたのが石炭であり石油であった(p248) ・老後を過ごすために今はなくてはならないと思われている「年金」ができたのは1961年で、その時の掛け金は月:100円であった(p250)
Posted by
教育をすればするほど、如何に自分が正しいかと主張して、自分だけが得をするというような人材をつくってしまう。 環境は人間の数と自然の力できまる。自然の力は土地の面積や太陽の光で決まる。人口密度重要な指標。 環境と言うのは目的に合致しているかではなく、目的を実行すると全体としてどうな...
教育をすればするほど、如何に自分が正しいかと主張して、自分だけが得をするというような人材をつくってしまう。 環境は人間の数と自然の力できまる。自然の力は土地の面積や太陽の光で決まる。人口密度重要な指標。 環境と言うのは目的に合致しているかではなく、目的を実行すると全体としてどうなるかと言うことを考えること。自然を利用することでまずいことが起こらないかを考える。 環境を考えるときは、総合的な効率を考えなければならない。発電機を作るエネルギーとか。保守点検のエネルギー 研究資金を獲得できればよいというような研究もある。 バイオエタノール。石油がない→バイオエタノール。石油が不足→生産量が減る可能性がある。 海洋ビジネス、元素ビジネス、河川と生活を一体化するビジネス。 砂埃から必要な元素や細菌が体内に入ることもある。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ITと環境は嘘がビジネスになる領域だということは、 社会人なら誰でも知っていることではないだろうか。 環境ビジネスの真の姿は、嘘で金を稼ぐことなので、 「偽」環境ビジネスは存在しないと思う。 嘘で固めなくても、ITと環境がビジネスになる可能性があるとすれば、それを示してほしかった。 どうすれば、環境でビジネスが成立するか。 システム工学では、ビジネスとして成立しないシステムを環境と定義しているのに。 不思議だ。
Posted by
特にNHKの報道を指弾している。これほどまでにひどいとは感じていなかったので、ちょっと驚いた。(ただ筆者は民放なんか相手にしていない様なので、報道内容としては民法はもっとひどいかもしれない)。 北極海の氷が報道後大きくなったが報道されない。ダイオキシンでも誤報。事実を伝えることよ...
特にNHKの報道を指弾している。これほどまでにひどいとは感じていなかったので、ちょっと驚いた。(ただ筆者は民放なんか相手にしていない様なので、報道内容としては民法はもっとひどいかもしれない)。 北極海の氷が報道後大きくなったが報道されない。ダイオキシンでも誤報。事実を伝えることよりも大衆に迎合する報道。視聴率を取らなければならない民法は仕方が無い面もあるが、何故NKHがこれほど愚民迎合的になるんだろう。 バード=ヘーゲル法やベルリンマンデートなど、温暖化議論のキーになる情報を教えてもらった。 過去の水銀規制、環境ホルモン騒ぎ、食の安全と評した(スケープゴードとしか思えない)特定企業バッシング、そして今回の熱病の様な温暖化ブーム。筆者の指摘は非常に示唆的。こんなことをズバズバ言う大学教授がいたんだと痛快に感じた。 科学者らしく、IPCC報告は否定せず、むしろその内容を根拠にNHKを責めている。
Posted by
改めて武田先生の環境ビジネスに関する記述は現代社会が支配される偽善を看破する鮮烈な一書だ。武田さんのこれまでの著書から比べても本書は癖がなくバランス感が纏まった素晴らしい出来になっている。 リサイクル問題や温暖化問題やエネルギー問題といった当たり前の事柄の裏にある本音や実態の部...
改めて武田先生の環境ビジネスに関する記述は現代社会が支配される偽善を看破する鮮烈な一書だ。武田さんのこれまでの著書から比べても本書は癖がなくバランス感が纏まった素晴らしい出来になっている。 リサイクル問題や温暖化問題やエネルギー問題といった当たり前の事柄の裏にある本音や実態の部分を深くえぐり出すかのような内容。 一部の天下り団体や行政による雇用、エネルギー利権のために一般国民は騙され税金をむしり取られていると気づく事ができる。
Posted by
昨今の「エコエコ」言っている風潮にはいかがなものかと常日頃思っているので、こういう「所詮ビジネスでやってんだよ」とズバリ言い切ってくれる本は読んでてスッキリします。ところどころ論旨が飛躍していたり、完全には同調できない部分もあるけど、世の中の主婦を騙しまくっているメディアや産業界...
昨今の「エコエコ」言っている風潮にはいかがなものかと常日頃思っているので、こういう「所詮ビジネスでやってんだよ」とズバリ言い切ってくれる本は読んでてスッキリします。ところどころ論旨が飛躍していたり、完全には同調できない部分もあるけど、世の中の主婦を騙しまくっているメディアや産業界にはこの本を読んで反省をしてもらいたいところ。
Posted by
2009.10.28 NHKや日本政府がここまで嘘をついて国民を省エネだとかエコに駆り立ててたのか…と嫌気がさした。日本の文化は好きだけれど、今の日本の現状はうんざりするばかりだ…
Posted by
暴走する「武田邦彦」, 2009/6/6 この人の指摘する事項について共感することも無くはないのですが、この人自体、最近は世間を騒がせせて、権威者とか素直に考えている人をバカにして見下す、そういう論調にシフトしてきて、最近は辟易しています ...
暴走する「武田邦彦」, 2009/6/6 この人の指摘する事項について共感することも無くはないのですが、この人自体、最近は世間を騒がせせて、権威者とか素直に考えている人をバカにして見下す、そういう論調にシフトしてきて、最近は辟易しています やや、論理が短絡的で、根本的に武田邦彦論で、環境問題を替えていくビジョンが見えないので残念 っていうか、最近、同じネタで本書いてませんかね
Posted by
この著者の本には、読むたびに驚かされる。環境問題について一般に信じられていることとは180度異なる見解が、しっかりとした(と思われる)資料的な基礎のもとに主張されるからだ。第一章では、NHKの環境報道や環境問題への取組みが徹底的に批判されている。たとえばNHKで「温暖化とともに南...
この著者の本には、読むたびに驚かされる。環境問題について一般に信じられていることとは180度異なる見解が、しっかりとした(と思われる)資料的な基礎のもとに主張されるからだ。第一章では、NHKの環境報道や環境問題への取組みが徹底的に批判されている。たとえばNHKで「温暖化とともに南極の氷が減っている」と報道されたが、事実(IPPCの報告)は、「南極の海氷面積には、引き続き年々変動と局地的な変化は見られるものの、統計学的な優位な平均的傾向は見られない」というのだ。 ◆京都議定書は、アメリカは批准せず、ヨーロッパは1990年を計算基準にして表面的には削減のように見せかけ、実質的には増加枠を獲得した。日本は1990年には省エネが終わっていて、京都議定書を締結すると産業界は大打撃を受けるので批准に反対した。P65 そして「日本政府は、産業界に具体的な削減義務を課さないという密約がなされた。つまり削減義務は国民に求めるということになった。P120 1990年を基準とすることで、たとえばドイツは、CO2排出量が実質11%の増加となり、日本はマイナス19%だから、マネーゲームとすればドイツが日本に対して30%もの利益を得たことになる。P115 ロシアは見かけ上でも0%の削減、実態は38%もの実質増加だった。P85 ヨーロッパは、温暖化をいかにEUの国際的な地位向上に役立てるかという基本戦略があったが、日本にはなかった。P84 武田の何冊かの本では、このあたりの事情が詳述されている。もう少し勉強して、本当にそういう事情があったのか、ある程度自分自身で判断できるだけの情報が欲しい。この辺の事情を探っていくことは、国際政治の現実の姿を知るうえで大切なことかも知れない。環境問題にはかなり極端な裏と表があり、政府やマスコミ、それに踊らされる国民の姿という問題が見えてくるかも知れない。
Posted by
- 1