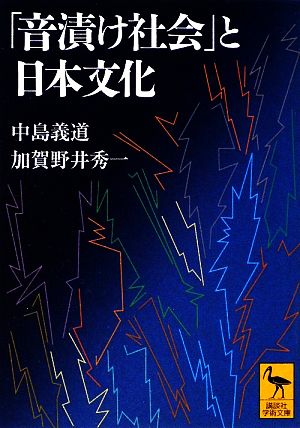「音漬け社会」と日本文化 の商品レビュー
この書簡集を読んで、改めて、対談や聞き書きとの違いってなんだろうか?を考えました。中島義道氏の「騒音」に関する著作だったか雑誌記事だったかは、ずいぶん昔に読んだ覚えがあり、学者というより、クレーマー偏屈じいさんみたいだなと感じながらも、言っていることに筋が通っているし、ストレート...
この書簡集を読んで、改めて、対談や聞き書きとの違いってなんだろうか?を考えました。中島義道氏の「騒音」に関する著作だったか雑誌記事だったかは、ずいぶん昔に読んだ覚えがあり、学者というより、クレーマー偏屈じいさんみたいだなと感じながらも、言っていることに筋が通っているし、ストレートとに「嫌だ」と言い切る姿勢に共感を覚えていました。 で、この書簡集を読んで思ったのは、書簡でのやり取りに漂う緊張感やすれ違いと、最後の対談の雰囲気が、随分と違うものだなぁと。書簡は、1人で書いて、相手に届いて読むまでのタイムラグがかなりあるという特徴から、たとえ相手への返信だとしても、考え抜いて書いているので、隙がない。だからこそ、辛辣な批判や、場合によっては人格を否定するような表現も、誹謗中傷に貶められることがない。 ただ、相手への返信を意識するあまり、テーマから逸れているように感じる箇所もあり、もう少し「日本的騒音」に対するお二人の知見を知りたかった。
Posted by
‹内容紹介より› 注意・勧告・案内・お願いなど、公共空間に日常的に撒き散らされている「音」。サービス・親切・気遣いのつもりの音の洪水が私たちに苦痛を与えるのは何故なのか。また苦情が理解されない背景には何があるのか。二人の哲学者の往復書簡の形で日本人の言語観・公共観・コミュニケーシ...
‹内容紹介より› 注意・勧告・案内・お願いなど、公共空間に日常的に撒き散らされている「音」。サービス・親切・気遣いのつもりの音の洪水が私たちに苦痛を与えるのは何故なのか。また苦情が理解されない背景には何があるのか。二人の哲学者の往復書簡の形で日本人の言語観・公共観・コミュニケーション観の特性を考察。感受性のマイノリティに救いの道はあるのか。 ーーーー 「哲学書」「思想書」でもありますが、中島義道と加賀野井秀一による往復書簡形式で話が進むので、読みやすく感じました。 一般的な哲学や現代思想の書籍に比べ、「相手(読者)に伝えよう」という意図がより明確に打ち出されていたように感じます。 中島と加賀野井の思想・思考のズレも読んでいて面白かったです。どちらの言い分にも納得できる部分と、「それは違うのでは?」と感じる部分とあり、自分の中で「他者を理解する」ということについて考えるいいきっかけになりました。 「あなたの考えは私とは違うけど、ひとはそれぞれちがうものだから、それでいいんじゃない」という志向スタンスは、「他者を理解」しているとはいえず、議論を打ち切ってしまい、相互理解にもつながらず、”マジョリティ”の価値観を無批判に受け入れる社会になりかねない、という言説にはとても共感できました。 「相手を完全に理解することはできない」ということを念頭に置きつつ、「相手が自分とは異なる価値観を有している」ということを認識し、互いに対話を続けることが重要なのではないか、と感じます。 この二人のように、「確固たる基盤」があるかどうか、ということに悩むのは大切かもしれませんが、まずは「自分が思っていること」を自分の中で言語化し、他者の批判にさらすこと。 これからの生活の中で取り入れていければよいな、と思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
加賀野井がオーソドックスな近代知識人路線であるのに対し、中島はその役割さえ嫌悪してみせる。インテリの大衆批判欧米礼賛はもう大衆の側から見限られている、と言うわけだ。確かに同意できる部分もあるが、中島の日本擁護がまた板についていないのはご愛嬌か。 最後の対談の二人の日常行動の異常さは必読。微笑ましい。
Posted by
『うるさい日本の私』で提起された、日本の「隠れた」騒音問題に関する本。 また同じテーマの焼き直しかなと思ったら、意外に面白かった。 本書は中島義道と加賀野井秀一の往復書簡の形式をとり、騒音問題を主軸としながら 日本の社会や文化の特異性を議論する。 その過程で浮き彫りになる、日本...
『うるさい日本の私』で提起された、日本の「隠れた」騒音問題に関する本。 また同じテーマの焼き直しかなと思ったら、意外に面白かった。 本書は中島義道と加賀野井秀一の往復書簡の形式をとり、騒音問題を主軸としながら 日本の社会や文化の特異性を議論する。 その過程で浮き彫りになる、日本と西洋を比較する際の両著者の スタンスの違いが読みどころ。 後半は両者の人格的な差異、その原因になったと思われるヨーロッパ体験の差異が 主な話題となり、徐々に殴り合いのようなやり取りになってゆくが、 両著者とも「言葉を信頼する」と宣言するとおり、紳士的かつ友好的な文体のまま 過激さを増していくあたりが読んでいて笑える。 繊細な感受性、言葉や議論を尊重する態度などの共通性を持ちながら正反対な 人生を送る両著者は、失礼ながら性格診断の格好の材料のように思える。 「エピキュリアン」の加賀野井氏と、「自虐的」な中島氏。 僕は、どちらかといえば中島氏に共感する。 「人生は楽しむべきものだ」と頭では理解するが、自分でもよくわからない後ろめたさ によって、それが実現できない。しかし、それを実現している人には憧れている。
Posted by
- 1