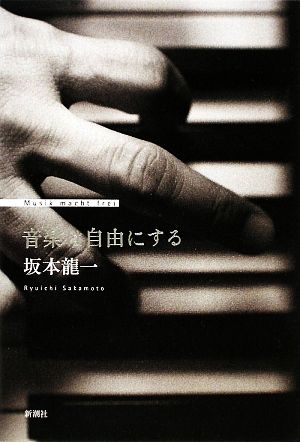音楽は自由にする の商品レビュー
昨年亡くなった坂本龍一氏が自分の人生を振り返った2009年の本。非常に自由に、自分のやりたいことをやってきたようだ。家族のこと、学生運動に参加していたこと、YMOでの活動、映画への出演など、そこで感じたことなどが本音で、しかし淡々と語られている。 音楽活動のことはもちろんだが、...
昨年亡くなった坂本龍一氏が自分の人生を振り返った2009年の本。非常に自由に、自分のやりたいことをやってきたようだ。家族のこと、学生運動に参加していたこと、YMOでの活動、映画への出演など、そこで感じたことなどが本音で、しかし淡々と語られている。 音楽活動のことはもちろんだが、学生運動や9.11のことが人生に大きく影響していることが伺える。筆者らしい、自分のスタイルと世界観を貫いた生き方が伝わる。
Posted by
新潟にピアノコンサートに来た時の物販で買ったままで、お亡くなりになってからずっと読まなければと思っていた。音楽について研究して音大も出て、そうして身につけたスキルやセンスが山下達郎や大瀧詠一はアメリカのロックで身についていたというのがすごく面白い。たどった道が違ってもゴールが一...
新潟にピアノコンサートに来た時の物販で買ったままで、お亡くなりになってからずっと読まなければと思っていた。音楽について研究して音大も出て、そうして身につけたスキルやセンスが山下達郎や大瀧詠一はアメリカのロックで身についていたというのがすごく面白い。たどった道が違ってもゴールが一緒、みたいなすごくロマンがある。スタジオミュージシャンをせっせとやっていた頃の活きのよさが楽しい。それからソロアルバムを作ってYMOをやって、映画音楽を作りまくる。 大好きな映画『オネアミスの翼』の音楽には全く触れられていない。 注釈を読むのが面倒だ。
Posted by
坂本龍一さんが亡くなられたのを知った直後から、半年間かけて大切に読んだ。坂本さんが音楽をどのようにとらえているよのか、歴史という物差しで見たときと、この内容を語られている現在地点での感覚の差分というか、変化の過程にある部分がとても興味深かった。 “大学に入ったときにはっきり心に...
坂本龍一さんが亡くなられたのを知った直後から、半年間かけて大切に読んだ。坂本さんが音楽をどのようにとらえているよのか、歴史という物差しで見たときと、この内容を語られている現在地点での感覚の差分というか、変化の過程にある部分がとても興味深かった。 “大学に入ったときにはっきり心に決めていたのは、「とにかく民族音楽と電子音楽は学び倒してやろう」ということでした。ぼくは不遜な小僧でしたらか、「西洋音楽はデッドエンドだ、この先に発展はない」と思っていた。発展があるのなら勉強して進んでいけばいいけれど、もう袋小路だとしたら、西洋音楽以外のものに目を向けるしかない。外側を見ていかなくてはいけない”(P.88-89) 音楽家としてのデビュー以前、このように考えていた坂本龍一の先見の明に、そしてその数年後に「千のナイフ」を書いたこと、この曲が坂本龍一の音楽家像のほぼすべてを物語っていることに驚かされるし、感動させられる。 本書の終盤、『out of noise』の制作背景についてジョン・ケージの「偶然の音楽」の話を引いて語っているが、それはのちの『async』にもつながるし、高校〜大学入学以前の坂本龍一の音楽観にもつながる。坂本龍一、なんて音楽家人生だったんだろうか、と思うと同時に「音楽とは果たして何なのだろうか」と考えさせられ続ける。
Posted by
【抜粋】 (p18)表現というのは結局、他者が理解できる形、他者と共有できるような形でないと成立しないものです。だからどうしても、抽象化というか、共同化というか、そういう過程が必要になる。すると、個的な体験、痛みや喜びは抜け落ちていかざるを得ない。そこには絶対的な限界があり、どう...
【抜粋】 (p18)表現というのは結局、他者が理解できる形、他者と共有できるような形でないと成立しないものです。だからどうしても、抽象化というか、共同化というか、そういう過程が必要になる。すると、個的な体験、痛みや喜びは抜け落ちていかざるを得ない。そこには絶対的な限界があり、どうにもならない欠損感がある。でも、そういう限界と引き換えに、まったく別の国、別の世界の人が一緒に同じように理解できる何かへの通路ができる。 (p91)電子音楽に興味を持っていたのは、「西洋音楽は袋小路に入ってしまった」ということのほかに、「人民のための音楽」というようなことも考えていたからなんです。つまり、特別な音楽教育を受けた人でなくても音楽的な喜びが得られるような、一種のゲーム理論的な作曲はできないものかと思っていた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
初めて自分で買ったCDは坂本龍一の「Gruppo Musicale」だった。それからずっとファンというより「信者」だったので逝去のダメージから未だに立ち直れないままでいる。 本書は氏自ら語った2009年までの半生記(以降は「ぼくはあと、何回満月を見るだろう」に続く)。 名編集者の父親と帽子デザイナーで進歩的な母親のもとに生まれ、幼稚園の課題で初めて作曲しピアノを始めた幼少期、ドビュッシーに心酔した中学時代、親友と共に学生運動に身を投じた高校時代、美術科との交流で得た人脈からスタジオミュージシャンとなった藝大時代、一躍時代の寵児となった反動で鬱屈したYMO時代、名監督に振り回された「ラストエンペラー」撮影・音楽制作秘話等々逸話の一つ一つが非常に濃密で面白い(そのうち映像化されそう)。 それは何者にもなりたくなかった天邪鬼な少年が、良き師良き友との交流を経て音楽家として成熟し、世界的に活躍するまでのビルディングス・ロマンでもある。 ファン必携、訃報で初めてその音楽に触れた人にもお勧めの一冊。
Posted by
小学生の頃からYMOは大好きだけど、坂本龍一さんの音楽は自分にはハードルが高いような、高尚過ぎるような気がしていて、誰でもが知っているような曲以外はあまり聴いてこなかった。 でも、「音楽は自由にする」を読みながら聴く坂本龍一さんの音楽は龍一さんに導かれるような感覚で、すごく幸せな...
小学生の頃からYMOは大好きだけど、坂本龍一さんの音楽は自分にはハードルが高いような、高尚過ぎるような気がしていて、誰でもが知っているような曲以外はあまり聴いてこなかった。 でも、「音楽は自由にする」を読みながら聴く坂本龍一さんの音楽は龍一さんに導かれるような感覚で、すごく幸せな読書&音楽体験だった。 そして、こんな本ができたのは「エンジン」という雑誌があったからこそだと思う。 と書いてみて調べてみたら、雑誌「エンジン」はまだ刊行中なんですね。すごい!素晴らしい!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
小さい頃の事から執筆当時までの事が淡々とつづられていて、とりあえずめちゃくちゃ面白かった。読んでいて声出して笑っちゃうところもあった。特に子供の頃の坂本龍一可愛すぎる。自分をドピュッシーの生まれ変わりだと本気で信じてサインの練習してたっていうエピソード可愛すぎて無理。 坂本龍一さんのことは戦場のメリークリスマスくらいしか知らない状態で読んだけれど、読み出してから音楽を聴くようになって、だいすきになった。 新しく出た自伝もはやく読みたい。
Posted by
子供の頃から、自分で選んだ選んでいないの条件はあるものの、驚くほど多動。子供の頃に身につけた作曲の技能は、音楽と異なる領域で活動する人々を理解し受け入れ協働するとき、当てはめの理論になっているように思いました。戦メリ、ラストエンペラーは役者としてのお誘いが先、戦メリに至っては自ら...
子供の頃から、自分で選んだ選んでいないの条件はあるものの、驚くほど多動。子供の頃に身につけた作曲の技能は、音楽と異なる領域で活動する人々を理解し受け入れ協働するとき、当てはめの理論になっているように思いました。戦メリ、ラストエンペラーは役者としてのお誘いが先、戦メリに至っては自ら音楽もやると条件を出したとは知りませんでした。YMOの公的抑圧あたりでは当時日本車か、日本家電か、YMOか、日本代表的な役回りに険悪していく様は読んでいて苦しさを覚えました。リスナーに届く音楽とは難しく戦メリもエナジーフローも5分ぐらいで作った、どうして受けたのか分からないとのこと。タイトルのように音楽は自由にする生活だったのかよく分からなくなってしまいました。幼稚園児から2009年までの振り返りです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2023年4月21日読了。図書館で借りた。 坂本さんが逝去された。自伝があったので借りてみた。 坂本さんが育ったのは特別裕福な家庭でもないが、母親が教育に関して進歩的で、音楽に導いてくれたのが最初のきっかけとなり、第一歩なのかなと。机上の勉強はしてこなかったということだけど、たくさん文学や哲学の本を学生時代から読んでおられる。そして社会問題、情勢などからもインスピレーションを得て、曲を作り、ソロのアルバムに入れていたりしたのは、全然知らなかった。社会問題に関して活動されているのはチラッとしか知らなくて、こんなにも曲作りに影響を与えていたのかと、この本を読んで驚いた。 あとがきの中にある、子供の頃からの問いに、答えは出たのでしょうか。しかしとても幸せな人生だったのではないか、と思う。 文章が読みやすい。曲を聴いて、答え合わせのようにまたこの本を読んでみたい。
Posted by
関ジャムの坂本龍一特集の中で紹介されていた。 中高校時代、おニャン子クラブなど、下手な歌のアイドルに嫌気が出て、Beatlesなどの洋楽やYMO、音楽図鑑、未来派野郎などに傾倒してアルバムやCDを本当に毎日聴いていた。 正直その時は坂本龍一のアルバムはそれぞれ全然違うなぁ。とは感...
関ジャムの坂本龍一特集の中で紹介されていた。 中高校時代、おニャン子クラブなど、下手な歌のアイドルに嫌気が出て、Beatlesなどの洋楽やYMO、音楽図鑑、未来派野郎などに傾倒してアルバムやCDを本当に毎日聴いていた。 正直その時は坂本龍一のアルバムはそれぞれ全然違うなぁ。とは感じて不思議におもっていたが、その時の環境など作品の背景が分かった。 また、以前テレビで自分の思いを言葉にする事はできないが、音楽なら出来る。的な発言をしていた。ファンではありつつ、本当に?と言う気持ちもあったが、今回随所にこの曲を聴くと当時の自分の気持ちを思い出すと言う事が書かれていて、本当だったんだ。やっぱり凄いな。と改めて感じた。
Posted by