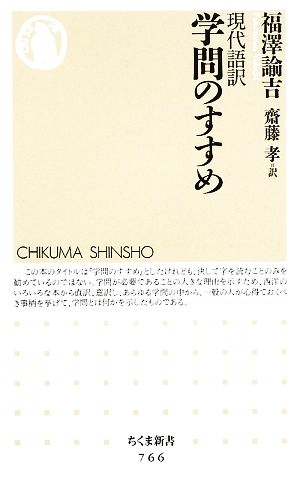現代語訳 学問のすすめ の商品レビュー
福沢諭吉の意見は非常に参考になり、多くの学びを得ることができました。 学問は、ただ知識を身につけるだけでなく、それを自分の仕事や働き方に活かし、社会に役立てていくことが重要だと感じました。 また、「怨望」を抱くことはよくないという考えにも深く共感しました。自分がやるべきことを...
福沢諭吉の意見は非常に参考になり、多くの学びを得ることができました。 学問は、ただ知識を身につけるだけでなく、それを自分の仕事や働き方に活かし、社会に役立てていくことが重要だと感じました。 また、「怨望」を抱くことはよくないという考えにも深く共感しました。自分がやるべきことを見極め、それを通じて文明を前進させるために行動する。単に家族を守ることにとどまらず、他人や社会全体に貢献できる人間でありたいと思います。 これまで、個人的に「自分や家族の幸せ」が最も大切だと考えていました。もちろん、それは基本であり大切なことですが、同時に、文明を進歩させ、世の中に貢献できる行動を取ることが重要だと気づきました。 そのためには、学問を通じて必要な知識を身につけることが不可欠であるという思いを新たにしました。
Posted by
なぜ学ばなければいけないのか。 途中難しい内容もあったが、モチベーションが上がる1冊だった。 はじめて読んだが、毎年一回は読みたい本になった。 自分にとって大事な一冊にしたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
学問で重要なのは、それを実際に生かすことである。実際に行かせない学問は、学問でないのに等しい 妬みは百害あって、一利なし 人間最大の災いは怨望であって、その原因は窮なのだから、言論の自由は邪魔してはいけないし、行動の自由は妨げてはいけない 人望とは、実際の力量で得られるものでは元よりないし、また財産が多くあるからといって得られるものでもない。ただ、その人の活発な知性の働きと、正直な心と言う徳を持って、次第に獲得していくものなのだ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
昔から名著で、日本で有名な本を挙げたら必ず挙がるであろう名著の現代語訳版。 非常に読みやすく現代語訳してあるので、肩ひじ張らずに読めました。 現在でも十分通じる内容が、直截に書かれていて、読んでいてくどくない。 内容としては、勉強し、世間と積極的に交わりあらゆることに興味を持ち、それらを観察・推察して活きた学問を得ることの大切さを述べていました。 そのための心構え、世間の考え方なども述べていて単なる自己啓発本だけではなかったです。 昨今の不平不満あふれる世の中を見ていると再びこの本の価値観は必要なのだと感じさせられます。
Posted by
渋沢栄一の論語と算盤に続いて、前の1万円札だった、福沢諭吉の学問のすすめを読みたくなった。 学問のすすめという言葉はずっと知っていたけど、実際に読んだことはなかった。冒頭に翻訳者もそのように言っている。 本の概要だが、国を頼りにしているばっかりではなく、民の気風を改革し、国を...
渋沢栄一の論語と算盤に続いて、前の1万円札だった、福沢諭吉の学問のすすめを読みたくなった。 学問のすすめという言葉はずっと知っていたけど、実際に読んだことはなかった。冒頭に翻訳者もそのように言っている。 本の概要だが、国を頼りにしているばっかりではなく、民の気風を改革し、国を自ら盛り上げることが大事だとと書いてあった。では、どうやって気風を高めることができるのだろうか。それが学問である。福沢諭吉は学問をただの机上の学びだけでなく、アウトプットが大事と言っていた。 さて、本で自分が面白いなと思ったところを紹介しよう。私は「この仕事で飯を食っている」という表現がなぜか嫌いだった。言語化できないが下品な感じがして嫌いだった。第9章のよりレベルの高い学問では、「衣食住だけ守る量では蟻と同じ、社会にいかに貢献するかが仕事というもの」と福沢諭吉は記している。また、別の章では当たり前のことができるできないと言ったレベルで議論するのはすごくレベルが低く、常に全体上を比べて前進することが品格につながるとあった。 自分が考えていた「この仕事で飯を食っている」という表現の気持ち悪さはまさにこのことである。最低限のレベルの仕事を誇らしく、言っているのが気持ち悪いなと思った。 2つ目に面白かったのは第15編の判断力の鍛え方。明治初期には西洋諸国が素晴らしいと疑いもなく思い込んでいる人が多かったらしい。判断力を養うのは学問であり、疑うことで進歩がある。確かにその通りで現状が不便だなあと思わなかったら、より良い社会は作れないのでそのとおりだと思った。 福沢諭吉の皮肉も面白くて西洋人が素晴らしくて、日本の文化が素晴らしくないって思い込んでいる人が。もし、日本と西洋の文化が逆だったらという想定で皮肉を言っていた。例えばちり紙文化について。「もし西洋の人がちり紙を使っていたら、衛生的にも進んでいると言っただろうし、日本にハンカチ文化があれば日本人は野蛮だから同じ布を何回も洗って使い回してすごく汚い。西洋はすごく進んでいるなぁ」と言っただろうと皮肉が書いてあった。めっちゃ面白かった。 この本の主題ではないが、福沢諭吉の1万円札が使われたのが1984年から2024年40年にわたって作られた。その40年の間に国から民へ移ったものといえば、鉄道、郵便局、高速道路などがある。まさに学問のすすめに書いてあった、国を頼りにするという姿勢からの民が頑張るといった心持ちの変化をしていった40年だったと思う。福沢諭吉が1万円札になった。メッセージというのは、こういうところからも感じることができるのではないだろうか… では、渋沢栄一が1万円札になった。この令和の時代は一体どういうメッセージがあるのだろうか?それも考えてみてみたいと思った。
Posted by
尊王攘夷によって世間がおかしな方向へと向かっていることに対して、「そんなことしたって異国に勝てねぇよ、勉強してみんなで優秀になろうぜ」的なメッセージを受け取りました。 個人的に男尊女卑が今以上に強そうな時代に、女性が社会進出することができると述べる姿に先見の名を感じました。本気で...
尊王攘夷によって世間がおかしな方向へと向かっていることに対して、「そんなことしたって異国に勝てねぇよ、勉強してみんなで優秀になろうぜ」的なメッセージを受け取りました。 個人的に男尊女卑が今以上に強そうな時代に、女性が社会進出することができると述べる姿に先見の名を感じました。本気で誰でも努力すれば、能力を伸ばせると信じていたのだと思います。
Posted by
「学問のすすめ」は最初は全17編の分冊で出版され、後に1冊に合本された。だから本書も17編からなっている。 その17編のうち、現在でも役に立つ不変の教えは含まれているものの、割合としては少ない。「人間は平等である」など現在では常識となっていたり、「日本の独立という課題」など時代...
「学問のすすめ」は最初は全17編の分冊で出版され、後に1冊に合本された。だから本書も17編からなっている。 その17編のうち、現在でも役に立つ不変の教えは含まれているものの、割合としては少ない。「人間は平等である」など現在では常識となっていたり、「日本の独立という課題」など時代に合わなかったりする方が多い。 現代では常識になっていることは、福澤諭吉らが啓蒙してくれたお陰で、文化として根付いたからに違いない。明治初期の人たちの生活や思想を知るには良い資料だ。 人間はいつまでも学ぶことは大切だが、本書の内容はこれから社会に出る人、特に学生や20代の人にお勧めの内容になっている。
Posted by
わかりやすい現代語訳 哲学的だが理解しやすい内容 推奨と批判のバランスが良い 説得力もあり、現代でも納得のいく思想が書かれている
Posted by
社会人になってから、歴史に名を残す著作、ちゃんと内容を知っておかねばと思って読んだ一冊。国家と国民の本来あるべき関係、納税の意義など、近代国家とは、がとてもわかりやすく説明されている。さすがは諭吉さん。でも、実際には理想どおりにいかないんだよなあ…。と、思いつつ、政治家の皆さん、...
社会人になってから、歴史に名を残す著作、ちゃんと内容を知っておかねばと思って読んだ一冊。国家と国民の本来あるべき関係、納税の意義など、近代国家とは、がとてもわかりやすく説明されている。さすがは諭吉さん。でも、実際には理想どおりにいかないんだよなあ…。と、思いつつ、政治家の皆さん、国民の皆さん、この本読んで一回原点に立ち返りませんか、と言いたくなった。 現代語訳なのでわりとすんなり読めた。
Posted by
「難しい仕事をする人を地位の重い人といい、簡単な仕事をする人を地位の軽い人という。およそ心を働かせてする仕事は難しく、手足を使う力仕事は簡単である。だから、医者・学者・政府の役人、また大きい商売をする商人、たくさんの使用人を使う大きな農家などは、地位が重く、重要な人と言える。」(...
「難しい仕事をする人を地位の重い人といい、簡単な仕事をする人を地位の軽い人という。およそ心を働かせてする仕事は難しく、手足を使う力仕事は簡単である。だから、医者・学者・政府の役人、また大きい商売をする商人、たくさんの使用人を使う大きな農家などは、地位が重く、重要な人と言える。」(p.10より引用) この主張がどうも癪に障る。わたし自身はここで言う「重い人」に該当するものの、手足を使う力仕事を簡単だと主張する福澤の語り口があまり気に食わない。 福澤の主張の9割は正しいと感じたし、愚痴っぽい主張も正直共感できた。ただ、出版物という公の場所で主張するにしては、軽度に過激な学問至上主義者で、学問から遠い場所にいると思われる人たちのことをうっすら馬鹿にしている感じを隠しきれておらず、Z世代の私としては、彼の主張は棘があるなと感じた。 まぁ日本を世界に通用させるような強い独立国家にさせるには、これくらいの愛国心と向上心が必要だなとは思う。
Posted by