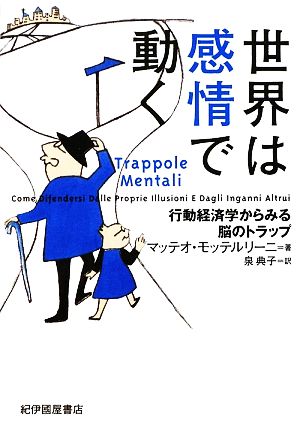世界は感情で動く の商品レビュー
同じ作者による行動経済学の二冊目の本。数ページのトピック毎に一話完結式で書かれており、どこからでも読める。前作よりはちょっと心理学よりの内容だが、一般的で平易。訳も気が利いており読みやすいが、前作を読めば十分かも。■非合理的な世界で合理的な投資の方法を探ることほど危険なことはない...
同じ作者による行動経済学の二冊目の本。数ページのトピック毎に一話完結式で書かれており、どこからでも読める。前作よりはちょっと心理学よりの内容だが、一般的で平易。訳も気が利いており読みやすいが、前作を読めば十分かも。■非合理的な世界で合理的な投資の方法を探ることほど危険なことはない(ケインズ)
Posted by
● 合理的な人とは、感情のない人ではなくて、感情のコントロールがうまくできる人なのだ。 ● 「多くの人は、熟慮していると思いながら、じつは偏見を整理しているにすぎない」ウィリアム・ジェームズ ● 人はある状況における自分の判断や行動は一般的なものであり、適切であるとみているの...
● 合理的な人とは、感情のない人ではなくて、感情のコントロールがうまくできる人なのだ。 ● 「多くの人は、熟慮していると思いながら、じつは偏見を整理しているにすぎない」ウィリアム・ジェームズ ● 人はある状況における自分の判断や行動は一般的なものであり、適切であるとみているので、他者もふつうなら自分と同じように判断し、行動するだろうと考えるのである。そして、もしそれを逸脱した他者に出会うと、その他者が特別なのか、あるいは変わった存在だとみなしてしまう。(フォールス・コンセンサス効果)
Posted by
原題(伊)“Trappole Mentali Come Difendersi Dalle Proprie Illusioni E Dagli Inganni altrui”Matteo Motterlini
Posted by
「ピークエンドの法則」 カーネマンが1999年に発表した「あらゆる経験の快苦は、ほぼ完全にピーク時と終了時の快苦の度合いで決まる」という法則 つまるところ「終わりよければすべてよし」 〜販売して終了ではなく、最後まで感謝して見送ること。 「アンカリング効果」 最初に印象に...
「ピークエンドの法則」 カーネマンが1999年に発表した「あらゆる経験の快苦は、ほぼ完全にピーク時と終了時の快苦の度合いで決まる」という法則 つまるところ「終わりよければすべてよし」 〜販売して終了ではなく、最後まで感謝して見送ること。 「アンカリング効果」 最初に印象に残った数字や言葉が、後の判断に影響を及ぼすことを言う。 〜エンドボードに安い価格を打ち出したほうがお客様は「この店は安いものを売っている」と印象をもつ。しかし反対にディスカウントショップであると 判断されて高額品をはじめから求めなくなる可能性もある。 行動経済学は「旬」な学問であり、ビジネスにも即利用できるメリットがある。商人たちが経験で培ってきた技術を現代の分析・統計から学問的な法則を見つけ出す。 すぐに使えるものは、すぐに使えなくなる、消費者は賢い。さらに先へ進む。生きている学問である。利用価値は大いにある。合理的な学問は現代受けがいいのも納得できる。
Posted by
「経済は感情で動く」読んで面白かったので買ってみたが、前作を読んでるとあまり目新しいことはなかった。 行動経済学はそこまで歴史の深いものではないので、 この手の本は1冊読めば十分なのかもしれない。
Posted by
「いかなる精神も、自分自身を考える力がなければ、十分な力は持てない。」 ―マーヴィン・ミンスキー 直感は頼りにできるのか?生活の中で存在する数々の脳のトラップ(罠)を知り、それに負けないための事典。 脱・ヒューリスティクス女!!
Posted by
「冷静な判断とは何か?」を冷静な検証で解説してくれる、迷った時には心強い本。「最大の敵は己」ということを非体育会的に教えてくれるので、クールな理屈系被害妄想タイプの人間には良い薬となってくれるんじゃなかろうか。人間の矛盾する行動というやつをおおまかに整理できるので、少しは実生活に...
「冷静な判断とは何か?」を冷静な検証で解説してくれる、迷った時には心強い本。「最大の敵は己」ということを非体育会的に教えてくれるので、クールな理屈系被害妄想タイプの人間には良い薬となってくれるんじゃなかろうか。人間の矛盾する行動というやつをおおまかに整理できるので、少しは実生活における『割り切り』ってスキルをみがけるのでは。まぁ、毒薬(タチの悪い皮肉屋になるやも)となるか解毒薬となるかはしりませんが。 にしても、カーネギーメロン大には面白い人が多い。
Posted by
認知のトラップについての書。 目に見えるもの、感じるものを絶対の事実としてどうしても認知してしまうが、人間の高度な処理能力によって、無意識のうちにフォーカスされたり編集されたりして、必ずしも真実すべてを認知しているわけではないという点に端を発した、錯覚について豊富な事例を元におも...
認知のトラップについての書。 目に見えるもの、感じるものを絶対の事実としてどうしても認知してしまうが、人間の高度な処理能力によって、無意識のうちにフォーカスされたり編集されたりして、必ずしも真実すべてを認知しているわけではないという点に端を発した、錯覚について豊富な事例を元におもしろく解説されている良書。 ただ、項目が多く、本質的には関連し合っていることも多く感じたので、もっと項目を整理・体系化されていたらもっとよかったのかなと思いました。
Posted by