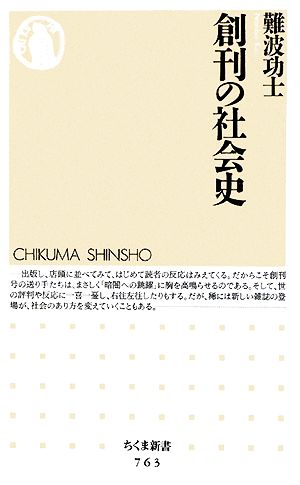創刊の社会史 の商品レビュー
電車で見るのは雑誌の広告だけで、雑誌を読んでいる人を見かけることはほとんど無くなりました。「雑誌冬の時代」という言葉さえもはや古語みたいになっている今、なんとなく7年前のこの新書を開きました。著者はほぼ同世代であり、社会学としての学術的な流れを横糸、70年代80年代90年代ゼロ年...
電車で見るのは雑誌の広告だけで、雑誌を読んでいる人を見かけることはほとんど無くなりました。「雑誌冬の時代」という言葉さえもはや古語みたいになっている今、なんとなく7年前のこの新書を開きました。著者はほぼ同世代であり、社会学としての学術的な流れを横糸、70年代80年代90年代ゼロ年代の時代の流れを縦糸とし、そこに個人的嗜好性という文様を忍ばせた、新書ならではの読み物に編み上がっています。そう、引っ越し時、昔流行で買った服を捨てようかどうか逡巡する時の胸の疼きみたいなものを感じました。それぞれの雑誌が創刊に至る経緯、そしてそこからどんどん読者を掴むために行っていく変容、それぞれの雑誌の相互性、そして廃刊へ。本書でも引用させているベンヤミン曰くの「新しい天使」は雑誌という紙の上には存在し得なくなっている今、スマホの中に居場所を見つけ出したのでしょうか?
Posted by
[ 内容 ] 創刊号をひもとくこと、それは封印された過去を追体験することに他ならない。 そこには、時代の情念がねばりつき、出版人の生あったかいドラマが織り込まれている。 本書では、「an・an」「POPEYE」「non・no」「JJ」「CanCam」「Olive」「Hot‐Dog...
[ 内容 ] 創刊号をひもとくこと、それは封印された過去を追体験することに他ならない。 そこには、時代の情念がねばりつき、出版人の生あったかいドラマが織り込まれている。 本書では、「an・an」「POPEYE」「non・no」「JJ」「CanCam」「Olive」「Hot‐Dog PRESS」「BOON」「GON!」「egg」「小悪魔ageha」などなど、70年代以降の若者雑誌をたどりながら、読者がメディアをどのように受容してきたのかをみていく。 [ 目次 ] 第1章 それは「山師」である。 第2章 それは「柳の下」である。 第3章 それは「瀬踏み」である。 第4章 それは「黒船」である。 第5章 それは「伴走者」である。 第6章 それは「兄弟姉妹」である。 第7章 それは「カレ誌」である。 第8章 それは「アウトサイダー」である。 第9章 それは「キャットファイト」である。 第10章 それは「青田刈り」である。 第11章 それは「忘れたい過去」である。 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
雑誌というメディアの魅力は何なのか。 この問いに対する明確な答えが返ってこない現状が、販売部数の減少や創刊→休刊サイクルの短期化などの現象を招いているのは明らかだ。 媒体としての魅力を失ったというよりは、媒体としてのあり方を見失ったというほうが適切かもしれない。 この本では、各...
雑誌というメディアの魅力は何なのか。 この問いに対する明確な答えが返ってこない現状が、販売部数の減少や創刊→休刊サイクルの短期化などの現象を招いているのは明らかだ。 媒体としての魅力を失ったというよりは、媒体としてのあり方を見失ったというほうが適切かもしれない。 この本では、各雑誌の生誕の背景、その派生から消滅に至るまで、時代の背景や風潮を踏まえながら考察していく。各誌にはドラマがあり、それを読む読者にもまたドラマがある。
Posted by
これはちょーおもしろい!ファッション誌に偏っているきらいはるけれど、すごく詳しく書かれているのには脱帽です。 というかギャル系の雑誌とかがおもしろすぎる…通勤電車で笑ってしまう。 「盛王GUY」って…読めますか??
Posted by
ポパイをはじめてみたのは小学校3年生のころ。その時からアメカジ。 ポパイがモノ情報をカタログ風に並べたのに対して、ホットドッグは商品情報をカタログとして提示した。 もしも雑誌業界が100人の村だったら、39人が10歳以下で、20歳以下は57名、30歳以下は70名。無事に還暦を迎え...
ポパイをはじめてみたのは小学校3年生のころ。その時からアメカジ。 ポパイがモノ情報をカタログ風に並べたのに対して、ホットドッグは商品情報をカタログとして提示した。 もしも雑誌業界が100人の村だったら、39人が10歳以下で、20歳以下は57名、30歳以下は70名。無事に還暦を迎えられるのは5名に満たない。
Posted by
いろいろな雑誌の誕生秘話とか、ある雑誌とある雑誌の意外な繋がりとかが知れて、すごくためになりました。
Posted by
ちくま新書の1冊。読み終わって,巻末の「好評既刊」を見たら,赤川 学,吉見俊哉,内田隆三,若林幹夫,と東大社会学出身の研究者が立て続けに書いていることに気づく。私はあまり新書を買わない。やはり,基本的に新書は研究者が読んで面白いようなものは滅多にないからだ。なので,新刊チェックは...
ちくま新書の1冊。読み終わって,巻末の「好評既刊」を見たら,赤川 学,吉見俊哉,内田隆三,若林幹夫,と東大社会学出身の研究者が立て続けに書いていることに気づく。私はあまり新書を買わない。やはり,基本的に新書は研究者が読んで面白いようなものは滅多にないからだ。なので,新刊チェックはしていないけど,本書はたまたま近所の図書館で,出版社が発行している,半分新刊案内を含んだ,でもフリーペーパーではなく,50円とかで売っている(だけど図書館などには寄贈される)小冊子に難波さんの小文が載っていて,本書の出版後記みたいなものがあり,知った。 難波功士さんは大学卒業後,広告代理店に就職し,暫くして休職して東大大学院の社会学に入学した。そしてそのまま研究者の道に入って,広告や雑誌の研究をしている,現在は関西学院大学の教授。 もちろん,彼の著書や論文をいくつか読んでいる私だが,前著の『族の系譜学』の前身となる文章を自分の大学の紀要に書いていて,マガジンハウス女性誌の分析のなかで,私の論文が2本ほど言及されていて,少し親近感を持った。結局,この紀要の論文があまり面白くなかったために,『族の系譜学』はまだ購入していないが,ちくま新書なら気軽に読めるし,安価なので新刊で買うことにした。もちろん,私も雑誌には興味があるし。一応,「若者向けのファッション誌・ライフスタイル誌を中心に,雑誌の栄枯盛衰の流れを概観してきた」とあるような限定つきで,日本の雑誌の創刊号について,1970年代から今日までを辿るという趣旨だ。 まあ,私も『Hanako』の研究をしているくらいだから,それなりの雑誌好きで,男性という自らの性差が故に,気軽に女性誌を見られないという制約のなかで,時折美容室で読んだり,大人になって付き合った女性の恋人の雑誌をゆっくり読んだりと,男性誌よりも女性誌に関心を持っていた私。もちろん,高校生の頃からファッションに興味を持ち出して,『Men's non-no』を何度か買っていた私は風間トヲルや阿部 寛,そしてこの雑誌のモデルから始まった大沢たかおや田辺誠一,あるいはglobeのマーク・パンサーなども雑誌でよく見ていたし。なので,本書が提示する雑誌に関する情報にはそれなりに楽しませてもらった。今日まで長い間続いている雑誌が創刊当時はとんでもない雑誌だったとか,出版同士誌の関係,親子雑誌や姉妹雑誌,などの系譜。最近は普通の男性でもてっぺんを盛り上げた奇妙な髪型をしていると思ったら,女性のギャルに続いて,男性のホスト的スタイルが雑誌などを通じて一般的になっていること。そして,普段表紙を見かけるだけで嫌悪感を抱いてしまうような雑誌の詳細まで。 まあ,確かに新書という形式ではそれほど難解な学術的含意を組み入れるのは望まれない。しかし,本書は圧倒的に雑誌の評論家的コメントに終始してしまい,これらの社会史(アナール学派的な歴史学的な含意を期待させるこのタイトルもどうだろうか)を通じて結局何が分かり何が主張したいのかということについても,「おわりに」に申し訳程度に加えられている程度だ。まあ,ともかく研究者としては物足りない一冊。新書でも,吉見俊哉や多木浩二は適所に学術的・批評的記述を織り交ぜている。 まあ,40歳間近になってまだ1冊も本を書いていない私は何も批判する権利をもっていないし,それなりに出版者的な事情も分かっているつもりだが,素直な感想をこうした半公的な場で公表しておくことも大事だと思う(少なくとも地理学雑誌に本書の書評を載せるのは難しいだろうから)。
Posted by
博報堂出身で創刊雑誌マニアの著者が綴る社会史。 研究者の心情も窺い知ることができ、エッセイ的な読み方も可。
Posted by
知らないことばっかりで面白かった! けどあんまり頭に残らなかったかも。 ただ、マガジンハウスがどういう考え方でこれまでやってきたかが見えたのはファンとして嬉しかった。
Posted by
- 1