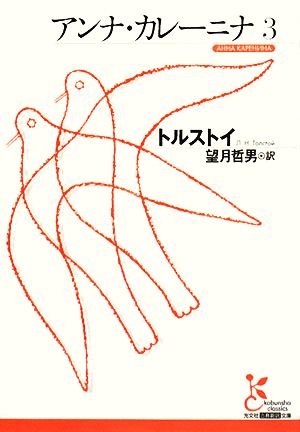アンナ・カレーニナ(3) の商品レビュー
なんだか後半は少し集中力が切れながらの読了になりました。ヴロンスキーが少しずつ今の生活に疲弊してきているのがじわじわ伝わってきて、アンナもそれに気づいているようで、二人の心情描写がしんどくなりました。
Posted by
新婚のリョーヴィンとキティの生活、そして兄ニコライの死…。アンナの息子セリョージャ再会希望の拒絶とわりあいいろいろ悲しいことが起きる。 ヴロンスキーは領主となってけっこう余裕ありそう…いろいろグループが固まっていくなかで次巻へ。
Posted by
後半の話(選挙の下り)が分かりにくかったけど、いよいよ話も大詰めとなって面白かった! 特にコズヌィシェフとワレーニカの場面の描写が美しい…。読み終わるのが楽しみです。
Posted by
第5部と第6部を収録。リョーヴィンの結婚にまつわる諸事と、徐々に行き詰まるアンナとヴロンスキーを描く。 リョーヴィン編は婚礼から新婚生活にいたるまで、出来事や心理が微細に描かれていて楽しい。しかし身近な人の死によって、自らの生死観に向き合わなくてはならなくなり、深い思索を重ねて...
第5部と第6部を収録。リョーヴィンの結婚にまつわる諸事と、徐々に行き詰まるアンナとヴロンスキーを描く。 リョーヴィン編は婚礼から新婚生活にいたるまで、出来事や心理が微細に描かれていて楽しい。しかし身近な人の死によって、自らの生死観に向き合わなくてはならなくなり、深い思索を重ねていくくだりには、誰にとっても他人事ではない切実さと、生活の忙しさにかまけてスルーしてしまっている「死」という現実への態度をどうとるかということを、強く考えさせられた。兄コズヌィシェフの求婚するかしないか?のエピソードはどこかリアルで、個人的には「その気持わかる」という結末だった。 いっぽうアンナは社交界でつまはじきにされ田舎に引き込むが、徐々にヴロンスキーとの関係や彼女自身の心に陰が生じていく。息子に無理やり会いに行くシーンはどうしたって泣ける……。不倫への淡い憧れやアンナへの好意を保ちながらも、自らの育児と家庭生活に立ち返っていくドリー。リョーヴィン側とアンナ側という、対比がより際立っていく2つのカップルの間を行き来する彼女の視点が興味深い。 恋愛や結婚だけではなく、様々な要素が織り込まている本作。3巻では重層的な物語空間に人々がいきいきと生きている感覚が強まり、どっぷりとこの世界にハマらせてくれる。
Posted by
5部はとにかくカオスで面白い。 まずはリョービンとキティの結婚式から始まるのだが リョービンのあの性格ゆえ、そう簡単には行かない。 やはり自分などキティが愛してくれるのだろうか? 思いとどまるなら今だと、キティに告に行くが… たぶん5分後には仲直り。 式の当日には、シャツを荷物...
5部はとにかくカオスで面白い。 まずはリョービンとキティの結婚式から始まるのだが リョービンのあの性格ゆえ、そう簡単には行かない。 やはり自分などキティが愛してくれるのだろうか? 思いとどまるなら今だと、キティに告に行くが… たぶん5分後には仲直り。 式の当日には、シャツを荷物と一緒に馬車で送ってしまったとかなんとかで…花婿大遅刻! リョービンの兄、ニコライの最後。 看取りのためについて行くと聞かないキティに困惑するリョービン。しかし、キティは、保養所での経験を活かし、ニコライに誰よりもつくし、働く。 その姿にまた己の情けなさに落ち込むリョービン。 そして、私の心配どころセリョージャ! 彼は誕生日にママが会いに来てくれるとどこかで信じている!! カレーニンは、イワーノヴナ伯爵夫人の手中にあり、宗教へと導かれる。 そこへ、アンナ!私たちのアンナ! 全てを振り切って、札束を小間使いに投げわたし、家に入ってゆく。愛しいセリョージャの誕生日祝いに。 後半6部は、 ドリーが子どもたちとリョービン夫妻の家で過ごす夏。彼女の主婦らしさ。 そして、リョービンの家から馬車でアンナを訪問に行く。 アンナとヴロンスキーの贅沢な暮らしぶりに辟易としつつも、彼女は決して人前で悪く言わない素晴らしい女性。幸せにいて欲しい。 リョービン、ヴロンスキー、オブロンスキーたちは選挙へ。 留守中のアンナの精神状態。 もうアンナはヴロンスキーに好かれるために必死。 ドリーにも説得され、カレーニンとの離婚を考え始める。。 と、こんなカオスぶり。 リョービンとキティの幸福な家庭ぶりと、 見せかけだけの、壊れてゆくようなアンナとヴロンスキーの行く先との対比を描く、 とくにアンナとリョービンの中にある感情のゆらぎ方とか、 トルストイの表現の上手さといったら!
Posted by
社交界から排除されたアンナ、ヴロンスキーと農村生活を送るキティ、リョーヴィンそれぞれの交友関係の描写が面白い。家族にしろ地域社会にしろ地方行政や官僚組織にしろ、システム化されているように見えても結局、動かしているのは人であることがわかる。人であれば、厳格、安定してるようであっても...
社交界から排除されたアンナ、ヴロンスキーと農村生活を送るキティ、リョーヴィンそれぞれの交友関係の描写が面白い。家族にしろ地域社会にしろ地方行政や官僚組織にしろ、システム化されているように見えても結局、動かしているのは人であることがわかる。人であれば、厳格、安定してるようであっても、脆さもあり、そのあたりの微妙な心理状態を上手く描いていると思う。 「「結局、あの時アンナさんが来てくれて、キティは助かったのね」ドリーは言った。「ただしあの方にとっては不運だったけれど。本当に、すっかり逆になったわけね。あの時はアンナさんがとっても幸せそうで、キティは自分を不幸に思っていたでしょう。まったくどんでん返しじゃない」p303 「アンナはもっぱら談話のリードの面でホステス役を務めていた。このような少人数の食卓で、おまけに管理人や建築士のようにまったく別世界の人間が混じって、慣れない贅沢な環境に怖気づかぬようがんばりながらも、全体の談話に長くは混じれないでいるような場合、ホステス役が談話を盛り上げるのはきわめて難しいものだ。だがドリーの見るところ、アンナは持ち前の如才なさで、その難しい役割をいとも自然に、むしろ喜んで勤めているようであった」p486 「享受している権利に見合った義務の感覚がないために、そうした義務を否定してしまうわけです」p493
Posted by
内容も面白いが最後の読書ガイドが素晴らしい 長編だからついつい以前のエピソードの事を忘れてしまいそうだけどこれを読み事により全体を把握出来大きな流れを失わずにいられる。
Posted by
アンナさん、生まれてくる時代を間違えた? 21世紀だったら、この生き方全然ありのような。 あるいは、それならそれで、もっと破天荒になってんのかな? まともな感想は最終巻で。
Posted by
アンナとリョーヴィンの状況が段々すり替わっていくかのように、アンナは不幸にリョーヴィンは幸せに近づいている感じがする。
Posted by
ぐいぐい引き込まれる面白さがある。 長編だが、「だれる」感じが全くない。 本巻巻末の解説は、本書のみならず読書一般に深みを与えてくれるものかもしれない。
Posted by