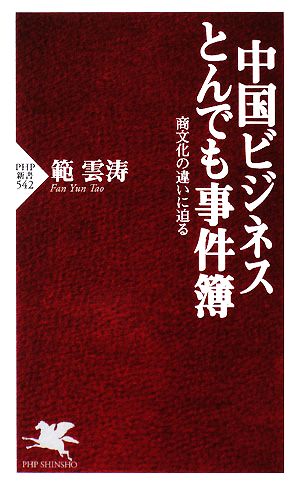中国ビジネスとんでも事件簿 の商品レビュー
弁護士の視点から、中国における法的リスクを具体的事例を挙げながら指摘している本。エピソードには少し笑った。
Posted by
サブプライムショックが起きた昨年でも好調な成長をした中国は10年以内には日本のGDPを抜いて、いずれはアメリカも抜くといわれています。もともと人口の多い国(インドや中国)が200年位までは世界1を争っていたのでそれは良いとしても、現在中国が経済成長を続けている中で、商習慣の違いに...
サブプライムショックが起きた昨年でも好調な成長をした中国は10年以内には日本のGDPを抜いて、いずれはアメリカも抜くといわれています。もともと人口の多い国(インドや中国)が200年位までは世界1を争っていたのでそれは良いとしても、現在中国が経済成長を続けている中で、商習慣の違いによるトラブルが発生しているようです。 この本はこのような中国でのビジネストラブルを長年にわたって解決されてきた弁護士の範氏によって書かれた本です。私の会社においてもアジアエリアの首都機能が、シンガポールから中国(北京、上海)に移されようとしていますが、今後益々、中国とのつながりが密接になっていくと思われますので、その意味でも参考になる本でした。 中国人は欧米人とにて権利を強く主張するタイプであり、日本人とは異なるため、弁護士さんの仕事も繁盛することになるのでしょうか。 以下は気になったポイントです。 ・本来であればメーカー側の製造物責任を追及すべきところを、CM広告出演者の過った消費者誘導行為を訴えられることになったケースがある(p79) ・中国企業でビジネスマンとして一流と目される条件として、1)豊富な専門知識と長い経験、2)状況・契約内容を冷静に分析、対策を論理的に組み立てる能力、3)計画を推進する実行力、リーダーシップ、4)リスクを回避する危機管理能力、である、(日本でも同じか)(p86) ・黄河より北部においては、トウモロコシ、高粱、大麦等を原料にする高アルコール度数の蒸留酒が好まれる、南部は米材料としたアルコール度数20度前後のもの(p92) ・中国では「主任」と言う肩書きは、中央省庁クラスでは、国務大臣を意味する組織の中ではもっとも偉い役職、職位・職級の前に「高級」「一級」という言葉が好まれる(p96) ・契約を交わす前に、弁護士による条文のリーガルチェックをせず、現地の通訳だけに頼って手続きをすると、とんでもないトラブルに巻き込まれるケースあり(p103) ・中国で気をつけるべき記念日、1月28日(上海事変勃発)、5月3日(重慶、日本軍の無差別爆撃)、5月9日(国恥記念日:対華21か条受け入れ)、9月18日(満州、日本に占領された日)、12月13日(南京陥落)(p110) ・タクシーに乗るときの注意、フロントガラスの星の数(3つ以上なら優秀ドライバー)、車体番号・運転手登録番号を記録しておく(p115) ・人間の交渉行動には3パターンあり、1)ハト派;13%(中長期的な視野に立って利益の最大化を考える)、2)タカ派;20%(他人に譲歩を迫り、取引における優勢性と主導権を握ろうとする)、3)サル派:67%(ギブアンドテイク、相手との相互依存関係を考える)、である(p133) ・日本人は義務意識型(権利を強く主張しない、義務の履行を強く求めない)に対して、欧米・中国人は権利意識型(日本人の反対)である(p161) ・中国は法体系のハードウェアについては備えられてきたが、肝心のソフト面(法の執行、解釈、適用上の統一性、厳格性、確実性)は、満足なレベルに達していない(p174) ・日系企業の対中ビジネスにおいて、中国人弁護士にしかできない役割があるので注意を要する(p191)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 不倫相手の日本人上司に、マンションや高級車を購入させた挙げ句「青春損害賠償」を要求した上海女の手口。 「台湾」の表記の仕方を誤って営業停止を食らうも、妙案によりブランドイメージを好転させた日本のラーメンチェーン。 政府高官が出席する会談で、卓上にバナナが山盛りになっているといった仰天エピソード…。 日系企業の「駆け込み寺」と呼ばれる弁護士の豊富な経験談から、日本と中国の商文化、法文化の違いが見えてくる。 契約の際の注意点、弁護士の選び方など、実践的アドバイスも満載。 [ 目次 ] 第1章 実録!日本人が嵌められた上海ガールの罠(行きずりの恋人ごっこ;あるエリート商社マンの上海夜曲伝説 ほか) 第2章 唖然!中国ビジネス交渉風景(欧米企業と日本企業の違い;現地スタッフを味方につける言葉 ほか) 第3章 刮目!日中契約文化の相違(対中交渉に向いていない日本人;中国人との交渉の極意 ほか) 第4章 実践!中国でトラブルを起こさないために(「チャイナリスク」にどう対処すべきか;「権力」が支配する超大国 ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
中国ビジネスへの興味本位で読むのには適さないと思う。 序盤のエピソードはそれなりに面白かったが、 別に中国固有のことでもないんじゃない?と思うものも多かった。 後半は細かい説明になって、専門知識がないと 難しいのだろうと思った。 私は途中で読むのを辞めた。 中国で仕事をする...
中国ビジネスへの興味本位で読むのには適さないと思う。 序盤のエピソードはそれなりに面白かったが、 別に中国固有のことでもないんじゃない?と思うものも多かった。 後半は細かい説明になって、専門知識がないと 難しいのだろうと思った。 私は途中で読むのを辞めた。 中国で仕事をすることが決まって差し迫っている人、 弁護士などの法律家などのための本としてはいいのかもしれない。
Posted by
北京オリンピック以後に、中国絡みで 必読書として取り上げられていた中の1冊です。 中国ビジネスでのトラブルを弁護士である 筆者の視点で紹介している。 こういった中国ビジネスに関する本は極力読んでいますが、 本書もそういった本の類です。 筆者が日中双方の視点を持てる人ですので...
北京オリンピック以後に、中国絡みで 必読書として取り上げられていた中の1冊です。 中国ビジネスでのトラブルを弁護士である 筆者の視点で紹介している。 こういった中国ビジネスに関する本は極力読んでいますが、 本書もそういった本の類です。 筆者が日中双方の視点を持てる人ですので、 ただの悪口本にもならず、 チャイナリスクを知るには もってこいの本だと思います。 今春から中国駐在なんて人にもお勧めです。 事例が身近なことを取り上げていたり、新しいケース だったりで、 類似の本を持っている人でも読んでみる 価値があるかもしれません。 学研の地球儀の話だとか、味千ラーメンの話だとか。 小姐に引っかかって、人生を台無しにはしたくないですね。 http://teddy.blog.so-net.ne.jp/2009-03-19
Posted by
- 1