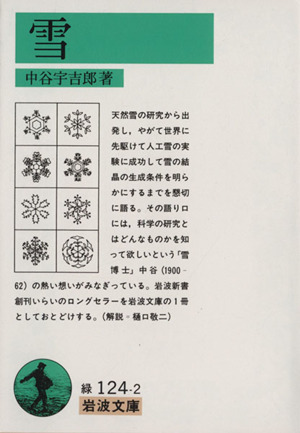雪 の商品レビュー
雪の結晶の分類など細かいところまで入り込んでいくと、まさにミクロの話しでちょっとついていけなくなる(じっさいかなり斜め読みしてしまった)。それよりも著者も述べているように、自然科学の研究とはこういう風にして進めていくのだ、ということがわかればよい、というスタンスで読んでいくとおも...
雪の結晶の分類など細かいところまで入り込んでいくと、まさにミクロの話しでちょっとついていけなくなる(じっさいかなり斜め読みしてしまった)。それよりも著者も述べているように、自然科学の研究とはこういう風にして進めていくのだ、ということがわかればよい、というスタンスで読んでいくとおもしろい。自分が好きだと思える者の研究に心から打ち込め、それでご飯が食べられるというのは何ともうらやましいことだ。もちろんそこに行くまでにはいろんな苦労があるわけだが。その苦労や失敗をあえて書いていないという指摘が読書会では出たな。
Posted by
あまり真面目な本を読んできていなくて,どう選べばよくわからないなー→とりあえず松岡正剛の千夜千冊で紹介されてる本を読んでみるか→ではまず1冊目から,という経緯で読んでみた。おすすめタグに「松岡正剛千夜千冊」が出てきたのを見るに,他にもそういう感じで読んだ人がいるのかな… 読んでい...
あまり真面目な本を読んできていなくて,どう選べばよくわからないなー→とりあえず松岡正剛の千夜千冊で紹介されてる本を読んでみるか→ではまず1冊目から,という経緯で読んでみた。おすすめタグに「松岡正剛千夜千冊」が出てきたのを見るに,他にもそういう感じで読んだ人がいるのかな… 読んでいて思ったのは,「あー,これがサイエンスコミュニケーションか」ということ。というかこの時代にそういうことを考えて物を書いていた人がいる,というのはすごいことのような気がする。寺田寅彦の存在があったから,というのもあるかもしれないけれども。ちょうど雪も降り始めた時期だったので,読んでいて楽しかったです。 次は2冊目を読もうか,それともリンクに書かれていた本を読もうか。次に読む本を悩むのもちょっと楽しい。
Posted by
高野文子の「どみとりーともきんす」を読んで。 雪の研究者による雪のエッセイ。柔らかい文章の中にも、科学の眼差しがしっかりあるのはやはり学者らしい。
Posted by
初めて人工雪を作った。 今では、夏休みの自由研究にもなっているが、当時の測定環境は大変だった。 科学とは、まさに巨人の肩に乗るのものだ。
Posted by
「雪は天から送られた手紙である」という有名な一節の原典はこの本である。 物理学者、中谷宇吉郎による、現在の版で本文170ページほどの本(中谷は「この小さい本」と読んでいる)は、昭和13年の初版時には、岩波新書から出されたという。書き下ろしの一般啓蒙書として世に送り出されたわけであ...
「雪は天から送られた手紙である」という有名な一節の原典はこの本である。 物理学者、中谷宇吉郎による、現在の版で本文170ページほどの本(中谷は「この小さい本」と読んでいる)は、昭和13年の初版時には、岩波新書から出されたという。書き下ろしの一般啓蒙書として世に送り出されたわけである。 以来、一時期は絶版に近い状態にも陥りつつ、平成6年に岩波文庫の1冊として刊行されることになる。時代を超えた「古典」と認められたといってもよいだろう。 中谷がここでしようとしていることは、狭義には、雪の結晶の観察およびその再現である。つまり、結晶を観察してその形状を分類し、温度・湿度などの外的条件と結晶の形状を関連づけ、人工的に結晶を作る装置を使って、自然と同様の雪の結晶を再現することである。 だが、本書は、もっと広く、「科学的に考えるということ」の1つの例を、研究者自らが語り起こしたものだといってもよい。 雪とは「水が氷の結晶となったもの」である。上空、高いところで結晶の核ができ、下界に舞い降りてくる間に徐々に成長する。空気に含まれる水蒸気が、芯となるものの周囲で固化して雪になる。 雪は白く、そしてときにきらめく美しい結晶を作る。 中谷も雪の結晶の美しさに魅せられる1人だった。北海道に職を得たこともあり、雪の結晶の研究に取り組むことになる。さまざまな工夫を重ねつつ、まずは顕微鏡写真の撮影に成功する。十勝岳を拠点とし、丹念な記録が始まる。どのような形のものが、どの程度の頻度で降ったか、そしてそのときの気象条件はどのようであったか。 世間では以前から、「雪は六花の形をしている」といわれていた。国内外でそれまでにも雪の結晶の図や写真はあったが、多くはこの六角形のものだった。だが、中谷らの研究の結果から見えてきたのは、六角形の結晶ももちろんあるが、針状や角柱、角柱や平板が組み合わされたもの、無定形など、形状はさまざまであり、雪はそうした雑多な結晶の集まりであるということだった。また、針状のものが比較的多く見られた。 さらに中谷は、天然の雪を再現する、人工の装置の開発にも取り組む。こうした装置が出来れば、雪の結晶が成長する過程をより詳しく研究できるし、また条件によって結晶の形がどう変化するかもより細かく見て行くことができる。 より自然に近い形で雪を作るには、どんな装置が適しているのか。試行錯誤しながら、装置の調整が続く。 ここに述べられているのは、世紀の大発見というわけではないかもしれない。多くの人にとって、雪の形がどうであろうと、あまり関係がないといわれればそれもそうかもしれない。そもそも雪の結晶の研究や、人工雪については、この本より新しい知見が出ているだろう、というのもその通りだろう。 では、本書が「古典」として価値があるのはどこか。 それは「科学的思考と実践」が述べられている点だろう。中谷はここでは、科学的に詳細に記載するよりも、一般の人に科学の「道筋」を示すことに重きを置いているように見える。 研究は一直線では進まない。実験しようと思ってもうまくいかないことも多い。仮説を立ててもそれがどうも正しくないようだとわかることもある。立ち止まってまた考える。こうしたらどうだろうか。実はこうなんだろうか。そしてまたやってみる。中谷は、本書中で、「研究というものは、このように何度でもぐるぐる廻りをしている中に少しずつ進歩していくもので、丁度ねじの運行のようなもの」だと語っている。 そういった一連の過程が、生き生きと、ときに熱く、示されているところに、本書の今に生きる意義がある。 冒頭の「雪と人生」と題される章では、雪が人々の暮らしに与える影響に触れている。雪は美しいばかりではなく、雪国では雪害を起こして「白い悪魔」と称されることもある。冬中、田野が雪に覆われて使えない上、除雪が必要となるなど経済的な損失も大きい。一方で、雪上で橇を使えば運搬にはむしろプラスになることもあるし、レジャーなどでの魅力もある。 本書の大半は、基礎科学にかかわる内容だが、中谷は、どこか遠い将来に、雪の結晶の解明が、実用・応用に役立つ可能性を心に描いていたようにも思える。 基礎と応用はそれぞれ別々ではない。基礎研究に取り組みつつ、どこかで社会への還元も考えること、それも科学者の「責務」と言えるのだろう。 一流の科学者でありつつ、名随筆家としても知られた中谷ならではの1冊だろう。
Posted by
炎暑である。そんな日にやっと読めた。高野文子「ドミトリーともきんす」という読書案内漫画で紹介されていた本の第一弾である。 一つ気がついたのは、やはり私の頭は理系ではない。詩的な或いは散文的な文章が多いところは、すらすらと読めるのだけど、いったん科学理論的な文章になるとなかなか進...
炎暑である。そんな日にやっと読めた。高野文子「ドミトリーともきんす」という読書案内漫画で紹介されていた本の第一弾である。 一つ気がついたのは、やはり私の頭は理系ではない。詩的な或いは散文的な文章が多いところは、すらすらと読めるのだけど、いったん科学理論的な文章になるとなかなか進まなかった。 (すじ雲やうす雲などの上層雲は)日本では一万米以上のことが多い。かかる上層の雲は水晶であるということは前に述べた通りである。されば、夏の日地上のわれわれが炎暑に苦しめられてあえいでいる時、上層を流れる白雲の世界は零下十度あるいはずっとそれ以下の寒冷の大気に充ちているのである。(69p) さて、雪は高層において、まず中心部が出来それが地表まで降ってくる間、各層においてそれぞれ異なる生長をして、複雑な形になって、地表にたっすると考えなければならない。それで雪の結晶形および模様が如何なる条件下で出来たかということがわかれば、結晶の顕微鏡写真を見れば、上層から地表までの大気の構造を知ることができるはずである。そのためには、雪の結晶を人口的に作ってみて、天然に見られる雪の全種類を作ることができれば、その実験室内の測定値から、今度は逆にその雪が降った時の上層の気象の状態を類することができるはずである。 このようにみれば雪の結晶は、天から送られた手紙であるということが出来る。そしてその中の文句は結晶の形及び模様という暗号で書かれているのである。その暗号を読みとく仕事が即ち人口雪の研究であるということも出来るのである。(162p) 「天から送られた手紙」という文句だけが一人歩きして、単なる「詩的な言葉」であると思っていた人が多い(←私か)と思うが、実はかなり「科学的な言葉」であり、かつ、「科学の社会的な役割」を意識した言葉でもあったのだ。それは、この本の第一「雪と人生」で、「アメリカへ支払うラッセル車一台の購入費を投げ出して、日本に降る雪の性質を根本的に研究したならば、日本のために真に役立つ除雪車は必ず出来るに違いない」(31p)と書いているのに繋がる。 人間的な科学者がここに居る。 2015年8月読了
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトル通り、雪の結晶について書かれたものですが、分かりやすい文章と内容で、科学書の中では親しみやすい方ではないでしょうか。 「…雪の結晶は天から送られた手紙である…」 の名文を残した中谷宇吉郎本人に興味を持った私でしたが、読み進むうちに、その興味は、一気に雪の結晶へとシフト。 著者と一緒に研究作業を進めているような感覚に落ち入りました。 雪(自然科学)を研究する楽しさ。ひとつのことを深く考え、辿っていく面白さを純粋に味わえる一冊です。 雪嫌いの方も、是非ご一読を。 雪への見方が変わりますよ。(T)
Posted by
実際は学問的な難しいところもありながらも,うつくしく,誰でもわかるように説明する能力はすばらしいものである.この本は実際の研究のほんの一部であるだろう.さらに,あたかも簡単なように書いてあるが,さまざまな工夫や困難のもとになしえた結果であることは少し考えれば想像できる.ともかく,...
実際は学問的な難しいところもありながらも,うつくしく,誰でもわかるように説明する能力はすばらしいものである.この本は実際の研究のほんの一部であるだろう.さらに,あたかも簡単なように書いてあるが,さまざまな工夫や困難のもとになしえた結果であることは少し考えれば想像できる.ともかく,研究をこのような形で発表できる高い技術に感激する.
Posted by
文章が美しい本。 とりあえず本論に入る前の第1章「雪と人生」。主張のひとつは「雪の降らぬ地に生活しているものに向かって、雪の災害を説き知らせることは至難のこと」というもの(初めに引用する『北越雪譜』という本の主旨らしい)。 そしてもうひとつは、「日本において雪の研究をもっと真剣...
文章が美しい本。 とりあえず本論に入る前の第1章「雪と人生」。主張のひとつは「雪の降らぬ地に生活しているものに向かって、雪の災害を説き知らせることは至難のこと」というもの(初めに引用する『北越雪譜』という本の主旨らしい)。 そしてもうひとつは、「日本において雪の研究をもっと真剣にしなければならぬ」ということで、こちらがメイン。 但し力ずくで説き伏せるのではなく、むしろ雪(国)に対する人々の生きざま・苦しみざまを丁寧に描写することで、いいたいことを自然に繰り返す構成は、説得力に満ち、心地よくさえある。 もっとも、主張への共感を求めるためにしたたかにそうしたというよりは、そもそも著者中谷自身が研究のモチベーションの底に社会性を抱きかつ保っているのだろうと敬意を抱くのだが。 雪の結晶の形状にもさまざまな姿があるとの話。涙ぐましいほどの努力が含まれていそうな内容で、ミクロな話なのに読んでいて手に汗握る。 それにしても、読んでいて心地よさを覚える。 研究の目的に「雪の本質を知りたい」ということと「雪とは天から送られた手紙であり、その暗号を読み解きたい」ということを併記しているロマンティックなところが好きた。 また、「とにかく、よく観る」という手法を徹底的に重視したり、「研究とは丁度"ねじ"の運行」と言って、その迂回を繰り返す方法論を示していたりするのも印象的。 「おっ」と思うのは、中谷の、研究(成果)への"謙虚さ"。「分かったみたいな書き方だけど、分からないこと(謎)はまだ多い」「ここに示した類型化も不十分("不定形"も案外多い」と言い切る謙虚な姿勢は、中谷の業績への自信の裏返しかもしれない。 ただ私にはそれが「読者へのきめ細やかな配慮」の現れであるように感じられてならない。文中でも度々、"読者への"メッセージを発しているし、述べる内容(レベルと量)の"調節"もしばしばうかがえる。それでいて、研究や観測の面白さ(及びそれを伝えるエピソード)は存分に伝えてくれる。"知識の本"ではない"知恵の本"との解説も見事。学生にうちに、こんな"ロマンティシズム"と"人間味"に満ちた研究の本を、読んでおきたかったものである。
Posted by
「雪の結晶は、天から送られた手紙である」という趣深い一文で有名な本作だが、同時にこれほどまでに科学的誠実さに溢れた本が他にあるだろうか。降り積もる雪のひと欠片を丁寧に観測し、吹きすさぶ冬景色の中、時には氷点下の実験室で根気強く分析を続けていく。やがてその研究は雪の結晶の多様性を明...
「雪の結晶は、天から送られた手紙である」という趣深い一文で有名な本作だが、同時にこれほどまでに科学的誠実さに溢れた本が他にあるだろうか。降り積もる雪のひと欠片を丁寧に観測し、吹きすさぶ冬景色の中、時には氷点下の実験室で根気強く分析を続けていく。やがてその研究は雪の結晶の多様性を明らかにし、世界初の人工雪の作成という偉業に結び付いた。エッセイ風に書かれた文章は理性的でありながらも簡潔な説明の中から気品の良さが滲み出ており、本人曰く「茶漬けのような味」の内容は滑らかに入ってくる。自然科学入門として最良の一冊。
Posted by