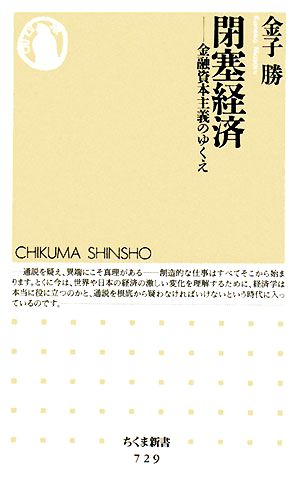閉塞経済 の商品レビュー
主流派(新古典派)経済学と非主流派の関係性を実際の経済政策に当てはめて整理できた。 全体的に新書ゆえのさらっと感、主張(結論)中心で説明が少ない印象があり、下記は自分で確認したい。 ○2004年年金改正など社会保障の話 ○新古典派は本書が批判するように単純なのか 構造改革の全体像...
主流派(新古典派)経済学と非主流派の関係性を実際の経済政策に当てはめて整理できた。 全体的に新書ゆえのさらっと感、主張(結論)中心で説明が少ない印象があり、下記は自分で確認したい。 ○2004年年金改正など社会保障の話 ○新古典派は本書が批判するように単純なのか 構造改革の全体像、情報の経済学、インセンティブなども詳しく知りたくなった。
Posted by
バブルの発生メカニズムとその要因、新自由主義とケインジアンとの相克、経済と倫理との関わり、の3つのテーマについて大括りで語られている。 どれも説得力のあるロジックではあるが、どの経済学者の主張もそれぞれに説得力があり、一体どれが真実なのかわからなくなる。従って本書も素直に100%...
バブルの発生メカニズムとその要因、新自由主義とケインジアンとの相克、経済と倫理との関わり、の3つのテーマについて大括りで語られている。 どれも説得力のあるロジックではあるが、どの経済学者の主張もそれぞれに説得力があり、一体どれが真実なのかわからなくなる。従って本書も素直に100%信頼することができない。例えば、経済政策として教育と再生可能エネルギーへの投資が重要というが、見習うべき例として挙げられていたドイツQ-Cellsは既に中国企業の手に渡り、FIT制度も破綻の危機にある。 結局歴史のフィルターを通してしか経済政策の正しさを証明できないとすれば、果たして経済学はこれでも科学といえるのだろうか? 最終章の倫理学と経済学の深い関わりは当然の帰結に思える。詰まるところ経済学とは哲学である。
Posted by
今日の世界を覆っている不自然な金融資本主義では、バブルや格差の発生は不可避である一方で、もはや神の手も公共対策も十分に有効ではないとの主張です。危機感はよく伝わってきましたが、それでは具体的にどんな処方箋が市民に受け入れられ得るかという点は言及が少ないと感じました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
古典経済学ではうまく説明していない、所謂バブルについての解釈が興味深い。 著者の説によると、金融改革を経て以降の世界ではバブルの成長と破綻はなるべくしてなると。 また、経済の中ではとかく原因と結果が逆に見られているのではないか、という意見に新鮮味があった。 経済学という側面から見ると、世界は発展しているのか、混迷しているのか、はたまたそういう見方自体がすでに何かしらのイデオロギーに染まっているのか、考えさせられる。
Posted by
[ 内容 ] サブプライムローン危機が世界を揺るがしている。 その原因を知るには、バブルの発生・崩壊のメカニズムと、七〇年代以降の世界のお金の流れを押さえる必要がある。 一方、日本国内を見ると、九〇年代以降、政府当局は「構造改革」と「金融自由化」により長期不況を脱する道を選んだが...
[ 内容 ] サブプライムローン危機が世界を揺るがしている。 その原因を知るには、バブルの発生・崩壊のメカニズムと、七〇年代以降の世界のお金の流れを押さえる必要がある。 一方、日本国内を見ると、九〇年代以降、政府当局は「構造改革」と「金融自由化」により長期不況を脱する道を選んだが、この選択は果たして正しかったのか。 政策のバックにある主流派経済学では、もはや問題を解決できず、格差の拡大など、社会の傷を深くするばかりだ。 経済学の限界を指摘し、日本社会の現状と将来を見据えた新しい経済学の可能性を探る。 [ 目次 ] 序 戦後最大の米国不況をどうとらえるか?金融資本主義の経済学 第1章 バブルの経済学-サブプライム危機はなぜ起きたか(バブルはなぜ起こるのか バブルはなぜ繰り返されるのか バブル崩壊に対して経済学は役に立つのか) 第2章 構造改革の経済学(供給サイドか需要サイドか 構造改革はどういう結末を迎えたのか 制度改革にはどういう思想が必要か) 第3章 格差とインセンティブの経済学(「正義の問題」と経済学 インセンティブ理論の落とし穴 新しいタイプの不平等) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
現資本主義体制の限界を露呈している。 政府及び中央銀行が行う需要側・供給側からの財政政策と金融政策の繰り返しは、もはや現在の経済には通用しなくなっており、その限界がサブプライプをはじめとする証券のバブル崩壊で明らかになった。 アメリカの経済、そしてそれを追随している日本経...
現資本主義体制の限界を露呈している。 政府及び中央銀行が行う需要側・供給側からの財政政策と金融政策の繰り返しは、もはや現在の経済には通用しなくなっており、その限界がサブプライプをはじめとする証券のバブル崩壊で明らかになった。 アメリカの経済、そしてそれを追随している日本経済は現状体制のままでは大丈夫なのだろうか。 この著はそんな問いをかけている。 具体的な答えを金子氏が述べているわけではないが、その懸念を私たちに感じさせる良書だと思う。 ぜひ金子氏の論文を読んでみたいと思った。
Posted by
なぜ貧者を救うべきか、社会として「機会の平等」と「結果の平等」のどちらを選ぶべきか、ということを考えさせられた。
Posted by
読めませんでした。 内容が高度過ぎるのか悪文なのかも分かりません。 いずれ再チャレンジしたいです。
Posted by
第一章:バブルの経済学 第二章:構造改革の経済学 第三章:格差とインセンティブの経済学 かなり読みやすかった。 一貫して新古典派経済学への批判。 (竹中、小泉さんへの批判は少しうけた) サブプライムについて述べている本かと思いきや、 アメリカを代表とする現代資本主義経済の限...
第一章:バブルの経済学 第二章:構造改革の経済学 第三章:格差とインセンティブの経済学 かなり読みやすかった。 一貫して新古典派経済学への批判。 (竹中、小泉さんへの批判は少しうけた) サブプライムについて述べている本かと思いきや、 アメリカを代表とする現代資本主義経済の限界について述べられていた。 バブル以降日本が模倣してきたアメリカの金融体制。しかし、実際はバブルが崩壊すると金融緩和、また新しいバブルを待って・・の繰り返しでごまかしてた。挙句、世界中にリスク分散させ失敗し、不況は全世界に波及してしまった。アメリカ型の金融政策を行ってきた日本の危うさを感じさせてくれました。 でも、個人的には、第三章が興味深かった。 「大きな政府」か「小さな政府」か。 →縦軸にGDP, 横軸に政府規模をとった場合、ここに相関関係は存在しないらしい。 小さな政府の成功例…アメリカ 大きな政府の成功例…北欧 では、これから日本政府はどうすればいいのか。現在注目されているのは、北欧の社会政策(Flexicurity)かと。ただ、これをすぐさま日本にそのまま導入出来るかというと難しいところ。現状の税制などとかなりのギャップがあるかと。ただ、アメリカの模倣で失敗した日本。さまざまな社会問題が浮き彫りになっている日本。現状の政策を維持し続けていてはいつか崩壊することは氏も述べている通り。 感想としては、現状経済に対し政府はどんな政策をとっていくべきなのかについてもっと言及してほしかった。 余談ですが、ロールズの『正義論』を読んでみたくなりました。 てか、やっぱ金融苦手。
Posted by
サブプライムローン問題やその背景となったマネーの流れがよく分かります。 筆者の通説を疑う視点は僕も見習いたいと思いました。 先生の授業を実際に受けるのが楽しみです。
Posted by
- 1