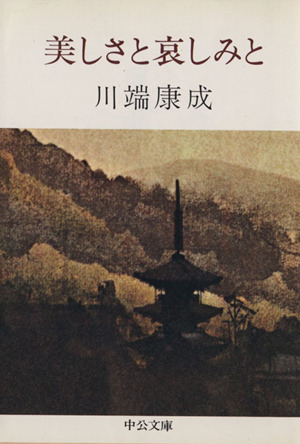美しさと哀しみと の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
美しさと哀しみと 著者:川端康成 発行:1973年8月10日 中公文庫 初出:1961年1月~1963年10月「婦人公論」 中学時代の同級生Oさんから教えられた作品。今年、50年ぶりぐらいに川端作品をひょんなことから読み返し、読書メモをポストしていたらOさんが教えてくれた。昔、白雪劇場でドラマ化され、それが面白かったので原作を読んだけどテレビの方がよかったというようなことを教えてくれた。僕の感想は、ちょうど半分あたりまではとても面白かったが、そこから急につまらなくなった。最後の落ちも、特段驚くべき点がなかった。 鎌倉に住む小説家の大木年雄が31歳の時、まだ16歳の女学生・上野音子を口説いて妊娠させてしまう。しかし、音子は妊娠8ヶ月で流産し、自殺を試みるが、一命は取り留め、一時入院させられる。そこは鉄格子のある病院、すなわち精神科だった。その後、音子の母はこの酷い男のことを忘れさせるために母娘で京都に移住する。音子は日本画家として名をあげる 音子が流産した時、大木年雄には妻子がいたが、2年後にはこの体験をもとにした小説「十六七の少女」を書き上げる。それは彼の代表作となり、ロングセラーとして一家の暮らしを支えることになる。 年雄は執筆した作品を文子にタイプさせる。「十六七の少女」をタイプしている途中、文子は妊娠したが、打ち終わって5、6日後に流産。出版すると再び妊娠、出産。 音子がその小説のモデルだと知れたのは、年雄が50歳を過ぎて作家としての地位があがってからのこと。 流産して別れた事件があってから24年。年雄は除夜の鐘を聞きに12月29日から京都へ一人で出向いた。目的は、音子と再会して二人でそれを聞くためだった。小説はここから始まる。京都についたとき、年雄を迎えにきたのは音子ではなく、音子の若い弟子で美人の坂見けい子だった。 前半は年雄と音子の過去の話が中心となり、後半はそこにけい子が入る三角関係、さらには年雄の息子・太一郎が関わる四角関係となり、年雄の妻である文子も加わってのややこしい関係が展開していくことになる。 ************ 除夜の鐘は、知恩院の近くで聞く。年雄、音子、けい子の3人。元日に帰郷する列車を見送りに来てくれたのはけい子一人。音子の絵をくれた。けい子は東京出身だから鎌倉など珍しくもだいだろうが、上京したら寄ってくれと言い残して年雄は帰郷。絵は音子の落款があるので自宅には持ち帰れず、別のところに置くことに。 年雄の留守中に、けい子が訪ねてきた。自身の描いた絵を2枚、置いて帰っていった。息子の太一郎がけい子を送りがてら、鎌倉案内をした。建長寺ほか。その日、年雄は会えなかった。 次にけい子が訪ねて来た時は、家には年雄一人しかおらず、2人で出かけて泊まった。同衾し、セックス直前に彼女は音子の名を叫び、セックスはしなかった。その前、彼女は左の乳房を絶対に触らせなかった。右はいいが左は嫌。理由は不明だった。形など変わらないし。 音子とけい子は、実は同性愛的な間柄だった。お互いの体を触り愛、かみ合い、なめ合い・・・性交に至っているかどうかは表現されていない。けい子は、音子があるコンテストで入選した絵を見て、音子の美しさに惹かれて弟子入りした。音子もけい子の美しさに惹かれていた。 けい子は、大好きな音子先生を苦しめたあの男(年雄)に復讐します、と宣言しているが、本心はなにを考えているのか不明。音子は、けい子を殺そうと一瞬思う。それは憎しみではなく、愛あるゆえか?音子は、死んだ我が子を見せてもらえなかった。描きたいと考えている。けい子の美しさも描きたと考えている。しかし、それはどちらも、結局は音子が自分自身に対するナルシズムが所以ではないかと自己分析する。 けい子は、太一郎と琵琶湖を旅する。けい子は、左の胸は許すが右の胸は触らせない。ここでも理由は不明。年雄とは逆の胸。 2人一緒であることを知らせるため。けい子自らが太一郎の母である文子に電話する。絶対に許さない文子。けい子と太一郎はモーターボートに乗って琵琶湖へ。事故がニュースになる。けい子は重体だが救出される。太一郎はまだ発見されず。鎌倉から駆けつけた年雄と文子、京都から駆けつけた音子。文子と音子がはちあわせ。 けい子は太一郎を殺したのか?復讐を遂げたのか? 大木年雄:31歳の時に16歳の音子の純潔を奪う 大木文子:妻、その時は23歳で男児の母親、元タイピスト 大木太一郎:長男、私大国文科講師、鎌倉と室町の文学研究 組子:娘、結婚してロンドンへ 上野音子:日本画家 坂見けい子:弟子 混血女性:音子の父親(音子12歳で死亡)の愛人、祖母がカナダ人、子が一人(音子の異母妹)、 おみよ:音子たちが住む寺の雇い女、53か4歳
Posted by
父と息子と一人の女。 この三角形はいつでも悲劇を呼ぶ。 ツルゲーネフ『初恋』 川端康成『千羽鶴』『美しさと哀しみと』 でも文章が美しいのは間違いないのよ。
Posted by
最初は、31妻子持ちの男が、16の純白な少女を犯し、子供を死産させた上、20年越しに会いに行った際には「まだ自分のことが彼女の中に残っている」とほざく自分勝手で独りよがさに、設定のありえなさと胸糞悪さを感じていたが、最後まで読み進めると、その設定によって川端康成が描きたかったこと...
最初は、31妻子持ちの男が、16の純白な少女を犯し、子供を死産させた上、20年越しに会いに行った際には「まだ自分のことが彼女の中に残っている」とほざく自分勝手で独りよがさに、設定のありえなさと胸糞悪さを感じていたが、最後まで読み進めると、その設定によって川端康成が描きたかったことがわかった。舞台となった鎌倉と京都の美しく静かな描写の中で、女の弟子「けい子」を中心に異様な世界観が漂い、人間の狂気が浮かび上がる。最後の怒涛の展開は、サスペンスドラマさながらのスピード感で進む。読了して始めて、けい子がなぜこの作品で登場するのか腑に落ちる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
鎌倉在住の55歳の作家大木が、四半世紀前、妻子ありながら通じた、音子。 音子は現在画家として身を立てて京都在住。 会いに行き、のち、音子の弟子にして同性愛の相手たる、若いけい子とも、関係を持つ。 けい子は師匠にして思い人の音子の復讐のために、大木とも、その息子太一郎とも関係を持ち……というあらすじ、正直いって、 SHO・U・MO・NEEE! DO・U・DE・MO・EEE! 大変に通俗的。悪い意味で。渡辺淳一かよ。レディコミ。悪い意味で。 掲載誌が「婦人公論」らしいので読者に合わせたのだろうが、作者にとっても読者にとっても、その「おもねり」って一体どうだったんだろう。 1961~1963年の女性読者って、こんなエロジジイの繰り言を提示されて、甘んじて感動しなければならない状況に置かれていたんだろうか。 私が1983年生まれ。 母が1960年生まれ。 1933年生まれの祖母が28歳から30歳で手に取っていたかもしれない雑誌だ。 あの闊達な祖母が、こんな小説を? あるいは1929年生まれの皆川博子が、32歳から35歳で手に取っていたのかもしれない作品。 ……と細かい年代にこだわってしまった。 若き日にうんたら~とか、忘れられない記憶がどうたら~とか、ああうっせえなあ~。 いっそ「血みどろ臓物ハイスクール」のキャシー・アッカー姐さんを召喚して蹴散らしてもらいたい。 「抵抗する――人生ではなく、忘却に」 「新鮮な肉だとよ、お嬢さんたち。あたしゃもっと若いけど、こちとらタフで堕落した腐れビーフ。わがオマンコは赤しオエッ」 てな具合に。 ただしちょっと冷静になって、60歳を超えた川端による願望充足モノ、と考えれば、業の深さ(≒底の浅さ?)が興味深くはある。 川端って想像力も構成力も決して秀でていないので、結構自分を切り売りしている。 厳密な私小説作家ではないにせよ、自分モデル小説が多い。 で、これ、妻・秀子にも養女・政子にも読まれる。 ちょっと面白いのは、大木の実子の太一郎は、政子の婿・川端香男里がたぶんモデルになっている。 義理の息子よりも自分のほうがプレイボーイであると。 ええとばっちりだ。 もう少し考えを進めてみれば、大江健三郎の中期以降と同じく、敢えて自家中毒的な自分モデル小説といえる。 大江(や西村賢太)が過去の自作のタイトルをもじって登場させていたように、「伊豆の踊子」をもじって「十六七の少女」とか。 非道な話らしいのに、青春文学として大衆に愛されて云々、とか。 どこかで川端は、作中では自分を厭な人物として描くと書いていたが、本作でもその通り。 イルカってくすぐったがりらしいけどあなたはどうですか、と元愛人の弟子を口説こうとするあたり、DO・U・KA・SHI・TO・RUUU! このノリ、自己卑下と露悪とパロディの精神ととれば、そこそこ面白い。 というか終盤の展開が決して悪くない。 左の乳はだめだとか、と思いきや右がだめといったりとか、やけにマゾヒスティックなサディストらしいけい子という人物の尋常じゃなさ、面白い。 思い返すと決して全編ひどいわけではい、どころか美味しさが判ってきたような気がする……不思議。 映画では池田満寿夫の絵が登場するのだとか。
Posted by
何度か映像化されている本作は、川端康成のキャリアとしては晩年に書かれた作品にあたり、執筆から数年後にはノーベル文学賞を受賞し、さらに数年後には自死を遂げることになる(事故死説もあるがここでは採用しない)。そう思って読むと、たしかにどこか翳を感じる部分がある。本作の登場人物である大...
何度か映像化されている本作は、川端康成のキャリアとしては晩年に書かれた作品にあたり、執筆から数年後にはノーベル文学賞を受賞し、さらに数年後には自死を遂げることになる(事故死説もあるがここでは採用しない)。そう思って読むと、たしかにどこか翳を感じる部分がある。本作の登場人物である大木年雄と上野音子のエピソードには、著者の実体験が反映されているらしく、作品に通底する妖しい雰囲気には、たしかに数年後命を絶ってもおかしくないような部分もある。実際、本作の結末でも、ある登場人物が死という道を選ぶ。まるで川端本人の心の闇がそのまま反映されているかのようである。物語自体はそこまで特別な内容ではなく、師匠であり同性愛関係にある女性の過去を知った画家が、彼女になり代わって復讐を誓い、その「過去」に関係した男性の長男に近づいてゆくというもので、いわゆる「悪女」の話であるが、その行動はタイトルにもあるように、時に「美しさ」を感じさせ、時に「哀しみ」を感じさせる。このアンビヴァレンツもまたテーマとなっており、坂見けい子は純粋に復讐しようとしているように見えて、それを超えた感情を抱いているようにも感じられるし、音子も過去を許しているようにもいないようにも見える。この二重性という部分に着目して、ひるがえって川端本人について見てみれば、ノーベル賞という最高の栄誉を受賞し、作家生活のまさに絶頂にいるなかで、突如命を絶ってしまう。これもまた「アンビヴァレンツ」である。そう考えてみると、本作は晩年の川端の思想がもっとも如実に反映された作品といえるのではないだろうか。
Posted by
❖会話を含めた作家の洞察力湛える緊張感のある文体に魅了された。息を呑むような感覚的な閃きはよくみがかれた鋭い刃のそれを連想させる。久しぶりに文体の鋭敏にふれ、文学者の凄味を思い知られた。といっても本作が作家の最良部の長篇『山の音』『雪國』と並ぶ傑作とは思わなかったけれど。感覚的に...
❖会話を含めた作家の洞察力湛える緊張感のある文体に魅了された。息を呑むような感覚的な閃きはよくみがかれた鋭い刃のそれを連想させる。久しぶりに文体の鋭敏にふれ、文学者の凄味を思い知られた。といっても本作が作家の最良部の長篇『山の音』『雪國』と並ぶ傑作とは思わなかったけれど。感覚的に(あるいは観念的であるにしろ)これだけ人物関係の陰翳を魅力的に描きだせる作家は稀有。登場人物たちの淫する情動の関係から人間の業のようなの官能性(おののき)を巧みに引きだし、作家はモラルではなく美意識で律してみせる。力技を堪能した。
Posted by
川端康成が1961年から1963年にかけて雑誌"婦人公論"に発表した長編小説。何度か映画化もされています。鎌倉と京都を舞台に、中年小説家、大木年雄と、かつて彼が愛した少女だった日本画家、上野音子、そして、その日本画家の内弟子、坂見けい子と年雄の息子、太一郎が繰...
川端康成が1961年から1963年にかけて雑誌"婦人公論"に発表した長編小説。何度か映画化もされています。鎌倉と京都を舞台に、中年小説家、大木年雄と、かつて彼が愛した少女だった日本画家、上野音子、そして、その日本画家の内弟子、坂見けい子と年雄の息子、太一郎が繰り広げる愛憎劇。やはり、川端康成の作品は日本語が美しい。作者が不安定な時期に書かれたとは思えないです。情景が目の前に浮かび上がってきます。登場人物も妖しく動き回ります。小説中の小説"十六七の少女"って読んでみたいな。
Posted by
俺が江ノ島でしていたことと似たようなことを江ノ島のまさに同じような場所でして、最後は何処かの大学の教授と同じような死に方(死なせ方)をする。意外に川端康成の晩年の作品で、おそらく最も完成度の高い最高傑作であろう。日本的な要素(美術と古典が中心の文学、京都…)や流麗な会話表現など、...
俺が江ノ島でしていたことと似たようなことを江ノ島のまさに同じような場所でして、最後は何処かの大学の教授と同じような死に方(死なせ方)をする。意外に川端康成の晩年の作品で、おそらく最も完成度の高い最高傑作であろう。日本的な要素(美術と古典が中心の文学、京都…)や流麗な会話表現など、それまでの作品のなかで培われてきたものの自然な集大成。作家自身のアナロジーでもあるだろうか。 30代の男(大木)と16歳の少女(音子)の恋愛というのはありうるのかわからないが、もしそれが実現したら、という縦軸(※横軸でもいい)と、音子に対する愛で大木に復讐をするけい子という横軸。大木や彼の妻や音子はかつての出来事の当事者であり、苦しみ囚われているのだが、ぽっと出てきた「妖精のような」[p]けい子と、大木の息子の太一郎は間接的にしか関わりがない。太一郎がこのように登場しなければ、太一郎とけい子の最後の京都の周遊を描かなくてもよかったかもしれない。ずっと大木を中心に(それと音子を多少)描いて、最後の悲劇に立ち会わせるだけでも十分ではないか。最初にけい子を太一郎が近くの駅ではなく遠くまで送って行ったと、だけ描いただけで二人の成り行きはその後の大木とけい子の描写からだけでも十分わかるだろう。 我田引水もあるが、画家と小説家、その他川端康成のあらゆる要素が程よく自然に集まっていることからも、最高傑作であろう。
Posted by
『抒情と官能のロマネスクである』って本の後ろに書いてあったから、川端康成が官能小説!?って思って初めて文豪の作品を読むことができた(^^)v まあ 『官能』ではなく『恋愛小説』だなと感じましたが、「あとはご自由にご想像ください」的な感じが、さすがは文豪!とか思ってしまった(^^...
『抒情と官能のロマネスクである』って本の後ろに書いてあったから、川端康成が官能小説!?って思って初めて文豪の作品を読むことができた(^^)v まあ 『官能』ではなく『恋愛小説』だなと感じましたが、「あとはご自由にご想像ください」的な感じが、さすがは文豪!とか思ってしまった(^^;) それとこんな時代から脱毛ってあったんだと、女ってやることたくさんあってホントに面倒だなおって思った
Posted by
- 1
- 2