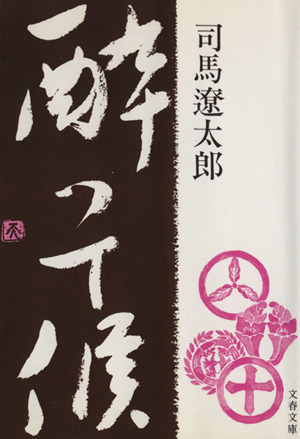酔って候 の商品レビュー
幕末の賢候たちの物語…
幕末の賢候たちの物語。「きつね馬」の島津久光、賢候と言えど所詮は見越しに過ぎなかった。維新後、御輿を降ろされた後は哀れである。
文庫OFF
幕末4人の短編 四賢候、薩摩の島津斉彬、 土佐藩の山内容堂、宇和島藩の伊達宗城最後は松平春嶽かと思いきや、肥前佐賀の鍋島氏。(幕府が落ちた後に薩長土肥と肥を入れた本人せっせと金を貯め、軍事力をつけつつも二重鎖国で外部には秘密裏にしていた) 再読。やはり司馬氏の時代小説は面白いと...
幕末4人の短編 四賢候、薩摩の島津斉彬、 土佐藩の山内容堂、宇和島藩の伊達宗城最後は松平春嶽かと思いきや、肥前佐賀の鍋島氏。(幕府が落ちた後に薩長土肥と肥を入れた本人せっせと金を貯め、軍事力をつけつつも二重鎖国で外部には秘密裏にしていた) 再読。やはり司馬氏の時代小説は面白いと再認識。幕末に生きる人物が生き生き描かれており、この頃はまだそれぞれの県(藩)に大分特色が有ったのだなぁと改めて思う。現代においても旅行にいった際に、時代から受け継ぐ際を見つけるのも楽しみだと思う。
Posted by
1985年の短編集、本棚から出てきて、30年数年振りに再読。酔って候、を読みつつ、昨年訪問した高知市山内神社にあった容堂公の像を思い浮かべる。(この場所は、`酔って候`の冒頭部分に出てくる南屋敷)また`伊達の黒船`では宇和島城から眺めた宇和島の海が思い出されます。`街道を行く`で...
1985年の短編集、本棚から出てきて、30年数年振りに再読。酔って候、を読みつつ、昨年訪問した高知市山内神社にあった容堂公の像を思い浮かべる。(この場所は、`酔って候`の冒頭部分に出てくる南屋敷)また`伊達の黒船`では宇和島城から眺めた宇和島の海が思い出されます。`街道を行く`ではないですが、旅と歴史と司馬遼太郎の本のコラボ等は、シニアの旅の楽しみの一つかと。次は、鍋島閑叟、島津久光の残影を探して九州へ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
高知城の追手門前には土佐24万石の藩祖、山内一豊の国内最大級の騎馬像があります。才気溢れる山内容堂が15代藩主として初のお国入りをする場面、先例では駕籠で入城すべきところ、明神様(一豊)の戦国の風にならい、駿馬に跨がって堂々と入城!『酔って候』は幕末にあって自身を戦国の英雄になぞらえて生きる容堂を見事に活写しています。クライマックスは陰謀渦巻く大政奉還後の小御所会議、酔った容堂が格好いい!
Posted by
司馬遼太郎さんの本は、青年期にかなりの作品を読みました。久しぶりに読みました。いつも思うことは作者の作品は、完全なノンフィクションではないかとということです。綿密な資料の読み込み、調査がそのように感じさせるのでしょう。文章から、登場人物たちの息遣いや汗の匂い、血の匂い、体温を感じ...
司馬遼太郎さんの本は、青年期にかなりの作品を読みました。久しぶりに読みました。いつも思うことは作者の作品は、完全なノンフィクションではないかとということです。綿密な資料の読み込み、調査がそのように感じさせるのでしょう。文章から、登場人物たちの息遣いや汗の匂い、血の匂い、体温を感じ取れます。司馬さんに、まだ生きていていただいて、戦後の世界を描いていただけていればと感じます。
Posted by
この中に収録されている「伊達の黒船」が大好きです。今の私が入るのは、この話があるから!と言っても過言ではありません。「自分の限界」とか考えている人がいたら、とにかく読んで欲しい!
Posted by
幕末の賢侯と言われた大名たちの狂言回しの役回り。山内容堂、島津久光、伊達宗城、鍋島閑叟。いずれも天才と言われ、地元で期待を担ったが、結局時代は彼らではなく彼らの部下たちが動かし、彼らは廃藩によりただの人に。皮肉を感じると共に、戦国期からの始祖時代から比較し、官僚化していた体制の問...
幕末の賢侯と言われた大名たちの狂言回しの役回り。山内容堂、島津久光、伊達宗城、鍋島閑叟。いずれも天才と言われ、地元で期待を担ったが、結局時代は彼らではなく彼らの部下たちが動かし、彼らは廃藩によりただの人に。皮肉を感じると共に、戦国期からの始祖時代から比較し、官僚化していた体制の問題として感じました。唯一、宇和島藩の黒船機関を造った堤燈張り職人のみが部下としては重要な登場人物として印象に残ります。
Posted by
土佐の山内容堂を主人公とする「酔って候」薩摩の島津久光を描く「きつね馬」宇和島の伊達宗城は「伊達の黒船」備前の鍋島閑叟は「備前の妖怪」と四人の幕末大名を材料に歴史の断片を明快に截る
Posted by
- 1