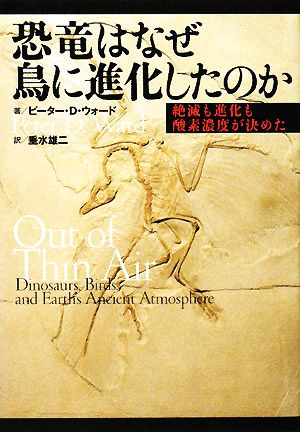恐竜はなぜ鳥に進化したのか 絶滅も進化も の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
地球の大気・海洋中の酸素濃度の変化が生物進化の方向を決めた。酸素濃度が低い時期には、生物が絶滅し、新たな進化が起こり、酸素濃度が高まると、生物は増える。
Posted by
原題は"Out of Thin Air"。恐竜や鳥がどうというよりも、バーナーの酸素濃度モデルをベースに生命史を通したボディ・プランの進化について一つの仮説を提案したもの。面白いのだが若干モデルに拘泥しすぎの感もあり。
Posted by
図書館で。読み終えるまでエライ時間がかかりましたがすごく面白かったです。何せ古生代のことについてあまり詳しいとは言えない自分なので(姉は好きで詳しいんですが)頭足類?腕足類って何?節足動物ってなんだっけ?今海に居る?とか友人に聞いてカニとエビじゃないと即答されああ、そうだったとか...
図書館で。読み終えるまでエライ時間がかかりましたがすごく面白かったです。何せ古生代のことについてあまり詳しいとは言えない自分なので(姉は好きで詳しいんですが)頭足類?腕足類って何?節足動物ってなんだっけ?今海に居る?とか友人に聞いてカニとエビじゃないと即答されああ、そうだったとかそういうレベルなんですがそんな人間が読んでも面白かった。 なんとなくですが昔の地球の酸素レベルも今とさほど変わらなかったのではと漠然と思っていましたが気の遠くなるような歴史の積み重ねで酸素・二酸化炭素のレベルが変動するってのは当たり前のようにありえたんだろうなあとしみじみ思いました。そして石炭も石油も古生物(植物や動物)の遺骸なんだなあと思うと色々と面白い。ご先祖様の恩恵にあずかって生きてるんだなあ、人間だってとかそんなことを思いました。 とりあえず私は三畳紀とジュラ紀と白亜紀の違いをきちんと覚えようと思います。今度もう少し初心者向けの本借りてこようっと。面白かったです。
Posted by
「酸素濃度が生物の進化を決めた」という著者の主張を元に、推理小説のように生物史を巡る出来事を読み解いていく。地球上でどんな生物が盛衰を繰り返してきたのか、なぜ大絶滅は何度も起きたのか、あらゆる情報を盛り込んだ何度も読み返したくなる一冊。地球の壮大さを感じるために、ぜひ読んだ方がい...
「酸素濃度が生物の進化を決めた」という著者の主張を元に、推理小説のように生物史を巡る出来事を読み解いていく。地球上でどんな生物が盛衰を繰り返してきたのか、なぜ大絶滅は何度も起きたのか、あらゆる情報を盛り込んだ何度も読み返したくなる一冊。地球の壮大さを感じるために、ぜひ読んだ方がいい。ここ数年の私のバイブル的一冊です。
Posted by
生命の形態的進化が起こった主な原因は酸素濃度の低下によるものという説を基に、五大絶滅が発生した時に見られる新しい形態の出現と、それがいかに酸素を利用するために優れたシステムであるのかを述べていく。 原題が「Out of Thin Air -Dinosaurs, Birds, an...
生命の形態的進化が起こった主な原因は酸素濃度の低下によるものという説を基に、五大絶滅が発生した時に見られる新しい形態の出現と、それがいかに酸素を利用するために優れたシステムであるのかを述べていく。 原題が「Out of Thin Air -Dinosaurs, Birds, and Earth's Ancient Atmosphere-」直訳すれば「薄い空気から現る〜恐竜、鳥、そして古代地球の大気について〜」という感じなので、邦題はちょっと恣意的だなあという気もする。タイトルだけで決めると拍子抜けするかもしれない。 食卓に上るエビや二枚貝の形態はなぜああなのか?という謎や、爬虫類の種類が多かった時代においてなぜ恐竜が抜きん出て発展を遂げたのかなど、読んだ後は鳥さんや海鮮を見る目が変わる一冊。
Posted by
人類を含むほとんどの生物が生存できない標高8847mのエヴェレストの、遙か上空をインドガンは苦もなく飛んでいく。なぜ鳥類はこうも薄い大気の中で活動できるのか? その問いに始まり、生物進化における壮大な仮説が展開される。 かのスティーブン・ジェイ・グールドが「ワンダフル・ライフ」に...
人類を含むほとんどの生物が生存できない標高8847mのエヴェレストの、遙か上空をインドガンは苦もなく飛んでいく。なぜ鳥類はこうも薄い大気の中で活動できるのか? その問いに始まり、生物進化における壮大な仮説が展開される。 かのスティーブン・ジェイ・グールドが「ワンダフル・ライフ」においてカンブリア紀の爆発的な多様性を、進化の壮大な実験という偶発的なものと捉えたのに対し、ウォードは地球の大気変動〜特に酸素濃度の大幅な変化に着目し、その変化によって淘汰、進化が起こったという仮説を立てる。肺や気嚢などの呼吸器官の痕跡を調べることで、進化の道筋を引き直す試みは、良くできた推理小説のように面白い。そして遠い未来に再び大陸がひとつにつながり、あらたな超大陸パンゲアが出来る頃、地球の大気はどうなっているのか。おそらく人類はもう生きてはいないだろう。それでいいのだと妙に納得してしまう。
Posted by
第1章 哺乳類の呼吸とボディ・プラン 第2章 地質年代における酸素濃度の変化 第3章 カンブリア紀大爆発はなぜ起こったのか 第4章 オルドビス紀 第5章 シルル紀=デボン紀 第6章 石炭紀=ペルム紀初期 第7章 ペルム紀絶滅と内温性の進化 第8章 三畳紀爆発 第9章 ジュラ紀 第...
第1章 哺乳類の呼吸とボディ・プラン 第2章 地質年代における酸素濃度の変化 第3章 カンブリア紀大爆発はなぜ起こったのか 第4章 オルドビス紀 第5章 シルル紀=デボン紀 第6章 石炭紀=ペルム紀初期 第7章 ペルム紀絶滅と内温性の進化 第8章 三畳紀爆発 第9章 ジュラ紀 第10章 白亜紀絶滅と大型哺乳類の台頭 第11章 酸素の未来を危ぶむべきか?
Posted by
このタイトルにもかかわらず、決して恐竜から鳥類への進化をテーマにした本ではない。 地球上の酸素濃度が生物の進化に与える影響について論じている。著者が述べているように、これまで酸素濃度と進化を関連づけた書はあまりなかったように思う。進化に関わる地球環境として気温などはよく論じられて...
このタイトルにもかかわらず、決して恐竜から鳥類への進化をテーマにした本ではない。 地球上の酸素濃度が生物の進化に与える影響について論じている。著者が述べているように、これまで酸素濃度と進化を関連づけた書はあまりなかったように思う。進化に関わる地球環境として気温などはよく論じられてきたが、酸素濃度はより重要なのではないか。 また酸素濃度が下がることによって、絶滅が起きその後の酸素回復によって生物が多様化するという論点は、二酸化炭素増加による危機は地球温暖化だけではないということにもつながる。人類を含めた地球上の生物の危機は予想以上に大きく、予想以上に近づいているのかもしれないと思わせる。2008.03.23(2)
Posted by
酸素濃度と呼吸器の形態からの進化論。これはこれで一つの見方だし、挿絵の様々な恐竜もそそるものがある。エネルギー産生の手段として、発酵のような無酸素代謝は極めて効率が悪く、有酸素活動の10分の1に過ぎない。酸素の量こそが体の大きさを決め、巨大化することで捕食される危険も少なくなる。...
酸素濃度と呼吸器の形態からの進化論。これはこれで一つの見方だし、挿絵の様々な恐竜もそそるものがある。エネルギー産生の手段として、発酵のような無酸素代謝は極めて効率が悪く、有酸素活動の10分の1に過ぎない。酸素の量こそが体の大きさを決め、巨大化することで捕食される危険も少なくなる。シルル紀には巨大なトンボなどもいたが、現在の酸素レベルではとても存在できない。これまでの酸素レベルはどうなっていたか。たとえば、黄鉄鋼は酸素がない状況で作られる鉱物で、22億年前より以前には酸素がなかったことを示しているが、最近ではもっと詳細に、ゲオカーブサーフというモデルを使って、カンブリア紀から現在までの酸素濃度の変化を見ることができ、このモデルによると、これまでの大絶滅5回のうち4回までは低酸素の時期に一致しているという。・ごく初期の生命で発達した鰓や節足動物の節は、表面積を大きくすることで水中の酸素を最大限取り込むために進化した構造。・ベルム紀の絶滅は、隕石の落下によるものだと先日のヒストリーチャンネルでやっていた。オーストラリア北西の海底にその跡がある、とも言っていたが、ベルム紀の絶滅は数100万年単位でおこっており、天変地異によるものとは考えにくい。この絶滅も酸素の低下によるものではないかという。・恐竜は、気嚢をもつことで巨大化し、地上を支配していた。気嚢は鳥類に受け継がれ、空気の薄い高度での生活を可能にしている。・キャリア制約両生類や爬虫類の肢は体の側面についており、移動の時には胸郭が歪むため、呼吸ができない。走っていても途中で止まって息継ぎをしないといけない。
Posted by
- 1