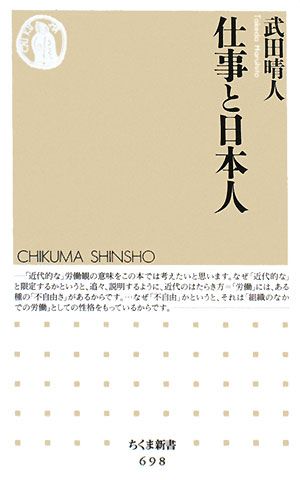仕事と日本人 の商品レビュー
日本での労働観の形成を追った本。 労働が時間の概念と密接にかかわっていることがわかる。 また、昔は労働と非労働が分けられていなかった。 近代になって工場などの発展により区別が生まれたことが分かる。 最終的に金銭目的の労働だけでなく、やりがいや生きがい、つながりが労働で実現されるべ...
日本での労働観の形成を追った本。 労働が時間の概念と密接にかかわっていることがわかる。 また、昔は労働と非労働が分けられていなかった。 近代になって工場などの発展により区別が生まれたことが分かる。 最終的に金銭目的の労働だけでなく、やりがいや生きがい、つながりが労働で実現されるべきと説く。 その意見に賛同はできないが、金のための労働が経済学的観点の話だという意見は面白いと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書のはしがきで引用される「働きマン」のなかのセリフ「私は仕事したな、と思って死にたい」。 このセリフは、幸せな職業人生を送った(または現に送りつつある)、極限られた人々にしか勝ち取れない言葉では、本来はないはずだ。人生の最も活動的な時代、睡眠以上の時間を費やす 「仕事」に賃金という対価を得るため以上の意味を見出せない現実に、満足せねばならないいわれはない。 本書は「働くこと」が即「生きること」であった時代から日本における「労働」観の変遷をたどり、労働=生産管理の必要上生じた「就労時間」や「賃金」、「残業」といった近代的諸概念が、「働くこと」の本質的意味を見失わせているのではないか、と問いかける。もちろんその答えは読者一人一人の考え次第。「飯の種」として割り切って働くことを否定するわけではない。 どんな結論に至るにせよ、管理職も新入社員も、定年間近の方も非正規の方も、時にはこんな本を読んで、「自分が何のために働いているか」について考えてみることも大事だと思う。
Posted by
現代社会人必読の書にしよう。 仕事に命かけたくないです!!! 仕事にもやりがいは勿論持ちたいけど、 それだけがやりがいなのはきつい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
書名の通り仕事と日本人について、またその周辺について様々な観点から語られているため一概にレビューするのは難しいが、主題としては「近代的な労働観」をどのように超克していくかという点にあるだろう。なぜ私たちの多くは往々にして「労働」という言葉に対して、忌避すべき対象として、またネガティブな対象として捉えることがあるのか。 著者は、それは近世から近代にかけて、農業主体の生活から工業主体のそれへと変貌を遂げていく中で、西欧的「時間」概念が導入されたこと、また生活と仕事の場が分離せざるを得なくなるなどの「ある種の不自由さ」がもたらした産物であるという(それは労働にかかわる主体性の喪失の過程でもあった)。分業と協業の代償として得られた現代の豊かな社会の功罪を、歴史や豊富な参考文献を紐解きながら客観的に分析しつつ、現状は現状として受け入れ、一方であらゆることに対しての評価基準となりつつある「お金」に縛られ過ぎない生き方、またそうした環境を作り出せるような成熟した社会を模索する姿勢は、落ち着いた筆致も手伝って、非常に共感を持てた。(個人的に今年読んだ中では一番良かったかも) 余談だが、日本(アメリカも?)の残業が多くなりがちな風土は、やはり日本固有の事情に深く根付くものであり、そうは簡単に変えられないものだと痛感した。孫引きになるが「労働への『自発的』参加、責任の広範な諸相への分散、企業帰属意識の強さは、従業員の『義務の無限定性』とワンセットをなす。」(P182)という箇所は、日本の残業風土を説明する上で非常に重要な示唆をしていると思う。ワークライフバランスって何だっけ?と時々考えることがある。そのたびに少し否定的な気分になったけれど、本書のおかげで少し前向きに考えられるようになった(気がします)。
Posted by
[ 内容 ] 資本主義であれ社会主義であれ、近代以降のあらゆる国家は「労働」を賛美してきた。 しかし、こうした仕事観が常識となったのは、それほど昔のことではない。 私たちの御先祖様は、金回りがよくなると、仕事を勝手に休んでいた。 彼らは「労働の主人」たりえたのだ。 それに比べて、...
[ 内容 ] 資本主義であれ社会主義であれ、近代以降のあらゆる国家は「労働」を賛美してきた。 しかし、こうした仕事観が常識となったのは、それほど昔のことではない。 私たちの御先祖様は、金回りがよくなると、仕事を勝手に休んでいた。 彼らは「労働の主人」たりえたのだ。 それに比べて、現代の労働のなんと窮屈なことか。 仕事の姿は、「会社」の誕生によって大きく変わったのである―。 江戸時代から現代までの仕事のあり方をたどり、近代的な労働観を超える道を探る「仕事」の日本史200年。 [ 目次 ] 第1章 豊かな国の今、問われる選択 第2章 「労働」という言葉 第3章 「仕事」の世界、「はたらき」の世界 第4章 「労働」観念の成立 第5章 時間の規律 第6章 残業の意味 第7章 賃金と仕事の評価 第8章 近代的な労働観の超克 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
「働くこと」の意味が近世から近代、現代へと変わっていく様子を、様々なデータや他の書籍の考察、諸外国との比較を通じて歴史的観点から明らかにし、さらに現代社会において「働くこと」とはどのようなものであるのかを説いている。結局現代では賃金を得るために働き、日常生活と労働が分離されてしま...
「働くこと」の意味が近世から近代、現代へと変わっていく様子を、様々なデータや他の書籍の考察、諸外国との比較を通じて歴史的観点から明らかにし、さらに現代社会において「働くこと」とはどのようなものであるのかを説いている。結局現代では賃金を得るために働き、日常生活と労働が分離されてしまっているために自己実現ができない、というような話だったが、随所に納得させられる部分が多い。というか、あまりにも当たり前になりすぎて、これまで疑問すら抱かなかった「労働」、「時間」に対する考え方にメスを入れられるような、新鮮な感じがした。個人的には、よく高校なんかで「やりたい職業は何か?」とか、大学でも「キャリア・デザイン」なんて話を聞くが、結局そういった理想と現実のギャップがあったことに気付くのは仕事を始めてからなんだよなー、仕事で自己実現なんてできるの一部の人だけじゃないの、と思ってしまった自分がいたことがよく分かった。最後の章では本全体のテーマがまとめられていて分かりやすい。(2008/02/10)
Posted by
日本人の労働に対する姿勢について分析されている。労働に対する姿勢の変化、勤勉とは等。あまり興味が沸かなかった。
Posted by
2008/1 日本人と仕事というものの関係を歴史的な流れを中心に考えている。よくある勤勉さとかそういうものをアピールしているわけでなく、その歴史時点での問題点や課題もかかれており、近現代の労働史と産業史の勉強には欠かせない一冊。
Posted by
- 1