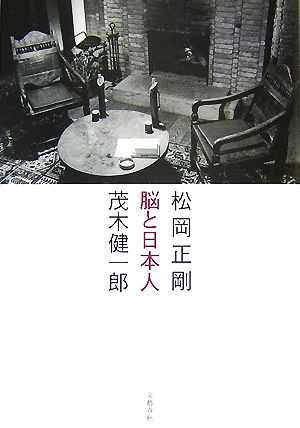脳と日本人 の商品レビュー
第一章 世界知を引き受ける 第二章 異質性礼賛 第三章 科学はなぜあきらめないか 第四章 普遍性をめぐって 第五章 日本という方法 第六章 毒と闇 第七章 国家とは何ものか 第八章 ダーウィニズムと伊勢神宮 第九章 新しい関係の発見へ 本対談は、二〇〇〇年七月十五日、MCプラン...
第一章 世界知を引き受ける 第二章 異質性礼賛 第三章 科学はなぜあきらめないか 第四章 普遍性をめぐって 第五章 日本という方法 第六章 毒と闇 第七章 国家とは何ものか 第八章 ダーウィニズムと伊勢神宮 第九章 新しい関係の発見へ 本対談は、二〇〇〇年七月十五日、MCプランニング主宰の「匙塾」で行われた対談を受けるかたちで、二〇〇六年十一月十二日と十三日の二日間にわたって二期倶楽部(栃木県那須郡那須町)にて行われたものをもとに構成されました。
Posted by
メモ→ https://twitter.com/lumciningnbdurw/status/1394134943194771457?s=21
Posted by
セイゴウ先生の繰り出す 『対話』の視点は・・・ 大きな編集術の中にある・・竹林の賢者のようで、 山水画のように どっしりとしている。 それに立ち向かう 血気盛んな憂学の徒 茂木健一郎 という感じで・・・ 遊学とは、セイゴウ先生のとりくんできた・・・ 編集術の由来のようなもので...
セイゴウ先生の繰り出す 『対話』の視点は・・・ 大きな編集術の中にある・・竹林の賢者のようで、 山水画のように どっしりとしている。 それに立ち向かう 血気盛んな憂学の徒 茂木健一郎 という感じで・・・ 遊学とは、セイゴウ先生のとりくんできた・・・ 編集術の由来のようなものであるが・・・ 茂木健一郎が、セイゴウ先生に問いかけているものは まさに、学問と科学を 憂えいているようで・・・ 『憂国』ではなく、『憂学』ともいえる。 ミメロギアするならば 『遊学の松岡正剛 憂学の茂木健一郎』 先ず命題として セイゴウ先生が言う 『20世紀は主題の時代で 21世紀は方法の時代だ』 ということを語り合う・・・ 主題とは 『平和、環境、民主主義、多様性、共生・・・』 しかし、それは、新しい世紀21世紀に入っても いまだに解決しているわけではない。 方法とは・・・編集であり・・編集することが イマ求められている ことを 時代の枠の中に定着させる。 セイゴウ先生は言う 『なんらかの出来事や対象から情報を得たときに、 その情報を受けとめる方法のすべてを編集』とよぶ。 茂木氏は 『「編集」という方法が、考えたり、書いたりという 人間の知覚や思考、表現のすべてにかかわっている』とまとめる。 賢者の対話のキャッチボールが スリリングである。 憂学の徒 茂木氏は 『多様さ 豊穣さを真剣に引き受けることは、 ある原理によって割り切り、世界がわかった気になるという 学問のメソッドをとっている人たちにとっては 非常に厄介なものに映る』・・・と切り込む。 セイゴウ先生は・・・ 『あのね。物理法則にする前に、世界観が必要なんですよ。』 という・・・ この対話は たのしい・・・ 疾風怒濤のような展開が楽しめそうだ・・・。 ミメロギア 『大局の松岡正剛 対局の茂木健一郎』 この対話に きちんと 言葉の脚注があるとうれしいのであるが。 『11次元のM理論』『クォークの理論』 自分で調べていくしかないか この高質な対話が 自分のものにするには・・・ ずいぶんと、苦闘しそうだと思われる。 『対話』からうまれる 知恵 を感じたい。
Posted by
私達が何者なのかを探すというのは、他人が作ったシステムの中の設定を調べるようなもの?設定がわかったとしてもその理由や過程は見えない。 システムの背景を文章にし、それを適宜更新するのが正しいとしたら、人間の歴史でもそんなことはできるのだろうか なんて、久しぶりに脳みそを動かして、...
私達が何者なのかを探すというのは、他人が作ったシステムの中の設定を調べるようなもの?設定がわかったとしてもその理由や過程は見えない。 システムの背景を文章にし、それを適宜更新するのが正しいとしたら、人間の歴史でもそんなことはできるのだろうか なんて、久しぶりに脳みそを動かして、とても楽しかった。 全然やる気のない仕事に占められる私の日々を、刺激的な驚きと興奮で包んだ、救世主的な一冊
Posted by
頭がいい二人の対談は 理解するのか難しい 松岡正剛いわく 編集とは新しい関係性を発見していくこと 不完全な完成しないものを 想像力をもって補う あるものが出来て、 それに何かが加わって、 たとえば、個人とか場が変わる 2つ以上の物事や 人間や世界観を さまざまな角度や...
頭がいい二人の対談は 理解するのか難しい 松岡正剛いわく 編集とは新しい関係性を発見していくこと 不完全な完成しないものを 想像力をもって補う あるものが出来て、 それに何かが加わって、 たとえば、個人とか場が変わる 2つ以上の物事や 人間や世界観を さまざまな角度や意味合いから見て そこから新しい関係を発見すること 茂木健一郎いわく 「クオリオ」という概念 脳の中の編集プロセス 脳の空(カラ) 何もない状態ではなく スキマがあり そのスキマを埋める 人生は一回性 生きることは 社会的にも 生物的にも 編集と感じた
Posted by
知的状況がどういうものか別として、そこに埋没してしまったらダメでしょう。埋没しそうになったら脱出する。 孔子の世界では、法の基礎は仁。 中国の社会や文化こそが正統でフォーマルなもので、日本の社会や文化は仮のものであるという通年がだんだん定着し、その考え方が江戸時代まで続いた。
Posted by
泳ぐように読んだ一冊。 読みながらずっと、私はせいぜい3−4人くらいの少人数と共に話すことに一番心地のよさを感じるなあ、なんてことを考えていた。 隣の席に座る男女の会話の、意味のないことをただ意味もなくたらたらと話す、ということに最大限の意味を見いだしている様が面白いなあと思った...
泳ぐように読んだ一冊。 読みながらずっと、私はせいぜい3−4人くらいの少人数と共に話すことに一番心地のよさを感じるなあ、なんてことを考えていた。 隣の席に座る男女の会話の、意味のないことをただ意味もなくたらたらと話す、ということに最大限の意味を見いだしている様が面白いなあと思った。 案外そういう流している関係の方が楽にうまくいくのかもしれない。 に、しても 知的な会話はやっぱり素敵である。 まだまだ仕事は残っているけれど、ここで一旦切り上げ。 タスクに関しては早く終わらせるに限る、のだけれど、何分一人で働いているのだから仕方がない。 週末、早くこーい。
Posted by
まず「クオリア」が何なのか飲み込めなくて苦戦・・。 会話の引き合いに出される著名人のエピソードなど知識量が凄まじくて、それらを気にとめてるとあっという間に本筋から離れてしまう私・・。でも知識の披露を繰り返すばかりで本筋に深く食い込んでいないような気も・・。繰り替えし読もう。 読...
まず「クオリア」が何なのか飲み込めなくて苦戦・・。 会話の引き合いに出される著名人のエピソードなど知識量が凄まじくて、それらを気にとめてるとあっという間に本筋から離れてしまう私・・。でも知識の披露を繰り返すばかりで本筋に深く食い込んでいないような気も・・。繰り替えし読もう。 読書家として有名なお二方の対談なだけに、贅沢ではあるけど内容をつかむのが難しい!私は話の表層すら理解できてなさそう。 たくさん読書してたらこんなに話題豊富になれるものなのかな〜。 広い意味で勉強にはなったと思うけど、ただ、おじさんたちの写真はあんなに要らないのでは。
Posted by
今売れている?脳科学者との対談。茂木健一郎は同じことの繰り返しに思える。研究しているヒマがあるのかね。
Posted by
ふと本屋で見かけて手にとりました。 その前にNHKの週刊ブックレビューで『千夜千冊』の特集で松岡正剛が登場してたのを偶然見て、頭に残ってた訳です。 この本は、茂木健一郎との対談ということで、気楽に読み始めたわけですが。 いやはや、すごい本でした。 松岡正剛がどんなヒトなのかを...
ふと本屋で見かけて手にとりました。 その前にNHKの週刊ブックレビューで『千夜千冊』の特集で松岡正剛が登場してたのを偶然見て、頭に残ってた訳です。 この本は、茂木健一郎との対談ということで、気楽に読み始めたわけですが。 いやはや、すごい本でした。 松岡正剛がどんなヒトなのかを知らないだけではなく、茂木健一郎がどんなヒトなのかも全然知らなかったんだなぁ…と、読みながら思い知った訳ですが。 理系と文系と分けてしまうのはすごく乱暴ではあるんですが、会話の中で、例えば理系の分野から文系の分野へキーワードが結びつき、新たな鍵を感じる(まだ「見つける」には遠いけれど)過程が、猛烈にスリリングでした。 最初松岡正剛の「編集工学」って「なんのこと???」と思っていたんですが、この対談を読んでいてまさに「別の分野」と「別の分野」の言葉、思想を結び付けることによって、今までにない視点が生まれてくる事を差しているんだな。と気付きました。 もちろん、二人の対談の内容自体もスリリングだったしね。 それと、これはすごく個人的な事。 大学時代…私は国文学科に在籍していたんだけど、その時の恩師が、卒業する直前のゼミで語っていた事を思い出しました。 「理系の人間は、自分が「何を研究してるのか」その表層的な内容や意味ではない、内包している意味を説明することができないだろう。 遺伝子解析をすることにどういう意味があるのか?物質の組成を突き止めることがどういう事なのか? 推論と実験と証明はできても、それを「表現」と捕らえてどう解釈するのか?今後、文系の人間の仕事はそれだと思う」 これって、まさに対談中、茂木健一郎の中に投じた思考の一滴なんじゃないのかしら? 今からもう16年前(ひーえー)、当時バブル景気崩壊で就職先が見つからず、文系の人間は冷遇されてました。 就職活動しながら自分の学んだものが、どう社会に生かせるのか?就職する時の武器になるのか? 不安になったものです。 でも、そういう私達に対して、先生はこうおっしゃってくれました。 その言葉を糧に、仕事しながら生きてきた訳ですが、この本を読んでいて、別の所からエールをもらったような気がして嬉しかったです。 (そういえばその恩師も、大学内では異端な感じで見られていたような…。。専門は「近世文学」…近松門左衛門という事だけど、年代なんか超越していろんな時代の文学をとりあげていたっけ。神話やアフリカの昔話、映画や漫画、村上春樹なんかも取り上げていたなぁ。着眼点が表現物から表出してくる「モノ」だったので、仕方ないんですがね)
Posted by
- 1
- 2