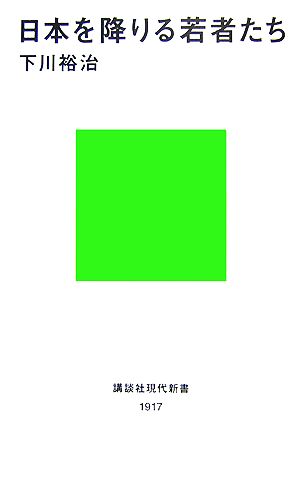日本を降りる若者たち の商品レビュー
引きこもりのように仕事もせずタイにひっそりと生きる「外こもり」、それぞれのエピソードに20代の時の自分が重なる部分が多く、興味深かった。 ある程度お金貯めてアジアを長期間旅しようかな…って考えてたな。。
Posted by
「外こもり」、一見矛盾した言葉のようで正に言い得て妙。日本の居心地が悪くなったのか、はたまた日本人が弱くなったのか。日本は依然として世界有数の暮らしやすい国だと、個人的には思う。外こもりが増えたのではなく、昔から一定数いた「馴染めない人々」のExit方法が増えたと見るのが妥当なの...
「外こもり」、一見矛盾した言葉のようで正に言い得て妙。日本の居心地が悪くなったのか、はたまた日本人が弱くなったのか。日本は依然として世界有数の暮らしやすい国だと、個人的には思う。外こもりが増えたのではなく、昔から一定数いた「馴染めない人々」のExit方法が増えたと見るのが妥当なのだろう。
Posted by
自分自身、バックパッカーでいろんなところを旅して、実際にこうやって暮らしているであろう人たちもたくさん見てきたし、行きなれたバンコクの地名もたくさん出てくるので懐かしく楽しく読むことができた。もちろん自分もこのような身の落とし方をしてしまう可能性もあったわけだけど、結局踏みとどま...
自分自身、バックパッカーでいろんなところを旅して、実際にこうやって暮らしているであろう人たちもたくさん見てきたし、行きなれたバンコクの地名もたくさん出てくるので懐かしく楽しく読むことができた。もちろん自分もこのような身の落とし方をしてしまう可能性もあったわけだけど、結局踏みとどまっていられた理由は何かな、と思うと明確にはわからない。でも、決して幸せそうには見えなかったから、だったら少しは日本で頑張ってみてから考えてもいいんじゃないか、ということかなぁと。 いろいろ考えさせられるところはあったけど、日本の経済システムから考えるとこういう人達が増えるのはあまりよい傾向ではないのだろう。とはいえ、処方箋も見つかりづらいので全体的に重苦しく終わってしまうのだろうな。
Posted by
物価の安いアジアに生活の拠点を移した人を追ったルポ。 この手のジャンルは大好物で、よくまとまってるとは思いますがどうにも話が浅いのと、彼らを「かわいそうな人」と思っていることがビンビン伝わってくる書きぶりはいかがなものかと。 彼らが自分でそう言っているのなら構わないですが、作者の...
物価の安いアジアに生活の拠点を移した人を追ったルポ。 この手のジャンルは大好物で、よくまとまってるとは思いますがどうにも話が浅いのと、彼らを「かわいそうな人」と思っていることがビンビン伝わってくる書きぶりはいかがなものかと。 彼らが自分でそう言っているのなら構わないですが、作者の私見を断定的に書かれても。
Posted by
失業、貧困、格差社会に我慢して収まっているより、正直ではないだろうか。 いわゆる海外に渡って成功した人のサクセスストーリーではない。 日本の不均衡きわまりない世界から抜けて、「私」自身として生きるひとの姿。 私も一度カオサンで暮らしてみようかと思ってしまった。
Posted by
この本はタイトル通り旅行の本の類などではなく、様々な理由があり海外(特にここではタイのバンコク)に来ている人たちについて書かれています。 毎日だらだらしているだけの外こもりの人間と、そうでなく現地で資格をとり仕事をしている人たちとを比較しながら書かれています。 下川さんの文章って...
この本はタイトル通り旅行の本の類などではなく、様々な理由があり海外(特にここではタイのバンコク)に来ている人たちについて書かれています。 毎日だらだらしているだけの外こもりの人間と、そうでなく現地で資格をとり仕事をしている人たちとを比較しながら書かれています。 下川さんの文章って悪く言えばおもしろ味がなく淡々としているけど言いたいことや問題が端的に表されてると思います。 またバックパッカーになりたいなぁ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本の中に出てくる人たちに、ある面では共感でき、ある面では全く共感できない部分があった。共感できない面の方は、一番最後の章の「タイに住みたい、そのために語学を勉強し、働く」という人たちを読んだ所でハッキリした。 日本の社会にいては「ダメな人」とされてしまう人が、タイにいけば「普通の人・旅人」という枠組みに括られてしまう。 だからこそ、日本に適応できなかった人たちがタイに行くと居心地がいいということになる。そして物価も安い。 実際僕が、中国に行ったときに感じた「居心地のよさ」と似たようなところがあると思う。自分のことを誰も知らない、言葉もあまり通じない、物価は安い、食事も問題ない、となれば実際に住む、という選択肢もなくはない。 が、それは、日本より中国の方が良い、という状況の時に採られるべき選択肢であって、日本がダメだから中国の方が良い、という場合は結局中国に行っても上手くいかないと思う。 最後の章以外の人たちは、後者が多いように思えた。 それが悪いわけではないが、魅力を感じる、というまでにはいかず、一つの生き方を提示した、程度に留まってしまう。 最後の章の人たちには、魅力を感じるのは前者であるからだと思う。 結局居心地がいいのは、「自分が変わった」からではなく「枠組みが変わった」からである。この部分を理解したうえでの生活であれば、それは一つの生き方の提示としては魅力的であると思う。
Posted by
少し昔、「外こもり」という言葉があった。日本でお金をためて海外でぼやっと過ごし、お金が無くなるとまたの話日本に戻ってきて短期労働をするというライフスタイルの人達の事だ。短期労働の職を得るのも大変な時代になってしまった今、彼等はどうしているだろうか?私もあの時海外で就職するといった...
少し昔、「外こもり」という言葉があった。日本でお金をためて海外でぼやっと過ごし、お金が無くなるとまたの話日本に戻ってきて短期労働をするというライフスタイルの人達の事だ。短期労働の職を得るのも大変な時代になってしまった今、彼等はどうしているだろうか?私もあの時海外で就職するといった選択肢もあったよなと、懐かしく思う。 老後タイで過ごすというのはよい選択肢かもしれない。
Posted by
興味深い。 日本というステージを降りて、バンコクのカオサンに長期滞在している「外こもり」の人たちの本。 リフレッシュやリセットするために海外へ・・・という考えは誰でも思うところ。 でも日本がイヤになり余りにもラクすぎて「サバーイ、サバーイ」と日本に帰れなくなってしまう...
興味深い。 日本というステージを降りて、バンコクのカオサンに長期滞在している「外こもり」の人たちの本。 リフレッシュやリセットするために海外へ・・・という考えは誰でも思うところ。 でも日本がイヤになり余りにもラクすぎて「サバーイ、サバーイ」と日本に帰れなくなってしまう人がたくさん存在するんだと初めて知りました。 この本には、外こもりの根源である日本社会への警鐘も、それに適応できない人への押し付けがましい同情もない。 淡々と描かれているその現状は、うーん、ちょっと苦い。暗い。 こんな世界もあるんだと考えさせられます。 もちろんタイでしっかり働いている人もいるからあくまで一部(それでも結構たくさん)の人たちだけど。 こんな時代だからこそ、「そんなの関係ねぇ」と笑い飛ばせる人って、逞しいと思うよ。
Posted by
若者に限らず、日本での生活に疲れて タイなど海外を拠点に暮らす人がかなり多い、ということを伝えている本。 著者はこの手の人間を突き放した眼で見ている。 本書で描かれているタイでの滞在生活は、 アジアに抵抗がなく疲れた日本人であれば、 多くの人が共感するだろう。 ただし、タイと...
若者に限らず、日本での生活に疲れて タイなど海外を拠点に暮らす人がかなり多い、ということを伝えている本。 著者はこの手の人間を突き放した眼で見ている。 本書で描かれているタイでの滞在生活は、 アジアに抵抗がなく疲れた日本人であれば、 多くの人が共感するだろう。 ただし、タイといえど永遠の楽園ではないし、 日本に「出稼ぎ」して短期的に稼ぐ、という生活が いつまでできるかわからない。 そして暮らすため働かなければいけない。どの土地であれ、 意思を持ってがんばる人と考えることを避けている人の間には、 何年もの間で差がついてしまう。 タイにとっても、滞在者に対する対応は少しずつ変わってきているようだ。 小野真由美氏による追章では、 タイでエネルギッシュにがんばる人間をレポートしている。 ここで描かれている人たちは、 日本を離れて生き生きとしているように描かれる。 みんながこうなればよいのだが、海外でがんばる日本人が増えれば、 それだけカオサン通りでまどろむ日本人たちが、 現実を突きつけられ憂鬱になり、さらにこもりがちになるのかもしれない。 結局、どこに行こうとも現実はついてまわる。 個人的には、外こもりには大いに共感し、若干の憧れもあるのだけれど……。
Posted by