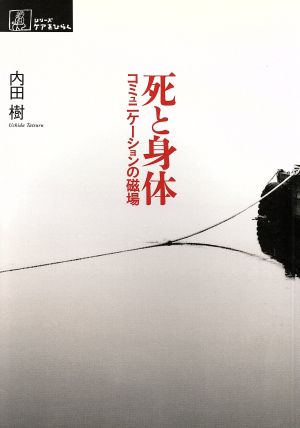死と身体-コミュニケーションの磁場 の商品レビュー
20年前の講演、若者は感情を失いつつあり淡々とした口調でムカツクしか言わないと。その若者が大人になった現在を自分は生きているだな。合気道という武道と哲学に関心のある著者、目からうろこ、共感…充実した講演会だった。 感度を上げて未来に逃げる、言葉より体を信じる、「定型」という退校...
20年前の講演、若者は感情を失いつつあり淡々とした口調でムカツクしか言わないと。その若者が大人になった現在を自分は生きているだな。合気道という武道と哲学に関心のある著者、目からうろこ、共感…充実した講演会だった。 感度を上げて未来に逃げる、言葉より体を信じる、「定型」という退校オプション、今を生きる(細かく割れた時間)、前未来的形、結論がでないことに耐える能力(知性)、沈黙交易、共感不可能な他者の存在と共存、死者の代弁をしない(無垢の被害者ステイタス)、「どうして人を殺してはいけないのですか」想像力の欠如
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フランス文学者にして武道家である内田樹さんならではの言語教育論と武闘における身体性に基づくアイデアをもとにしたエッセイである。 この本で思ったのは考えるとは脳を使って単に思考することではない。「腹落ちする」という身体性について目を向けようということだと思う。 私自身は「手を動かす」ことを最近意識するようになった。その昔プログラミングを習いたての頃はコンピュータも非力だったこともあり設計した内容と主要コードは手書きしてそれを見ながらデバックまでしていた。 コンピュータの能力が上がると手でことなしにコンピュータ上でワークフローは完結する。しかし、コードある程度入力する、コンパイル(人が読めるコードを機械用に変換することをコンピュータの業界ではこう言う)する、エラーがでる、修正する、コンパイル、実行する、うまくいかない、修正する、コンパイル、実行…と延々と繰り返し効率がすこぶるわるいい。 結局手で紙に書いてそれを直した方が効率が良い。手を動かす(キーボードで打つではダメで手で書く・描く)=考えるなのだから。 上記の経験を裏付ける事例が出てくるだけでなく、普段の自分なら知りえない情報もありとても参考になった。 私自身はグラフィックレコーディング等会議の見える化という研修講座を作ったりもするのだがレヴィ=ストロースの構造主義などに触れるきっかけや講座におけるいくつかのアイデア(緋色の研究の研究、等)は拝借させていただくなど非常にお世話になっている。この場を借りてお礼を申し上げたい。
Posted by
内田先生の本をほとんど読んでいるつもりであるが、まだまだ読めていない本はある。2004年か。私はまだ内田先生を知らなかった。いつから読むようになったのか。2006年頃かなぁ。 17年後に読んだ今、「変わっておられない」と思うのは失礼なのかどうなのか⁉︎17年前から待っていてくださ...
内田先生の本をほとんど読んでいるつもりであるが、まだまだ読めていない本はある。2004年か。私はまだ内田先生を知らなかった。いつから読むようになったのか。2006年頃かなぁ。 17年後に読んだ今、「変わっておられない」と思うのは失礼なのかどうなのか⁉︎17年前から待っていてくださった⁉︎ 時間が逆に流れる話が書かれていたが、ちょっと関係ある?ないかな。でも、私の知らない時から知っていた感じがする。(何を書いているのか、私)。
Posted by
どっかで一回読んだなー、という内容もあった。『先生はえらい』だっけかな?奥義伝授の話。そりゃそうだ、初版が2004年だった。内田先生は常々、違うこといってると思わせといて全部同じ話、っていう論法をとられているから、既視感あるのは正解なのかな。うん、たぶん、そうだ。 面白かったのは...
どっかで一回読んだなー、という内容もあった。『先生はえらい』だっけかな?奥義伝授の話。そりゃそうだ、初版が2004年だった。内田先生は常々、違うこといってると思わせといて全部同じ話、っていう論法をとられているから、既視感あるのは正解なのかな。うん、たぶん、そうだ。 面白かったのは、過去は未来によって作られる、っていう話。それから、居着く、の話。うんうん、そうだなって思いながら読んだ。でも、わかった気にならないように、注意、注意。「わかった!」は思考停止のフレーズだから。 やっぱり、定期的に内田先生の話を読むと、身心が整って呼吸が深くなる。ありがたい。
Posted by
タイトルにあるような死についての記載がなかなか始まらずに、読み初めは少しもどかしさを感じていた。 読み進めれば進むほど、面白さが出てきた。どんどんハマっていってしまう。 クライマックスは、死者がいると言う言葉にあるように、生と死を宙ぶらりんにしておく、ということ。 それが人...
タイトルにあるような死についての記載がなかなか始まらずに、読み初めは少しもどかしさを感じていた。 読み進めれば進むほど、面白さが出てきた。どんどんハマっていってしまう。 クライマックスは、死者がいると言う言葉にあるように、生と死を宙ぶらりんにしておく、ということ。 それが人間らしさの原因か結果かはわからないけれども、宙ぶらりんにしておける、そのことが、ヒトが人であるのかもしれない。 言葉を発した時、発する前、どちらもその時点で言葉は出ていないし正確ではない。そんな言葉を紡ぐことができる著者を尊敬てしまう。
Posted by
目を啓かれたなと思った事ども。 ○「本は身体で読む」謂れの例としての哲学書の読み方。 一度読む。全く分からない。毎日少しずつでも読む。繰り返し読む。するとじんわり「こういうことが言いたいのかな」が沁み入ってくるような感覚は、わずかながら経験がある。ひいては「すぐ後にこんな論述/...
目を啓かれたなと思った事ども。 ○「本は身体で読む」謂れの例としての哲学書の読み方。 一度読む。全く分からない。毎日少しずつでも読む。繰り返し読む。するとじんわり「こういうことが言いたいのかな」が沁み入ってくるような感覚は、わずかながら経験がある。ひいては「すぐ後にこんな論述/言い回しが続くじゃないかな」の察しがつく境位があるらしい。練習を積んでいくと、「球筋が見え」たりそこにアジャストするように身体が「意図せずとも」動いたりするような感じが思い起こされる。 ○前未来的に現在を語れるのは人間特有の知性であること。 「自分はこうなりたい」を語るときにはすでに「自分がそうなった」時点からのまなざしをもって今を語っている。「自分のこの営みが完遂された時点」(究極的には自分の死んだ後)を参照ポイントとして現在(からその時点)までを語る/捉える「時間のずらし方」をとるならば、そのまなざしで遭遇している「今」の事態は「過去(=既知)」ということになり、未知への場当たり的な事態としての「今」よりも対処可能になるだろうこと。
Posted by
この本は「ケアをひらく」というテーマでシリーズで出ている本の中の1冊です。内田先生もこの本を書こうと思って執筆したわけではないようでして、出版社からこの企画が持ち込まれたときには、新規の仕事の入り込む余地もなく、また専門外の分野ということで断った筈なのに・・この本が出来上がってい...
この本は「ケアをひらく」というテーマでシリーズで出ている本の中の1冊です。内田先生もこの本を書こうと思って執筆したわけではないようでして、出版社からこの企画が持ち込まれたときには、新規の仕事の入り込む余地もなく、また専門外の分野ということで断った筈なのに・・この本が出来上がっているという不思議さで先生自身も首をひねっておられる経緯があとがきに書かれてありました。 ・・ということで、講演会で先生がしゃべったことが中心となっている内容なので、比較的読みやすい中身になっています。(但し、やはり哲学系なので何だか分からないことも多いのですが、理解できているようで、できていない状態が知的活動にはいいらしいのでその点では主旨にあった理解の程度なのかもしれません) この本を読んでいたら、テレビで東日本大震災で大切な家族を失った人たちの霊的な体験を語る番組がちょうどにあり、まさにこのことなのかと思い当たりました。 人間がサルから進化したのは、「死者は存在する」「死後の世界はある」という信憑によるとあります。葬礼するものが人間であるということです。死者は物体ではないので、死者は死んで「いる」ものだから、死者からのメッセージも聞き取る能力があるということになります。 あの番組でも、死者から(死んでいるのに)元気でいるよと言われて安心した・・と語っていた方がいました。いるけどいない、いないけどいる・・この両方の間を行ったり来たり、そうやって考えられるのが人間の所以らしいのです。この他にもこの本には、興味深いお話がいっぱいでおすすめの本です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
コミュニケーションについて少し考え始めたときにタイトルや帯に引かれて手に取りました。 講演のテーブなどからのまとめとの事で、他の著作は読んでませんが、読んでいて読みやすい文章でした。 思考を広げ、思考を持続させる事、結論を出さない事に対しての持続力についての下りはとても興味深かったです。 (実感として、考える事を放棄する事、簡単に済まそうとする事、単純にしようとする事で、逆に自分の中で難しくなったり面倒になったり、取り返しがつかなくなったりがあるな、という事に思い至ったり。) 他の著作も読んでみたくなりました。
Posted by
「ハードになってはいけない。ものごとをただ受け入れてはいけない。感覚を消してはいけない。苦痛や怒りを敏感に察知しなければいけない。誰かがぶちのめそうとしたら、そんなことが起きる前にその場を立ち去れ。それでも間に合わないときは、全力を尽くして抵抗しろ。けっして相手の好きなようにさ...
「ハードになってはいけない。ものごとをただ受け入れてはいけない。感覚を消してはいけない。苦痛や怒りを敏感に察知しなければいけない。誰かがぶちのめそうとしたら、そんなことが起きる前にその場を立ち去れ。それでも間に合わないときは、全力を尽くして抵抗しろ。けっして相手の好きなようにさせるな。それが生きのびるためのただひとつの方法だ。」p66
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
講演をまとめた本だけど、内田先生のエッセンスが詰まっていると思う。メタ・メッセージ、身体を割る、ことばの身体性、教養とは、時間を割る、コミュニケーション、他者と死者、倫理、葬礼、交換などなど、、、いろいろなキーワードがやっと自分の中でも繋がってきた気がする。他の本にはあまり書いてないことで、印象的だった箇所を引用します。 『「死んだ後のわたし」を消失点に据えて、そこから前未来形で現在を回想するような時間意識をもつことのできた人間はよく生きることができる。』(p.149) 想像的視野の範囲を出来るだけ遠く未来に進ませる。その視点からみて今のふるまいを決定することができる。構造的に先をとること。このように振る舞えたら目の前のちょっとした問題で悩みすぎなくなると思う。 他者と死者についても正に医療的なテーマでもあるので、別の本のところに記録したいと思います。
Posted by