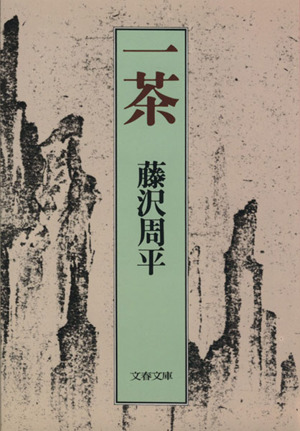一茶 の商品レビュー
小林一茶の生涯を描いた作品。 一茶といえば、有名な句から親しみ深さを感じるため、のほほんとした人物像を思い描いていたが、いやいや印象一変! 金、愛情、出世欲、安寧などしたたかに求めてもがき苦しみ、しかしどこかで純粋に俳諧を愛した泥臭い生涯。結構めちゃくちゃな所があるのに、何故か憎...
小林一茶の生涯を描いた作品。 一茶といえば、有名な句から親しみ深さを感じるため、のほほんとした人物像を思い描いていたが、いやいや印象一変! 金、愛情、出世欲、安寧などしたたかに求めてもがき苦しみ、しかしどこかで純粋に俳諧を愛した泥臭い生涯。結構めちゃくちゃな所があるのに、何故か憎めない人柄に不思議と惹かれました。
Posted by
1981年第一刷、文藝春秋の文春文庫。藤沢周平の小説で、文化人の一代記の形式。一茶は化政文化の代表的な俳人とされて、江戸時代の俳人というと芭蕉、蕪村、一茶が称される。が、一茶って同時代ではあまり代表的な俳人ではないということを知った。農民の出というのも比較的珍しいのではないだろう...
1981年第一刷、文藝春秋の文春文庫。藤沢周平の小説で、文化人の一代記の形式。一茶は化政文化の代表的な俳人とされて、江戸時代の俳人というと芭蕉、蕪村、一茶が称される。が、一茶って同時代ではあまり代表的な俳人ではないということを知った。農民の出というのも比較的珍しいのではないだろうか。 他:「あとがき」(昭和53年3月)、「解説」藤田昌司(時事通信社・文化部長)、初出:別冊文藝春秋一三九 - 一四二、単行本:「一茶」昭和53年6月文藝春秋刊
Posted by
小林一茶。人間味があるというか人間臭いというか。 嫉妬や嫉み僻みと、貧困や自分の家族などなど。 自分が俳諧師だという誇りを只々持って生きていたのかなと感じる 幼少期から亡くなるまでの流れがまるで滝の様。 月よ花よとロマンティックな俳句ではなく その辺の今の現代にも通じる、ごく身の...
小林一茶。人間味があるというか人間臭いというか。 嫉妬や嫉み僻みと、貧困や自分の家族などなど。 自分が俳諧師だという誇りを只々持って生きていたのかなと感じる 幼少期から亡くなるまでの流れがまるで滝の様。 月よ花よとロマンティックな俳句ではなく その辺の今の現代にも通じる、ごく身の回りの俳句を詠むので有名だけど 俳諧師といえど生活に雲泥の差があったり 流派云々で人付き合いも変わるのだなと知った。 それにしても、読んでいくにつれ何と世の中は残酷なんだと思うことが多かった それでも生涯俳諧師でいたことはすごいなと心から思う。
Posted by
「一茶」観が180度変わる。 正直一茶については、数編の俳句を知るのみで、その俳句からは明るくて陽気な北国の俳諧師という程度の知識であったけれど、この小説で一気にそんなフワフワした一茶に人間的な重さがまとわりつく。
Posted by
「痩蛙まけるな一茶是にあり」「やれ打つな蠅が手を摺る足をする」などの句で親しまれている俳人小林一茶。しかしその生涯は15歳で家を出てから貧困との戦いであった。生涯に二万句を詠んだといわれる一茶の伝記。
Posted by
俳人一茶の生涯が書かれている。 元々金がほしくて始めた俳句だったがそのままハマり才能を開花するのだが、貧乏から抜け出せず、孤独からも抜け出せなかった。 努力はそれほど報われず、流行に飲み込まれる。
Posted by
普段は短編集しか手にしないのですが、伝記小説かと思い購入してみました。 短編小説のほうが好きかなと思います。
Posted by
孤独で貧乏でも俳句だけがあった。 俳句詠みなんて人たちは浮世離れした聖人めいた人たちなんだ思いこんでたけど 俗っぽい悩みでいっぱいだったんだな。 あの小さい生き物に注ぐ視線の低さは優しさじゃなくて世間を疎ましくかんじる卑屈な心からきていたんだ。びっくり
Posted by
俳人小林一茶の生涯を描いた小説 名句の背景や彼の苦悩、作品からは想像出来ない意外な一面も、人間一茶がますます好きになる
Posted by
一茶というと、「痩せ蛙まけるな一茶是にあり」、「やれ打つな蠅が手を摺り足をする」といった句で知られるように、善良な目を持ち、多少こっけいな句を作る俳諧師のイメージがありました。 しかしこの小説を読んでみて、一茶の全く違ったイメージにびっくり。 世俗にまみれ、生活に苦労し、諸国を廻...
一茶というと、「痩せ蛙まけるな一茶是にあり」、「やれ打つな蠅が手を摺り足をする」といった句で知られるように、善良な目を持ち、多少こっけいな句を作る俳諧師のイメージがありました。 しかしこの小説を読んでみて、一茶の全く違ったイメージにびっくり。 世俗にまみれ、生活に苦労し、諸国を廻っては生活の糧を得る。 貧乏は生涯ついて廻る。 それでも俳句を捨てず、独自の境地を開いていく。 その俳句は、結局は俳諧には受け入れられず、孤高の人となっていきます。 とうとう晩年は遺産分配でトラブルを起こしてまでも、故郷に帰らざるを得なくなってしまいます。 老境に入ってから娶った妻と子どもに死に別れ、これでもかこれでもかと不幸が襲ってきます。 しかしそのような境遇にあっても、けっして俳句への情熱は忘れません。 自分や自分の境涯を皮肉った句の中にも、どこかユーモアが漂うのはなぜでしょう。 初めて一茶という人に触れ、その生き様に感銘しました。
Posted by
- 1