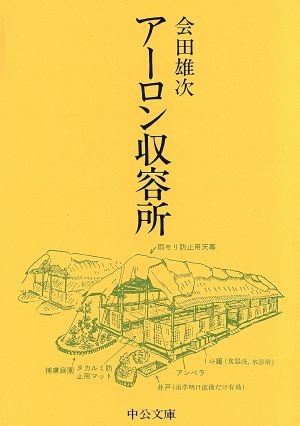アーロン収容所 の商品レビュー
著者が第二次大戦後、…
著者が第二次大戦後、ビルマのアーロン収容所に抑留された体験記。日本兵、イギリス兵、ビルマ人、インド人などの生態が生々しく記されています。
文庫OFF
行く先の暗い、何のために戦っているのか分からなくなるような兵隊時代よりも、決着の着いた後の捕虜時代の方が嫌だったと言う著者の考えに驚かされた。 本の中でふれられている収容所は、すごし易いとは言えないが、他の場所と比べるとかなりマシなのではないか。 それでも、たとえ無能でも、上層部...
行く先の暗い、何のために戦っているのか分からなくなるような兵隊時代よりも、決着の着いた後の捕虜時代の方が嫌だったと言う著者の考えに驚かされた。 本の中でふれられている収容所は、すごし易いとは言えないが、他の場所と比べるとかなりマシなのではないか。 それでも、たとえ無能でも、上層部の視線の先に、故郷が、家族が見えるという事が、希望になり、前に進む力になっていたのだろうか。 海外で外国人に支配された時、家族との絆が遠くなったと感じた時、苦しさがこみ上げたのだろうか。
Posted by
戦争を通して、異国間の文化や人種間の価値観の違いなどを知ることのできる本。 人間性は、その環境によって様々に感じられるといえことがよくわかった本だった。
Posted by
読むのが辛くて挫折。 やっぱり戦争はだめです。どんなに大きな崇高な大義があってもだめです。 …という月並みなことしか言えない。読むのが辛かった。
Posted by
"終戦とともにイギリス軍の捕虜となった経験談を語った本。 日本版「夜と霧」ともいえる本。 イギリス人、インド人、ビルマ人それぞれの当時の環境下での行動を語っている。 戦闘状態で尊敬を集めていた人物が、捕虜となったときに尊敬を集めているとは限らない。 それぞれの環境で、リ...
"終戦とともにイギリス軍の捕虜となった経験談を語った本。 日本版「夜と霧」ともいえる本。 イギリス人、インド人、ビルマ人それぞれの当時の環境下での行動を語っている。 戦闘状態で尊敬を集めていた人物が、捕虜となったときに尊敬を集めているとは限らない。 それぞれの環境で、リーダーとなる人物が登場するところも興味深い。 この平和な時代にこそ読み継がれるべき名著だと思った。"
Posted by
ビルマ戦線で終戦を迎え、そのまま英軍捕虜として過ごした二年間を綴った一冊。歴史書、文明論、日本人論として優れているのは言うにおよばず、才能の活かし方など自己啓発本と読める箇所もある。 本書が、こうしたいろいろな読み方ができる良書になっているのは、捕虜という特別な環境に置かれながら...
ビルマ戦線で終戦を迎え、そのまま英軍捕虜として過ごした二年間を綴った一冊。歴史書、文明論、日本人論として優れているのは言うにおよばず、才能の活かし方など自己啓発本と読める箇所もある。 本書が、こうしたいろいろな読み方ができる良書になっているのは、捕虜という特別な環境に置かれながらも 冷静に客観的に人間を観察できた著者の力量に因るところが大きい。 時代を間違えば右翼的な書と扱われた可能性もあるけれど、今は日本人なら読むべき一冊として誰にでも推せる。
Posted by
「夜と霧」「イワンデニーソブィチの1日」など他の収容所ノンフィクションとの違いは、生々しくて 自分が囚人になったように感じること、生命の危機を感じないこと 最後まで 希望を感じない本だった。西洋人観は なるほど と思う反面 なぜ 捕鯨に 反対するのか 不思議に思った 日本人...
「夜と霧」「イワンデニーソブィチの1日」など他の収容所ノンフィクションとの違いは、生々しくて 自分が囚人になったように感じること、生命の危機を感じないこと 最後まで 希望を感じない本だった。西洋人観は なるほど と思う反面 なぜ 捕鯨に 反対するのか 不思議に思った 日本人、イギリス人、インド人など 国で人を分けるのが、戦争なのだろうと感じた。坂本龍馬のように 国を超えた世界観を持つにはどうすればいいのだろうか
Posted by
第二次大戦後の捕虜収容所の話。この前読んだ虜人日記も面白かったが、本作も面白かった。この二作は著者の立場は違うが(本作は学徒の一兵卒、後者は軍属のエンジニア)どちらも逞しさを感じられて頼もしい日本人像に憧れるところがある。また、収容する側の違いも(本作は英国、後者はアメリカ)興味...
第二次大戦後の捕虜収容所の話。この前読んだ虜人日記も面白かったが、本作も面白かった。この二作は著者の立場は違うが(本作は学徒の一兵卒、後者は軍属のエンジニア)どちらも逞しさを感じられて頼もしい日本人像に憧れるところがある。また、収容する側の違いも(本作は英国、後者はアメリカ)興味深い。日常から軍隊、前線、敗走、捕虜と変化目まぐるしい中にしか見えてこない人間の本質のようなものがそこにはあるのかも知れない。生きるってどういうことなのかを考えさせらる。
Posted by
会田雄次(1916~1997年)は、京都市生まれ、京都帝大文学部卒、第二次世界大戦時にビルマ戦線に従軍した後、神戸大学文理学部助教授、京大人文科学研究所教授、京大名誉教授。専門はイタリア・ルネサンス研究だが、日本人論、日本文化論でも多くの著作を残した。 本書は、自らがビルマ(現ミ...
会田雄次(1916~1997年)は、京都市生まれ、京都帝大文学部卒、第二次世界大戦時にビルマ戦線に従軍した後、神戸大学文理学部助教授、京大人文科学研究所教授、京大名誉教授。専門はイタリア・ルネサンス研究だが、日本人論、日本文化論でも多くの著作を残した。 本書は、自らがビルマ(現ミャンマー)で英軍捕虜として過ごした約2年間の体験を綴ったものである。 収容所(ラーゲリ)における想像を絶する経験を描いた作品には、フランクルの『夜と霧』、石原吉郎の『望郷と海』、ソルジェニーツィンの『イワン・デニーソヴィチの一日』など少なからぬ著名な作品があり、そこで主に描かれたものは極限状態に置かれた人間の姿である。 しかし、本書に描かれたものはそれらとは異なり、「この経験は異常なものであった。・・・捕虜というものを私たちは多分こんなものだろうと想像することはできる。小説や映画やいろいろの文書によっても、また、日本軍に捕えられたかつての敵国の捕虜を実際に見ることによっても、いろいろ考えることができる。・・・ところが実際に経験したその捕虜生活は、およそ想像とかけちがったものだったのである。・・・私たちだけが知られざる英軍の、イギリス人の正体を垣間見た気がしてならなかったからである。いや、たしかに、見届けたはずだ。それは恐ろしい怪物であった」と語るもので、“収容された日本人”側の姿ではなく、“収容した英国人”側の異常な姿である。 それは、裸で自分の下着を持ってきて、洗濯をしている日本兵に、「これも洗え」と放り投げる英軍女性兵士であり、うつ伏せで死んでいるビルマ人の顔を靴の先で蹴り上げ、「finish(deadではない)」と気の無さそうにつぶやく英軍軍曹の姿である。 著者はそこに、英国人の言葉ではごまかせない人種差別・偏見を見てとる。即ち、英軍女性兵士からすれば、植民地人や有色人は「人間」ではなく「家畜」にひとしいものだから、それに対し人間に対するような感覚を持つ必要はないのであり、英軍軍曹からすれば、ビルマ人の死は、一匹のネズミの死と同じであり人間の死ではないのである。 そして著者は、その経験は、ヨーロッパ(人)というものの特殊な姿を浮かび上がらせ、ヨーロッパ(人)に対する見方を根本的に変えるべきであることを示唆してくれたのだと語る。 私は外国人とともに仕事をする機会が少なくなく、この類のテーマに安直に結論を出すことを好ましいとは考えないが、最も多様な人種を受け入れてきた米国においてさえ今なお頻繁に表面化する人種差別の実態を見るにつけ、現実の難しさを感じると共に、自らのプリンシプルを確立するためには、本書に描かれたような様々な事実(過去であれ現在であれ)を知った上で、それらを消化する必要があると思うのである。 (2012年4月了)
Posted by
ビルマでの2年間の捕虜生活体験談。同じ抑留でもソ連とは全く逆の、イングリの狡猾さが良くわかった。グルカ兵やインド兵や濠州兵や地元ビルマ人の観察もおもしろい。しかしなんと言っても、著者も含めた日本兵の様子が新鮮。現代日本のサラリーマン社会とあまり変わらないかも。 戦時に活躍する人...
ビルマでの2年間の捕虜生活体験談。同じ抑留でもソ連とは全く逆の、イングリの狡猾さが良くわかった。グルカ兵やインド兵や濠州兵や地元ビルマ人の観察もおもしろい。しかしなんと言っても、著者も含めた日本兵の様子が新鮮。現代日本のサラリーマン社会とあまり変わらないかも。 戦時に活躍する人と平和時に頭角を現す人は異なるという話(昼行燈大石内蔵助)や、抑留中の士官の権威の保ち方なども具体的に書かれていておもしろかった。
Posted by