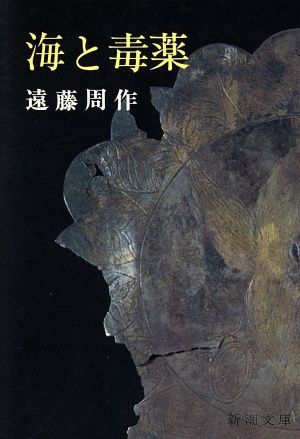海と毒薬 の商品レビュー
11冊目『海と毒薬』(遠藤周作 著、1960年7月、2003年4月 改版、新潮社) 太平洋戦争中に起きた戦争犯罪「九州大学生体解剖事件」を題材にした名著。 戦争に歪められる医師の姿が描かれるが、本作が追及しているのは現代にも通じる人間の本質。出世欲や絶望、孤独、嫉妬、傲慢、恋慕、...
11冊目『海と毒薬』(遠藤周作 著、1960年7月、2003年4月 改版、新潮社) 太平洋戦争中に起きた戦争犯罪「九州大学生体解剖事件」を題材にした名著。 戦争に歪められる医師の姿が描かれるが、本作が追及しているのは現代にも通じる人間の本質。出世欲や絶望、孤独、嫉妬、傲慢、恋慕、そのような欲望や感情が罪の意識を鈍らせることを示し、責任を転嫁することで罰から逃れんとすることの浅ましさを我々に突き付ける。 本作が描く悪に、無関係ではいられない。 〈夢の中で彼は黒い海に破片のように押し流される自分の姿を見た〉
Posted by
海と毒薬。この本が課題読書だと知り合いが話していたので興味があり、読んでみたのですが、罪と罰、日本人とは何か。 戦争中はこんなにも人を変えてしまうのか。 という強い衝撃を受けました。 また、実際の事件があった場所がとても身近な場所であったため、改めて様々なことを考えさせられる1...
海と毒薬。この本が課題読書だと知り合いが話していたので興味があり、読んでみたのですが、罪と罰、日本人とは何か。 戦争中はこんなにも人を変えてしまうのか。 という強い衝撃を受けました。 また、実際の事件があった場所がとても身近な場所であったため、改めて様々なことを考えさせられる1冊となりました。
Posted by
和風「少年の日の思い出」ハードモード 心のなかに罪の意識を抱えながら、変わらぬ日常を送る人々の不気味さが際立つ内容でした。 冒頭の十数ページでそんな罪を抱えながらも変わらぬ日々を送る人々の恐ろしさを感じられるのも本書の魅力でした。また、印象的なのはp144の戸田の独白。 『ぼ...
和風「少年の日の思い出」ハードモード 心のなかに罪の意識を抱えながら、変わらぬ日常を送る人々の不気味さが際立つ内容でした。 冒頭の十数ページでそんな罪を抱えながらも変わらぬ日々を送る人々の恐ろしさを感じられるのも本書の魅力でした。また、印象的なのはp144の戸田の独白。 『ぼくはあなた達にもききたい。あなた達もやはり、ぼくと同じように一皮むけば、他人の死、他人の苦しみに無感動なのだろうか。多少の悪ならば社会から罰せられない以上はそれほどの後ろめたさ、恥ずかしさもなく今日まで通してきたのだろうか。そしてある日、そんな自分がふしぎだと感じたことがあるだろうか。』 罪に対して罰や赦しを与える神を持たないから、罪悪感を持ってもそれをどうすることもできない。もっと言えば社会や世間から罰せられなければ悪にすらならない。だから日常を過ごすこともできてしまう。匿名の名のもとに口撃を行いながら平素では善良な人など、今でもこうした姿は感じられるのでこの独白は印象的でした。 こうした罪悪感に対して良心の呵責が働くのか。そもそも良心の罰とは存在するのか。そんな問いがあるという解説を読んで、たしかにな…どうなんだろ…ととても考え込んでしまう読後感でした。
Posted by
終始引き込まれ続ける。 人体実験という、人間としてのタブーを犯した医師たちの話。 初めから終わりまで、とにかく重い空気感が漂う。 本からここまでの重圧を感じた事は今までほとんどなく、何か心の奥を抉られ続けるような感情で読み進めるという新しい読書体験になった。 遠藤周作の本はこれが...
終始引き込まれ続ける。 人体実験という、人間としてのタブーを犯した医師たちの話。 初めから終わりまで、とにかく重い空気感が漂う。 本からここまでの重圧を感じた事は今までほとんどなく、何か心の奥を抉られ続けるような感情で読み進めるという新しい読書体験になった。 遠藤周作の本はこれが初めてだったのだけど、凄まじい没入体験だった。 映画が好きだったので、沈黙も読んでみようと思った。
Posted by
「日本人とは?」という問いを投げかけ続ける作家。 戦争というものがこのような出来事を起こすきっかけとなっただけなのか、それとも日本人がそのような人種なのか。 僕らにはどういう血が流れ、どういう社会ぎ長きに渡って築かれてきたのか。 罪と罰について、歴史上の事実を、小説を通して再考さ...
「日本人とは?」という問いを投げかけ続ける作家。 戦争というものがこのような出来事を起こすきっかけとなっただけなのか、それとも日本人がそのような人種なのか。 僕らにはどういう血が流れ、どういう社会ぎ長きに渡って築かれてきたのか。 罪と罰について、歴史上の事実を、小説を通して再考させられる。 暗くどんよりとした重い課題が、読了後も頭の中でこだまし続ける。
Posted by
白眉はその構成、特に導入部と戸田の回想だろう。程度の差はあれど、戸田の青年期に似た経験がある自分が、これを読んでまたホッとするという最大の皮肉。 神なき世界で、黒い海のうねりのある波に押し流されながら、われわれは自己を罰することはできるのだろうか
Posted by
戦争末期に九州の大学附属病院で実際に行われた米軍捕虜の生体解剖事件を小説化し、新潮社文学賞を受賞した作品。 その事件の当事者たちは、感情も何もないサイコパスのような人達ではなく、ごく一般的な感情を持ち得た日本人ということがわかる。ただその時代、その場所に生きていたがために、そ...
戦争末期に九州の大学附属病院で実際に行われた米軍捕虜の生体解剖事件を小説化し、新潮社文学賞を受賞した作品。 その事件の当事者たちは、感情も何もないサイコパスのような人達ではなく、ごく一般的な感情を持ち得た日本人ということがわかる。ただその時代、その場所に生きていたがために、そうした残虐的な行為に手を染めてしまった。時代が作り上げた事件とも言えるのかもしれない。 読後感も非常に重く沈鬱な気持ちになるが、日本人として向き合わなければならない歴史の断片である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「やがて罰せられる日が来ても、彼等の恐怖は世間や社会の罰にたいしてだけだ。自分の良心にたいしてではないのだ。」 果たして自分は彼等と違うのか? もし自分が、その時代、その場所にいたとして、良心に従った行動できるのか? 砂埃、海、灯の灯らない街。ひたすら暗い風景描写とともに、良心の輪郭がじわじわとぼやけていくような感覚に陥る。 おそらく自分もこの登場人物たちと同じ道を辿ることになるだろうと思った。 神のように何か縋るものや、深い信仰があったとしても、結局なにも変わらないような気もする。西洋でだって同じようなことは起きてたわけだし。 救いがない、ただひたすら暗い気持ちになる。
Posted by
太平洋戦争のさなかに九州の大学病院でおこなわれた、アメリカ軍の捕虜に対する生体解剖事件にかかわった者たちの心理をえがいた作品です。 勝呂二郎は、「おばはん」と呼ばれていた女性患者の死が近いことを憂えており、そんな彼の感傷的な態度を、彼とおなじ研究生の戸田はからかっていました。し...
太平洋戦争のさなかに九州の大学病院でおこなわれた、アメリカ軍の捕虜に対する生体解剖事件にかかわった者たちの心理をえがいた作品です。 勝呂二郎は、「おばはん」と呼ばれていた女性患者の死が近いことを憂えており、そんな彼の感傷的な態度を、彼とおなじ研究生の戸田はからかっていました。しかし、大学病院内での出世争いのために一人の患者の手術をおこなった橋本教授をはじめとする、彼のまわりの人びとの態度に虚無的な思いをかかえるようになります。そんななかで、「おばはん」が死を迎え、勝呂は橋本教授たちに求められるまま、捕虜の生体解剖に参加することになります。 看護師の上田ノブは、橋本教授の妻で、ヴォランティア精神から患者たちの世話を引き受けているヒルダが、みずからの善意を疑いもしないようすに反発をおぼえます。彼女は捕虜の生体解剖のサポートを引き受け、ヒルダが知らない橋本の罪を自分が知っていることに、ある種の満足感をおぼえます。 少年時代から、大人たちが求める優秀な生徒を演じることに慣れていた戸田は、自分のなかに他者のことを心から思いやる気持ちが欠如していることを知っていました。彼は、捕虜の生体解剖に参加することで、あるいは自分が罪の意識に苦しむことになるのかもしれないという期待をいだきます。 これほどの非人道的な罪を犯しながらも、罪の意識を人びとがいだくことのない、日本という風土にせまるという著者の問題意識にもとづいて構成された作品です。こうしたテーマをあつかいたいという著者の意図が先行している印象はありますが、考えさせられる問題であることもたしかだと感じました。
Posted by
高校以後、数十年ぶりに再読。 話のあらすじは覚えていたが、数人の独白で構成されていたことすら忘れていた。 各人の独白の際、心理描写は緻密で、罪を犯す人の心情はこのようなものなのだろうかと疑似体験した気分になる。 また、誰しも犯してしまう軽微な悪事に対しての良心の呵責は自分自身もこ...
高校以後、数十年ぶりに再読。 話のあらすじは覚えていたが、数人の独白で構成されていたことすら忘れていた。 各人の独白の際、心理描写は緻密で、罪を犯す人の心情はこのようなものなのだろうかと疑似体験した気分になる。 また、誰しも犯してしまう軽微な悪事に対しての良心の呵責は自分自身もこんなものかもしれないとも思わされる。 人の底深い闇から自身の心の薄暗い所を垣間見る作品。 解説にある「日本人とは?」という問いかけよりも、「人とは?」と問われている気がする。 戦争時の無法状態の中では人の本性が顕になるのか、権力に抗えないときは無力になるのか、その状況に陥らないとわからないのかもしれないけれど、いろいろ考えさせられた。 映画「生きてこそ」をまた見たくもなった。
Posted by