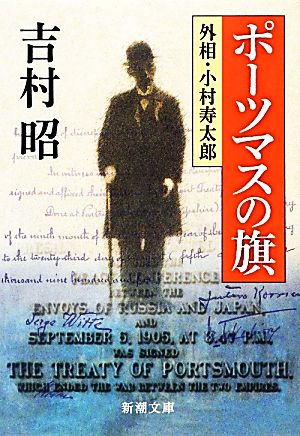ポーツマスの旗 の商品レビュー
小村が外相だった輝いていたときと、それ以外との対比が良かった。彼の人生が何かを象徴している感じがした。
Posted by
図書館で借りた。 日露戦争の講和条約、ポーツマス条約。これを交渉して締結に結びつけたのが、当時の外務大臣・小村寿太郎。小村寿太郎がポーツマス条約を締結する歴史小説だ。日露戦争と言うと、司馬遼太郎の『坂の上の雲』があまりに有名だが(私は未読)、こちらもリアルで非常に面白い作品だ。 ...
図書館で借りた。 日露戦争の講和条約、ポーツマス条約。これを交渉して締結に結びつけたのが、当時の外務大臣・小村寿太郎。小村寿太郎がポーツマス条約を締結する歴史小説だ。日露戦争と言うと、司馬遼太郎の『坂の上の雲』があまりに有名だが(私は未読)、こちらもリアルで非常に面白い作品だ。 終われば悪役になると分かりつつ、賠償金を1銭も取れずに厳しい駆け引きが続く雰囲気は手に汗握る。当時の海外のメディアや一般市民の様子も垣間見えて興味深い。 偉大なる先輩たちに作られて現代日本が今ある。とても勉強になったし、感動した。
Posted by
日露戦争の講和交渉の末、ポーツマス条約が結ばれたが、国民からは評価されず。ロシアが日本に対して一切の賠償金を支払わず、領土については、日本軍が占領していたサハリン島のうち南半分を日本の領土とし、ロシアが有していた中国東北部の権益は日本に譲渡される、という内容だったが、死傷者総数2...
日露戦争の講和交渉の末、ポーツマス条約が結ばれたが、国民からは評価されず。ロシアが日本に対して一切の賠償金を支払わず、領土については、日本軍が占領していたサハリン島のうち南半分を日本の領土とし、ロシアが有していた中国東北部の権益は日本に譲渡される、という内容だったが、死傷者総数20万人以上という犠牲と、戦費負担のための金銭的の国民の我慢が報われないと感じられたからだ。そのため、東京では講和に反対する市民によって「日比谷焼打事件」と呼ばれる暴動が引き起こされたという、これは歴史の教科書にも書かれる内容だが、本書は、ここに至る経緯に迫る。 小村寿太郎や金子堅太郎の活躍がよく分かるが、特に金子の胆力やルーズベルトの関係性を活かした交渉は迫力がある。また、まだ通信傍受やその対策も未熟だった時代。そのためのエピソードも綴られる。 しかし、改めて。停戦に際して如何に対価を得ようと努力し、そのために樺太侵攻を決めた経緯は正しい判断だったと感じたが、第二次大戦ではそれの意趣返しか、中立条約を破り占領された北方領土。戦争とはこういうものだと、考えさせられる。
Posted by
日露戦争は日本海海戦で終結した訳ではなく、ポーツマス条約締結交渉が最後の戦い。世界中の諜報網、各国の思惑、世界のマスコミを相手にしたもう一つの戦い。国内世論と現実との乖離。真実を国内に明らかにすると露や世界との交渉が不利になるジレンマ。国内不満の皺寄せは最後は政治エリートが負うと...
日露戦争は日本海海戦で終結した訳ではなく、ポーツマス条約締結交渉が最後の戦い。世界中の諜報網、各国の思惑、世界のマスコミを相手にしたもう一つの戦い。国内世論と現実との乖離。真実を国内に明らかにすると露や世界との交渉が不利になるジレンマ。国内不満の皺寄せは最後は政治エリートが負うという覚悟。このような覚悟を持った政治家の歴史記録でした。
Posted by
小村寿太郎のキャラクターも、ポーツマス条約の交渉の実情も、ほとんど何も知らなかったので読んでよかった。
Posted by
文字通り国の存亡をかけた綱渡りの駆け引きが丁寧に書いてあって、日本史的な結論はわかっているんだけどドキドキしながら読んだ。この構成、最高。 自分としては小村寿太郎の私生活が意外にクズだったのが面白かった…
Posted by
歴史小説として個人的には満点の作品でした。 国の尊厳をかけたギリギリの外交交渉。容易に譲れない全権たちが、それでも講和成立に向け妥協点を探りあう。そんな緊迫した様子をまるで同室で見ているような臨場感が、この小説にはありました。小村という人物にも大変興味をもちました。乃木や東郷が英...
歴史小説として個人的には満点の作品でした。 国の尊厳をかけたギリギリの外交交渉。容易に譲れない全権たちが、それでも講和成立に向け妥協点を探りあう。そんな緊迫した様子をまるで同室で見ているような臨場感が、この小説にはありました。小村という人物にも大変興味をもちました。乃木や東郷が英雄ならば小村も同等に英雄なのでは、そう思いました。
Posted by
作品は、基本的に叙事詩的な文章で書き進められており、淡々と当時の時間の流れと出来事を連ねているが、それがポーツマス条約の緊縛した場面をより強く浮き彫りにしていると思う。困難なポーツマス条約を成立させた優れた外交官、政治家として記憶していた小村であるが、"私"の...
作品は、基本的に叙事詩的な文章で書き進められており、淡々と当時の時間の流れと出来事を連ねているが、それがポーツマス条約の緊縛した場面をより強く浮き彫りにしていると思う。困難なポーツマス条約を成立させた優れた外交官、政治家として記憶していた小村であるが、"私"の方はとても陰の部分が濃い人生だったことは、この作品で知った。 日本が近代国家として名乗りを挙げた日露戦争の勝利の一方、このポーツマス条約が後のさらなる悲惨な戦争の歴史に繋がっていくことを考えると歴史の皮肉さを思う。 この度のウクライナ戦争もあり、読んでみた一作であった。
Posted by
米村万里さんの書評がきっかけで読んでみた一冊。 恥ずかしながら、小村寿太郎という名前もポーツマス条約という名詞も「教科書に載ってたなぁ」くらいの記憶しかなかったけれど、こんなにも熾烈な駆け引きがあったとことが授業で教えられていたら興味の持ち方が違ったと思いました。 当時の外交...
米村万里さんの書評がきっかけで読んでみた一冊。 恥ずかしながら、小村寿太郎という名前もポーツマス条約という名詞も「教科書に載ってたなぁ」くらいの記憶しかなかったけれど、こんなにも熾烈な駆け引きがあったとことが授業で教えられていたら興味の持ち方が違ったと思いました。 当時の外交、戦争、政治がどのようなものだったのか、垣間見ることができる良作。 果たして現代日本の政治家に、これほどの熱量があるのだろうかと改めて疑問を抱いてみたりもしました。 ポーツマス条約における小村氏の功績だけでなく、家庭人としてのダメっぷりも記されているのが本作の面白さ。 決して教科書っぽくならず、小説として楽しめる理由の1つはここにあるのでしょう。 これまであまり歴史小説は読んできませんでしたが、 戦争や人種差別に強い関心が出てきたのもあってか、近代歴史小説にはハマる予感がします。 2020年55冊目。
Posted by
日露戦争の講和条約締結に尽力した小村寿太郎の話。 日露戦争の海戦を描いた海の史劇の後に読んだ。 前半は出来事の羅列が多く、若干読みづらいが、後半のロシア全権ウィッテとの緊迫した交渉は、息詰まるものがあった。 また、当時のロシアのマスコミ(新聞)操作も印象的で、時代は違えど、戦...
日露戦争の講和条約締結に尽力した小村寿太郎の話。 日露戦争の海戦を描いた海の史劇の後に読んだ。 前半は出来事の羅列が多く、若干読みづらいが、後半のロシア全権ウィッテとの緊迫した交渉は、息詰まるものがあった。 また、当時のロシアのマスコミ(新聞)操作も印象的で、時代は違えど、戦争におけるマスコミ、民衆の印象操作が重要なのは、今も昔も変わらないことが分かる。 日露戦争後の民衆の暴動、軍部の権力拡大など、このあたりから日本の外交はおかしな方向へと進んでいくことになり、あとがきにあるように、小村の行った外交は、全然日本の最後の英知といえるそうだ。
Posted by