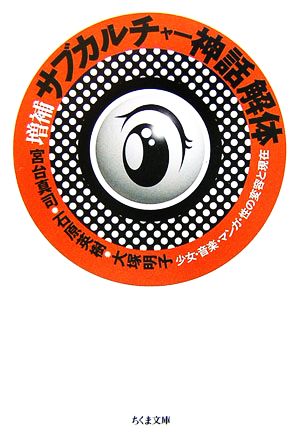増補 サブカルチャー神話解体 の商品レビュー
貞包英之「サブカルチャーを消費する」という本を読んで新しい学者の新鮮な視点が面白く、で、サブカルチャーだったら1959年生まれ、ど真ん中研究者の宮台真司をもう一度、ということで本書を開きました。たまたま今年、著者と同世代の庵野秀明によるシン・ウルトラマンが公開され、あの頃のコンテ...
貞包英之「サブカルチャーを消費する」という本を読んで新しい学者の新鮮な視点が面白く、で、サブカルチャーだったら1959年生まれ、ど真ん中研究者の宮台真司をもう一度、ということで本書を開きました。たまたま今年、著者と同世代の庵野秀明によるシン・ウルトラマンが公開され、あの頃のコンテンツについての再評価がいろいろされているのもタイミングを感じました。とは言っても、この本、60年代70年代80年代のサブカルを最速で振り返る1993年の本の文庫版だったりして、それからほぼ30年経っていたりします。少女マンガ、音楽、青少年マンガ、性産業と、ジャンルを超えた縦横無尽感が宮台真司ならではのものです。統計をベースにした「システム理論」というのをひっさげて、サブカルと社会、個人の共振関係を解き明かしていきます。この本、共著本なのですが、やはり宮台スタイルが満ち満ちています。全然、関係ないのですが長州力が、維新軍を引き連れてさまざまなリングを駆け巡っていた時代のイメージが浮かびました。実際、研究者としてでなく、その後、彼の立ち位置のひとつとなるフィールドワーカー、さらには東京の私立高校出身としてのコンテンツ消費者としてのバイオグラフィー、すべてを込めて高ぶっています。リキラリアットが「システム理論」か…その武器で、団塊の世代の研究者や同世代の研究者もぶった切っていくイキオイを感じました。実は、最近、彼の講演ウェビナーに参加し、その時代分析に目から鱗、だったのですがそれはパワーより老練さに対してだったのかもしれません。1993年を折り返しとする、前30年、後ろ30年の理論構築、よろしくお願いします!っていいたくなりました。例えば「サブカルチャー全史」。この文庫版(2007年)に収録された上野千鶴子の解説「宮台真司はどこにいく?」は本書を彼のベストワンとすることで、今後を叱咤激励する文章は胸アツ!
Posted by
面白かった。 本文とズレるけどサブカル飽和の「今」を語るとしたらどう語られるんだろうか。 総コクーン化?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著作の名前と著者の名前で、売れたんだろうなと思った。 サブカルについても社会学についても、素人向けではない。時代とジャンルも多分齟齬が生じるだろうから自称くらいのオタク向けでもない。 てゆーかこのヒト全く優しくない。なんか大学教授の布教用って感じ。 ピンク映画の項だけつまみ食いして終わりました。
Posted by
[ 内容 ] マンガでも音楽でも、今や誰もが知る作品などほとんどない。 サブカルチャー自体が細分化し、誰が何を享受しているのか見えにくい。 少女カルチャーや音楽、マンガ、AVなど各種メディアの歴史をたどり、それがどういう若者に受容されたかを分析することで、こうした不透明な状況が生...
[ 内容 ] マンガでも音楽でも、今や誰もが知る作品などほとんどない。 サブカルチャー自体が細分化し、誰が何を享受しているのか見えにくい。 少女カルチャーや音楽、マンガ、AVなど各種メディアの歴史をたどり、それがどういう若者に受容されたかを分析することで、こうした不透明な状況が生じるまでを明らかにする。 社会の大掛かりな変容を描き出した歴史的論考。 新たに「サブカルチャー神話解体序説」を付す。 [ 目次 ] 序章 サブカルチャー神話解体序説―少女マンガ・音楽・宗教から見た若者たち 第1章 少女メディアのコミュニケーション 第2章 音楽コミュニケーションの現在 第3章 青少年マンガのコミュニケーション 第4章 性的コミュニケーションの現在 第5章 サブカルチャー神話解体論の地平 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
表層的には変化してはいるが、現在でも延々と生き続ける「かわいい」という価値観の普遍性には驚く。この相当深く根ざした価値観は変化・崩壊する事はないのだろうか?(最近流行りの少女が機関銃持つ系の世界ってのは元々は80年代の映画の世界で大ブームになってるので所詮その発展系としか思えない...
表層的には変化してはいるが、現在でも延々と生き続ける「かわいい」という価値観の普遍性には驚く。この相当深く根ざした価値観は変化・崩壊する事はないのだろうか?(最近流行りの少女が機関銃持つ系の世界ってのは元々は80年代の映画の世界で大ブームになってるので所詮その発展系としか思えないのだが) 続編への期待としては、ネット社会における「共有」の概念、「関係の偶発性」、「他者」の概念等々の変化・進化を取り入れての再定義といったところか。
Posted by
難しかったけどすごく興味深く読めた。少女カルチャーと音楽カルチャーの部分は、わたしの知ってる作品も多かったので理解しやすかった気がする。再読したい。
Posted by
たぶん僕と宮台先生の関心はかなりかぶっているのだが、出てくる結論やその背後にみられる思想がかみ合わないのに、時代というファクターはどの程度影響を与えているのだろうか? 巻末の上野千鶴子の引用にもあるように、この本で扱われているサブカルチャーは、僕ぐらいの年の人には古めかしいもの...
たぶん僕と宮台先生の関心はかなりかぶっているのだが、出てくる結論やその背後にみられる思想がかみ合わないのに、時代というファクターはどの程度影響を与えているのだろうか? 巻末の上野千鶴子の引用にもあるように、この本で扱われているサブカルチャーは、僕ぐらいの年の人には古めかしいものとして映ると思う。少なくとも僕は、「生まれ落ちた時から世界が不透明であるがゆえに、不透明であることが特にコンプレックスの源泉にならない」人間であるがゆえに、宮台先生が抱いているような問題を体感的に理解することも難しい。ただ、歴史書としての本書は高い価値を持っていて、宮台先生がなぜそのような思想に行き着くかの背景の少なくとも一部を雄弁に説明してくれていると思う。 本書はいろいろと実の詰まった本なので、一読しただけですべてを論じるわけにはとてもいかない(そもそもこのような気軽にコメントだけ残すような場で真剣に論じるということはどの本であっても困難を極めるが)。 ただ、巻末の上野千鶴子の解説は非常に良い点をついているとはいえる。今までろくに著作も読まずに「ジェンダーおばさん」とステレオタイプしてきたが、これから機会を見計らって彼女の著作に手を出すのもありかもしれない。
Posted by
(推薦者コメント) 『サブカルチャー神話解体 少女・音楽・マンガ・性の変容と現在』は既に所蔵されているが、増補されているため推薦する。『サザエさん』『鉄腕アトム』『ドラえもん』など、極めて有名で、誰もが一度は何らかの面(漫画、アニメ、ドラマなど)から触れたことがあるであろう作品は...
(推薦者コメント) 『サブカルチャー神話解体 少女・音楽・マンガ・性の変容と現在』は既に所蔵されているが、増補されているため推薦する。『サザエさん』『鉄腕アトム』『ドラえもん』など、極めて有名で、誰もが一度は何らかの面(漫画、アニメ、ドラマなど)から触れたことがあるであろう作品は過去の作品ばかりである。現在、果たしてこれらのように誰もが見たことのある、または知っている作品は存在するだろうか?サブカルチャーの細分化は、誰が何を楽しんでいるかを分かりづらくした。本書では、そんな細分化した現代の若者文化の変容を歴史的に見ていく。
Posted by
とり扱っているサブカルチャーが1993年までのものなので、よく分からない部分もあった。 「かわいさ」のツール機能としての解釈には興味を持ったが、上野千鶴子の解説が一番おもしろかった。
Posted by
宮台真司の切れ味ここにあり。彼の最高傑作。 社会システム論をツールとした、文化分析が鮮やか。 学術書にあるまじき、爽快感。 切れ味がよすぎて、怪しいといえば怪しいが僕は批判できない。
Posted by
- 1
- 2