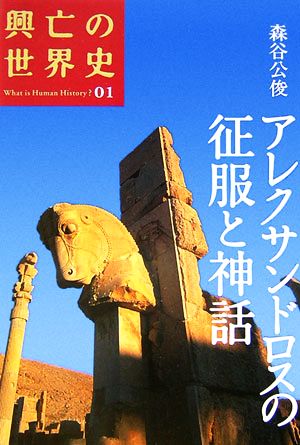アレクサンドロスの征服と神話 の商品レビュー
興亡の世界史01。 アレクサンドロスの成したことを全て読者が知っている前提で、「ヘレニズム」の一般的捉え方を吟味したり、「アレクサンドロス大王」の一般的捉え方を吟味したりする、中級者以上向けの内容だと感じた。 アカデミックな内容も含み、固めの印象。それでも冷静に史実を積み上げて観...
興亡の世界史01。 アレクサンドロスの成したことを全て読者が知っている前提で、「ヘレニズム」の一般的捉え方を吟味したり、「アレクサンドロス大王」の一般的捉え方を吟味したりする、中級者以上向けの内容だと感じた。 アカデミックな内容も含み、固めの印象。それでも冷静に史実を積み上げて観察している(と素人には読める)内容であり、当時の社会状況もリアルに解説されている。 特に終章のアレクサンドロスの人物像についての記述が印象深かった。 著者のアレクサンドロス観はかなり冷静で、ややもすると批判的にも映る。決して批判的ではないと著者も断っており、あくまで後世からの神格化された"アレクサンドロス像"を捨て去り、時代背景や当時の価値観からよりリアルな実像を描こうとしているのだと感じた。結果、帝国というビジョンはない場当たり的な政治方針だったとか、個人的な名誉欲に突き動かされていた、という評価になったのだと思う。 そしてそれが"批判的"だと感じてしまうのも現代人である我々のバイアスだろう。価値観が異なるし、アレクサンドロスの時代にはろくにモデルケースも確立されていなかったのだから。 アレクサンドロスに対してのそうした見方が獲得できたため、とても有益な読書体験だった。
Posted by
アレキサンドロス3世の物語は、大王死後、300から800年後にギリシヤで書かれたものがほとんどで、ギリシヤ優位な思考で描かれている。 当時のペルシャは、すでに他民族を征服して、緩やかな統治で発達している。 つまり、アレキサンドロス3世の物語は、書き手のオリエンタリズムのフィルタ...
アレキサンドロス3世の物語は、大王死後、300から800年後にギリシヤで書かれたものがほとんどで、ギリシヤ優位な思考で描かれている。 当時のペルシャは、すでに他民族を征服して、緩やかな統治で発達している。 つまり、アレキサンドロス3世の物語は、書き手のオリエンタリズムのフィルターがかかっているので、 できる限り帝国のアレキサンドロス3世の帝国の実態を見て、アレキサンドロス3世の姿を描こうとしている。 東方遠征出発前、アレキサンドロス3世が即位して2年の出来事が、アレキサンドロスの後の東方遠征の原型となると言っている。 テ-ベの消滅は、驚くわ やっぱりと思ったことは、ペルシャを治めるには、ペルシャ人貴族の協力が不可欠とわかっていながら、彼らとの間に安定的な統治システムを構築するのに失敗したとしている点。 戦闘能力と統治脳力は異なることが証明されたのではないか?
Posted by
大王像を多角的な面から見ている。 Q.英雄のいない国は不幸か A.英雄を必要とする国が不幸である。
Posted by
西洋の東洋に対する優位性の誇示(コンプレックスの裏返しという感もあるが)というのが、アレクサンドロスを語る上でのキーワードということらしい。ただ、西洋における過大評価という面を差し引いても、わずか数年でギリシアからインドの一部まで征服したことは史上でも随一ではないだろうか。 誰も...
西洋の東洋に対する優位性の誇示(コンプレックスの裏返しという感もあるが)というのが、アレクサンドロスを語る上でのキーワードということらしい。ただ、西洋における過大評価という面を差し引いても、わずか数年でギリシアからインドの一部まで征服したことは史上でも随一ではないだろうか。 誰もが思うことだろうけど、アレクサンドロスがせめてあと10年生きていたら世界史はどうなっていたんだろう。あれ以上の征服は難しだろうから、ヘレニズム諸国と似たようなもんで、案外変わらなかったりするかも。
Posted by
マケドニア、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、エジプト、イラク、イラン、アフガニスタン、パキスタン。アレクサンダー大王が征服した国の多くが今も戦火に見舞われていることに、因果関係は見つかるだろうか。本書はアレクサンダー大王の出生前から死後まで、...
マケドニア、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、エジプト、イラク、イラン、アフガニスタン、パキスタン。アレクサンダー大王が征服した国の多くが今も戦火に見舞われていることに、因果関係は見つかるだろうか。本書はアレクサンダー大王の出生前から死後まで、歴史と文化の周辺事情をまとめた解説本。 時代が時代だけに原典が限られていることもあって、大王について記すべき事項は全体的に記載されている。先王フィリッポス2世の活躍に始まり、ギリシャ征服、先王暗殺、グラニコスでの一騎打ち、ゴルディオンの結び目の一刀両断、アモン神殿での信託、イッソスとガウガメラの会戦、ペルセポリス王宮の放火、アケメネス朝の滅亡、インド侵攻、スーサでの集団結婚式、そして死後の後継者将軍達の戦争。特に、戦記モノではあまり書かれない文化や社会事情の変遷の紹介は、大王の行動だけでなく、歴史に与えた影響をも伺い知ることができる。 ただ、それでもやはり全部が載っているわけではなく、それぞれの戦での戦術詳細や、遠隔地での生活、書かれていない後継将軍のその後など、Wikipediaの方が詳しい箇所も多々ある。だが、その欠落した箇所への興味を持たされることこそが、本書の役割なのかもしれない。 大王の人物像に迫るも、戦術詳細に迫るも、その後の歴史に迫るもよし。セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプト、アンティゴノス朝マケドニア、アッタロス朝ペルガモン。大王の時代から先は、全てローマと繋がっている。
Posted by
日本語で読めるアレクサンドロスの概説書としては、最もオススメできそうな一冊。 冒頭でアレクサンドロスがこれまでどのようなイメージを付与され、受容されてきたかを整理したうえで、本書のスタンスを以下の通りとしている。 まずあくまで可能な限り客観的な歴史的条件のもとで彼の行動を分析す...
日本語で読めるアレクサンドロスの概説書としては、最もオススメできそうな一冊。 冒頭でアレクサンドロスがこれまでどのようなイメージを付与され、受容されてきたかを整理したうえで、本書のスタンスを以下の通りとしている。 まずあくまで可能な限り客観的な歴史的条件のもとで彼の行動を分析すること。 そしてその意義を、彼の前後の歴史的展開も踏まえた長い視野で捉えること。 このような姿勢を貫きながら、アレクサンドロス個人の人となりを描きつつも、それ以上に彼の築いた帝国の実態と、後世に与えた影響をより鮮明に描き出している。 綿密な史料批判や先行研究の批判的な検討に基づいて論が進んでいくために、かなり幅広い視点から、アレクサンドロスの実態を追うことができる。 アレクサンドロスについては、多くの書物にあたるより、よくよくこの一冊を読み込んでから、他に手を出すのが最も効率的なように思う。
Posted by
00巻よりはややまともで、アレクサンダー大王について多少は詳しく書かれているのですが、いいとこ塩野程度の水準で、暇つぶしに読むならともかく世界史に興味があるのならなるべくは他の本を手に取るべきでしょう
Posted by
わりと当たり外れが無くて、安心して読める興亡の世界史シリーズ16冊目。これで残りは5冊。 この本のテーマは「神になりたかった男、アレクサンドロス」。やったことは、ありていに言えば「実写版聖闘士星矢」とでも言えるかもしれない。 といっても神話が日常世界と近しく親しまれていた古代...
わりと当たり外れが無くて、安心して読める興亡の世界史シリーズ16冊目。これで残りは5冊。 この本のテーマは「神になりたかった男、アレクサンドロス」。やったことは、ありていに言えば「実写版聖闘士星矢」とでも言えるかもしれない。 といっても神話が日常世界と近しく親しまれていた古代ギリシャという背景を考えると、全く荒唐無稽な夢想ではなかったし、本人自身あくまで統治の手段としての神格化、という割り切りもあったようだ。軍事的な大天才であることは疑いないが、政治的な戦略性と柔軟性も兼ね備えた稀有の人物であったことが本書全体から伺える。 一方で、後のルネサンスを経て古代ギリシャの血脈を受け継いだ西欧世界による「ヘレニズム」=「西欧世界によるアジアの啓蒙」という一義的な解釈への警鐘も繰り返し述べられている。 そう考えると、日本ではアレクサンドロスやヘレニズム世界って、そんなにメジャーな歴史上のモチーフでは無いと思うのだが、西欧人だとまた違った見方から彼を英雄とみなす向きもあるのかもしれない。 いずれにしても僅か10年でエーゲ海からインド洋まで攻め貫いた稀代の天才が35歳という若さで夭逝した事は、歴史の綾を超えて、神のいたずらとも感じられる。解釈の仕方は人それぞれだと思うが、個人的にはこの早すぎる死こそが、彼に伝説性と神格をもたらしたのではないだろうか、と思ってしまった。 本書について言えば、綺麗な章立て、丁寧な文章、慎重な解釈、1つのエピソードを敢えて繰り返し登場させることで文脈を絡めていくテクニックなど、歴史文献としてかなりの完成度に達している本だと思いました。
Posted by
一般読者向けに、平易に著された入門書。アレクサンドロス大王の魅力に迫る。学者が書いた割に、ロマンを感じさせる雰囲気をもった一冊に仕上がっている。
Posted by
たくさんの史料をもとに書かれた本らしく、実際はこうらしい……、という新しい知識が増えた。元々、アレクサンドロスに関しては一次史料がほとんどないっていうか、現在確認できる(参照できる)一番古い史料でもアレクサンドロスの時代から300年近く後に書かれたということでこんな点からも歴史の...
たくさんの史料をもとに書かれた本らしく、実際はこうらしい……、という新しい知識が増えた。元々、アレクサンドロスに関しては一次史料がほとんどないっていうか、現在確認できる(参照できる)一番古い史料でもアレクサンドロスの時代から300年近く後に書かれたということでこんな点からも歴史の事実を探すのは難しいと思いつつ、さらにはこの時代のことがよく残っていたなぁとか思う。
Posted by
- 1
- 2