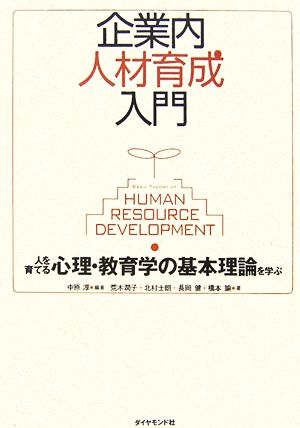企業内人材育成入門 の商品レビュー
”理論“と”実践“の関係性について、 気付くことができました。 “良い理論”を知ることは、 “良い実践”につながることになります。 だからこそ、“正しい理論を知る”べきです。 ”オトナの学習“についての記載があり、 豊富な経験が逆に邪魔していることも、 理解できました。 ア...
”理論“と”実践“の関係性について、 気付くことができました。 “良い理論”を知ることは、 “良い実践”につながることになります。 だからこそ、“正しい理論を知る”べきです。 ”オトナの学習“についての記載があり、 豊富な経験が逆に邪魔していることも、 理解できました。 アンラーニングの言葉の意味が、 より深まりました。 この本から学んだことを 自分の行動に当てはめて見たいと思います。 人事関連部門の方だけでなく、 実務現場で人を預かる立場の方こそ、 人の人生にすら影響を与える可能が高いため、 正しい理論を身に付けるために、 読むべき本だと感じました。
Posted by
前半は理解がしやすかったのに、後半だんだんむずかしくなっていった、、あるあるなんだけど、私の集中力の問題かな。整理してからもっかいコメント書こう。
Posted by
◯3. 動機付けの理論 ・高次の活動に効果的な内発的動機づけ、その源は知的好奇心と自律性。 ・前者は例えば新しいことに挑戦する面白さ、これを活用した学習法が発見学習で、自ら仮説検証をして主体的に学ぶ ・後者は自分が周囲環境を効果的に処理でき、自分の欲求をどのように充足するかを自由...
◯3. 動機付けの理論 ・高次の活動に効果的な内発的動機づけ、その源は知的好奇心と自律性。 ・前者は例えば新しいことに挑戦する面白さ、これを活用した学習法が発見学習で、自ら仮説検証をして主体的に学ぶ ・後者は自分が周囲環境を効果的に処理でき、自分の欲求をどのように充足するかを自由に決められる状態。 ・外発的動機付けを内発的に変えるには、規則や価値を自分なりに噛み砕いて消化して行く「統合」という過程が必要。 ・無気力は後天的に学習されるもので、性格ではない。自分がコントロールできない状態に置かれ続けると受動的で無気力になる(学習性無気力) ・評価制度で、基準や過程がわからず、上司の主観で決められると、部下は自分で変えられないと感じやる気を失う。求められるもの、プロセスが明らかな場合は、主体的に行動する。 ・学習の結果の原因を自分の中にあり、変えられるもの、すなわち努力に求める時、学習意欲が高まる ・本人が自分の環境や成果をコントロールできる「随伴性の認知」が大事 ・自分はある行動を取れるはずだという自信(効力期待)があるときに、やる気(結果期待)は高まる。 ・他者から評価されることに関心をもち、成功や他者へ勝ちたいというパフォーマンス目標を持つ場合、評価を得られないとやる気を失いやすい(能力固定観)。自分の能力を自分でどれだけ高められるか、ラーニング目標を持つ場合は目標達成へ継続的な努力ができる。 ・人が辛く困難な状況であっても、やりがいを見出すのは 1. やっていること自体に楽しみ感じるから 2. 夢を共有しているから、企業が掲げるミッションやビジョンに共鳴するから ◯成果主義の問題点 1. 評価によって将来が決まってしまう人材選抜 2. お金がインセンティブになるのか 3. そもそも頑張る体制にあるのか 4. 短期の成果に縛られ、長期のチャレンジをしなくなる 成果主義が一部の人にとって都合よく運用されてはならず、公平性と透明性が重要。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いろんな組織開発の理論が紹介されるとともに、具体的にわかりやすいよう、架空のストーリーにもなっている。 実際の社会、企業、現場ではたして活用できるのかどうかは、まだ検証されていない本なので、これからという感じ。 理論を知ることは大切だけど、実学として学ぶ意識でありたい。
Posted by
「研修開発入門」が手段やノウハウを解説しているとしたら、前段となる”なぜ人材育成をするのか?”を問う内容。学習理論や研修効果など様々な理論が紹介されています。教育研修に関わる人のバイブル的存在。
Posted by
人材育成に纏わる諸々の理論をまとめてくれている教科書的な印象。一定期間、人事の仕事をやっていれば聞いたことのある話、読んだことのある本からの話題が多いが、それが全て頭に入って実践できているわけでは当然なく、本棚に眠っている原著、『最強組織の法則』やら金井先生の本やらを再読しようか...
人材育成に纏わる諸々の理論をまとめてくれている教科書的な印象。一定期間、人事の仕事をやっていれば聞いたことのある話、読んだことのある本からの話題が多いが、それが全て頭に入って実践できているわけでは当然なく、本棚に眠っている原著、『最強組織の法則』やら金井先生の本やらを再読しようかなと思う。 扱うテーマが多岐に渡るので、備忘がてら目次だけ記載。 ・学習のメカニズム ・学習モデル ・動機づけ理論 ・インストラクショナルデザイン ・学習環境のデザイン ・教育・研修の評価 ・キャリア開発の考え方 ・企業教育の政治力学 章によって著者が違うので、あるときは物語風のモデルケースなど、書き方が異なるのは少々気になる。
Posted by
人材育成に携わる上で、基本的なことをざっと理解するにはとても良い本。 動機づけ理論、フロー理論、ナレッジマネジメント、学習する組織…1章ごとに本が一冊書けそうなくらい濃い内容なので、人材育成に必要な知識を学ぶ入口としておすすめ。
Posted by
人材育成は勘や経験によるものではなく、学習についての理論がありそれに基づいた方法論がある、と言う。これから人材育成を考えるにあたって基本となる考えを身につけることができた。
Posted by
企業における人材育成に関する広範囲な基礎理論が紹介されている。 各種学問だけでなく、政治力学や評価などにも言及がある。 この本で広く体系的に知ることができ、詳しく読むべき本も紹介されているため、 企業での育成に関わり始めた教育担当者やマネージャー、研修講師におすすめしたい。
Posted by
人材育成をされてた先輩に紹介してもらい手にとった本書。 もっと早くに出会えば良かったというのが率直な感想。 「よい理論ほど実際に役に立つものはない」を体現した一冊。
Posted by