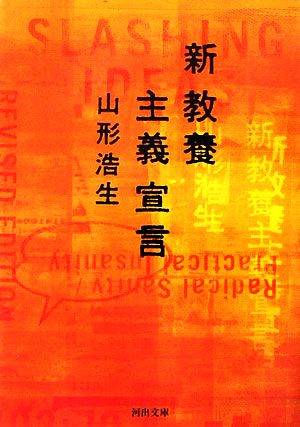新教養主義宣言 の商品レビュー
教養でもくらえ! そう啖呵をきって、 著者山形浩生は口角泡飛ばしながら雑多な話をべらべらと捲し立てる。 ご大層な題目の本書だが、 小難しいながらも分かりやすい語り口で、 タイトルほど堅苦しくなく(なんならこの堅苦しいタイトルはネタであるように思う)文章自体はするする読む事がで...
教養でもくらえ! そう啖呵をきって、 著者山形浩生は口角泡飛ばしながら雑多な話をべらべらと捲し立てる。 ご大層な題目の本書だが、 小難しいながらも分かりやすい語り口で、 タイトルほど堅苦しくなく(なんならこの堅苦しいタイトルはネタであるように思う)文章自体はするする読む事ができる。 ただ、予備知識はある程度必要だ。 そしてその予備知識が多くの人間に備わってない事が問題だ。と、本書の序盤でも書いている。 予備知識があれば、 それを踏まえてもう一段先の話が出来るのに、 そしてもう一段先の話からが、 本当に面白い話になるというのに。 だから教養ってのは大事で、 生きて行くのに必要の無いトリビアみたいな扱いにするのは間違いで、 実用的で本質的な知を、思想を、アイディアを、もっと人々は知るべきだ。 みたいな話。 この本を手に取ったのは、 別にインテリぶってマウンティングしたいわけでもないし、 ムズカシイ本読んでる俺カコイイを演出したいわけでも、 世間の馬鹿さ加減を憂慮してるわけでもない。 いや、 結局はそんな見苦しい下卑た思いも含まれてはいるけれど、 教養とは何か?という学歴コンプレックスからくる教養の無さを埋めたいという思いと、単純な知的好奇心が働いたというのが、大体の理由だ。 さっぱりわからないところもあるけれど、 なるほどと得心するところも多々あった。 特に、 第一章のメディアは人間の気遣い力を破壊するの項は、現在の日本の状況を言い当ててる。 見たいモノしか見ない人間の管見さ、 キャパの狭さは、 読解力や認識力を低下させる。 みたいな話。 つい最近Twitterで見かけた、 A:このツイートに上げてる曲名なんですか? B:うっせぇわ A:なんやその態度、ブロックしたろ の一連の流れに顕著に出ていると思う。 これBはAdoの「うっせぇわ」という曲を紹介してて、それをただの暴言だと認識してしまったAが怒った。という馬鹿みたいな話だが、曲名が勘違いさせる要素を多分に含んでいたとは言え、 気遣い力、読解力、認識力が有れば防げた事態でもある。 そう、 うっせぇわという曲名が、 相手を勘違いさせるかもしれないと考えて、 「うっせぇわという曲です」とか、 「Adoのうっせぇわです」とか、 Bがちょっとだけ丁寧に返事を返せば済むはずだし、 Aも、話の流れを鑑みて急に暴言吐かれたと考えずに一旦その言葉をググればよかったんじゃ無いかと思う。まぁでも誰でもAみたいに勘違いするよな、普通。 これはBが投稿してた話で、 被害者ヅラしてたけど、 BもBで配慮が足らなかった事を反省するべきだと思う。 まぁ一番悪いのはこんな曲を作ったAdoだったりする。 うっせぇわ。 あとは、 消費税あげようとか、 選挙権売ろうぜとか、 小説とか映画の面白さを伝えるのムズイとか、 色々言ってて一理あったりする。 子のつく女の子は頭がいいっていう本の書評もなかなか。 子がつく女性はメディアに毒される前につけられた名前だから云々って話で、 その裏付けに紅白歌合戦の参加者にどれだけ子がつくかデータとったとか、説を立証させる切り口が斬新。 今はキラキラネームのカウンターで、 普通の名前ブームが来てるけど、 (普通の名前ブームって変な言葉だな) 読みは普通だけど漢字が凝ってたり、 なんだかそれもそれでって感じ。 ピカチュウちゃんとか、 キラヤマト君とか、 ハローキティちゃんは、 今何歳になったんだろう? そして彼等が大人になった時、 子供にどんな名前をつけるんだろう? ピチューとか、 百式とか、 ポムポムプリンでない事を祈ろう。 そんなこんなで、 教養がいかに必要かというよりは、 その教養がどんな知的生産だったり、 知的好奇心をもたらすのかといった、 脈絡のない思考の澱みたいな本だ。 冒頭でミームの話があったし、 ミーム然とした本として在るのは当然と言えば当然か。 僕がまだミームという言葉を知らない時、 無意味にも意味があるという意味で、 無意味を逆から読んでミームという言葉を作ってみたことがある。 その曖昧でごにょごにょしたイメージは、 本来の意味のミームと少し似ている気がする。 思考やアイディアの塊としてのミームは、 またその触手を伸ばし、 僕の元へとやって来た。 それからまた、 誰かの概念の中に住み着き、 また広がっていく。 そういうふうに、 教養と言われるものも広がって、 どこかの誰かが、 その概念とともに知を求める面白さに目覚めて、ミームとなって脳に侵食していけば、 破綻した民主主義の中にも、 一縷の光が差し込むかもしれない。
Posted by
2021/12/07読了 おもしろかった! 書かれていることが刊行から20年近く経った今でも古くなく今のSNSやインターネットの状況を予言してるのか?ってくらいメディアやその周辺への指摘が鋭い あとおもしろさと教養についての話がすごいよかった
Posted by
1993〜1999ころの山形氏の書評、あとがき、コラム等をまとめたもの。ミルグラム実験(服従の心理)の本を翻訳した人だが、こんなに面白い人とは思わなかった。 自分の考えに自信があり、さらに論理的で反論のあとのこともよく考えられているようだ。 金融政策のことも10年以上前に書かれた...
1993〜1999ころの山形氏の書評、あとがき、コラム等をまとめたもの。ミルグラム実験(服従の心理)の本を翻訳した人だが、こんなに面白い人とは思わなかった。 自分の考えに自信があり、さらに論理的で反論のあとのこともよく考えられているようだ。 金融政策のことも10年以上前に書かれたことながら、古くなっていない。 ふざけた内容も多くあるが、読むと面白い。 今後もこの人に注目したい。
Posted by
教養論だと思って、去年の三月に購入したらしいのだが、教養について論じたものではなく、著者のもつ具体的な教養を陳列したもの。文章を書ける人はいいなあと思う。こういう先生は早熟なんだろう。
Posted by
途中から何となく、独りよがりで、読者を意識してない感じの展開について行けなくなってしまい、3分の1を過ぎた辺りからは、斜めに読み飛ばす事になった。 部分部分では、成る程と思う所もあるんだけど、自分にとって面白く読み進めるという本ではなかった。
Posted by
文学、思想、政治、経済、情報といったあらゆるジャンルに大胆な横断線を引きつつ軽やかに展開される、著者の知的アクロバットに瞠目させられるばかりです。それも、ひところ流行ったポストモダン的知性とは正反対の、「解説」の宮崎哲弥が言うところの「アメリカ的健全性」に貫かれた文章で綴られてい...
文学、思想、政治、経済、情報といったあらゆるジャンルに大胆な横断線を引きつつ軽やかに展開される、著者の知的アクロバットに瞠目させられるばかりです。それも、ひところ流行ったポストモダン的知性とは正反対の、「解説」の宮崎哲弥が言うところの「アメリカ的健全性」に貫かれた文章で綴られています。 そして、これも宮崎が指摘していますが、この健全性の背後には、啓蒙性、それも民主的啓蒙ではなく、真の自由を啓蒙するという著者の意図が裏張りされています。そのため、いったい著者は本気で書いているのか、それとも読者に自由な思索のあり方を示すために意図的に大胆な発言をしているのか、見分けがつかないところがあります。 大胆でとことん自由でちょっとだけ押しつけがましい著者の知性が放つ熱量に当てられたのか、自分でもなんだかよく分からないようなインスピレーションを受けとった気にさせられました。いずれにしても、たいへんおもしろい本ではあると思います。
Posted by
上から目線が鼻につくが、先見性があるのはたしか。 もともと、クルーグマンの紹介者として、筆者を知ったが、他にも面白い本の目利きでもある。 本書は断片的にいろんな話題に飛ぶが、一つのテーマを深く掘り下げたものも読んでみたい。
Posted by
借り物。 借りたから読みますか、くらいのテンション。 いわく、 教養には啓蒙が必要である、 今の日本は文化的教養の地盤となるものがない、とか ごたいそうに憂えてくださって、 どうもこの癖のある文体のせいか、割と早めの段階でかちんときて 斜に構えて読んでしまいました。 読みやす...
借り物。 借りたから読みますか、くらいのテンション。 いわく、 教養には啓蒙が必要である、 今の日本は文化的教養の地盤となるものがない、とか ごたいそうに憂えてくださって、 どうもこの癖のある文体のせいか、割と早めの段階でかちんときて 斜に構えて読んでしまいました。 読みやすくしようとしているのか、 それとも多少の羞恥心が入っているのか、わかるんだけど 文章じたいにこういう余計なものが入ってると、内容どころじゃない。 まあはっきり言うと好きじゃない。 押しつけがましくて独善的、と、感じる人もいるんじゃないかな。 残念ながら私はそっちでした。 プロジェクト杉田玄白自体はいいと思うんですけどね。 言ってること自体は別に間違ってはいないので 面白く素直に読める人であればすごくハマるかも。
Posted by
知的好奇心は必ず伝染する。 「はじめに」からわくわくしました。 単発のものを次はそれらを繋げていかなくてはいけない。教養は体系やある種のまとまりがあって、初めて意味を持つから。 何かのブームが終わった後には何も残っていない。それをもっと活かす方法があったはずなのに。 伝えるべ...
知的好奇心は必ず伝染する。 「はじめに」からわくわくしました。 単発のものを次はそれらを繋げていかなくてはいけない。教養は体系やある種のまとまりがあって、初めて意味を持つから。 何かのブームが終わった後には何も残っていない。それをもっと活かす方法があったはずなのに。 伝えるべきは、教養そのものではなく、教養の持つ力であってその面白さ。あらゆる分野にいろんな形で存在していることを山形浩生さんは伝えようとしています。 楽器が単に音を立てていたのが、いきなり音楽と化す不思議。その経験をきちんと説明して伝えられれば、必ずそれは伝染して追随者を生む。 途中略しましたが、以上のようなことが書かれています。 山形浩生さんは翻訳者でもあるため、本編では訳した本をフランクな語り口調で要約して解説しています。 情報処理と意思決定の速度の話が特に印象に残っています。 情報処理速度が速くなったからといって、意思決定の速度が速くなることには限界がある、という話。 私は確かに意思決定が速くなる速度に限界はあると思いますが、情報処理が速くなることには人の一瞬のひらめきを助けたり、待ち時間のいらつきを抑えることが出来て結局は人の気持ちを左右することにもつながるかとも考えました。 しかし、著者の言いたいことは理解できました。特に、「情報だけで片付くなら、人はふられてつらい思いをすることなんてない」っていう喩え話には納得してしまいました。 私のように反論するための本ではなく、海外の長い本の中から色々な考え方があることを示してくれている本なので素直に受け止める方が賢い読み方だと思いました。 全体的に飽きが来ない話で、翻訳本の方も何冊か購入しました。
Posted by
宣言という勇ましいものではなく、この時代のこの時代らしい生業にいそしむ者の、荒れた、極めて切迫した、焦燥と自己満悦に溢れる歪な教養の姿、と言っていいだろう。杉田玄白プロジェクトと後半の漫画評は読めるもも。
Posted by
- 1
- 2