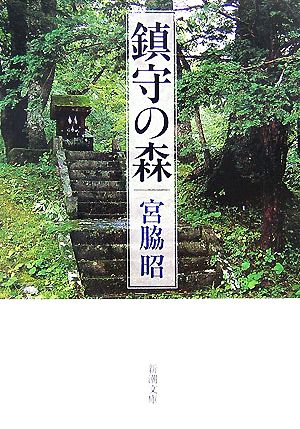鎮守の森 の商品レビュー
森にとっての最適条件は適度な我慢 人間も同じ、常に満たされている状態は危険であり衰退の原因となる 神道、仏教の自然崇拝という自然との共生思想を忘れてしまったことで日本人の誇りも失われた 潜在自然植生で木を植える 魂の森は人々の心の拠り所
Posted by
一志 治夫作「魂の森を行け 3000万本の木を植えた男」は宮脇昭氏の人生を描いた名作です。ある意味アクの強い宮脇氏のエッセンスを客観的に描いており、「鎮守の森」という概念を世界に広め、数々の森を復活させてきた偉業を余すことなく書いています。 そして本作はその後本人が書いたその名も...
一志 治夫作「魂の森を行け 3000万本の木を植えた男」は宮脇昭氏の人生を描いた名作です。ある意味アクの強い宮脇氏のエッセンスを客観的に描いており、「鎮守の森」という概念を世界に広め、数々の森を復活させてきた偉業を余すことなく書いています。 そして本作はその後本人が書いたその名も「鎮守の森」 これは彼の熱い熱い思いがぐらぐらと煮えたぎっていて、文章なのにとっても前のめり。 森作りという静謐に思える行動を熱くアグレッシブに行動していきます。なんだかんだ20年前くらいの本ですが、あれからどれくらい森が復活したんだろうかと思うとワクワクします。 川もそうですが、人が本気で取り組むと自然も本来の美しい姿を取り戻すんですね。多摩川や荒川なんて昔どぶでしたから。 針葉樹を植えて緑化したと言っている自治体は今でも有りそうですね。我が住まう自治体は杉を売り物にしている町なんですがどうなんでしょうか・・・。 繰り返し繰り返し同じ事を書いている部分も有りますが、まるで宮脇氏の肉声を聞いているようで楽しいです。御年90になるようですがお元気なのでしょうか。 今でもイオンの植樹祭は続いているようです。継続は力なり!
Posted by
昔から人々の隣には、神社があり、その周りには林というか森があった。蚊に刺されながら飛び回ったり、ガマガエルを捕まえたり、ドングリを拾ったり。そんな子供時代を思い出した。遊びの場であった、そんな森には、地域を守る大きな役割があったことを教えてくれる。
Posted by
「鎮守の森」というタイトルは、 本書を読むほどに、筆者の訴えたいことを端的に象徴している。 ポイントは2点。 1)どこの土地にもあるはずの「固有の植生」、そこには防災上、宗教上、文化的伝承、生物多様性保全などの重要な意味がある。 2)固有のものであれそうでないものであれ、植生に...
「鎮守の森」というタイトルは、 本書を読むほどに、筆者の訴えたいことを端的に象徴している。 ポイントは2点。 1)どこの土地にもあるはずの「固有の植生」、そこには防災上、宗教上、文化的伝承、生物多様性保全などの重要な意味がある。 2)固有のものであれそうでないものであれ、植生には「生理的最適」(居心地の良い状態)と「生態的最適」(嫌な奴とも何とか折り合いをつけながら存在している状態)が存在し、後者にこそ健全性がある。 これらの点を踏まえない緑化は不適切なのだそうだ。また、緑化を適切にやるにも、相応の覚悟を持ってやり切ることが必要との主張も筆者はしている。 少なくはなったが、日本にはまだ各地に鎮守の森が残っているという。本書の最後にその代表的な場所が紹介されている。 学者にありがちな難解で押し付けがましい主張は厳しく抑制された書き方がされていて、全体に穏やかな筆致で論旨は進んでいく。それでいて「火事場の野次馬」のような、エモーショナルな表現が時折繰り出され、それが心地よいアクセントになっている。 よく語られる「持続可能」ということの本当の意味は何か、の解の一つが本書であるように思う。 また、環境保全の話から始まり、それを超えた部分にも目を向けた啓蒙的な主張、「生態的最適」論に代表されるような、人間社会の処世術まで考えさせるところが面白い。 人付き合いに何らかの倦怠感を抱いた時、本書を読み返して最寄りの鎮守の森を訪れると、もしかしたら、森が何らかの啓示を与えてくれるかもしれない、そんな気持ちを持たせてくれる一冊だった。
Posted by
土地本来の植生(生態)を考えた森作り 我が家の庭も金ばかりかかる見せかけの緑か。 森が形成されるプロセスは個々の相互作用の結果。 森は人を育み,人が森を育む。そこはある種の宗教的シンボルとなる。宗教性を失った人間は横暴になるのか。
Posted by
生態的な最適条件とは、生理的な欲望を全て満足出来ない、少し厳しい、少し我慢を強いられる状態であることを、長い命の歴史は教えている。 という文書が印象的。確かに全てを手に入れてしまうと、堕落してしまうのかなと。。やはりバランスだね。自分の我慢できることを見定めて、切磋琢磨すること...
生態的な最適条件とは、生理的な欲望を全て満足出来ない、少し厳しい、少し我慢を強いられる状態であることを、長い命の歴史は教えている。 という文書が印象的。確かに全てを手に入れてしまうと、堕落してしまうのかなと。。やはりバランスだね。自分の我慢できることを見定めて、切磋琢磨することが大事なんだ、きっと。
Posted by
「本当の森」というものは、その土地本来の樹種が、高木、低木、下草と階層的に共生した状態である。そのような本来の森は、ほとんど失われてしまったが、日本の寺社のまわりに鎮守の森として残されている。 著者はその土地固有の植生を割り出しながら、国内外で3000万本以上の植樹活動を続けて...
「本当の森」というものは、その土地本来の樹種が、高木、低木、下草と階層的に共生した状態である。そのような本来の森は、ほとんど失われてしまったが、日本の寺社のまわりに鎮守の森として残されている。 著者はその土地固有の植生を割り出しながら、国内外で3000万本以上の植樹活動を続けてきた世界的権威。 この本では、生態学的な内容だけにとどまらず、文明論にまで踏み込んだ示唆に富む考察も含まれている。名著。
Posted by
ブルータスでおすすめされてた本だけど、おもしろい!生態学、日本古来の森をつくり直す話しだけど、宗教、人間につながり、ビジネスにも置き換えることができる。植物にとって最高な状況は最適でないため、それは長く生き続けることができない。満たされていない状況がよりよい成長を促す。人と同じで...
ブルータスでおすすめされてた本だけど、おもしろい!生態学、日本古来の森をつくり直す話しだけど、宗教、人間につながり、ビジネスにも置き換えることができる。植物にとって最高な状況は最適でないため、それは長く生き続けることができない。満たされていない状況がよりよい成長を促す。人と同じですね。眼に見える物、数値化できるものばかりにとらわれ、見えないものをみようとしない結果、大切なものを失った日本人。森と歴史は同じなんだ、と。いやはやおもしろい。
Posted by
日本禅t内でいえば戦前にはおそらく15万以上の鎮守の森があった。しかし今はかなり少なくなっている。 欧州では9000年ほど前に最後の氷河期が去り、氷河期にスカンジナビアから運ばれてきた土砂がそのまま残された。 肉食人種であるゲルマン民族は有史以前から森の中に山羊、牛などの家畜を放...
日本禅t内でいえば戦前にはおそらく15万以上の鎮守の森があった。しかし今はかなり少なくなっている。 欧州では9000年ほど前に最後の氷河期が去り、氷河期にスカンジナビアから運ばれてきた土砂がそのまま残された。 肉食人種であるゲルマン民族は有史以前から森の中に山羊、牛などの家畜を放牧して森を破壊した。 世界史を振り返ってみれば、かつての文明を支えた都市とその周辺はメソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマ帝国の勢力範囲も含めて、ほとんど土地本来の森は消滅している。 鎮守の森とは実は最もダイナミックsに安定したひとつの森社会である。 通産省は工場立地法をつくった。すなわち新しい工場をつくる場合にはその敷地面積の20%以上を緑地にしなければならないという法律。 自然界にはまだあまりにもなぞが多い。 唯一神がたった2000年の間で、地球をダメにしてしまった。唯一神や人間が中心の教養や思想であったために、他の生き物や自然環境は征服し、利用するためのものであった。
Posted by
土地本来の植生に適合する樹木は、成長が早く厳しい環境にも耐え、定期的な保全活動がなくとも安定した森を形成する。その森はまた、災害にも強い。そのような土地本来の森の多くが、この数千年で地球上から姿を消した。が、日本ではそのような森が意図的に残され、畏敬の対象となってきたのだ。それが...
土地本来の植生に適合する樹木は、成長が早く厳しい環境にも耐え、定期的な保全活動がなくとも安定した森を形成する。その森はまた、災害にも強い。そのような土地本来の森の多くが、この数千年で地球上から姿を消した。が、日本ではそのような森が意図的に残され、畏敬の対象となってきたのだ。それが鎮守の森である。本書は、鎮守の森に象徴される「ふるさとの木によるふるさとの森」を守り育てよう、という提言と、その実践の記録である。 ここで肝心なのは、日本の潜在自然植生が照葉樹林であって、里山・雑木林・田んぼといった懐かしげな風景を作るものたちではないということだ。照葉樹林にはひどく暗い森という印象があり、またここしばらく雑木林にちょっとばかり関心を持っていることもあって、当初はずいぶん抵抗を感じた。しかし、鎮守の森という呼称はあまりに良すぎる。理論、実践、実績の裏づけもさることながら、自分の中にある鎮守の森の風景と畏敬の念の記憶に思い当たったとき、どうにも納得せざるを得なかった。 さっそく、近くの神社でドングリを拾ってきた。向かいの空き地(人の)にこっそり植えるのだ。毎年夏になると背丈ほどの雑草で埋まるあの土地(人の)が森になったら、どんなにいいだろう。どうかこのゲリラの森が、大きく育ちますように。
Posted by
- 1