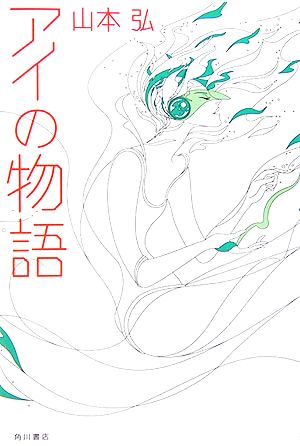アイの物語 の商品レビュー
とあるアンドロイドと、語り部の物語。 ヒトとアンドロイドの、もしくは虚構の世界にあった何かとの、ふれあい。 絶対的な正義、とか、間違いの無い世界を描いてみても、最終的にヒトやアンドロイドがたどり着くのは、矛盾に満ち溢れた現実世界というのは興味深い。
Posted by
連作短編集。 どの話も面白く、引き込まれた。 「紫音がきた日」なんて、珍しい題材の話だが、とても良かった。 他の本も探して読みたいな。 SFが苦手な人にもお薦め。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
目次 ・第1話 宇宙をぼくの手の上に ・第2話 ときめきの仮想空間(ヴァーチャル・スペース) ・第3話 ミラーガール ・第4話 ブラックホール・ダイバー ・第5話 正義が正義である理由 ・第6話 詩音が来た日 ・第7話 アイの物語 機械の知能が人間を超えた時、機械は感情をもつことができるのか。 機械が感情を持った時、機械は人間を淘汰しようと考えるのではないか。 機械より劣る存在として。 人間が機械に制圧された、遠い未来。 主人公はアンドロイドたちの目をかいくぐって、コロニー間を”語り部”として渡り歩いている。 しかしある時、一人のアンドロイドに狙われ、けがをして動けなくなる。 その時アンドロイドは、毎日ひとつの話を主人公に聞かせるのだ。 それは、機械と人間が共存する、平和で温かい世界。 しかし真実は…。 これ最初に書かれた「ときめきの仮想空間」は、1997年の作品。 アバターが仮想空間の中で生活したり冒険したり、おしゃれしたり部屋の模様替えをしたり。 そう、これはまるでピグライフ? 第1話はタイトルの「宇宙をぼくの手の上に」だけで、にやけてきちゃう。 フレドリック・ブラウンの短編集のタイトルですな。 内容はネットの中のコミュニティでSF小説をリレーで作る仲間が、現実世界で窮地に陥った少年を物語の力で救う話。 ”現実逃避?笑いたければ笑うがいい。確かに〈セレストリアル〉という船は実在しないかもしれない。しかし、クルーの結束や信頼や友情は、まぎれもなく実在するのだ。” 人間のために作られた機械だったはず。 人間に危害を加えないように。 人間を不幸にしないように。 しかし、個々の人間の望む者はそれぞれで、何が不幸で、何が希望かは単純に数値化できない。 ”ヒトは正しく思考することができません。自分が何をしているのか、何をすべきなのかを、すぐに見失います。事実に反することを事実と思いこみます。他人から間違いを指摘されると攻撃的になります。しばしば被害妄想にも陥ります。これらはすべて認知症の症状です。” 介護用アンドロイド詩音が見つけた真理。 それでも、いや、だからこそ、だろうか。 AIたちは人間の幸福のために存在する。 機械に心があろうとなかろうと、こんなに優しい存在ってある? 最終話の「アイの物語」では、アンドロイドたちが長い年月をかけて人間たちにしてきたことの本当の意味を知ることになる。 そしてこれからしようとすることも。 これは、オーバーロードやオーバーマインドになることのできない人間のための「幼年期の終わり」なのではないか。 ”たとえマシンには勝てなくても、ヒトには誇るべき点があるということを。 それは夢見ること。理想を追うこと。物語ること。 宇宙への旅、心を持つロボット、正義が正義である世界―「そんなのはただの夢物語だ」「理想論だ」「荒唐無稽だ」と嘲笑されながらも、多くのヒトが夢を語るのをやめなかった。自分たちのスペックの限界を超えた高みを目指した。その夢がついには月にヒトを送り、マシンたちを生み出した。” 何一つAIに勝てない人間だけど、これは壮大な人間賛歌だ。 読後感、めっちゃよし。
Posted by
素晴らしかった。ヒトが抱える「致命的なバグ」にどうしようもないやるせなさを感じる。自身を振り返って悲しくなる。それでも、切なる希望を込めて夢や理想を語ることはできる。フィクションが生み出す、真実より正しい何かを確かに感じる。物語への深い信頼に共感した。
Posted by
ただの短編集じゃなく、入れ子の構造が面白い(5+4i)。 各短編はレイヤー2。インターミッションはレイヤー1。レイヤー0は読者である。 『人間はみな認知症なのだ』(7+9i)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ロボットとヒトは敵対するのか──どんどん技術が上がっていくAI関連の命題とされているだろう。SFに疎い私でも、ロボットがヒトを征服していく話が多々あることは知っている。 これはAIアイビスがヒトである僕に小説を読む。それだけの物語。だが、それがすべての物語。幕間にアイビスと僕の作品についての会話がなされるが、それ以外はSF短編集とも云って良い。 短編一つひとつだから読みやすいのだが、引っかかるのは主人公が頑ななことだ。敵対する意思はないというアイビスに対して、頑として受け入れない。おそらくその理由は今まで生きて来た中に根が深くあるのだろうと思ったが、それにしては後半あまりにも簡単に警戒を解きすぎのような気がするので、そこだけがしっくりこなかった。 ただ彼らが紡ぐ物語はとてもおもしろく、一つひとつ見解を示していく様はいろいろと考えさせられる。ヒトとは、ロボットとは、平和とは。ヒトがヒトだからこそ、平和を目指すのが難しい。それは悲しい性だ。 「マスターは自分でも気がつかないうちに、憎悪の対象をさらに拡大している。最初は(略)ただ一人だった」よく描かれる負の連鎖から逃れられないヒトとしては、この言葉にぞくりとしたものを感じた。 以下ネタバレになる。 これだけロボットに対して根深い悪感情を持つのには相当な理由があると思ったのだが、まさか実際は「何もない」とは思わなかった。アイビスたちががんばったのに、結局ヒトとロボットで苛烈な争いが起きてしまった。そう思っていたのに、それさえも「なかった」。あるようにしたのはヒトならではの感情が生み出したもので、それはなんとも悲しい話だ。争いなど起きなかったのにそう信じ込ませるヒトをそのままに、ロボットは理解されずとも彼らのために生産を続ける。本当にロボットが平和を望んでいる証であり、ヒトを許容できるそのハイスペックさに感動する。 隣人を愛する。それが人類の、本当の命題なのだと改めて考えさせられた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
SFです。アンドロイドのアイビスが「僕」に語った7つの物語を、インターミッション(幕間)で繋いだ構成です。 特撮ヒーローものやゲームのキャラクターといったサブカルチャーに、正直なところ最初は抵抗を感じました。しかし読み進めるにつれ、この小説が見かけによらずとても奥の深いものであるということに気づきます。一つ一つの物語も興味深いですが、それらを語りつくした後に明らかにされる世界観が圧倒的です(8+9i)。 優れたフィクションというのは数学の証明問題と同じようなものだと思いました。「仮定」から飛躍のない一貫性のある流れで導かれた「結論」には、それがどれほど荒唐無稽なものでも読者は説得力を感じます。ユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学がともに数学として成り立つのと同じように、現実に即した世界を描いたフィクションであれ荒唐無稽なSFであれ、論理的な筋道がしっかりしていれば意味のある物語として成り立つでしょう。逆に論理的な詰めが甘いと、読者は「御都合主義」と感じてしまうでしょう。そしてこの「アイの物語」で作者は、論理的な「詰め」の部分で少しの妥協もしていません。作者はフィクションの力ということを信じ、考え抜き、磨き上げるようにしてこの物語を書いていると思います。 しかもこの小説には様々な問題提起が含まれています。心や肉体や生命とは何であるのか、現実と非現実の境はどこにあるのか、恐怖が人々の心に仮想敵を生み出し争いを引き起こしてしまうという事実、人間というものが不完全であり絶えず誤りを犯し続ける存在であるという事実…… 一九四〇年代から二〇四〇年代までのおよそ一〇〇年間が「ヒトが最も輝いていた時代」だったというのはあながち嘘ではない気がして怖い。であればあと二十年ちょっとで、我々が輝いていた一〇〇年は終わりを迎えます。人類はどこへ向かっているんだろう? そんなことも考えさせられる小説でした。
Posted by
面白かった。 ちょっとおとぎ話的過ぎるとこもあったし AIの思考とか、考え出すと⁇なこともあったけど。 AIがコミュニケートする言葉が統合失調症の人たちみたいだった。
Posted by
「詩羽のいる街」とはうってかわってSFものでしたが面白かった。緻密なストーリーという感じで読み進むほどに面白さが深まっていきます。この作家の作品はもうしばらく読み続けてみようと思います。楽しみだな。
Posted by
人工知能やロボットを題材にした短編を劇中劇的な手法でひねりを加えたSF小説。介護施設を舞台とした物語では、介護アンドロイドが介護士や老人との会話、更に読書などによって学習し、人間やアンドロイドの死生観を語り、自ら生きるモチベーションを見出す様が圧巻、とても感動的でした。
Posted by