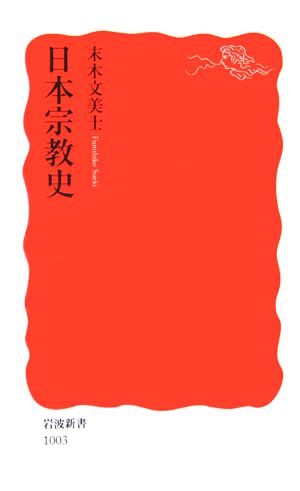日本宗教史 の商品レビュー
(2024/11/05 10h) 新書1 冊だけで古代から現代までにおける日本の宗教観を総覧している稀有な本。内容はまとまっていて、過去に学んだ日本史と結び付けつつ楽しく読んだ。 少ない紙幅ながら、情報はいくつも散りばめられているために、ここからいくらでも掘り下げられる。深掘...
(2024/11/05 10h) 新書1 冊だけで古代から現代までにおける日本の宗教観を総覧している稀有な本。内容はまとまっていて、過去に学んだ日本史と結び付けつつ楽しく読んだ。 少ない紙幅ながら、情報はいくつも散りばめられているために、ここからいくらでも掘り下げられる。深掘しては整理するため読み返すのに有用でありがたい本。 『どちりいなきりしたん』において、キリストの教えを広めるために、既に日本に馴染んだ仏教の用語や「天狗」のような語を用いている点はおかしみがあった。 神道の定着しない点については、葬式の定着度合いが分け目になったという指摘もある。いまでも葬式は仏教式が主流であり、納得できる。 国家神道として、各宗教観の揺らぎ・政教分離の如何について触れられており、避けられない靖国問題や創価の公明党についても言及。 現代においては新新宗教として、カルト宗教についてもサラリと記載がある。現代に生きる自分にはここをもっと知りたいと思うし、物足りないが、なにぶん1冊中の数ページなので仕方ない。ここから掘り下げて読んでいきたいと思う。
Posted by
日本の宗教史が詳しくかかれており、どのような形をえて、現在の日本のかたちなったのかが良くわかる本です。浅く広く宗教史を書いている感じで勉強になりました。
Posted by
著者、末木文美士さん、どのような方かというと、ウィキペディアには、次のように書かれています。 ---引用開始 末木 文美士(すえき ふみひこ、1949年9月6日 - )は、日本の仏教学者。国際日本文化研究センター名誉教授、総合研究大学院大学(総研大)名誉教授、東京大学名誉教授...
著者、末木文美士さん、どのような方かというと、ウィキペディアには、次のように書かれています。 ---引用開始 末木 文美士(すえき ふみひこ、1949年9月6日 - )は、日本の仏教学者。国際日本文化研究センター名誉教授、総合研究大学院大学(総研大)名誉教授、東京大学名誉教授。専攻は仏教学、日本仏教を中心とした日本思想史・宗教史。田村芳朗の弟子の一人。 ---引用終了 で、本作の内容は、次のとおり。 ---引用開始 『記・紀』にみる神々の記述には仏教が影を落とし、中世には神仏習合から独特な神話が生まれる。近世におけるキリスト教との出会い、国家と個の葛藤する近代を経て、現代新宗教の出現に至るまでを、精神の“古層”が形成され、「発見」されるダイナミックな過程としてとらえ、世俗倫理、権力との関係をも視野に入れた、大胆な通史の試み。 ---引用終了
Posted by
最初と最後が面白かった。丸山眞男の提唱した古層論にたいして、どのように捉えるべきなのか。古層とは、一環的なものじゃなくて、それ自体が歴史的に形成されてきたもの。 イザナミイザナギの時代の話から創価学会まで分かりやすく説明されてる。 鎌倉仏教とかキリシタンの話は眠かったけど、大学...
最初と最後が面白かった。丸山眞男の提唱した古層論にたいして、どのように捉えるべきなのか。古層とは、一環的なものじゃなくて、それ自体が歴史的に形成されてきたもの。 イザナミイザナギの時代の話から創価学会まで分かりやすく説明されてる。 鎌倉仏教とかキリシタンの話は眠かったけど、大学受験の内容を復習出来てなかなか面白かった。
Posted by
日本の宗教の発生より現在までを俯瞰して描く。 筆者の広範で詳細な知識にはただただ驚くばかりだが、宗教史どころか日本史の素養もない私から見ると、分からない表現や説明も多かった。 もう少し、ざっくりと各宗派の流れが分かればよかったのだが…。
Posted by
表層に現れず私たちに蓄積されているもの。これらを「古層」というキーワードに当てはめ、日本宗教史を解説。筆者の立場は、日本古来の「古層」は存在ぜず(解明されておらず)、歴史的に作られたものだとする。確かに、古事記や日本書紀が書かれたのは天武朝以降のことであり、それ以前の文字史料はな...
表層に現れず私たちに蓄積されているもの。これらを「古層」というキーワードに当てはめ、日本宗教史を解説。筆者の立場は、日本古来の「古層」は存在ぜず(解明されておらず)、歴史的に作られたものだとする。確かに、古事記や日本書紀が書かれたのは天武朝以降のことであり、それ以前の文字史料はないのだから、その通りだろう。 続いて中世以降の仏教と神道における複雑な関係性、近世以降におけるキリスト教の伝来の影響や仏、神、儒の関係など解説。近世後期には、国学において復古神道の流れから仏教以前の日本の「古層」を探る運動が大きく展開した。近代になり明治政府は国家神道の体制を整えるに至るが、江戸後期から展開したこの流れは仏教以前から存在した日本本来の「古層」ではなく、つくられた「古層」であることを指摘する。戦後は国家神道が解体されたが、それ以降大量に現れた新興宗教乱立の動きを筆者は「宗教のラッシュアワー」と呼んでいる。 上記のように日本宗教史のエッセンスを、「古層」というキーワードをとおして概観できる。日本人古来の「古層」はこの先解明されないのだろうか、と思う一方、この多様な変遷そのものが私たちの「古層」と呼べるものなのだろうか、と考える。安易な右派的言辞にも注意を要することに気付かされる。
Posted by
神道だけでなくその他の日本で信仰されたり影響を与えた宗教の歴史をざっとさらっており、しかし新書の丁度読みやすい分量であった。末尾の現代宗教の言及から、日本人が宗教に耽溺していることを危険とし、少なくとも良くは思わないという風潮から現代日本人は曖昧な信仰心を抱き、それが俗に言う日本...
神道だけでなくその他の日本で信仰されたり影響を与えた宗教の歴史をざっとさらっており、しかし新書の丁度読みやすい分量であった。末尾の現代宗教の言及から、日本人が宗教に耽溺していることを危険とし、少なくとも良くは思わないという風潮から現代日本人は曖昧な信仰心を抱き、それが俗に言う日本人の無宗教的思想の根幹にあるのではないかと考えた。今回の読書で自身の日本史基礎的知識の欠乏が顕著となったため、次は日本史の基礎的知識を仕入れたい。
Posted by
丸山真男が言う歴史を貫く唯一の古層などない。層の重なりがあり埋もれている古層を宗教史を通じ検討する。 近代における過去の発見は近代に都合の良い古層を作り出す作業であった。古代最大の文献は記紀である。記紀神話は仏教と無関係ではなく影響がある。 神仏習合は最も深い古層である。集合には...
丸山真男が言う歴史を貫く唯一の古層などない。層の重なりがあり埋もれている古層を宗教史を通じ検討する。 近代における過去の発見は近代に都合の良い古層を作り出す作業であった。古代最大の文献は記紀である。記紀神話は仏教と無関係ではなく影響がある。 神仏習合は最も深い古層である。集合にはいくつかの形態があるが、何も仏教側が土着的信仰を吸収する形である。 日本仏教思想の基礎は平安初期に最澄空海により確立された。9世紀後半から律令制が崩壊し荘園制へ移行した。宗教もまた国家的祭祀から私的祭祀へと性格を変えた。 死に関する儀式は仏教、現世利益は仏教・神祇信仰・陰陽道があわせ用いられた。 信仰を強めるため末法思想が広められた。鎌倉仏教は日本仏教の最盛期と見られている。煩雑な儀礼的要素を排し平等な救済を説いた。ありのままの現状を肯定する本覚思想が現れ、最も日本化した仏教思想と言われる。 本地垂迹とは遠くの仏より近い神の方が貴いとする説であり、山王信仰がある。 中世は偽書も多いが、合理主義の奥の古層レベルにおいて偽書も生きることがある。 近世では朱子学が正統とされたが、仏教神道思想が衰えたわけではなく、百家争鳴の状況だった。
Posted by
日本の宗教史をざっとさらった一冊。長すぎず短すぎず、古代から現代までにおける宗教の数々を拾ってかいつまんで説明しているので、概論を押さえるのには良書だと思う。 筆者は丸山眞男の「古層」という考え方を元に日本の宗教史を展開していっており、その古層は時代を上るとともに「発見」され、「...
日本の宗教史をざっとさらった一冊。長すぎず短すぎず、古代から現代までにおける宗教の数々を拾ってかいつまんで説明しているので、概論を押さえるのには良書だと思う。 筆者は丸山眞男の「古層」という考え方を元に日本の宗教史を展開していっており、その古層は時代を上るとともに「発見」され、「創出」されていくことを説明している。これらは特に江戸時代や明治時代において顕著であり、日本の原始から存在する思想はなにか、日本的ルーツはどこにあるか、というのは昔からの大きなテーマだったことがよくわかる。 宗教とは関係なくなってしまうけれど、個人的には筆者が聖徳太子を『源氏物語』の光源氏と結び付けたところに面白味を感じた。ともに天皇の子というやんごとなき血筋を受け継ぎながらも、自らは天皇とならずに自由に動ける身を謳歌し続けた。二人のカリスマ性は、確かにそういう特徴からきている部分もあるのだろうな、と思った。
Posted by
古代から現代にいたるまでの日本における宗教の歴史をたどりつつ、著者自身の関心にもとづく考察をおこなっている本です。 著者は、丸山眞男の「古層」の概念に触れて、「古層」は歴史を通して一貫したものとして存在しているのではなく、むしろ歴史のなかでつくられてきたものと考えるべきなのでは...
古代から現代にいたるまでの日本における宗教の歴史をたどりつつ、著者自身の関心にもとづく考察をおこなっている本です。 著者は、丸山眞男の「古層」の概念に触れて、「古層」は歴史を通して一貫したものとして存在しているのではなく、むしろ歴史のなかでつくられてきたものと考えるべきなのではないかと主張します。本書はこうした考えにもとづいて、日本の宗教のありかたが、歴史のなかでどのようにかたちづくられてきたのかを論じています。 そのさい著者は、仏教、キリスト教、神道がたがいにどのような影響をあたえあってきたのかということに、とくに注意をはらっています。中世における神仏習合の実態や、近代以降の神道とナショナリズムのむすびつきなどの事実を紹介しながら、現代におけるこの国の宗教のありかたを可能にしたものがいったいなんであったのかという問題へと、読者の思索をみちびいています。 また最終章では、著者自身がこれまでにも論じてきた、死者とのかかわりにおいて宗教のありかたをあらためて考えなおす必要があるという議論も提出されています。
Posted by