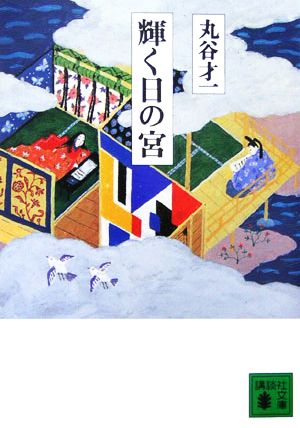輝く日の宮 の商品レビュー
国文学者の女性が源氏物語の失われた一巻を探っていく。 作中人物に、漢詩の発音は適当でよいと言わせながら、本作は(も?)旧仮名遣い。 いろいろ趣味的だが、通俗的な面白さもある小説と思う。 中村(萬屋)錦之助が好きな外人が出てきて嬉しかった。
Posted by
見事と言う他無い。 著者らしいユニークな表現法やインテリが結晶した集大成。 古典文学や『源氏物語』に興味関心が無ければ、「ふぅん」で終わる内容が大半を占めるが、物語的工夫が半端ないので読ませられてしまう。 古典アレルギーの方でなければ一読の価値あり。
Posted by
源氏物語には 「桐壺」と「帚木」の間に“輝く日の宮”と題された巻があったのでは、とされる説があります。その根拠は、幾つかあり、本書でも触れられています。 この小説は、エピローグ“0“ で主人公の国文学者・安佐子の高校生時代のスリリングな小説から始まります。そして、この小説が作中...
源氏物語には 「桐壺」と「帚木」の間に“輝く日の宮”と題された巻があったのでは、とされる説があります。その根拠は、幾つかあり、本書でも触れられています。 この小説は、エピローグ“0“ で主人公の国文学者・安佐子の高校生時代のスリリングな小説から始まります。そして、この小説が作中、所々でエッジを効かせます。 実は、私は本書は、「源氏物語第1.5帖 輝く日の宮」なる創作物語としての小説のみを読むつもりでいたのです。全く思い込んでいて。 各章で、多種な場面設定が用意されて、多様な知識人が登場します。芭蕉、武藏、鏡花等々、彼らを媒体として多彩な文学評論がなされていきます。これが、ストーリーを伴って無理がない。 作品半ば4項あたりから源氏物語の核心に近づいていきます。安佐子が、悩みながら研鑽を重ね「輝く日の宮」の執筆となります。豊富な資料、幅広い知識、深い考察に圧倒されます。特に、紫式部と藤原道長との関係性からの、「輝く日の宮」廃棄説は、それなら許せるかしらと思わせるものでした。 そして、それだけでなく、安佐子と独身主義者の彼(武藏好きでなかなかのエリート)との大人の恋の行方がこの小説を馴染みやすくさせ、いろごのみ感を楽しめます。 なかなか一読では読み切れません。もう少し源氏物語を読んでから再読しようと思います。
Posted by
読書の愉悦とはこのことですね。「源氏物語」に関する造詣は「光の源氏の物語」で存じていますが、本作では、その成立論を中心に、紫式部と藤原道長の関係性を現代の安佐子と長良に重ねる重層性をみせたり、「源氏物語」の語りの多重性を章立てごとに表現形式を変えて見せることで表したりと、碩学が大...
読書の愉悦とはこのことですね。「源氏物語」に関する造詣は「光の源氏の物語」で存じていますが、本作では、その成立論を中心に、紫式部と藤原道長の関係性を現代の安佐子と長良に重ねる重層性をみせたり、「源氏物語」の語りの多重性を章立てごとに表現形式を変えて見せることで表したりと、碩学が大空を自在に遊ぶ境地を見せつけられます。巻末の鹿島茂さんの解説が、本作を読み解いた興奮が隠しきれないような書き振りで微笑ましい。執筆時の丸谷才一さんは御歳77歳でしょうか。羨ましいばかりの歳の重ね方です。
Posted by
丸谷才一 「 輝く日の宮 」 源氏物語の謎解きと共に、源氏物語という時代小説に隠された 人間の意図を 小説の随所に組み込んだ内容 源氏物語論だけでなく 文学論まで飛躍していると思う。文学=国家からの自立であり、風雅 著者の源氏物語論 *紫式部の生活と夢としての源氏物語〜源氏=...
丸谷才一 「 輝く日の宮 」 源氏物語の謎解きと共に、源氏物語という時代小説に隠された 人間の意図を 小説の随所に組み込んだ内容 源氏物語論だけでなく 文学論まで飛躍していると思う。文学=国家からの自立であり、風雅 著者の源氏物語論 *紫式部の生活と夢としての源氏物語〜源氏=藤原道長→女達=紫式部。安佐子と長良 *アジール論としての源氏物語=逃亡者を保護する領域(社会逃亡者を保護する社寺) *反体制としての源氏物語〜国家=天皇、藤原氏。反国家=左翼、共産 *風雅や御霊信仰と結びつく源氏物語=松尾芭蕉 紫式部の生活と夢としての源氏物語 *源氏=藤原道長→女達=紫式部 *紫式部と藤原道長との関係性=雇用主、娼婦、読者、批評家、紙の提供者 安佐子=紫式部 という構造 *小説の中の小説(序章)は 安佐子の生活と夢の物語→源氏物語は 紫式部の生活と夢の物語 *国史学者(皇国派)の父と 国文学者の娘の関係性=安佐子と紫式部の共通性 輝く日の宮 の内容 *朝顔の姫君 *六条御息所と源氏の始まり *藤壺と源氏の最初の関係 道長が 源氏物語から 輝く日の宮を省いた意図 *深手をかすり傷程度に見せるため *余白により 味を濃くして 趣を深めるため 歴史(日本書記)と小説(源氏物語)の違い *日本書記=藤原氏の支配下で語られる *源氏物語=藤原氏の支配下になく、人間の愚かな面白いエネルギー *文学=純粋、自立、隔絶 *歴史を読むとニヒリストになる〜人間は愚かなもの 芭蕉論 *文学というより風雅〜風雅=いろいろな価値と結びつく→遊戯性、嗜み(倫理性と美的が一緒になった) *奥の細道の主題は 時間→「月日は百代の過客なり」という時間論に始まる *芭蕉はなぜ東北へ行ったのか(奥の細道)→義経を弔う旅
Posted by
なにぶん勉強と知識が足りないので、わからないことばかりだったけど、それでも学会やシンポジウムでの学者のやりとりにはわくわく。
Posted by
丸谷さんらしいというか。。。 ストーリーは自立した女性の恋愛物語で「たった一人の反乱」あたりに似た雰囲気があります。一方でもう一つの主題が国文学で、こちらがちょっと難題。 「芭蕉はなぜ東北に行ったのか」「輝く日の宮」について、延々と説が述べられます。それはそれで面白いのですが...
丸谷さんらしいというか。。。 ストーリーは自立した女性の恋愛物語で「たった一人の反乱」あたりに似た雰囲気があります。一方でもう一つの主題が国文学で、こちらがちょっと難題。 「芭蕉はなぜ東北に行ったのか」「輝く日の宮」について、延々と説が述べられます。それはそれで面白いのですが、特に後半は「輝く日の宮」についてのミステリーになっている感もありまして、源氏物語を知らない(あるいは興味の無い)私には、ちとしつこ過ぎるかと。 とは言え、如何にも丸谷さんらしい、知的遊戯に溢れた作品でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2006年(底本2003年)刊行。 読み進めながら、正直、本書はいったい何を描こうとしているのか全くつかめなかった(そのため読破にかなり時間がかかった)。 が、鹿島茂の解説を読んで、登場人物に藤原道長、式部の関係性を仮託しつつ、存在の確証のない源氏物語2章「輝く日の宮」の内容や成立過程、削除過程に関する論争と仮説を提示するものとのこと。また、学者界隈の模様や、出版・雑誌業界の裏ネタ、醜い実相を散りばめており、もう少し多様な要素があるようだが。 かかる実験的作品は大切とも思う。しかし、正直、恋愛パートはあまり面白くなく、要らないと感じる。 「輝く日の宮」存否や、その内容に関する謎解きをしていく中で、それと余り関係のないメタ小説的な描写が果たして有効なのだろうか。 謎解き重視のミステリー小説で、関係のない描写(特に、謎解きのための伏線でない場合)を延々とされた場合に感じるイライラ感。これに似た読後感があったことは否定できない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これはすごい本でした。 一読巻を措く能わずの面白さでしたが、いかんせん細切れ読書です。 巻を措いていた間は、頭の中フル回転で、反芻していました。 タイトルから『源氏物語』の話であることはわかりますが、読んでみたらこれが、『奥の細道』あり、泉鏡花あり、御霊伝説あり、19世紀日本文学ありの、文学的、民俗学的指摘や批評がてんこ盛り。 主人公の女性が国文学の学者で、その父親が民俗学の学者なものだから、自然な形でこれでもかと多種多彩な学術的な話題が提供されるのだけれど、それがいちいち興味深くて面白い。 そして、私ならどう解釈しようかなどと、同じ土俵の片隅でちんまり考えてみるのがことのほか楽しい。 昔から『源氏物語』には欠けた巻があるのではないかと言われていたそうで、現存する54ではなく、全60帖と記されている文献もあるとか。 その中で、「輝く日の宮」という章が、あるのかないのか。 あったのならば、なぜ今はないのか。 主人公はあるという立場で考えていますが、ないと考える根拠も書かれていますので、自分なりに仮説を立てながら読むこともできます。 ところがこの小説、リドル・ストーリーなんですね。 結末は読者に任せるということで、いろんなことをはっきりさせないで終わる。 結局それはあるのかないのか。 または、主人公は結婚するのかしないのか。 これは、現在出版されている小説の多くが、実にわかりやすく懇切丁寧に書かれ過ぎていることに対する、丸谷才一の異議申し立てなのではないかと思いました。 行間を読む。プロットを読む。文章に書かれていないことを読み解く。 そういう読書がもっとなされていいのではないかと。 消化のいいお粥のような本ばかりではなく、歯ごたえのある強飯も食べてみてはいかがかと。 文体も、小説風あり、戯曲風あり、年鑑風ありといろいろ。 そのなかで、安佐子と紫式部、長良と道長が二重写しのように重なり合い、導かれて、読み手も成長をしていく。 0章が、安佐子が15歳の時に書いた小説で、これが結構長いこと本筋に関わってくる。 けれどその意味が解らないまま最後まで読んで、鹿島茂の解説を読んで「あ」と気づく。 道長が言わんとしたこと、けれどはっきりと最後まで言わなかったこととは、これだったのか。 自力で読み解けるほど、私もまだまだ力が足りません。 そもそも「源氏物語」も橋本治の訳で読んだくらい。 あとは大和和紀の漫画「あさきゆめみし」と、小泉吉宏の「大掴源氏物語 まろ、ん?」で補強。 まろ、ん?―大掴源氏物語/幻冬舎 ¥1,404 Amazon.co.jp これ、いいですよ。 一帖が8コマで、全54帖を網羅しています。 光源氏の顔は栗、頭の中将の顔は空豆になっていますから、後々人間関係がややこしくなっても、どちらの系統の人間かすぐ分かる。(栗顔と豆顔) 数ページごとに、家系図や相関図、地図や暦などちょっとした豆知識が書いてあるので、大変ためになる一冊です。 これからもう一度読み直そうっと。 さて、直接この本の主題とは関係ありませんが(いや、あるのかもしれませんが)、主人公の父親の台詞に引っ掛かりました。 「歴史といふ物はどうも詰まらないな。結局かうなるに決まつてたといふ所からものを見るから、人間の持つてる、馬鹿ばかしい、おもしろいエネルギーをつかまへられない」 僭越ながら反論を。 結果が決まっているからこそ、なぜ、どうしてそうしなければならなかったのかを考えるのが面白い。 倒叙物のミステリだってそうでしょ? 矛盾がないか確認しながら、あーでもないこーでもないと考えるのが楽しいんざます。素人的には。 そう言った意味で、『源氏物語』という結果を前にしながら、あーでもないこーでもないと考えるこの小説は、大変面白うございました。 大満足。
Posted by
知的かつ軽い風俗小説、豊かな内面の表面がありつつも、一人に偏らず軽く突き放したところがあって、もちろん読み易い シンプルに言って最高だった。源氏物語関連はあまり知らなかったけれど、分かっていればもっと良かったのだろう。 やや色っぽい会話の機知だとか、フェミニズムに関するちょっとし...
知的かつ軽い風俗小説、豊かな内面の表面がありつつも、一人に偏らず軽く突き放したところがあって、もちろん読み易い シンプルに言って最高だった。源氏物語関連はあまり知らなかったけれど、分かっていればもっと良かったのだろう。 やや色っぽい会話の機知だとか、フェミニズムに関するちょっとした偏見(への批評的な語り)が面白かった。
Posted by