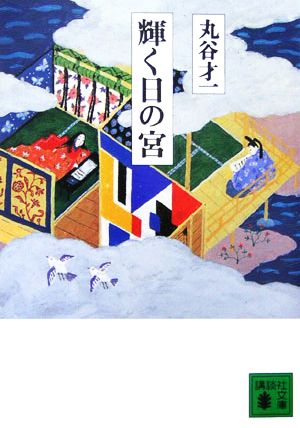輝く日の宮 の商品レビュー
学者という立場を借りて、「奥の細道」「源氏物語」の解釈を展開していく。その手法は学術誌の原稿だったり、シンポジウムだったり、小説であったり。 小説内に幾つもの入れ子があり、その一つ一つに驚かされた。 0章 最初なぜ0から始まるのか? その引っ掛かりが「源氏物語」で存在の有無...
学者という立場を借りて、「奥の細道」「源氏物語」の解釈を展開していく。その手法は学術誌の原稿だったり、シンポジウムだったり、小説であったり。 小説内に幾つもの入れ子があり、その一つ一つに驚かされた。 0章 最初なぜ0から始まるのか? その引っ掛かりが「源氏物語」で存在の有無が不明な「輝く宮の巻」にかけている等、凝りに凝った小説に思う。 少々薄っぺらな話の0章 。「源氏物語」の書き出しも、そうだったのだろうか、とも解釈できる。 学識の深さと美しい日本語にほれぼれする作品でした。
Posted by
なんという 小説なのだろうか。 松尾芭蕉の奥の細道 そして源氏物語を ひもといていく。 その徹底した構成力と 文体の変化に 作者自身の 智力 と 洞察力。 人間模様の 変化 など。 円熟した ふでさばき の職人ワザ。 恐ろしいほどに 切り込んでいく。 まったく、スゴイ人が い...
なんという 小説なのだろうか。 松尾芭蕉の奥の細道 そして源氏物語を ひもといていく。 その徹底した構成力と 文体の変化に 作者自身の 智力 と 洞察力。 人間模様の 変化 など。 円熟した ふでさばき の職人ワザ。 恐ろしいほどに 切り込んでいく。 まったく、スゴイ人が いるんですね。 そのことだけで、ため息が でるほどの スリリングな 読後感。 源氏物語を 挫折した ニンゲンが、 再度 読んでみたいと思わせるほどに。 道長 という権力の保護のもとに 紫式部の 才能が さらに磨かれ 熟練していく。
Posted by
源氏物語の幻の章、輝く日の宮はあったのか、をめぐるミステリー仕立ての主題に、主人公の恋愛や様々な文学論をちりばめた、贅沢な作品。章毎に文章のスタイルも変わり、最初はそれが分からなくて戸惑ったが、途中からは一気に読めた。筋の面白さは一級で、特に源氏物語をかじった人ならきっと興味を引...
源氏物語の幻の章、輝く日の宮はあったのか、をめぐるミステリー仕立ての主題に、主人公の恋愛や様々な文学論をちりばめた、贅沢な作品。章毎に文章のスタイルも変わり、最初はそれが分からなくて戸惑ったが、途中からは一気に読めた。筋の面白さは一級で、特に源氏物語をかじった人ならきっと興味を引かれる内容。いろんな伏線が張り巡らされていて、再読して初めて気付くことも多々ありそうな作品。 (2015.4)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 女性国文学者・杉安佐子は『源氏物語』には「輝く日の宮」という巻があったと考えていた。 水を扱う会社に勤める長良との恋に悩みながら、安佐子は幻の一帖の謎を追い、研究者としても成長していく。 文芸批評や翻訳など丸谷文学のエッセンスが注ぎ込まれ、章ごとに変わる文章のスタイルでも話題を呼んだ、傑作長編小説。 朝日賞・泉鏡花賞受賞作。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
とても面白かったです。特に「源氏物語」ファンにはタマラナイでしょう。僕はそうじゃないんですけど、舌を巻きました。 やっぱり丸谷才一さんは、凄いなあ、と。なんていうか、好きか嫌いか、という趣味の問題はもちろんあります。 なんていうか、ソコと別次元で、「知っている」「考えている」「...
とても面白かったです。特に「源氏物語」ファンにはタマラナイでしょう。僕はそうじゃないんですけど、舌を巻きました。 やっぱり丸谷才一さんは、凄いなあ、と。なんていうか、好きか嫌いか、という趣味の問題はもちろんあります。 なんていうか、ソコと別次元で、「知っている」「考えている」「自分の趣味を貫く」「肩の力が抜けている」「小説である、ということに意識的である」「モラルがあるが、押し付けない」とでも言いましょうか。 2003年発表の小説だそうです。舞台は、まあだいたい1980年代~1990年代です。 主人公は、杉安佐子、という名前の、日本文学者。つまり大学の教員さんです。30代~40代くらいの感じです。 若い頃に同じく大学の学者さんと恋愛結婚したけど、子供が出来る前に離婚したようです。バツイチ独身さん。 専攻は18~19世紀日本文学。つまり江戸時代から明治時代ですね。 「事件として起こること」で、言いますと。 ●「奥の細道」の解釈を巡って、大家の先生と摩擦を起こしてしまう。その発表を巡って知り合った学者の男性とのロマンス。 ●「源氏物語」の解釈、特に存在したかしていないかが議論になる幻の章「輝く日の宮」について、同じく女性の源氏研究家と大激論対立してしまう。 ●ミネラルウォーターを売る会社の重役の年上独身主義の男性とのロマンス、結婚するかしないかのお話。 以上、です。 杉安佐子さんの人生とロマンスを追っていきたい、という読み方をしていると、とても焦らされます。 彼女の研究内容と思索の内容に、大幅に脱線していくからです。 そうなんだけど、それが実は脱線じゃなくてなんとなく関連がある。 そして、焦らされるけど、ちゃんと満足させてくれる。 そして、脱線かと思われた内容が、実はこの本のいちばんの狙いなんだなあ、と。 それは全て、純粋にある科学実証的な事柄ではなくて、それが芭蕉であれ紫式部であれ、ある心情というか、ブンガクと人生というか。 そういう内容に収斂していきます。まあとくに源氏物語なんですが。 結局それが、人生と恋愛というか、人生の皮肉というか、老いだったり、エロスだったり、孤独だったり、社会との関係だったり、すれ違いだったり。 そういうある風景に見えてきます。 そしてそれを、書き言葉、日本語で表すということの面白み、つまり小説という愉しみというか、その快楽の不思議さというか、その愉しみ自体を眺める興味深さというか。 そういうところにじんわりと沈殿していくような。大人な愉しみに満ちています。 ちなみに、章ごとに文体が変わります。一人称だったり、三人称だったり、作者が語り込む形式だったり、戯曲になったり。 遊び心に満ちていますが、それが後段は源氏物語という巨大な謎と格闘する主人公の思索に生きてくるような感じです。印象ですが。 主人公は、父親も学者さんで、何だか資産家です。全然生活苦はありません。イイ御身分です。 そういう意味では呑気な話です。 だからそういうところでつまずいちゃう読み手だったら、どっちらけだと思います。僕も、ある年代まではそうだったかもしれません。 でも、そういう次元を超えたところで、人間ドラマというか、大変に豊穣です。 と、ここまで書いて思いましたが、要するにここ20年くらいのウディ・アレン映画の味わいですね。 僕にとっては無上の楽しみです。 文庫版で読んだのですが、鹿島茂さんが解説を書いています。 それを読むと、「ああ、俺はまだ、この小説の持っている滋味というか、愉しみを満喫できていないなあ。また10年後、20年後に読んでみたいなあ」と思いました。 でも、それは読みながら実は半ば判っていたことだったりします。 また、作者の丸谷さんも、そういう風に受け取られることは百も承知で書いています。きっと。 それでも十分面白い。また読みたくなって、この小説の中で言及されている本をまた読みたくなります。 謎が残ります。判然としません。すっきりしません。でもイイんです。だから面白いんだなあ、と思います。 判らないところ、もやもやするところが快感です。 そういう意味では僕は、村上春樹さんの小説にも似ているなあ、と思います。 レイモンド・チャンドラーさんもそんな気がします。 そして、コレは小説でしかありえない表現だなあ、と嬉しく思います。 そんな小説でした。 昔々、谷崎潤一郎版で「源氏物語」を読んだんですが、内容の99%は失念しています。 またいつか、何かの翻訳版で良いから、読んでみたいなあ、と思いました。 なんていうか、「ああ、このままずっと読んでいたいなあ」という文章ですね。 日本という国が、風土が、文化が、素敵だとかそうじゃないだとか、そういう議論をするならば、こういう本を踏まえてしたいなあ、と思いました。
Posted by
丸谷才一さんの長編小説『輝く日の宮』を読了。これは多分もう一度読んだ方がよりこの作品の深い部分ができるであろう作品。今まで再読した小説はあまりないが、これはいつか読んでみてもよいかなと思わせる作品だった。女性国文学者の恋愛をベースにした話なのだが、恋愛にまつわる話を一応時間進行の...
丸谷才一さんの長編小説『輝く日の宮』を読了。これは多分もう一度読んだ方がよりこの作品の深い部分ができるであろう作品。今まで再読した小説はあまりないが、これはいつか読んでみてもよいかなと思わせる作品だった。女性国文学者の恋愛をベースにした話なのだが、恋愛にまつわる話を一応時間進行の為の素材に使いながら実は源氏物語の中であったといわれる幻の1帖の謎に関しての考察が見事に展開されていて、丸谷才一さんの文芸批評の才能が光っている。不思議な作品だが楽しめた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読み終わったとたんああ、とため息をついて目を上げたくなる、そんな本だった。先へ先へと読まされてしまった感じ。 安佐子は紫式部そのものなのだなあと。男性視点からの理想化もだいぶまじっている気がするけれど。最後に佐久良と話していてとつぜん千年前の情景が「おりてきた」シーンは美しくて恍惚とする。 安佐子という一人の女性の現実的な苦悩も織り交ぜながらも、めまぐるしく移り変わる場面の一つ一つが黄金色に霞む王朝文化の情景と重なり合って、雅やかな「物語めいた物語」がそこにある、というふうに感じました。
Posted by
職人的な手つきで綴られる現代絵巻物。 百年の孤独と同じ構造物を裏口から入ったかのようである。 色調は淡く、少し面白みに欠けるというか、 それこそ「幽玄」なのであろうが、 もっと堂々とやってくれてよい。 後半部分、何か丸谷君のエクスキューズが隠れてるようでそれが残念。 もっとも...
職人的な手つきで綴られる現代絵巻物。 百年の孤独と同じ構造物を裏口から入ったかのようである。 色調は淡く、少し面白みに欠けるというか、 それこそ「幽玄」なのであろうが、 もっと堂々とやってくれてよい。 後半部分、何か丸谷君のエクスキューズが隠れてるようでそれが残念。 もっとも非常に味わい深いだけでなく、 読者としては楽しく遊ばされましたけどね。 2013年5月ののほんよめとーく対象本。 来週くらいするのでUstream見てね。
Posted by
丸谷才一追悼が続きます。 前に読んだ時の感想にも、こんな面白い本をどうもありがとうございます、と書いてあったけど、うんうん、ホントにそれが一番言いたいこと、ですね。 前の感想を読むと、私がこの本を読むのは4回目のようです。 その度に、たぶん、ゆっくり時間をかけて読めるようになっ...
丸谷才一追悼が続きます。 前に読んだ時の感想にも、こんな面白い本をどうもありがとうございます、と書いてあったけど、うんうん、ホントにそれが一番言いたいこと、ですね。 前の感想を読むと、私がこの本を読むのは4回目のようです。 その度に、たぶん、ゆっくり時間をかけて読めるようになっているのだと思うのだけど、(私は速読の悪癖があるので、筋が気になるといくらでも速くに読めてしまって・・。)今回も、これまで以上に、一行、一行、大事にしながら読み進められてそれが嬉しかった。・・・なんか変な感想だけど。汗 丸谷先生って、意地悪だなぁ、(*^_^*)と学者の世界のいかにもありそうな抗争!!を描いているのが痛面白くてたまらない。 新聞記事や学者のシンポジウムでの発言、論文の文章など、活字になっていたり、公の場でのことだったり、という設定の「源氏物語」に“欠損”に絡まるあれこれが、時にそんな馬鹿な!というくらいの滅茶苦茶な論旨で、うん、こんなことってあるのかもね、いくら偉い先生が言ってたからといって、あるいは権威ある新聞で活字になってたからといって、それがそのまま、正しいってわけじゃないんだ、なんて、改めて可笑しくもなったりして。(*^_^*) 「源氏物語」に、果たして“輝く日の宮”という巻は存在したのか。 う~~ん、どうかなぁ。 確かに急に朝顔の宮のエピソードが既出のこと、みたいな扱いで出てきた時にはあれれ??と思ったけど、それはそれで奥行があっていいんじゃないの?というか、そんな疑問を持つなんて考えもしてなかったから、だけど・・・。 源氏と藤壺中宮の「二回目」から語られたことには全く違和感がなかったしね。 でも、今回、大筋が先に書かれ、そのあと、サイドストーリーとしての幾多の女御たちの巻が差し込まれた、という説には、改めて、うん、それはそうなんだろうな、と。(*^_^*) 、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現代の学者・安佐子と彼女の恋人を縦糸に、紫式部と道長を横糸に、まさに「見てきたような」展開で、こんなに面白い本をどうもありがとうございます、と御礼を申し上げたいくらい。^^; たぶん、今回で三回目。 一回目は発行されてすぐ、凝った構成と、何より源氏物語の欠巻がある!という驚きで、随分先を急いで読んでしまったような。二回目はその後すぐに、だったはずで、もちろん面白かったと思うのですけど、今回、意識してゆっくり、じっくり読んでみたら、なんて面白い話なんだぁ~~~~!と。(#^.^#) (#^.^#) 国家権力の嫌いな丸谷先生らしく、のっけの昭和の暗い匂いのする、主人公の習作が最後まで尾を引いているところが、うん、なるほどね・・・。 そして、本題の、源氏物語への考察ですけど、現代の学者・安佐子と彼女の恋人を縦糸に、紫式部と道長を横糸に、まさに「見てきたような」展開で、こんなに面白い本をどうもありがとうございます、と御礼を申し上げたいくらい。^^; 戯曲仕立ての学者のシンポジウムも、その仄暗さが妙にリアルでよかったし、丸谷先生は大学に勤務されていたこともあったのだから、学者の世界の実態かなぁ、なんて思ったり。 「輝く日の宮」の巻が本当に途中から削除されてしまったのか、どうか、は議論の余地があると思うのですが、(私はそれで納得してたから、始めから書いてなかった、というのでもいいけどなぁ)小説の技法の考察としても楽しんで読めました。「日本最古の長編小説」に、ここまで現代のテクニックを当てはめて書いたのか、と思うと、当時の読者をも含めて、やるじゃん!なんて嬉しかったりもしますしね。 最後の最後まで新しい展開を見せてくれて、尻尾まで餡子の入った美味しい鯛焼きを食べたような気分です。(#^.^#)
Posted by
昨年他界した丸谷才一のベストセラー。立ち上がりに奇妙な感覚におそわれる。ちょっとした夢物語のような....。 残念ながら源氏物語を読んだ事がないので、小説にある中身をすべて理解できたわけでない。本書を本当の意味で理解するためには源氏物語や紫式部や、その時代の背景を知っておくと深く...
昨年他界した丸谷才一のベストセラー。立ち上がりに奇妙な感覚におそわれる。ちょっとした夢物語のような....。 残念ながら源氏物語を読んだ事がないので、小説にある中身をすべて理解できたわけでない。本書を本当の意味で理解するためには源氏物語や紫式部や、その時代の背景を知っておくと深く楽しめるだろう。 最後に出て来る表題にある「輝く日の宮」についてもまさにそのことが言える。そういう意味で準備不足な読書でした。 ただこれまで2冊の丸谷才一の著書を読んで、旧仮名遣いが普通に、普通の速度で読めるようになったのは大収穫です。
Posted by