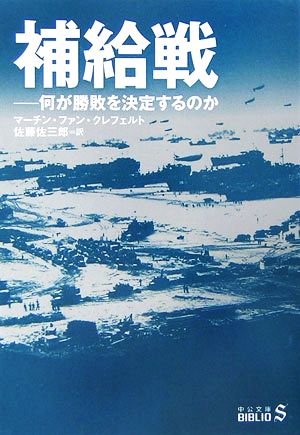補給戦 の商品レビュー
表題にあるように戦争の結果を決定づける兵站。 その兵站という観点で古くは16世紀の中世戦争から、ナポレオンの戦争、普仏戦争、そして第一次世界大戦、第二次世界大戦まで戦争の推移と共に解説している。 おそらく一般の読者を想定しているわけでなく、戦史研究の歴者学者か軍人を対象に書かれ...
表題にあるように戦争の結果を決定づける兵站。 その兵站という観点で古くは16世紀の中世戦争から、ナポレオンの戦争、普仏戦争、そして第一次世界大戦、第二次世界大戦まで戦争の推移と共に解説している。 おそらく一般の読者を想定しているわけでなく、戦史研究の歴者学者か軍人を対象に書かれているのだろう。 戦争の推移や背景は事前知識としては付いていけないうえ、細かい数字の羅列が続くうえに、著者の強い主張が所々入ってくるので、中々頭に入ってこない。 しかしながら兵站上の問題が如何に大きな問題を引き起こすかはよく分かった。 結局、兵站上で戦略に影響を及ぼすほど大きな被害を受けなかったのはWW2の連合軍ぐらいっだたようだ。 以下、知って意外だった事。 ・中世~近世の戦争では現地略奪が主だった。 ・軍が移動していれば補給の問題は起こりにくいが、包囲戦などで止まるとたちま干上がる。 ・第一次大戦以前の補給は食料と飼葉程度で弾薬や武器自体は携行で事足りた。 ・鉄道時代以前は常に輸送用馬の飼葉問題で兵站が破綻していた。 ・近代戦では攻撃部隊の速度に補給が付いていけず、また補給量が多いとたちまち渋滞し機能停止してしまう。 などなど。こう思うと戦う人のみならず現地人にとっても戦争に巻き込まれることは餓死と隣り合わせの地獄な事がわかり、やはり戦争は恐ろしい。
Posted by
三十年戦争から第二次大戦まで、18世紀以降の主要なヨーロッパでの戦争や、名将として評価されるヨーロッパの軍人らのいくさの仕方を、兵站や補給から再検証する一冊。教科書的に戦史を知ってるだけだったので、全てにおいてこれまでの理解を覆された。 古い時代の戦争の補給で重要だったのは食料や...
三十年戦争から第二次大戦まで、18世紀以降の主要なヨーロッパでの戦争や、名将として評価されるヨーロッパの軍人らのいくさの仕方を、兵站や補給から再検証する一冊。教科書的に戦史を知ってるだけだったので、全てにおいてこれまでの理解を覆された。 古い時代の戦争の補給で重要だったのは食料や馬の餌で、銃砲の弾は携行品で賄えたとか、鉄道は戦闘初期の兵力移動では役に立つものの、補給の面でみると十分に機能しないこともあったとか、なるほどという内容が多い。十分に理解できていないのでまた読み直したい。 基本的にヨーロッパが事例として出てくるので、三国時代の中国とか、日露戦争とか、太平洋戦争とか、東アジアの補給戦も気になってくる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分の中の兵站の概念が変わった一冊。 戦術、戦略には興味があり、兵站術は戦略の一部だと思って読み始めたが、読み進めるうちにその印象が変わってしまった。 巻末にある解説の、前半の概要が秀逸で、本書の内容を端的にまとめている。 本文は少し冗長な感じもするので、この解説の前半部分を読んで結論を理解した上で、その結論が導かれる過程を読む方がわかりやすいかもしれない(:論文と同じ読み方)。 本書は単純な兵站術の話では無く、補給がいかに大事かを理解できた。本書序盤の30年戦争の部分で、近世以前の現地での略奪による戦争が土地や住民を疲弊させることがよく分かった。「後詰めのない籠城戦は勝てない」と言われながら小田原城が落ちなかったことが腑に落ちないでいたが、相手方の補給を絶つと言う意味では、援軍が見込めなくとも籠城戦は大きな意味があったことがわかり、長年の疑問が解決した。 また、近世以前と現代では、軍隊が停止している場合と移動している場合で補給の受けやすさが真逆になっているのも面白い。
Posted by
兵站のお話。 軍事の天才的な将軍は小説だけの中の話というのが、良く分かった。でも、ナポレオンはやはり偉大ですね。
Posted by
三十年戦争以降,近代の大きな戦争において,兵站が果たした役割を定量的に分析した一冊.まず兵や馬に必要な糧食を賄うこと自体が一大事であって,現地徴発に頼っていた時代は意外と長く,第一次大戦でもなおその傾向があったというのが意外.その観点からしても軍はマグロのように動き続けて略奪する...
三十年戦争以降,近代の大きな戦争において,兵站が果たした役割を定量的に分析した一冊.まず兵や馬に必要な糧食を賄うこと自体が一大事であって,現地徴発に頼っていた時代は意外と長く,第一次大戦でもなおその傾向があったというのが意外.その観点からしても軍はマグロのように動き続けて略奪することでしか生きられなかったが,Louvoisが貯蔵庫を整備したことで,基地から支援を受けて行動する軍というモデルが作られた.以降のWWIまでは往々にして輸送に必要な車両数を確保できなかったり,確保したものの様々な不備で数の通りの力を発揮できなかったりといった問題が多くなった.Napoléonは,準備不足で臨んだAusterlitz会戦で,中世型の,空腹に任せて進撃する道を選んだことが結果的に功を奏した一方,綿密に計画を立てたロシア攻撃は失敗した.19世紀に鉄道という輸送機関が登場したが,敵国に攻め入る場合には敵国の鉄道をそのまま利用する上で課題も多く,道路優先になりがちな攻勢の中で鉄道防御が疎かになって鉄道が破壊されたり,貨車の徴発に依存したりといった問題がある.プロイセンは鉄道をよく利用したことで成功したという通説も,実際には普仏戦争でもフランス側のほうがよく鉄道が整備されていた.WWIIにおいても,輸送アセットの不足問題に悩まされたナチスのロシア攻撃は不調となり,ロンメルは補給線の長さを無視した攻勢で失敗をもたらした.一方,史上初めて・最大の規模と綿密さをもって行われた連合軍の反攻は,その綿密さ故に不調をきたした一方,現場の機転が功を奏した事例でもあり,これはNapoléonのAusterlitz会戦と似たところがある.今日は高度に情報化が進んでおり,戦場と中枢との間で絶えず連絡をとり,綿密かつ柔軟な計画を立てることが可能であることから,ここで書かれていることから進んだことが起きていると思う.「軍事とロジスティクス」をこの後読むので,それも含めていろいろと考えたい.
Posted by
ナポレオン戦争といい、シュリーフェンプランといい、ノルマンディ上陸作戦といい、目から鱗がボロボロと落ちるというか、ショックですよ!!今更かなあとか思ったけど、読んで良かったね。ホント
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2006年(底本1980年)刊。17C以降の、主に欧州内戦役での補給・兵站の技術的・軍略的変遷を解説し、戦争(特に戦術面)での補給の意義と、戦略・政略面への影響を検討する書。著者のモルトケ批判、クラウセヴィッツ批判が舌鋒鋭く、戦史分析に新たな光を当てた点は良だが、これほど多数の頁を費やしたにも拘らず、著者の出した結論は実に身も蓋もない。また、工兵能力(補給基地や飛行場の設営能力、鉄道敷設能力)には余り触れず。太平洋戦争における米軍のそれ(が、米軍の補給も限界近くだったらしいが)から見て、この欠落は痛い。 結局、補給についても相対的なもの(日米対比)、状況依存(交戦能力の高低、時期にも依存。戦場と本国や基地との遠近)なのかなぁ、とも。さらに、朝鮮戦争やベトナム戦争などに触れないのは問題のようにも(後者は刊行時期からして無理かもしれないが)。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
過去の戦争における兵站について書かれた書籍。戦争に関する多くの書籍ではその戦闘戦略に重点をおいて書かれますが、この本ではあえて兵站という側面から有名な戦争のいくつかを取り上げています。「昔はほとんどの食料が現地調達だったために、自ら攻める方向を決められなかった。停止していると大軍の補給が滞るから常に移動しなければならなかった。」などはこの本から初めて知りました。組織構築に応用できるといいな。
Posted by
補給戦というと「失敗の本質」に取り上げられたインパール作戦が思い出される。連合軍の補給基地を攻略するというあまりにひどい作戦だが、この本を読んだ後ではまともに補給を計画してたとしても実行はほぼ無理だったのだと思える。ヨーロッパ戦線ですら補給が戦略を制限していたのだ。 この本で取...
補給戦というと「失敗の本質」に取り上げられたインパール作戦が思い出される。連合軍の補給基地を攻略するというあまりにひどい作戦だが、この本を読んだ後ではまともに補給を計画してたとしても実行はほぼ無理だったのだと思える。ヨーロッパ戦線ですら補給が戦略を制限していたのだ。 この本で取り上げたのは17世紀の戦争に始まり、軍事の天才ナポレオン、鉄道を補給に使ったプロイセンのモルトケ、第一次大戦下のドイツ、トラック輸送を使ったナチス・ドイツ、砂漠の狐ロンメル、そしてノルマンディ上陸以降の連合軍だ。 ナポレオンの兵站制度に間しては「戦争論」のクラウゼヴィッツが誤解の根源だと言う。1805年の三帝会戦ではナポレオンの兵站の計画は充分なものだった。しかしナポレオンが主力の11万6千の兵のために25日以内に75万人分のビスケット・レーションを準備しろという要求は一ヶ月後にも半分しか準備できず、さらに30万食が後方で準備されたが作戦開始時には届かなかった。輸送隊の準備も全く間に合わず現実的には「大陸軍」の進路を分け現地で食料を徴発し、支払いはともかくそれは充分巧く機能した。弾薬の補給についても当時は使用量が極めて少ないためまったく問題なくナポレオンの意図して形ではなかったが組織は機能し補給は上手くいった様だ。一方で1812年のモスクワ敗戦は兵站の不足と冬将軍に負けたということになっている。ではナポレオンが兵站を軽視していたかというとそうではなく24日分の食料を準備し、戦争開始が6/24になったのも兵站上の理由だ。ナポレオン軍の最悪の不足状態は進撃最初の2週間におこり徐々に改善された。規律の守られた軍においては現に現地調達は巧く機能しナポレオン軍は住民に歓迎されたしモスクワに近づくほど土地は豊かになっている。ナポレオンは完全な兵站はできないことをわかっており、補給が完全に破綻する前にモスクワを攻略するという計画を立てた。それは必ずしも分の悪い賭けではなかったが。 普仏戦争のモルトケは補給に鉄道を活用したと評価されている。これは一部正しく、大部分では謝っている様だ。たしかに国内の最前線へ兵を集結させるには鉄道は圧倒的な威力を発揮したのだが最前線では結局馬車が輸送の中心だった。しかもこれは第一次大戦まで変わらない。馬車の何が問題化というと大量に必要な飼い葉だ。しかも一般の軍隊と輜重隊が一緒に移動すると輜重隊は後回しにされたりする。結局人間の食料を送ることさえ難しい軍隊では飼い葉はとても手に負えず、現地調達に頼ることになっていた。現地調達の場合移動していれば何とかなるのだが一旦同じ場所に留まり続けると食い尽くしてしまう。籠城といえば日本では鳥取の飢え殺しなど包囲された方が飢えるイメージだが、適地での包囲戦では調達が出来なければ包囲側も大変だったのだ。これは同じ道を大群が通る場合にも似た様なことが起こるので、大軍団は分散して進軍せざるを得ない。鉄道による後方からの補給に関しても駅での荷下ろし能力が不足すると汽車は倉庫になってしまい、先が詰まると結局輸送も思う様にならない。船の輸送の場合も港での荷下ろしがネックになっている。結局戦車軍団や騎馬軍団がいたとしても軍団全体としては輜重隊の行動能力、せいぜい1日15マイル程度に制限される。補給部隊の規模が大きくなればなるほどこの距離を達成するのは難しくなっていった。 トラックの時代になってもすぐに兵站が改善されたわけではなく、道が悪かったりするとタイヤの補給が問題になったりする。砂漠の狐ロンメルはもし補給が充分にあればイギリス軍をエジプトからたたき出すことが出来たというがこれはかなり怪しい。まず補給港トリポリの港湾能力が小さく、次にトリポリから前線までの距離は非常に離れている。地中海で輸送船が沈められたことよりもアフリカでの輸送そのものが当時の能力を超えるものだった様だ。ビルマの山奥のインパール作戦はどうやっても上手くいかない計画だったのだろう。唯一の可能性は地元民を味方につけて現地調達することしかなかった様に思える。 面白い研究なのだが原文のせいか翻訳のせいか少し読みにくい。それにしても飼い葉が戦略を規定してしまっていたとは知らなければなかなか想像できない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] ナポレオン戦争から第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦に至るまでの代表的な戦闘を「補給」という観点から徹底的に分析。 補給の計画、実施、戦闘への影響を、弾薬、食糧等の具体的な数値と計算に基づいて説明し、補給こそが戦いの勝敗を決するということを初めて明快に論じた名著。 待望の復刊。 [ 目次 ] 序章 戦史家の怠慢 第1章 一六~一七世紀の略奪戦争 第2章 軍事の天才ナポレオンと補給 第3章 鉄道全盛時代のモルトケ戦略 第4章 壮大な計画と貧弱な輸送と 第5章 自動車時代とヒットラーの失敗 第6章 ロンメルは名将だったか 第7章 主計兵による戦争 第8章 知性だけがすべてではない [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by