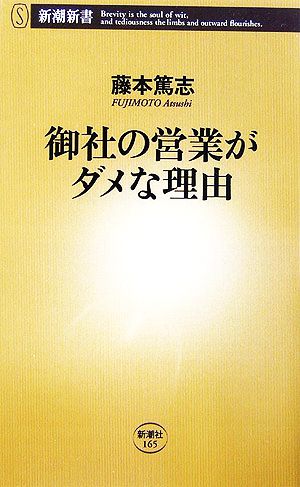御社の営業がダメな理由 の商品レビュー
オススメです
「営業結果」を「営業量」と「営業能力」に分類して説明している本書。効率の良い営業を妨げる要因は何か、時間ロスはどこで生まれるのか。実際に営業に回る人もだが、それをまとめるマネージャーにも目を通してほしい。
yui
細かいテクニックではなく仕組みの作り方について書かれている。機会をどう増やすか、管理職への目標設定と動き方、日報>部下との面談など。
Posted by
巷の営業関連の本のノウハウを否定する前衛的な本でしたが、ある程度理解を示せる中小企業のあるあるが立ち並んでいます。 個人的には、そうはいってもできることはあるから放棄しなくても、、、と感じる部分もありますが営業効果のプライオリティをしっかり見定めた内容でした。
Posted by
結果は営業量×能力。 まずは量を増やす仕組みを作る、具体的には結果的怠慢時間(無駄だけど仕事している気になる仕事)を減らす。 能力はセンスに関するところは伸ばしにくいので、社内ノウハウの蓄積に集中する。 課題に対し力技ではなくスキームで対処するという論理は共感する。これは組織的...
結果は営業量×能力。 まずは量を増やす仕組みを作る、具体的には結果的怠慢時間(無駄だけど仕事している気になる仕事)を減らす。 能力はセンスに関するところは伸ばしにくいので、社内ノウハウの蓄積に集中する。 課題に対し力技ではなくスキームで対処するという論理は共感する。これは組織的改革なのでマネジメント層の権限と度量、覚悟が必要。
Posted by
新書なので、それほど驚くようなことは書いてなかった。対象とする企業もエクセレントカンパニーではなさそう。 一方、「営業プロセスは確率論であり、母数を増やさなければ結果は出てこない」「ヒヤリングが日報より重要だ」などは自分が思うところであったり、共感できた部分である。
Posted by
内容紹介 「うちの営業は頼りない」「いい営業マンが育たない」等、会社員なら誰もが一度は感じたことがある不満——。 諸悪の根源は「営業力」にまつわる幻想だった。 問題の原因は個人の能力ではなく、システムにある。 営業のメカニズムを解き明かす三つの方程式とその活用法を知れば、...
内容紹介 「うちの営業は頼りない」「いい営業マンが育たない」等、会社員なら誰もが一度は感じたことがある不満——。 諸悪の根源は「営業力」にまつわる幻想だった。 問題の原因は個人の能力ではなく、システムにある。 営業のメカニズムを解き明かす三つの方程式とその活用法を知れば、凡人揃いのチームが確実に最強部隊に変身できる。 営業理論のコペルニクス的転換を提唱する全企業人必読の一冊。 内容(「BOOK」データベースより) 「うちの営業は頼りない」「いい営業マンが育たない」等、会社員なら誰もが一度は感じたことがある不満―。諸悪の根源は「営業力」にまつわる幻想だった。問題の原因は個人の能力ではなく、システムにある。営業のメカニズムを解き明かす三つの方程式とその活用法を知れば、凡人揃いのチームが確実に最強部隊に変身できる。組織論、営業理論のコペルニクス的転回を提唱する全企業人必読の一冊。 著者について 1961年大阪生まれ。 大阪市立大学法学部卒。USEN取締役、スタッフサービス・ホールディングスの取締役を歴任。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 藤本篤志 1961(昭和36)年大阪生まれ。大阪市立大学法学部卒。USEN取締役、スタッフサービス・ホールディングスの取締役を歴任。2005年(株)グランド・デザインズを設立。代表取締役に就任し、営業コンサルティング事業、営業人材紹介事業を始める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 目次 第1章 「スーパー営業マン」誕生という幻想(あるダメ会社の光景 嘘の報告をする部下 ほか) 第2章 二‐六‐二の法則で会社を考える(働き蟻の法則 中小企業に最優秀者は来ない ほか) 第3章 「営業センス」は伸ばせない(標準社員に注目する 第三の方程式の意味 ほか) 第4章 営業日報が元凶だった(疑惑の営業日報 嘘は見破れない ほか) 第5章 営業を「因数分解」する(「追い込み」に意味があるか トップセールスマンはアベレージヒッター ほか)
Posted by
営業スキルをつけるという話かと思いきや、組織論の話であった。厳しく部下の管理をして、また自らもプレーイングマネージャーとして活躍するのではなく、まず、自社にはスーパープレーヤーがいない事を自覚し、作戦を練る事から始まる。部下に無駄な時間を過ごさせないようにする、例えば「業務日誌」...
営業スキルをつけるという話かと思いきや、組織論の話であった。厳しく部下の管理をして、また自らもプレーイングマネージャーとして活躍するのではなく、まず、自社にはスーパープレーヤーがいない事を自覚し、作戦を練る事から始まる。部下に無駄な時間を過ごさせないようにする、例えば「業務日誌」の廃止だ。一見、部下を管理出来ているように感じるが、いざやってみるとその日誌は無駄な作成時間をうみ、強いては部下に嘘の報告をさせる事につながる。そのため、業務日誌を廃止し、部下とのヒアリング時間を毎日設けることが必要だ、大変なことのように聞こえるが、声に出す言葉には嘘が少なくなるし、総じて無駄な時間が減る。部下とコミュニケーションを図ることで問題の解決策が見つかるかもしれないし、難問には同行訪問をし、真摯な姿を相手方に見せることで、業績がよくなる。
Posted by
難しい職種である営業を科学的に理解できればいいと思っていたが、かなり納得することができた。ただこれを一面としてさらにほかにも営業本を読むことも大切だと感じた。
Posted by
営業論というよりは、組織運営、組織の組み方論として面白かった。スーパーエリートと、ノーマル兵の存在を認めることから始めよう。 営業テクニックの話自体は潔く皆無。そこが新鮮。
Posted by
正直、これは期待はずれ。 現実を見ろ、と諭された気分。いや、それが営業の最大の問題なのかも。側面を見る分には良いが、いまひとつ、パッとしないまま終わってしまった。
Posted by