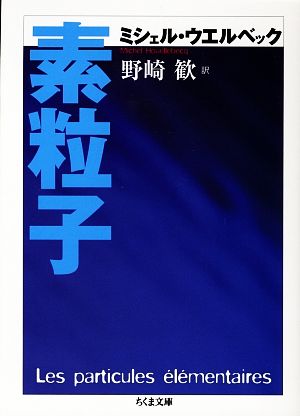素粒子 の商品レビュー
本書の中で描かれているのは、単なる中年男の孤独だろうか。そうは思えない。 誰もが心の何処かで持っている寂寥感や人恋しさが根底にあって、その上で満たされない気持ちをどうするか? という問いが含まれているように思う。
Posted by
ミシェルは分子生物学者、ブリュノは高校の文学教師で、二人は異父兄弟だ。現在40代となった二人は同じように愛を求めている。ミシェルは休職し思索にふけり、ブリュノは失われし青春を求めてセックスに狂っている。人生に対する埋めがたい空虚さを人はどうして埋めたらよいのか。主に二人の男の人生...
ミシェルは分子生物学者、ブリュノは高校の文学教師で、二人は異父兄弟だ。現在40代となった二人は同じように愛を求めている。ミシェルは休職し思索にふけり、ブリュノは失われし青春を求めてセックスに狂っている。人生に対する埋めがたい空虚さを人はどうして埋めたらよいのか。主に二人の男の人生を描いているだけだが、性別、遺伝子、セックス、幸福、資本主義、宗教、種族といった観点について、社会を再構成していくための方法を模索している。最終的には壮大なSF作品たる結びで終わる。 ヒッピーってそんなに重要なのだろうか。 海外の人ってそんなに乱交ばかりやっているのか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
すごい本だけど刺戟的に過ぎる部分もあり、感想としてはめちゃくちゃだったといった感じ。ラストはちょっと賛同しかねる。 しかし、人間への根本的な愛を感じる一作である。
Posted by
テーマは『ある島の可能性』とほぼ同じ、というより、あちらが、この『素粒子』の続編みたいなものらしい。 若い時分に読んだらそれこそ死にたくなるような気分にさせられたかも。なんともやるせない小説。 女たちが次々自殺するがそれもご都合主義ではなく、切実さとリアリティを持って感じられた。...
テーマは『ある島の可能性』とほぼ同じ、というより、あちらが、この『素粒子』の続編みたいなものらしい。 若い時分に読んだらそれこそ死にたくなるような気分にさせられたかも。なんともやるせない小説。 女たちが次々自殺するがそれもご都合主義ではなく、切実さとリアリティを持って感じられた。 非モテ系の話と聞いていたけれど、作家のポートレイトを見る限りでは意外にも美男子(私がそう感じるだけ⁉︎) 訳者あとがきによると、主人公のひとりブリュノの人生は、ほぼ作家の人生と重なるそうだ。数度にわたる精神科入院など、驚いた。 ほぼデビュー作であるこの作品は、なんというか、怒りや絶望、作家の痛みが直に伝わってくるようで、読んでいて辛かった。『素粒子』の成功である程度余裕を持って書かれた『ある島の可能性』はこちらより完成度も高いと思うし、楽しんで読めたのだけど。
Posted by
静と動、性と死が激しい物語。 対局的に位置する二人の兄弟の虚しさが上手く描かれている。取り分け、時間の流れ(若さ)への恐怖は読者をも病む。 あからさまな性の表現が多く、それ自体はいいが、もう少しミシェル側のストーリーが欲しかった。 なにかしら残ってしまった自分のしこりが、上手...
静と動、性と死が激しい物語。 対局的に位置する二人の兄弟の虚しさが上手く描かれている。取り分け、時間の流れ(若さ)への恐怖は読者をも病む。 あからさまな性の表現が多く、それ自体はいいが、もう少しミシェル側のストーリーが欲しかった。 なにかしら残ってしまった自分のしこりが、上手く解決できず、戸惑っている。
Posted by
2014年6月の課題本です。 http://www.nekomachi-club.com/side/12885
Posted by
読むのが超辛かった 現代社会の構造、生殖、生物の細胞遺伝子レベルまで一つ一つ丁寧に確認するとそこには悲しみが徹底的に染み渡っていて、でもそれを確認できたら、なぜか私は安心した。 いや、安心したのはやっと読み終わったからか… でも早朝の湖畔を散歩しているような気持ちになった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
久し振りの現代フランス文学。読メ友のfishdeleuzeさんお薦め。一見したところ文学作品には見えないタイトルなので、自分で手に取ることはなかっただろうと思う。なお、タイトルは原題の直訳。ブリュノもミシェルも親に捨てられ、また子どもとの縁も薄い。常に勃起し、女を求め続けるブリュノ。一方のミシェルは、ほとんど性的な関心を持つことがない。1960年代のヒッピーからニューエイジを経て、性と社会や人間性の解放が謳われるが、ここに描かれた主人公たちの人生と共に、それはむしろ愛の不毛を確かめただけであるかのようだ。
Posted by
相対性理論と量子力学による現代科学のパラダイム・シフトは20世紀を物質主義的価値観に塗り替えた。それは宗教的抑圧からの解放に繋がることでサド侯爵的性の快楽と同調し、しかしながらも性の自由は競争原理を呼び寄せる事で逆説的に性の抑圧へと結び付く。性への強迫観念に囚われたブリュノと禁欲...
相対性理論と量子力学による現代科学のパラダイム・シフトは20世紀を物質主義的価値観に塗り替えた。それは宗教的抑圧からの解放に繋がることでサド侯爵的性の快楽と同調し、しかしながらも性の自由は競争原理を呼び寄せる事で逆説的に性の抑圧へと結び付く。性への強迫観念に囚われたブリュノと禁欲的な生物学者ミシェルという異父兄弟の生涯を濃厚な性描写と情報量で描きながら、人生に対するやり切れない諦観を滲み出させている。ニューエイジの怨霊を駆逐し、ハックスリーの亡霊を21世紀に呼び寄せる本書は、打ちひしがれる様な凄い本。
Posted by
相反する貞淑と自由恋愛の概念、オクシデントへの僕らの眼差しは依然として、性に対しては十分に自由な選択を彼らは行っているに違いないというものだといえるが、本書を通してみると、月並みな表現であるがなにもかもいいことづくめではないようだ。 「恋愛先進国」(こういってよければ、そして現代...
相反する貞淑と自由恋愛の概念、オクシデントへの僕らの眼差しは依然として、性に対しては十分に自由な選択を彼らは行っているに違いないというものだといえるが、本書を通してみると、月並みな表現であるがなにもかもいいことづくめではないようだ。 「恋愛先進国」(こういってよければ、そして現代において恋愛とはすなわち性行為と結婚を後に控えた個人の一大スペクタクルである)フランス作家界の旗手ウェルベックの最高傑作と謳われる今作、一般的には個人的な問題として片付けられて来たセクシュアリティを、遺伝子と先端科学というフィルターを通して、社会変革プログラムの超えるべき壁として呈示する。 日本においても、高度経済成長を境に進む都市への人口流入、それによってもたられた「核家族」という家族構成の最小単位と、凄まじい移り変わりの中に僕らの”性”こういってよければ”生”は置かれてきたといえる。人間を取り巻く環境が人間を作り出すという「唯物史観」的な観点にたてば、観念的な異性関係とは、正しい性関係・夫婦関係とは、などという論の立て方は、厳格なカトリックがその信徒に教会を通して指導してきた方針と同様にお笑いぐさである。 しかし、ポストモダン的・脱構築的手法がすべてを解体し、白日の下に曝したとき、僕らがこれまで信じて来た”性関係”とは空無であったという”衝撃的”な事実に未だ耐えられない”ピュア”な僕たちというのもまた事実である。論理だけで生きていくことはできない。いかに馬鹿な決まりであれ、文化というのは撞着語法的なものなのである。そこに”ある”と強く信じることにによって何かが見たされている空無、それが文化の本質である。 ラカンのテーゼに従えば、「異性関係は存在しない」。ここでいう異性は、広く他者ということもできるし、言葉通りの異性でも言える。僕らは性交を行うとき、相手の性器と自分の性器をこすりあわせてマスターベーションをしているのである。平たく言えばこういうことだ。それは、とりもなおさず他者表象や他者とのコミュニケーションの地平を揺るがす、断絶である。 そういった、不通・不全のなかで、僕らの性関係、言い換えるなら遺伝子にインプリントされた醜いプログラム”再生産”をどう扱うのか、唯物的に歪められてきた性の変遷に終わりはあるのか、日本においては現代美術家の中原浩大がその作品『デート・マシン』で表現した”再生産過程の現時点におけるスペクタクル的表象”をどう乗り越えていくことができるのか、性の商品化の動きと、それらと切り離せない、”性の実験”ともいえる西洋のニューカルチャーの歴史的記述と、それらに対する辛辣な批判と幻滅、そしてそれの悲しい残滓をあけすけに記述してゆく。 弁証法的な解決を著者自身ももはや望めない世界に対して、SF的な解決を用意するあたり、個人的には非常に面白いが、ここでは善し悪しが別れるところであろう。
Posted by