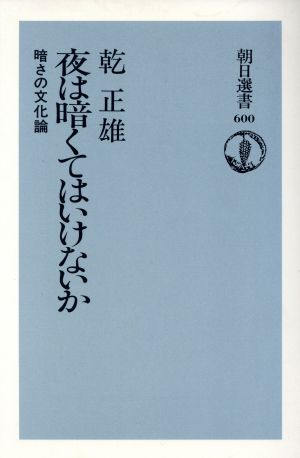夜は暗くてはいけないか の商品レビュー
夜が明るくなって、人間の活動時間は大幅にのびたけど、その分考えることが少なくなってるんだって。ちょっと分かる。 ジャンルは全然違うけど、「極夜行」(角幡唯介)の人とかめっっちゃ考えてたもん。 あれ暗かったからなんだね。 それ以外にも、日本とロンドンの日照時間の違いとか、共産党の...
夜が明るくなって、人間の活動時間は大幅にのびたけど、その分考えることが少なくなってるんだって。ちょっと分かる。 ジャンルは全然違うけど、「極夜行」(角幡唯介)の人とかめっっちゃ考えてたもん。 あれ暗かったからなんだね。 それ以外にも、日本とロンドンの日照時間の違いとか、共産党の国における電飾看板の規制とか、興味深い記述もあり。
Posted by
カテゴリ:図書館企画展示 2013年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」第1弾! 入学&進級を祝し、本学教員から本学学生に「是非読んでもらいたい本」の推薦に係る展示です。 西原直枝講師(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:2013...
カテゴリ:図書館企画展示 2013年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」第1弾! 入学&進級を祝し、本学教員から本学学生に「是非読んでもらいたい本」の推薦に係る展示です。 西原直枝講師(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:2013年4月8日(月) ~2013年6月17日(月)【終了しました】 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース 大学院修士課程の頃に出会った本です。建築物、照明、芸術作品などを例とし、日本とヨーロッパを比較しながら、人間らしい思考や生活に適した光・視環境について論じています。私が学生の頃、様々な場面において明るいものが良い、というような風潮があった中で、この本に出会い、光と陰、明るさと暗さの両方の美しさに触れ、少しほっとしたことを思い出します。谷崎潤一郎『陰翳礼讃』をあわせて読むとより楽しめます。
Posted by
この本が、ブリューゲル「雪中の狩人たち」から 始まらなかったら、手に取らなかっただろうな 本の印象って不思議です 谷崎の陰影礼賛って、面白いな~ 暗いことが味わいがあるっていうか(^_^) 作者の言う、畳のことも 日本人ながら気がつかなかった 畳は、明るくて下から上へ溢れ出る ...
この本が、ブリューゲル「雪中の狩人たち」から 始まらなかったら、手に取らなかっただろうな 本の印象って不思議です 谷崎の陰影礼賛って、面白いな~ 暗いことが味わいがあるっていうか(^_^) 作者の言う、畳のことも 日本人ながら気がつかなかった 畳は、明るくて下から上へ溢れ出る 普通は、上から下だもんね 日本は夏と冬は、寒暑の違いがある ロンドンは、昼間の長さが違う 過ごしてみないとわからないよね 黄昏の時間が長いんだよね 自分が、夏至のころにドイツに行った時は 10時ごろまで明るかったっけ ロマネスク教会のところでは 暗さを★でランキング なんか、マニアックで笑っちゃう(^_^); 日本のお寺のほうが明るいなんて意外 すぐ、室内に入るから、 目が慣れないせいもあるんだけど オフィスの不均一照明もいいよね 実際、こういうのって目が疲れたりしないのかな? 次は、LEDの時代だね 作者は、どんな考察をしてるかな
Posted by
北欧の照明文化と日本の照明文化の違いや、西洋人と日本人の虹彩の違いが照明や日射に対する眩しさ感覚の違いを理解できた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
西欧と日本での光に対する感性の違いから、その文化の違いを論じていく本。 途中で頓挫、最後まで読めませんでした。 内容は難しくないのですが、どうも筋道立てて物事を説明するのが作者は苦手なようです。文章の前後関係で矛盾とまではいかなくてもつながりがおかしい部分がかなりあり、読んでいて疲れます。 暗さの文化論という着眼点は悪くはないですが、それを論じ切るだけのしっかりした文章を書いてほしかったです。 二度と読まないでしょうから、読み終わったとしておきます。
Posted by
この本を知ったきっかけは,東日本大震災後に読んでいた本で,節電の影響で夜が暗くなった,というようなくだりで,いや,いままでの日本の夜は明るすぎたのだ,という文脈で紹介されていたように思う。 建築,照明の専門家である著者は,アルプス以北のヨーロッパを例として,照明の歴史=いいかえれ...
この本を知ったきっかけは,東日本大震災後に読んでいた本で,節電の影響で夜が暗くなった,というようなくだりで,いや,いままでの日本の夜は明るすぎたのだ,という文脈で紹介されていたように思う。 建築,照明の専門家である著者は,アルプス以北のヨーロッパを例として,照明の歴史=いいかえれば,いかにヨーロッパは暗かったか,ということを述べていく。暗さは人を思考にいざなう,というように,暗さの効用を指摘する。 私自身,ヨーロッパの夜の街を歩いたことがあるが,現在の日本の都市の夜の明るさはちょうどそれと同じ程度である。 間接照明のよさ,谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』への言及(私もこの随筆は高校時代に読んで大好きだ)など,豊富な話題によって,暗さの効用について考えさせてくれる。
Posted by
夜の暗さを楽しみたいタイプです。だんだん暗くなっていくのを、照明を灯さずに眺め味わいたいと思っています。 著者は建築家らしいので、内容も建築寄りと思われますが、題名に惹かれて。 目次は以下の通り。 1 暗さのもたらすもの 鉛色の空 『陰翳礼讃』再読 暗いことの意味...
夜の暗さを楽しみたいタイプです。だんだん暗くなっていくのを、照明を灯さずに眺め味わいたいと思っています。 著者は建築家らしいので、内容も建築寄りと思われますが、題名に惹かれて。 目次は以下の通り。 1 暗さのもたらすもの 鉛色の空 『陰翳礼讃』再読 暗いことの意味 2 暗さをたずねて 光の文化 石の家 ロマネスク教会の光と陰 3 現代に暗さをつくる 照明の変遷 夜は暗くてはいけないか オフィスビルの採光と照明 不均一照明のすすめ
Posted by
Ⅰ 暗さのもたらすもの 1 鉛色の空 「雪中の狩人たち」 寒かったブリューゲルの時代 ヨーロッパの冬空の暗さ なぜ曇り空が青いのか イギリスの天気 完全曇天雲の性状 暗さを理解しなかった日本の文明開化 2 『陰蔭礼讃』再読 谷崎の美意識と実生活 関西古建築巡礼 日本座敷の光の流れ...
Ⅰ 暗さのもたらすもの 1 鉛色の空 「雪中の狩人たち」 寒かったブリューゲルの時代 ヨーロッパの冬空の暗さ なぜ曇り空が青いのか イギリスの天気 完全曇天雲の性状 暗さを理解しなかった日本の文明開化 2 『陰蔭礼讃』再読 谷崎の美意識と実生活 関西古建築巡礼 日本座敷の光の流れ 暗さと黒さの入れ子 古い建築の現代化 明るくなった日本 3 暗いことの意味 狩猟民族のパーティー 暗さ好きのヨーロッパ人たち 眼のはたらき 虹彩の色による眼のちがい 明るさから暗さへ 暗いときの視覚 Ⅱ 暗さをたずねて 1 光の文化 気候の比較、東京とロンドン 防寒だけでよいヨーロッパ 黄昏の比較、東京とロンドン 昼間と夜間の境目 「寒暑の文化」と「光の文化」 2 石の家 石造住宅の窓 木材をうがち開けた窓 室内側から見た窓 絵から見積もれる照度と輝度 採光権 石の家の住むということ 石の家の居住経験から 住宅の歴史の連続性 現代版・究極の石の家 3 ロマネスク教会の光と陰 キリスト教建築のおおもと 実地調査の概要 特色のある教会 教会採光の三つの類型 日本の寺の礼堂 寺院の暗さの日仏比較 ロマネスク教会の終焉 教会の建物の再利用 Ⅲ 現代に暗さをつくる 1 照明の変遷 石油ランプまで ガス灯 白熱電球 蛍光灯 マイケル・ファラデイ 照明の歴史の連続性 日本の住宅照明 日欧の照明文化の比較 2 夜は暗くてはいけないか 真の闇 光っている夜の地球 夜らしい顔 ライトアップの是非 夜のベルン 星の見える夜空 3 オフィスビルの採光と照明 オフィスの発生 ビルの巨大化 ガラス製箱形ビル 高層ビルの限界 新しい照明 箱形ビルからの脱皮 ビルの採光三例 4不均一照明のすすめ 明るいことはよいことか 不均一ということ 均一照明 不均一照明の復活 明暗の共存の必要性 昼光の不均一性 夜の照明の不均一性 今でこそ照明と快適性の関係は新聞や雑誌でも見かけるようになったけど、数年前に初めて読んだ時にはものすごく斬新だと思った。 この本を読んでから、天井の直接照明を外して間接照明を増やした。不均一照明は、やってみると凄く快適だ。 白い光の蛍光灯より黄色い光の白熱電球の方が好みだってこともわかった。 調光器 明るさを調節できる
Posted by
照明について調べていて読んだ。 日本とヨーロッパの違いなどは面白いが、ヨーロッパのいくつかの教会についての暗さの比較は俺の手に余るという印象。
Posted by
- 1