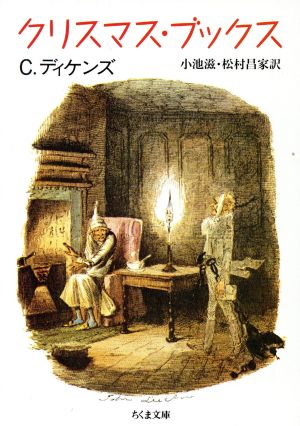クリスマス・ブックス の商品レビュー
クリスマス本の二冊目…
クリスマス本の二冊目として熱狂的に迎えられた「鐘の音」。風刺雑誌『パンチ』の画家として有名なジョン・リーチらの幻想性に満ちた挿絵と現実が奇妙に溶けこんだ不思議なファンタジー。
文庫OFF
ディケンズのクリスマス小説「クリスマス・キャロル」と「鐘の音」の2篇を収めた本。 吝嗇家の金持ちであるスクルージを主人公にした「クリスマス・キャロル」、貧しい配達人であるトビー・ヴェックを主人公にした「鐘の音」、主人公はそれぞれ対照的ながら、富裕層に対する批判的な叙述は似通った...
ディケンズのクリスマス小説「クリスマス・キャロル」と「鐘の音」の2篇を収めた本。 吝嗇家の金持ちであるスクルージを主人公にした「クリスマス・キャロル」、貧しい配達人であるトビー・ヴェックを主人公にした「鐘の音」、主人公はそれぞれ対照的ながら、富裕層に対する批判的な叙述は似通ったところがあります。特に「鐘の音」の方は風刺がきいており、「貧乏人の味方」を標榜する金持ちが貧しい人たちに労働の尊さを訴えるあたり、苦笑いがこみあげてきます。 この本を読む以前から「クリスマス・キャロル」の大筋は実は知っていました。というのも、ビル・マーレイ主演の「三人のゴースト」という映画を見ていたからです。この映画がクリスマス・キャロルを下敷きにしている、というのを知ったのはずいぶん後になってからですが。 あらためてクリスマス・キャロルを読んでみて、筋自体はかなり似通っていたんだな、と改めて思った次第です。
Posted by
ディケンズが書いたクリスマスものは『クリスマスキャロル』の他にも数作あって、この中には『鐘の音』という物語も入っている。 最初は新潮文庫の『クリスマスキャロル』を読もうと思ったのだが、何回も読んでいるので、たまには違う訳者の本を読んでみた。 たぶん新潮文庫版のほうが訳とし...
ディケンズが書いたクリスマスものは『クリスマスキャロル』の他にも数作あって、この中には『鐘の音』という物語も入っている。 最初は新潮文庫の『クリスマスキャロル』を読もうと思ったのだが、何回も読んでいるので、たまには違う訳者の本を読んでみた。 たぶん新潮文庫版のほうが訳としては正しいのだと思うけれど、こっちのほうが訳が自由で、たぶん勝手に書き加えていて、落語みたいで、読みやすい。ウケ狙いなのに時折すべっているところがご愛敬。初めて『クリスマスキャロル』を読む人に向いているかどうかはわからないが、また新しい魅力があるのは確か。 『鐘の音』という話は、クリスマスの精霊の代わりに、教会の鐘の精霊が出てきて、『クリスマスキャロル』のスクルージと同じように、主人公の郵便配達人のおじさんを夢の世界へと連れて回る話。このおじさんは娘の結婚に反対して(貧乏人が結婚してもろくな未来はないとお偉いさんに言われて、悲嘆して消極的に反対した)それにより起こる悲惨な未来をひたすら見て回る。 あ〜あ、反対しなきゃ良かった、と改心するところは『クリスマスキャロル』と一緒。スクルージは金への執着と冷酷さだったけど、こちらの主人公は世間へのおもねりと臆病のゆえに不幸に陥る。でも最後には改心して、案の定の展開でハッピーエンドになる。 この「案の定」というのは結構大切だ。クリスマスにハッピーエンドが待っていなかったら、キリスト教徒はいつ幸せになるのだ。山下達郎の歌のような寂しい内容は、たぶんキリスト教徒じゃないから作れるのだ(勝手な憶測) どちらにしろ、人としての本当に大切なものは何かということを教えてくれる。 人生の幸福と不幸なんて、所詮は心が決めるもの。心が変われば世界も変わる。 来年のクリスマスには、また違うディケンズ作のクリスマス作品を読みたいと思う。
Posted by
ディケンズのクリスマスキャロルともういっこ なぜか落語調 クリスマスキャロルはすっごくよかった こんな話だったのかー ケチで冷たいスクルージおじさんがクリスマスの精に過去と今と未来とみて 自分の死後とかもみて 改心する イイ話だった。 もういっこはなんだか頭にさっぱり入...
ディケンズのクリスマスキャロルともういっこ なぜか落語調 クリスマスキャロルはすっごくよかった こんな話だったのかー ケチで冷たいスクルージおじさんがクリスマスの精に過去と今と未来とみて 自分の死後とかもみて 改心する イイ話だった。 もういっこはなんだか頭にさっぱり入らず断念 わたしにしては珍しい よっぽどつまらないのか読みにくいのかなんなのか‥
Posted by
ディケンズの「クリスマス・ブックス」と言われる作品は5作品なるのだけど、そのうち最初の2作品「クリスマス・キャロル」と「鐘の音」が収録されてます。 「クリスマス・キャロル」は違う訳で既に読んでいたし、映画も何種類も観たほど好きな作品。 ディケンズはよく朗読をやっていたということ...
ディケンズの「クリスマス・ブックス」と言われる作品は5作品なるのだけど、そのうち最初の2作品「クリスマス・キャロル」と「鐘の音」が収録されてます。 「クリスマス・キャロル」は違う訳で既に読んでいたし、映画も何種類も観たほど好きな作品。 ディケンズはよく朗読をやっていたということで、ここでは落語口調で訳されてる…のが面白いな。と思ったのだけど、まぁ途中からそんな工夫は特に効を奏してもいないかも…という感じで普通に読んだ。 で、目当ては「鐘の音」のほうだったのでした。 これ、クリスマスでなくて大晦日の話だった。 主人公は人がいいけど、いろいろ社会的事情で未来に希望を抱けなくなったおっさんで、教会の鐘の精の導きで、このままだとどんどんと不幸になっていく未来の娘の姿を見せてもらう…。 というプロットは「クリスマス・キャロル」によく似た話。 映画「素晴らしき哉、人生」にも似てますね。 「クリスマス・キャロル」の焼き直し感がある上に、前作以上の面白さがない。のが残念。 登場人物もあまり魅力がないし、暗いばかりで楽しくなる場面描写もない。 当時の社会批判の色が高めなので、いま読んで普遍的に伝わるものがあるわけでもない。 面白い…というか映像化して観てみたいと思った場面が一つだけあった。 なんか鐘の音がなってる間だけ、鐘の中から無数の様々な鐘の精が出てきて、音がなると次々に死んでいく…という場面。 ディケンズはファンタジックの場面の描写がけっこう丁寧で、この人はほんとにこういうものが見えてしまう人だったんじゃないだろうか?なんて思ってしまう。
Posted by
- 1