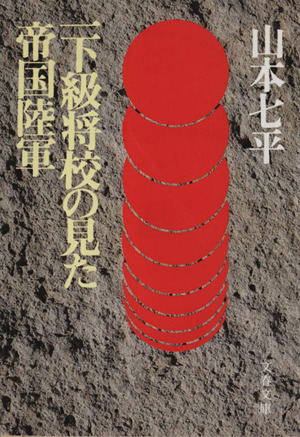一下級将校の見た帝国陸軍 の商品レビュー
衝撃を受けました。 目前の仲間うちの摩擦を避けること 奇妙な「気魄」でものごとを解決できると思うこと 「言いまくり型私物命令」を出す人間が組織を牛耳ること これの克服ができなければ、 「日本全体が第二の帝国陸軍となる」とされています。 50年前に書かれた本ですが、現代日本の病...
衝撃を受けました。 目前の仲間うちの摩擦を避けること 奇妙な「気魄」でものごとを解決できると思うこと 「言いまくり型私物命令」を出す人間が組織を牛耳ること これの克服ができなければ、 「日本全体が第二の帝国陸軍となる」とされています。 50年前に書かれた本ですが、現代日本の病巣を正確に表しています。 第二次世界大戦での敗戦から何も学ばず、同じことを繰り返して衰退の一途を辿る日本。そろそろ考え直したほうが良いと思いますが、考え直すことが大の苦手な国民性からしてもう救いようは無く、ひたすら衰退をし続けることでしょう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一下級将校の見た帝国陸軍 (文春文庫) 文庫 – 1987/8/8 「帝国陸軍」とは一体何だったのか。 この、すべてが規則ずくめで超保守的な一大機構を、ルソン島で砲兵隊本部の少尉として苛酷な体験をした著者が、戦争最末期の戦闘、敗走、そして捕虜生活を語り、徹底的に分析し、追及する。現代の日本的組織の歪み、日本人の特異な思考法を透視する山本流日本論の端緒を成す一冊。 目次より 〝大に事(つか)える主義〟/すべて欠、欠、欠……。/だれも知らぬ対米戦闘法/地獄の輸送船生活/石の雨と鼻の雨と/現地を知らぬ帝国陸軍/私物命令・気魄という名の演技/参謀のシナリオと演技の跡/組織と自殺/敗戦の瞬間、戦争責任から出家遁世した閣下たち/言葉と秩序と暴力/統帥権・戦費・実力者/組織の名誉と信義/あとがき 以前読み、レビューも書いたのだが、失われた為、再度記入することにする。 吉越浩一郎の著作の中で本書を紹介する部分があり、それで本書題名を知った。読んでみて感じたのは当時の理不尽さ、補給のなさ、旧日本軍の悲惨さだ。 特に武器や弾薬の在庫数を帳簿上と合わせる為だけに奔走する無意味さ、横との連携が取れていないことなど多くの課題を感じる。 フィリピンは常夏で食料は手に入るはずと十分な調査もないまま出撃させていた大本営。 (実際、畑ではなくプランテーションが続き、食料が手に入らず餓死に追い込まれていく) アメリカ軍の充実さ、荒れ地を重機を使いならして、テニスコートにしたり、アイスクリームを食べることができたり、交代制勤務。一方の日本軍は24時間、米軍監視業務。 他の方の戦争体験談でもそうだけれども、悲惨であるとしか言いようがない。 もちろん独ソ戦の悲惨さに比べるとマシに見えるかもしれないが・・・。 2022/10/08(土)記述
Posted by
1987年の日付アリ、34年前に読んだ本を、改めて読み返しつつ、帝国陸軍の混乱(欠、欠、欠)と、コロナ感染症の時代における組織(政府、医療体制の構築等)の混乱に同じような物語を感じます。昭和18年8月(1943年8月)、学徒動員された山本七平は、豊橋第一陸軍予備士官学校士官学校で...
1987年の日付アリ、34年前に読んだ本を、改めて読み返しつつ、帝国陸軍の混乱(欠、欠、欠)と、コロナ感染症の時代における組織(政府、医療体制の構築等)の混乱に同じような物語を感じます。昭和18年8月(1943年8月)、学徒動員された山本七平は、豊橋第一陸軍予備士官学校士官学校で対ロシア戦での砲兵の在り方を学びつつ、今、そこにある戦い(南太平洋での米軍との戦い)についての講義が無いことに驚く。(今、教えられていることがまったく役に立たない、という事実に)そして、陸軍は、対米戦争の準備は、殆ど行っていないというリアルに思いが至る。ではどうするか、と考えつつ原隊に戻ると、そこにあるのは、普通の忙しい軍隊の日常。そんな流れのままに、南方方面への地獄の船旅に送り出され、更にフィリッピン戦線での惨憺たる負け戦、生きながらえての俘虜としての日々。わずか30数年前の出来事を振り返る、山本七平の筆致には、臨場感があります。一下級将校が見た、帝国陸軍の敗北のリアルであります。それにしても、帝国陸軍とは酷い組織だったな、と思いつつ、今でも似た組織が身近にあること等に想いが至ります。いやはやどうしたものか、と溜息ですが、★五つであります。
Posted by
当事者だからかける事を淡々と、だけど臨場感を持って、かつ納得感が感じられる内容で書かれている。今の日本の社会にも旧陸軍の悪弊がどこか残ってないか?
Posted by
"大に事える主義"◆すべて欠、欠、欠……。◆だれも知らぬ対米戦闘法◆地獄の輸送船生活◆石の雨と花の雨と◆現地を知らぬ帝国陸軍◆死の行進について◆みずからを片づけた日本軍◆一、軍人は員数を尊ぶべし◆私物命令・気魄という名の演技◆「オンリ・ペッペル・ナット・マネー...
"大に事える主義"◆すべて欠、欠、欠……。◆だれも知らぬ対米戦闘法◆地獄の輸送船生活◆石の雨と花の雨と◆現地を知らぬ帝国陸軍◆死の行進について◆みずからを片づけた日本軍◆一、軍人は員数を尊ぶべし◆私物命令・気魄という名の演技◆「オンリ・ペッペル・ナット・マネー」◆参謀のシナリオと演技の跡◆最後の戦闘に残る悔い◆死のリフレイン◆組織と自殺◆still live, スティルリブ、スティルリブ……◆敗戦の瞬間、戦争責任から出家遁世した閣下たち◆言葉と秩序と暴力◆統帥権・戦費・実力者◆組織の名誉と信義 著者:山本七平(1921-1991、東京)[青山学院卒]作家
Posted by
員数主義、気魄といった文化は、今の日本にも持ちこされている気がする。だいぶ薄まってきた気はするけど…。フィリピンでの軍の生活は本当に悲惨。やっぱり戦争はいかん。
Posted by
運命を達観した大学生が学徒出陣し、死線を乗り越え、捕虜生活までの「体験談」と「現代での分析や振り返り」を随所に織り込んだエッセイ以上で論文未満の名作。 読み終えた2017年夏現在、 著者が実経験から、後輩たる我々日本人や(企業)組織に対し、警鐘した「戦略欠陥の克服」や「問題提起...
運命を達観した大学生が学徒出陣し、死線を乗り越え、捕虜生活までの「体験談」と「現代での分析や振り返り」を随所に織り込んだエッセイ以上で論文未満の名作。 読み終えた2017年夏現在、 著者が実経験から、後輩たる我々日本人や(企業)組織に対し、警鐘した「戦略欠陥の克服」や「問題提起する義務」に対して真摯に向き合っているか?と思うと、悩んでしまう作品。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1987年(底本1974年)刊行。 青山学院大学繰上げ卒業、直後入営後4か月で予備士官学校入校、2か月繰上げ卒業で見習士官のまま原隊復帰せずフィリピン戦地へ。かように士官候補生の速成が進みつつあった時期に遭った著者。 彼の、戦中〜戦後収容所期までの、陸軍内での見聞事項を乾いた筆致で描写する。 テーマは軍人教育・教練の無意味さ、私物命令を平気に出す、真の命令者たる現地参謀の頽廃、現地を知らなすぎる本土・大本営、員数主義(詳細は本書にて確認を。友軍からの窃盗が日常茶飯事という他書指摘の理由を見た思い)に彩られる軍人ら。 これらのテーマにつき、確かに乾いた筆致で描写するが、所々挿入される怒りとも祈りとも見える文章の数々。 ① 「比島が…兵器・弾薬・食糧…の集積所…のような顔をして『現地で支給』『現地で調達』の空手形を(本土での命令で)乱発しておきながら…現地では殆ど全部不渡り…。従って私は何も信用していない」。 ② 武器に関する一点豪華主義。ミンクのコートに草鞋を履く如し。時間当たり砲弾発射回数は世界最多級だが、砲弾を手と足で倉庫から運ばなければならない。 ③ 我々の中には「歴戦の臆病者はいるが、歴戦の勇士はいない…。 だが『歴戦の臆病者』の世代は、いずれはこの世を去ってしまう。…この問題はその後の「戦争を”劇画的にしか知らない勇者”の暴走」にあり、その予兆は、平和の…背後に、すでに現れているよう」。 等々がそれだ。 著者を食わず嫌いすべきではなかった、といたく反省させられた一書である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
衝撃的な本。ここ最近読んだ本の中では最高傑作であり、是非とも多くの方に読んでもらいたい。この本は帝国陸軍という異常組織が、実は日本人という国民性が生んだ日本人としの標準的な組織だったということを、戦後から現代(とは言っても昭和40年ごろと思うが)の日本人の思考・行動と照らし合わせて著者の洞察を展開している。これ(日本人の国民性)は昭和40年どころか、戦後70年を過ぎた現在でも全く変わっていないということに驚かされる。名著「失敗の本質」での問題提起が結局は日本人には避け得ないものだということが切実に分かる。自らの思考法、会社の論理、全てが戦前から変わっていない。これを読むと、また日本人は戦争をやるのではないかと心配になってしまう。「事大主義」「員数合わせ」「仲間ぼめ」「私的命令」「気魄」「気魄演技」「組織の名誉」「不可能命令」。少なくとも自分はそこから抜け出したい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
終わりらへんの「旧占領軍の天皇の軍隊が去って、新占領軍のマッカーサーの軍隊が来たが、この方が天皇の軍隊より話がわかる」という言葉に衝撃を受けた。確かに軍事国家というのは自国の軍に占領されている状態とも言えるのかも知れない。それから最後あたりは人間像というか、人間とは?と考えさせられる。それに、この本には派生的に読みたくなる本の題名がよく出てくる。 あと個人的なことを言えば、ここ数年のあいだ戦争に関連する本をよく読むようになった。それが好奇心からくるのか恐怖心からくるのか知らないが、すべてはアナログ的であってその極致が戦争なのかも知れないと思う。僕は日常の生活の中で、非戦闘的で戦争的な何かに嫌悪感を抱きつつ、こういう世界には必ずまた戦争が起きると恐怖を感じているのかも知れない。
Posted by