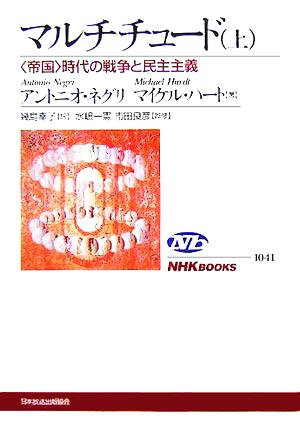マルチチュード(上) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
-2007.11.13記 アントニオ.ネグリとマイケル.ハートによる「帝国」の最終章は「帝国に抗するマルチチュード」と題されていた。 グローバル化した世界の新秩序たる<帝国>に対抗しうるデモクラシー運動を根底的に捉えるために、彼らが導入したのは17世紀の哲学者スピノザに由来する「マルチチュード」という概念であった。 ネグリとハートのコンビによる「帝国」に続く書「マルチチュード」はNHKブックスの上下本として05年10月に出版され、私の書棚にも2年近く積まれたままにあったのだが、このほど走り読みながら上巻をやっと読了。 マルチチュードとは<多>なるものである。人民.大衆.労働者階級といった社会的主体を表すその他の概念から区別されなければならない。 人民=Peopleは、伝統的に統一的な概念として構成されてきたものである。人々の集まりはあらゆる種類の差違を特徴とするが、人民という概念はそうした多様性を統一性へと縮減し、人々の集まりを単一の同一性とみなす。これとは対照的に、マルチチュードは、単一の同一性には決して縮減できない無数の内的差違から成る。その差異は、異なる文化.人種.民族性.ジェンダー.性的指向性、異なる労働形態、異なる生活様式、異なる世界観、異なる欲望など多岐にわたる。 マルチチュードとは、これらすべての特異な差違から成る<多数多様性>にほかならない。 大衆=Massという概念もまた、単一の同一性に縮減できないという点で人民とは対照をなす。たしかに大衆はあらゆるタイプや種類から成るものだが、互に異なる社会的主体が大衆を構成するという言い方は本来すべきではない。大衆の本質は差違の欠如にこそあるのだから。すべての差違は大衆のなかで覆い隠され、かき消されてしまう。大衆が一斉に動くことができるのは、彼らが均一的で識別不可能な塊となっているからにすぎない。 これに対してマルチチュードでは、さまざまな社会的差違はそのまま差違として存在しつづける-鮮やかな色彩はそのままで。したがってマルチチュードという概念が提起する課題は、いかにして社会的な多数多様性が、内的に異なるものでありながら、互にコミュニケートしつつともに行動することができるのか、ということである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
国家主権の戦争から民族内紛へ。単一主権からマルチチュードへ。 集中型からネットワーク型。 こういった世の中のトレンド変化を踏まえた記述である。 ただ、本書は哲学の書であり、なぜかそういうトレンドとなっているのかや、処方箋を示しているわけでもない。 筆者達は左翼の復権とか、究極の民主主義を願うとは言っているが。 (スピノザの『政治論』が再解釈がベースらしい) (共著3部作) 『帝国』 大学319.N62 『マルチチュード』(本書) × 『ディオニュソスの労働』 人文書院 2008
Posted by
民主主義と自由、これが彼らの信じるほどよいものかは微妙だが、世界の道行きに関してはだいぶ正確に見通してると思える。荒唐無稽な理論などではなくて、様々な現象をむしろ帰納的に整理して見せたのだ。 で中身は?と聞かれるならば、グローバルと生権力という2つの傾向があるわけで、ミクロとマク...
民主主義と自由、これが彼らの信じるほどよいものかは微妙だが、世界の道行きに関してはだいぶ正確に見通してると思える。荒唐無稽な理論などではなくて、様々な現象をむしろ帰納的に整理して見せたのだ。 で中身は?と聞かれるならば、グローバルと生権力という2つの傾向があるわけで、ミクロとマクロに引き裂かれながら人々は微塵切りにされていく。いかにして美味しいミックスジュースになるかではなくて、いかにして硬く抵抗するかでもなくて、この傾向を受け入れた上で有効な言説を練り上げようというのがこの本だ。 国民国家はいまや喘いでいる。ならば、この本は尚更に読まれるべき。
Posted by
個別のテーマでは、すごく興味深くてクリアだと思う。現代の戦争のあり方か、ウエストファリア条約以前・主権国家体制以前のあり方と概念的に類似しているという再確認。経済学的な生産活動=付加価値・情報の生産であると見直した観点からの、新古典派批判・マルクスの再解釈…。概念的な話や振り返り...
個別のテーマでは、すごく興味深くてクリアだと思う。現代の戦争のあり方か、ウエストファリア条約以前・主権国家体制以前のあり方と概念的に類似しているという再確認。経済学的な生産活動=付加価値・情報の生産であると見直した観点からの、新古典派批判・マルクスの再解釈…。概念的な話や振り返りが多くてふわっとした印象でございます。 そしてそういう変化の根底にある、といいたいらしい『民衆の変化=マルチチュード化』がよくわからない!実感ベースでいっても、現代の我々の没個性化・大衆化は変化していないような気がしますが?
Posted by
終わり無き戦争を必要とするグローバル経済を教科書として育つ 新らたなグローバル的共生民主主義のことをマルチチュードと呼ぶ人々がいる そもそもグローバルと言う言葉を逆手にとって使い 密かに一般大衆を欺く搾取経済がゴリ押しされていることに気付く必要がある それは単にゲリラ戦法...
終わり無き戦争を必要とするグローバル経済を教科書として育つ 新らたなグローバル的共生民主主義のことをマルチチュードと呼ぶ人々がいる そもそもグローバルと言う言葉を逆手にとって使い 密かに一般大衆を欺く搾取経済がゴリ押しされていることに気付く必要がある それは単にゲリラ戦法を真似しているだけでなくネットワーク上に広がる 国家・民族などのように中心を持たず組織も持たず 手をつないだり離したり刻々と変化する状態に隠れて 部分的に片寄った利害を目的とするグローバル経済 それに対して争うことなくネットするすべての個に 必要十分な環境が行き渡るグローバル民主主義共生ネット社会が巷に広がる 広くシェアーし合うことで無駄を無くし貯蓄を必要とせずに 自律した心を持った集いがこの世に実現しだす 少なくとも彼らは目標として方向をとらえ進むことができる この建前でない納得できる民主主義の姿をマルチチュードと呼ぶ この本は現在のアメリカを中心にしたかに見える 帝国主義的グローバル推進経済社会の現実を深く広く克明に解き明かす 更にそれに押しつぶされることなく精神を鍛えて 敵対することなく共生を可能にしていく人々の現状を伝えている 恐怖が故に執ように戦いを挑む頭人間と それ以上に根気よく先を見つめて生き抜く心人間とが お互いに自分の道を究めていく中で切磋琢磨が起こり理解を広げていく 取り込もうとする者と自らを求める者との共生世界が織り成す妙!!ここにあり
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] マルチチュードとは何か。 グローバル化に伴い登場しつつある、国境を超えたネットワーク状の権力“帝国”。 この新しい権力の形成途上で生じる終わりなきグローバルな戦争状態への抗議運動は、それぞれの特異性を保ちながらも、共通のネットワークを創りあげる。 権力と同型の、ネットワーク状の形態で闘う多種多様な運動の先に、グローバル民主主義を推進する主体=マルチチュードの登場を予見する。 “帝国”論の新たなる展開、ついに日本語版登場。 [ 目次 ] 共にある生―グローバル民主主義に向けて 第1部 戦争(ジンプリチシムス―終わりなき戦争を見る目;ネットワーク化する対反乱活動;抵抗の系譜) 第2部 マルチチュード(“危険な階級”はいかに構成されるか;グローバル資本という身体―搾取と階層秩序の地勢図) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
ざっと斜め読み。『芸術とマルチチュード』の副読本として手元に置いておこうと思う。 「帝国」に対抗しうる「マルチチュード」については、少々楽観的過ぎるような気がする。もう少しバラバラのような気がするのだけれど。どこまで有効か疑わしいが、ネグリの議論には興味をもった。フランスの構造主...
ざっと斜め読み。『芸術とマルチチュード』の副読本として手元に置いておこうと思う。 「帝国」に対抗しうる「マルチチュード」については、少々楽観的過ぎるような気がする。もう少しバラバラのような気がするのだけれど。どこまで有効か疑わしいが、ネグリの議論には興味をもった。フランスの構造主義/構築主義の後、生政治に対抗できるのはイタリア思想か。
Posted by
オンラインで読書会をやってました。 まだ終ってませんが…。 http://orc.lolipop.jp/pukiwiki/pukiwiki.php?%A5%DE%A5%EB%A5%C1%A5%C1%A5%E5%A1%BC%A5%C9
Posted by
- 1