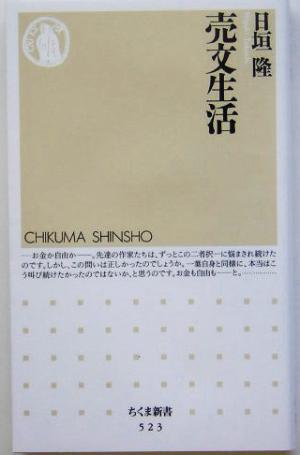売文生活 の商品レビュー
文章を生業とするというのはどういうことか。 過去の作家のお金の話を引きながら、現代あるいは未来の売文生活の可能性を見据える。 しかし、昔の作家さんは本当にお金持ちだったんだなと改めて驚く。 プロの物書きについて考えさせられる一冊。
Posted by
エビデンスに基づく、作家の原稿料について書かれた珍しい本。 巻末に掲載されている大量の参考文献に圧倒された。 ただ、作家、ライター、出版社などの業界以外にはあまり興味を持たれないジャンル。
Posted by
原稿料の考察。文章が一体いくらになるのか、日本の夏目漱石をはじめ、どのように文筆家が報酬を得てきたのか。をガッキィが膨大な資料から考察している興味深い一冊。
Posted by
字を書くことを生業とする人たちの収入とかについて。漱石あたりからバブル期まで、幅広く言及。本書はここまで。今やWEBで電子書籍なるものが出てきてるもんなあ。このbooklogも知らん間にAMN新書とか出してるし。恐ろしい子…
Posted by
物書きってどのくらい稼いでるの?原稿用紙一枚につきいくら?クレジットカードが作れない?そんな素朴な疑問がスッキリ解消。
Posted by
[ 内容 ] 投稿生活をへて作家・ジャーナリストとなった著者のみならず、物書きにとってお金の問題は避けて通ることのできない重大事だ。 本邦初の“フリーエージェント宣言”をなし遂げた文豪・夏目漱石、公務員初任給の一〇〇倍は稼いでいた「火宅の人」檀一雄、「底ぬけビンボー暮らし」に明け...
[ 内容 ] 投稿生活をへて作家・ジャーナリストとなった著者のみならず、物書きにとってお金の問題は避けて通ることのできない重大事だ。 本邦初の“フリーエージェント宣言”をなし遂げた文豪・夏目漱石、公務員初任給の一〇〇倍は稼いでいた「火宅の人」檀一雄、「底ぬけビンボー暮らし」に明け暮れた作家・松下竜一…。 明治の文士から平成のフリーライターまで、物書きたちはカネと自由を求めて苦闘してきた。 本書ではそうした姿を、出版界の“秘部”とも言いうる「原稿料事情」を通じて描き出す。 類例なき作家論にして日本文化論である。 [ 目次 ] 序章 私的売文生活入門 第1章 原稿料とは何か 第2章 幸せな黄金時代 第3章 標準としての夏目漱石 第4章 トップランナーたちの憂鬱 第5章 貧乏自慢もほどほどに 第6章 現代日本の原稿料事情 終章 お金も自由も [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
文字で紙を埋めることを生業とする方々についての、散在的な記事みたいなもの。 夏目漱石の売文生活や、樋口一葉の売文生活のことがわかる
Posted by
「原稿料」という視点から書かれた、数としては珍しい種類の内容の本だと思います。 夏目漱石と筒井康隆、立花隆に主に重点が置かれていました。 これから文筆家になろうとする人以外にも、「そもそも文筆家ってどれぐらいのお金をもらっているの?」と気になっている人にはぜひともおすすめです。...
「原稿料」という視点から書かれた、数としては珍しい種類の内容の本だと思います。 夏目漱石と筒井康隆、立花隆に主に重点が置かれていました。 これから文筆家になろうとする人以外にも、「そもそも文筆家ってどれぐらいのお金をもらっているの?」と気になっている人にはぜひともおすすめです。日垣氏自身のエピソードも交えながら、原稿料の仕組みや変遷について平易に書かれています。 研究職やその他の文筆業、また様々な場面で原稿を書く立場にある人は必携です。文筆の世界で馬鹿にされないためにも、まずはこの本を一読してみてはいかがでしょうか。 日垣氏は有料メルマガをやっていらっしゃるので、そのあたりを交えて、日垣氏の売文生活をもっと教えてくれるような本を書いてくれないかと、この本の読後に感じました。 それにしても、夏目漱石はずいぶんと押しが強かったんですね。意外でした。胃は弱かったのに。
Posted by
文章を売るプロとして原稿料へのこだわりを書き綴った論考というよりエッセイ。いろいろ資料を元に生真面目な内容。ときおり挿入されるユーモアが救い。「シャラップです」(P22)の一言が、妙にウケた。
Posted by
- 1