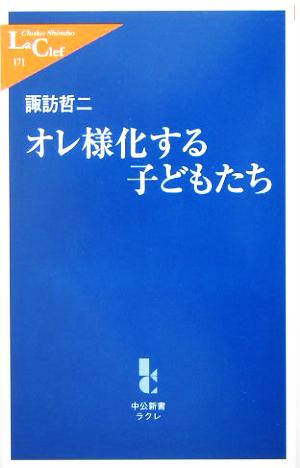オレ様化する子どもたち の商品レビュー
近代化を進めることによって、人権の確立が起こった。 高度成長期以降、明確な目標を失った。 キリスト教的一神教文化がないために、絶対的な存在を持たない。 子供が大人と対等であることを主張してきたときに、それに明確に答える論理を持っていない。
Posted by
筆者は教師という立場から「オレ様化」した子供について、「畏れる」ものを何も持たず、自ら自己を主張して何ら憚るところがないと述べている。 また、子供たちの内面のその自信に比して、その表れの何たる貧弱なことよ、とも。 これについては、親の立場から子供と接する身としても非常に同感する。...
筆者は教師という立場から「オレ様化」した子供について、「畏れる」ものを何も持たず、自ら自己を主張して何ら憚るところがないと述べている。 また、子供たちの内面のその自信に比して、その表れの何たる貧弱なことよ、とも。 これについては、親の立場から子供と接する身としても非常に同感する。 筆者が本著でも述べているように、親は育児をする機会が一度きりであり、この子供の態度が近代化の結果なのかどうかは私にはわからないが、その根拠のない自信に満ちた態度にたじろぐことは度々経験したものである。 ただし、だからといって筆者の述べる従来の教育が子供の教育環境として今日望ましいのかどうかは、これもまた判断できなかった。 分かることは、この子供たちの相手をする教師たちの負荷はこれまでの教師たちのそれに比べて遥かに大きなものになっているであろうことぐらいだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
プロ教師としての教育論 戦後60年間でこどもがかなり変容をとげてしまったということを前提に教育論を語るべきという主張。 なんといっても、教育における共同体的要素=社会化の重要性を強く主張しているところが特徴。また実践者の感覚でもある。 ・教育における共同体的要素の必要性:宮台の考え方の否定。共同体的対市民社会的 ・生活指導の必要性:和田秀樹と上野千鶴子の(生活指導などではなく)授業に集中する学校への回帰論がいかに現実的でないか ・子供は聖域ではない:特に、いわゆる教育の内部(家庭、学校、地域)だけの影響を受けているわけではない。すでにメディアによる共同体的要素の破壊は大きい。尾木直樹はユートピアから課題指摘を学校だけに対してしている ・共同体的枠組みの重要性:村上龍のは好奇心に偏りすぎ ・かといって贈与にだけ偏る世界は教育はない。水谷修の「夜回り先生」は、聖者であって教師ではない 結論として、子供は「教育の外部」の影響を大きく受けており、子どもが教育現場に入ってくる前に大きく情報メディアの影響を受けている。また、農業社会、産業社会、消費社会と変化してきた中、消費者としてのこどもは、強い自己に固執。要するに教育の内部である地域、家庭、学校を超えた世界の影響によって子供は「オレ様化する」
Posted by
初めて諏訪先生の本を読んだ。昭和臭い部分もあるので、諏訪先生は、まあ上司にしたくはないタイプの人かもしれませんね。なるほどって感じ。教育論者の比較・検証をする章は圧巻だった。変わる子ども変わらない教師も面白かったかな。すぐ一般化するから、単語を理解しながら読まないと苦しくなる。
Posted by
前時代的な老害教員が書いた感じがする。 保健室に行く生徒を非難するくだりは人の心がないなと思った。
Posted by
フロイト好き? 10年ちょっと前の著作だが、SNSが普及した今の状況をどう見ているだろうか。 現場の意見なので、ああそうなのかとも思うが、教師を唯一神の補完するものとしてとらえているのは納得しかねる。
Posted by
久々再読。農業社会、産業社会、消費社会という社会の移り変わりで子どもや教育のニーズ、世の中の価値観が変化して来たことは納得。子どもが消費者化してしまうような社会の在り方を実感する。じゃあ、子どもを信用せず、厳しくドライな教育を小学校でも行うべきという筆者の主張については、小学生と...
久々再読。農業社会、産業社会、消費社会という社会の移り変わりで子どもや教育のニーズ、世の中の価値観が変化して来たことは納得。子どもが消費者化してしまうような社会の在り方を実感する。じゃあ、子どもを信用せず、厳しくドライな教育を小学校でも行うべきという筆者の主張については、小学生と日々接した実感からとは思えないし、自分にも実感もない。問題が多々起こる高校現場での実感と解決法を小学生段階から行うというよりも、そういう高校生になる要因は何なのか、小学校・中学校時代にどのような経験を積むべきかを考えたい。
Posted by
子どもは親(教師)の思い通りに行かないと思うのだが、それでも80年代90年代と子供たちは代わってしまったと感じることがある。 「プロ教師の会」というのがあるらしい。論争を煽り、批判する集団なのか? 2部構成になっており、第1部は子どもが悪い、といことの検証。第2部は教育論者の子ど...
子どもは親(教師)の思い通りに行かないと思うのだが、それでも80年代90年代と子供たちは代わってしまったと感じることがある。 「プロ教師の会」というのがあるらしい。論争を煽り、批判する集団なのか? 2部構成になっており、第1部は子どもが悪い、といことの検証。第2部は教育論者の子ども観。 ゆとり教育はうまくいかなかった。変わる子ども、変わらない教師。 教育が贈与から商品交換となった。 子供たちは、個性=自分独自=他人と異なる、という比較を嫌う。大人と対等な関係を望む。
Posted by
「プロ教師の会」代表が「子どものオレ様化」を軸に、教育を論じているのが本書。 「オレ様化」とは? ただ生徒がエラソーになったというだけのことではない。かつて「生徒」というものは、人格的にも知識的にも半人前で、教師から一方的に「贈与」を受け取る存在だった。しかし社会の近代化にとも...
「プロ教師の会」代表が「子どものオレ様化」を軸に、教育を論じているのが本書。 「オレ様化」とは? ただ生徒がエラソーになったというだけのことではない。かつて「生徒」というものは、人格的にも知識的にも半人前で、教師から一方的に「贈与」を受け取る存在だった。しかし社会の近代化にともなって、子どもは変わった。大人と対等の存在、教師と対等の1人の「個」として現れてきた。教師-生徒関係が、「贈与」から「商品交換・等価交換」になってきたのが、教師の権力の失墜→学級崩壊→不登校・いじめ・援助交際・ひきこもり、へとつながっていくのだ……と本書は説く。 いつの時代も子どもは変わらないとか、子ども1人1人に合った教育をしなければならないとか、子どもが自ら学ぶ姿勢を大事にとか……そういう考え方を著者は教壇に立ち続けた経験から「甘い」と切って捨てる。子どもたちにまず必要なのは「個性化」ではなく「社会化」であると。 「子ども」と「学校」の関係だけでなく、「子ども」と「社会」との関係を織り込んで展開される論理は、教師としての実感に支えられているぶんだけ、他の教育論者に比べうわすべりしていない。第1章の論理に従って、第2章で宮台信司、和田秀樹、上野千鶴子、尾木直樹などの教育論が批判されるが、一理あるなぁと思う。 しかし、本著に従えば、「子ども」の変化に対応するには、「学校」を変えるだけでは足りない。「社会」が子どもに注ぐ視線も変えなくてはいけない。それをどうするかまではさすがに荷が重いようで、明確に言及はされていない。それは読者1人1人の課題となるだろう。 また、本著で展開されているのは、しょせんは「精神論」であり、学校のカリキュラムをどうするか、入試をどうするかという現実的な施策を超えたところに成立していることを忘れてはならない。難しいのは、「そっから先」なんである。 先生や親が子どもと友だちのような関係を結びたがったり、小学生のうちから「個性を伸ばす」教育を施したり、学校に「市場原理」を持ち込もうとしたり……つーのは、この本をあてにすると、かなりヤヴァイことのように思える。「ゆとり教育」か「詰め込み&反復」か、「生きる力」か「学力」か。そういう二項対立の図式からすこし視点をずらして考えるために、悪くない本だと思う。
Posted by
2007年くらいに買って読んだんじゃないかなぁ…と思います。 小林よりのり氏推せん!! ワシ様もオレ様が嫌いだ!! と帯にイラスト付で描いてあります。 この本は、今パラパラ見ると、アクがない感じにすら、受けてしまう…。 その理由は簡単。 大筋が社会通念的にOK採用されているよう...
2007年くらいに買って読んだんじゃないかなぁ…と思います。 小林よりのり氏推せん!! ワシ様もオレ様が嫌いだ!! と帯にイラスト付で描いてあります。 この本は、今パラパラ見ると、アクがない感じにすら、受けてしまう…。 その理由は簡単。 大筋が社会通念的にOK採用されているように感じるから。というより、次の段階へ行ったって感じ? ただ、買って読んだころは、そうではない世の中の空気が流れていたと思う部分アリ。
Posted by